
第一章 謎めいた中世音楽
第二章 ルネサンスと「音楽」の始まり
第三章 バロック 既視感と違和感
第四章 ウィーン古典派と啓蒙のユートピア
第五章 ロマン派音楽の偉大さと矛盾
第六章 爛熟と崩壊 世紀転換期から第一次世界大戦へ
第七章 二○世紀に何が起きたのか
「ただ一つ、本書を通して私が読者に伝えたいと思うのは、音楽を歴史的に聴く楽しみである。・・・『このような音楽はどこから生まれてきたのか』、『それはいったいどんな問題を提起していたのか』、『こういう音楽を生み出した時代は、歴史の中のどの地点にあるのか』、『そこから何が生じてきたのか』。こういうことを考えることで、音楽を聴く歓びのまったく新しい次元が生まれてくる、そのことを伝えたいのである」。著者は本書の趣旨をこう述べる。
そして、この歴史を記述する方法論として、「ドイツの著名な音楽史家ハンス=ハインリッヒ・エッブレヒト」の「唯一の客観的な歴史(ザ・ヒストリー)」は存在しない。『歴史』とは常に『私から見た歴史』であり、『数ある可能な歴史のうちの一つ(ア・ヒストリー)』以外ではありえない」という至言に従い、「私」と歴史との対話をベースに置く。
また、テーマの「西洋音楽」について「俗にいう『クラシック音楽』は、この本で扱う『西洋芸術音楽』と、必ずしも同じものではない。西洋芸術音楽は1,0001年以上の歴史をもつが、私たちが普段慣れ親しんでいるクラシックは、18世紀(バロック後期)から20世紀初頭までのたかだか200年間の音楽にすぎない」と定義する。
さらにあえて「西洋芸術音楽」とした点について、「主としてイタリア・フランス・ドイツの知的エリートによって支えられてきた音楽」、「芸術として意図された音楽」であり、それは「紙に書かれた=設計された音楽」であり、だと述べる。
その歴史は、6世紀後半に生まれた「単旋律によって歌われる、ローマ・カトリック教会の、ラテン語による」グレゴリオ聖歌を9世紀半ばに理論化した「ムジカ・エンキリアディス」から始まる。中世音楽の頂点としての12世紀ノートルダム楽派、音楽が宗教的意義から「美」となった15世紀ルネサンスのフランドル楽派、17世紀の絶対王政と寄り添ったバロックへと発展する。
そして、18世紀「神に捧げるためでもなく、王侯を賛美するためでもない、『市民による、諮問のための、市民の心に訴える』古典派が誕生する。それは19世紀になると「個性」百花繚乱のロマン派へと発展し。20世紀、第一次世界大戦によってその輝きを失っていく。ここに至り、西洋音楽は破壊と秩序の再構築という実験を繰り返していく。
現代から見る「芸術音楽」の限界と可能性は、サン=サーンスによって次ぎのように語られる。「音楽はもはやその発展の限界に達している、調性は死に瀕しているのである。これはもっぱら長調と短調ばかりを使い続けてきたことから生じた問題である。今日古い旋律が見直されつつあり、それとともに素晴らしい多彩な東洋の旋法が芸術の中に入ってきている、これらが使い尽くされた旋律に新たな要素を与え、実り豊かな時代を生むだろう」。
しかしこのテーマは、中世から各時代区分の末期毎に提示され、新たに異質なものを取り入れ発展し、今に至る問題でもある。ただ、「西洋芸術音楽」が「芸術音楽」として裾野を広げつつ、または細分化しつつ、どこかで新たな世界を築きつつあることはおそらく間違いはないだろうと思う。
第二章 ルネサンスと「音楽」の始まり
第三章 バロック 既視感と違和感
第四章 ウィーン古典派と啓蒙のユートピア
第五章 ロマン派音楽の偉大さと矛盾
第六章 爛熟と崩壊 世紀転換期から第一次世界大戦へ
第七章 二○世紀に何が起きたのか
「ただ一つ、本書を通して私が読者に伝えたいと思うのは、音楽を歴史的に聴く楽しみである。・・・『このような音楽はどこから生まれてきたのか』、『それはいったいどんな問題を提起していたのか』、『こういう音楽を生み出した時代は、歴史の中のどの地点にあるのか』、『そこから何が生じてきたのか』。こういうことを考えることで、音楽を聴く歓びのまったく新しい次元が生まれてくる、そのことを伝えたいのである」。著者は本書の趣旨をこう述べる。
そして、この歴史を記述する方法論として、「ドイツの著名な音楽史家ハンス=ハインリッヒ・エッブレヒト」の「唯一の客観的な歴史(ザ・ヒストリー)」は存在しない。『歴史』とは常に『私から見た歴史』であり、『数ある可能な歴史のうちの一つ(ア・ヒストリー)』以外ではありえない」という至言に従い、「私」と歴史との対話をベースに置く。
また、テーマの「西洋音楽」について「俗にいう『クラシック音楽』は、この本で扱う『西洋芸術音楽』と、必ずしも同じものではない。西洋芸術音楽は1,0001年以上の歴史をもつが、私たちが普段慣れ親しんでいるクラシックは、18世紀(バロック後期)から20世紀初頭までのたかだか200年間の音楽にすぎない」と定義する。
さらにあえて「西洋芸術音楽」とした点について、「主としてイタリア・フランス・ドイツの知的エリートによって支えられてきた音楽」、「芸術として意図された音楽」であり、それは「紙に書かれた=設計された音楽」であり、だと述べる。
その歴史は、6世紀後半に生まれた「単旋律によって歌われる、ローマ・カトリック教会の、ラテン語による」グレゴリオ聖歌を9世紀半ばに理論化した「ムジカ・エンキリアディス」から始まる。中世音楽の頂点としての12世紀ノートルダム楽派、音楽が宗教的意義から「美」となった15世紀ルネサンスのフランドル楽派、17世紀の絶対王政と寄り添ったバロックへと発展する。
そして、18世紀「神に捧げるためでもなく、王侯を賛美するためでもない、『市民による、諮問のための、市民の心に訴える』古典派が誕生する。それは19世紀になると「個性」百花繚乱のロマン派へと発展し。20世紀、第一次世界大戦によってその輝きを失っていく。ここに至り、西洋音楽は破壊と秩序の再構築という実験を繰り返していく。
現代から見る「芸術音楽」の限界と可能性は、サン=サーンスによって次ぎのように語られる。「音楽はもはやその発展の限界に達している、調性は死に瀕しているのである。これはもっぱら長調と短調ばかりを使い続けてきたことから生じた問題である。今日古い旋律が見直されつつあり、それとともに素晴らしい多彩な東洋の旋法が芸術の中に入ってきている、これらが使い尽くされた旋律に新たな要素を与え、実り豊かな時代を生むだろう」。
しかしこのテーマは、中世から各時代区分の末期毎に提示され、新たに異質なものを取り入れ発展し、今に至る問題でもある。ただ、「西洋芸術音楽」が「芸術音楽」として裾野を広げつつ、または細分化しつつ、どこかで新たな世界を築きつつあることはおそらく間違いはないだろうと思う。












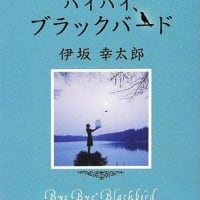







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます