

雑誌「かまくら春秋」2月号から引用。今日から750年ほど前にこの彫刻のモデルになった人間がいまもここにいるような気がした。
ホモサピエンスのこれまでの長い歴史から言えば、シャカムニが生きておられた2500年前も今も人間の顔かたちや感情や思念に変わりはないのだろう。
自分が現生人類・ホモサピエンスである限り、この仏像のモデルになった人と同じく自分は“生老病死”と共に在る。


雑誌「かまくら春秋」2月号から引用。今日から750年ほど前にこの彫刻のモデルになった人間がいまもここにいるような気がした。
ホモサピエンスのこれまでの長い歴史から言えば、シャカムニが生きておられた2500年前も今も人間の顔かたちや感情や思念に変わりはないのだろう。
自分が現生人類・ホモサピエンスである限り、この仏像のモデルになった人と同じく自分は“生老病死”と共に在る。
これはすごい質問。
— Tad (@TadTwi2011) January 28, 2021
小池晃議員、官房機密費について。
「総裁選の間に官房機密費から4820万円が使われていた。総裁選に使ったのではないか。国民には自助を押し付けて自分は公助にどっぷりと浸かって来た」 pic.twitter.com/twyfz8aJB2
「総裁選の間に官房機密費から4820万円が使われていた。総裁選に使ったのではないか。国民には自助を押し付けて自分は公助にどっぷりと浸かって来た」
去年の終わり頃に平川農園さんから立派なムラサキ山芋や下仁田ネギなどを頂いた。太くて芳醇な下仁田ネギをたっぷりと使った肉丼はうまかった。
宅急便の中には「ドン・フランシスコ キリシタン大名 大友宗麟」という初めて食べるお菓子も同梱されていた。みんなでおいしく頂きました。

少年が目指した目的地は「江戸川公園の大滑り台」というので、都電の早稲田駅から歩きだして2分ほどの所にある神田川の遊歩道を歩き出した。


あれっ、ここ歩いたことがあるとすぐに思った。しばらく歩くと 昨年の11月に永青文庫を訪ねた時に見て回った隣の「肥後細川庭園」&こちら←click の南門が現れた。

少年が庭園に入りたいという。聞くと日本庭園は大好きと言う。へーっと思いながら中に入った。中へは無料で入れる。

永青文庫はさすがにパスするというので入り口までの小山を登ってから降りた。

今年の春に亡くなられた森哲雄さんが田中さんと一緒に座って一休みしたベンチがあってしばし瞑目した。
ほぼ一年後にこの場にまた来ることになるとは思ってもいなかった。





ししおどし(鹿威し)の前で少年はかなり長い間佇んで、何回も何回も水が満ちると出るカーンという竹筒と岩が当たって出す音色を楽しんで動かなかった。



花嫁と花婿の衣装を着けた二人がブライダルアルバムのための?撮影に来ていた。

珍しく蒲の穂を見た。つい「大黒さまの いうとおりきれいな水に 身を洗い
がまのほわたに くるまればうさぎはもとの 白うさぎ」と因幡の白兎の童謡を思い出して口から出たが
正確には歌えなかった(笑)。

都民の日で休日の中学生のグループが弁当を開いていた。


つづく
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1003 自己流エクササイズ フルセット完
1 片足立ち一分 右足左足それぞれ5回 合計10分の片足立ち

2 スクワット 20秒×5

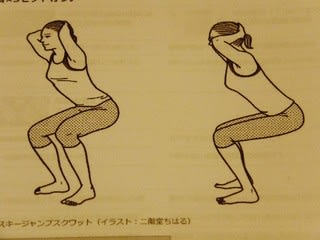
3 腕立て伏せ 15回

4 膝を曲げずに5本の手の指を平らに床につける 一回20秒を前屈5回 手を挙げて後屈一回20秒を5回
5 少し足を広げ身体を左右横へ思い切り傾転 左右それぞれ20秒 5回づつ
6 四股ストレッチ 30秒×3
所要時間 35分
(トップの画像はグリ・アミールの大天蓋と残月)
丸亀市にお住まいのTさんが昨年10月、関西空港からウズベキスタン航空を利用し、ウズベキスタンはタシケント空港にご夫婦で直航されました。
昭和39年ごろのある日「世界中で最も訪ねてみたいところはどこか」を、新婚のお二人で話し合った事があったそうです。
当時はまだ海外旅行などは「夢のまた夢」の時代です。お二人の希望地がたまたま一致しました。それが当時はソ連圏にあったサマルカンドやタシケント、
つまり現在のウズベキスタンだったそうです。
それから何十年も経って、体力などを考えるとそろそろ行かなければと焦りを感じ始めたある日、ウズベキスタンのグループツアー(9泊10日)が目に留まり、
ほぼ1400キロメートルを走る強行軍の旅であることが少し気になったそうですが、迷う暇もなく、あっという間にこれに参加することにされました。
ヒバの城壁。
明け行くヒバ。
ブハラのカラーン・モスク遠望。
カラーン・モスクで声を上げて祈る学生。
遺骸から復元されたウルグ・ベクの顔。
家路に急ぐ人々(タジキスタンの道路)
ウズベキスタンは奥さんにとっては、アムダリア(アム河)とシルダリア(シル河)の流れる大地、そして東西交易と南北交易の交わる地点であり、
ご主人には、わずかの期間に大帝国を築いたティムールと、その孫で天文学に秀で、実の息子に殺されたウルグ・ベクが支配した地域でした。
奥さんは高校時代の人文地理の時間にこれらの地名を耳にし、いっぽう、ご主人は高校時代の世界史の時間にこれらの地名を耳にした、その土地がウズベキスタンでした。
♪このシャープな一連の画像が、常にウエットな空気が流れる日本と言う國の風土との違いを、視覚で瞬時に知覚させてくれます。
青いタイルの大天蓋に昼の白い月、家路にいそぐ人々など全写真に唸りました。灼熱に空気そのものが炎上しているような気配を感じます。
常に水分を含む空気がある日本の自然との異質さを切り取りながらも、やはりここにも太古から人間が住むんだと。東西の文明の灼熱の十字路の地!! 地球は広いですね。
ウズベキスタンの参考情報はこちら。



屋上菜園119 (2020.6.1~) https://t.co/tXLWafZxgL
— achikochitei (@achikochitei1) June 8, 2020
『人類学とは何か』分けられない人間性に取組む学問として - HONZ https://t.co/YF1FJKsdrM
— achikochitei (@achikochitei1) May 30, 2020
日本人(アジア)にどうして新型コロナが広がらないか、どんどん権威ある説が出てきたので紹介するよ。コロナは日本では恐くない #BLOGOS https://t.co/xlU212wRMz
— achikochitei (@achikochitei1) May 19, 2020
菜園で採れた無農薬野菜を送って頂いた。近くに住む一家にもおすそ分けだ。
お礼メールを送信した。
「19時頃瑞々しく色彩鮮やかな野菜がきちんと格納されて届きました。
近くに住む家族にも早速おすそ分けします。
いつも これが本来の野菜だ!(笑) という野菜を
送って頂き感謝に堪えません。
極早生タマネギは初めて知りました。次々新しい種類が
栽培されているんですね。
ありがとうございました。奥様にもよろしくお伝えください」
平川さんとはお互い1995年1月の阪神淡路大震災を大阪支社時代に体験した仲だ。
事業部は違ったがお互いの本部が東京にあるせいか大阪支社で席がはしっこの隣同士になり、いつしか終業のあと隣のビルの地下にある「小ぼけ」で飲むようになった。
呑み助ということで知り合ったが、彼も私も久富さんという方をリスペクトしていたのも共通点だった。
あれから30年近く経っているし、1997年に阿智胡地亭が広島に転勤になったので大阪で飲むのはその時点で終わったが・・
お互い定年になってからも4,5年おきに会ってきて、先日は有楽町でも飲んだのは楽しかった。
日本人が「お上の要請」に真面目に従う根本意識 統治客体意識からの脱却は20年以上叫ばれたが | コロナショックの大波紋 - 東洋経済オンライン https://t.co/GMu1lkI25C #東洋経済オンライン @Toyokeizaiさんから
— achikochitei (@achikochitei1) April 28, 2020
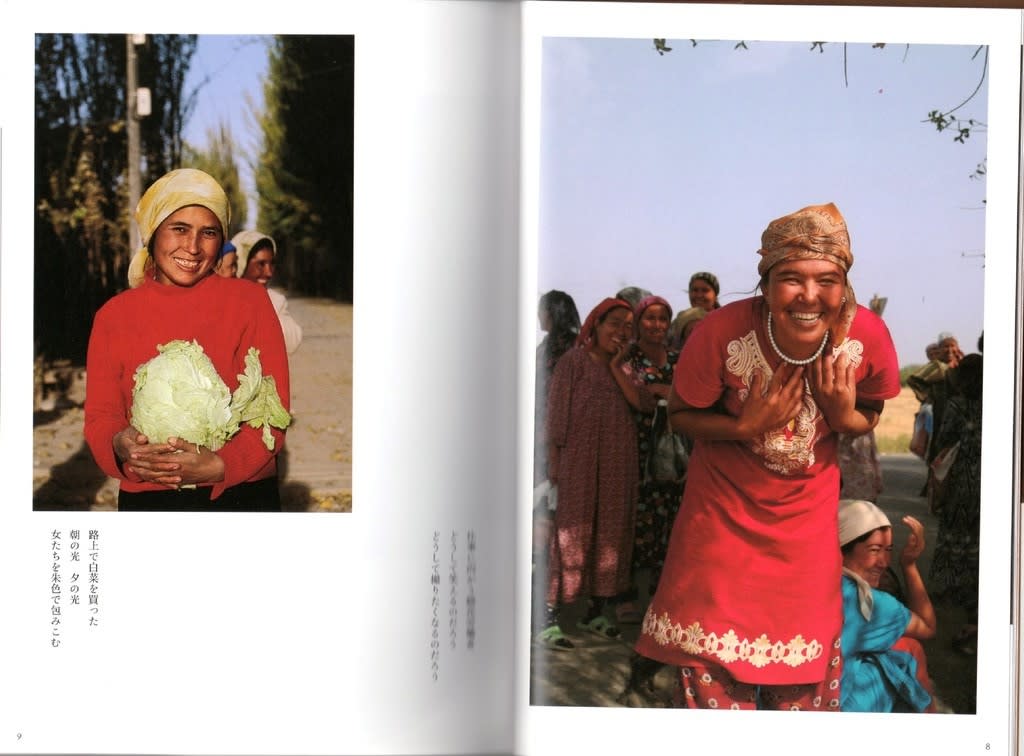


◎長倉さんという写真家は「うつくしい」ということをずっと追いかけてきた人だと思う。
彼の「うつくしさ」は人間の持つ「うつくしさ」を教えてくれる。
古い時代から十一面観音像が作られて、当時から人には11の顔があると知られていた。
一度滋賀県長浜市高月町を訪ねたとき、11面観音の全てのお顔をぐるっと360度まわって拝観させてもらった。
邪悪、嫉妬、憎悪などの表情を持つ顔のその中に「うつくしい」顔があった。それは真正面に位置していた。
当時の人は毎日このお顔と対峙していたんだと思った。
人はうつくしくあるものだと長倉さんは言っている。
2017年4月15日掲載:

 |
 |
|
| 1952年、北海道釧路市生まれ。京都での大学生時代は探検部に所属し、手製筏による日本海漂流やアフガン遊牧民接触などの探検行をする。1980年、勤めていた通信社を辞め、フリーの写真家となる。以降、世界の紛争地を精力的に取材する。中でも,アフガニスタン抵抗運動の指導者マスードやエルサルバドルの難民キャンプの少女へスースを長いスパンで撮影し続ける。戦争の表層よりも、そこに生きる人間そのものを捉えようとするカメラアイは写真集「マスード 愛しの大地アフガン」「獅子よ瞑れ」や「サルバドル 救世主の国」「ヘスースとフランシスコ エルサルバドル内戦を生き抜いて」などに結実し、第12回土門拳賞、日本写真協会年度賞、講談社出版文化賞などを受賞した。 2004年、テレビ放映された「課外授業・ようこそ先輩『世界に広がれ、笑顔の力』」がカナダ・バンフのテレビ祭で青少年・ファミリー部門の最優秀賞「ロッキー賞」を受賞。2006年には、フランス・ペルピニャンの国際フォトジャーナリズム祭に招かれ、写真展「マスード敗れざる魂」を開催、大きな反響を呼んだ。
|
||
FUJIFIlMのホームページ「the Photographer 2005 写真を語る」にて詳細なプロフィールが紹介されています。 |
||
今年の長倉さんのアフガニスタン訪問報告⇒こちら。
個展会場の一場面


漫画家の西原理恵子さんとのトーク。
プロフィル:
1952年、北海道釧路市生まれ。京都での大学生時代は探検部に所属し、手製筏による日本海漂流やアフガン遊牧民接触などの探検行をする。
1980年、勤めていた通信社を辞め、フリーの写真家となる。以降、世界の紛争地を精力的に取材する。
中でも,アフガニスタン抵抗運動の指導者マスードやエルサルバドルの難民キャンプの少女へスースを長いスパンで撮影し続ける。
戦争の表層よりも、そこに生きる人間そのものを捉えようとするカメラアイは写真集「マスード 愛しの大地アフガン」「獅子よ瞑れ」や
「サルバドル 救世主の国」「ヘスースとフランシスコ エルサルバドル内戦を生き抜いて」などに結実し、
第12回土門拳賞、日本写真協会年度賞、講談社出版文化賞などを受賞した。
2004年、テレビ放映された「課外授業・ようこそ先輩『世界に広がれ、笑顔の力』」がカナダ・バンフのテレビ祭で青少年・ファミリー部門の最優秀賞「ロッキー賞」を受賞。
2006年には、フランス・ペルピニャンの国際フォトジャーナリズム祭に招かれ、写真展「マスード敗れざる魂」を開催、大きな反響を呼んだ。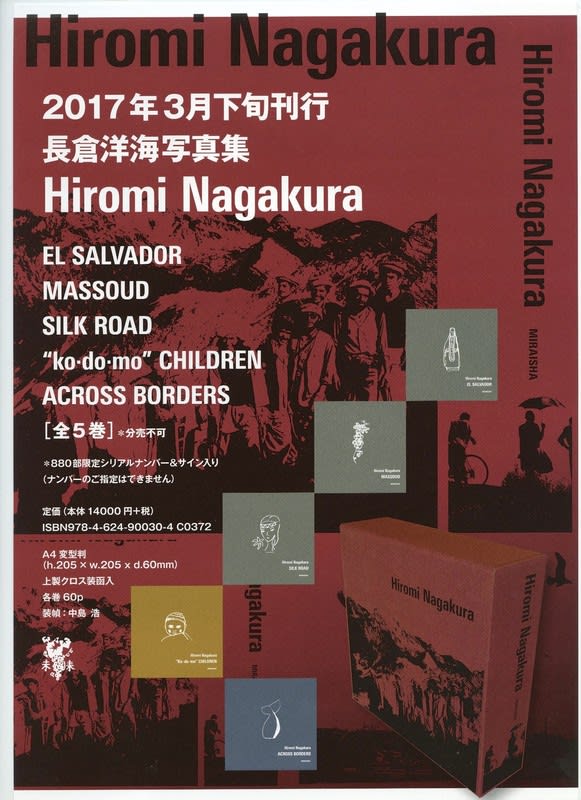

上記のアナウンスがありましたので「慶応義塾大学病院のサイト」表示を上のように掲載しました。4月13日記
ちなみにアナウンスの対象となったマニュアルの内容は次の通りです。4月19日記
⇒ 注意事項
ウイルスが出てくるのは咳とか唾とか呼気
でも普通の呼気ではうつりません
これまでのほとんどの感染は
①感染者から咳やクシャミで散った飛沫を直接吸い込む
②飛沫が目に入る
③手指についたウイルスを食事と一緒に嚥下してしまう
という3つの経路で起こっています
感染にはウイルス粒子数として100万個ほど必要です
1回のくしゃみや咳や大声の会話で約200万個が飛び散ると考えられています
つまり感染者がマスクをしているとかなり防ぐことができます
なるべく鼻で息を吸いましょう
口呼吸で思い切りウイルスを肺の奥に吸い込むのはダメです
外出中は手で目を触らない 鼻を手でさわらない(鼻くそをほじるのはNG) 唇触るのもだめ 口に入れるのは論外
意外と難しいが 気にしていれば大丈夫です
人と集まって話をする時は マスク着用
食事は対面で食べない 話さない
食事に集中しましょう
会話は食事後にマスクして
家に帰ったら 即刻手を洗う
アルコールあるなら 玄関ですぐに吹きかけて ドアノブを拭きましょう
咽頭からウイルスがなくなっても 便からはかなり長期間ウイルスが排出されるという報告があります
ノロウイルスの防御法と同じように対処を忘れずに
感染防御のルールを再度整理します。
①マスクと眼鏡の着用
②手指の洗浄と消毒
③会食は対面ではせず 1人で食事を短時間で済ませる
④外から帰宅時は先にシャワーを浴びてから食事
陽性患者さんの多くは 手指から口に入るか 食事の時に飛沫感染しているようです
以上を守って元気でいましょう。
昨年も大分県国東半島の平川農園さんから収穫物を送って頂いた。農園主とは大阪支社勤務時代の飲み仲間だった。
お互いがそれぞれ属していたのが関東系の事業部という共通点があり、かつ支社での部門の席がフロアーのはしっこで隣同士だった。
呑み助ということで知り合ったが、彼も私も久富さんという方をリスペクトしていたのも共通点だった。
今年送って頂いたダイジョ(大薯)は毎年頂くものに比べても格段に大きく厚みがあって立派な代物だった。
いつも食べる時は、きっと丸木船に乗った南方の海洋民族が、黒潮に乗って東海の島を目指した時に貴重な保存食として船に乗せていたものだろうと頭に浮かぶ。





まだまだ何回か食べられるので楽しみだ。平川農園主さんいつもありがとうございます。やはり旨いです!!
| ダイジョ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ダイジョの葉
|
|||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||
| Dioscorea alata L. | |||||||||||||||||||||
| 和名 | |||||||||||||||||||||
| ダイジョ、ダイショた 他 | |||||||||||||||||||||
| 英名 | |||||||||||||||||||||
| Ube, Purple Yam, Water Yam, Violet Yam, Greater Yam |
ダイジョ(大薯、ダイショ)は、ヤムイモ(ヤマノイモ目ヤマノイモ科ヤマノイモ属の食用種)の1種の芋類。学名 Dioscorea alata。シンショ(参薯)、デンショ(田薯)、コウシャイモ(拳薯)、オキナワヤマイモ(沖縄山芋)、タイワンヤマイモ(台湾山芋)、ウベ (フィリピン語:ube)、パープルヤム (purple yam)、ウォーターヤム (water yam) とも。奄美方言ではこうしゃまんという。
ときおり同属のヤマイモの1種と誤解されるが、ヤマイモ(ヤマノイモ、D. japonica)は同属別種である。ショヨ(薯蕷)とも混同されるが、ショヨはナガイモ(D. polystachya)のことで、これも同属別種である。
芋の中身は鮮やかな紫色をしているものが多いが、白色の品種もある。紫色のものはベニヤマイモ(紅山芋)、ベニイモ(紅芋)とも呼ぶ。紫色の色素はポリフェノールの1種アントシアニンで、ムラサキイモと同じである。ただし、ムラサキイモはサツマイモ(ナス目ヒルガオ科サツマイモ属サツマイモ。学名 Ipomoea batatas。)の紫色の品種で、ダイジョとは近縁ではない。なお、呼び分ける場合はダイショをベニイモ、サツマイモをムラサキイモと呼ぶ。[要出典]
アジア、オセアニアなど、世界中の熱帯地域で広く栽培される。世界的にはヤム類の中でも主要な栽培種であり、ヤムイモの世界生産高の大部分はダイジョによって占められる[2]。
日本では沖縄県で広く栽培されるほか、鹿児島県の奄美群島を含む九州・四国などでもわずかに栽培される。本土では苗を保温施設で育てることもある。