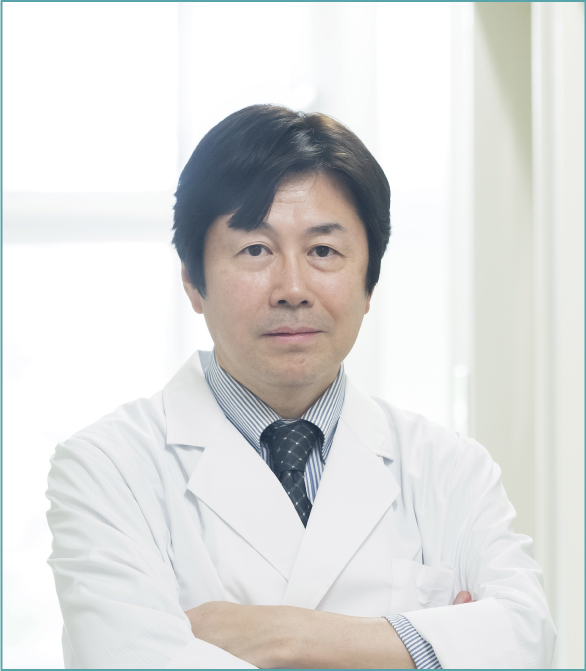2023/12/31(日) 8:00日刊スポーツ
生活習慣病を放置すると、心筋梗塞といった血管が悪くなるだけでなく、心臓機能も低下していく。本来の働きができない状態を心不全といい、急に悪くなると突然死につながる。が、慢性的に機能が低下していく慢性心不全もある。
「生活習慣病など心臓病のリスクがあるときは、心不全の前段階のステージAと考えます。心筋梗塞や弁膜症などで心臓の動きが悪くなると、前心不全のステージB。ステージAやBは、心不全につながる『隠れ心不全』といえます」とは、
東京都健康長寿医療センターの原田和昌副院長
循環器専門医・地方評議員、高血圧専門医・評議員などの資格を有し、心臓病の診断・治療・研究を数多く行っている。
「隠れ心不全の段階であれば、心不全を回避することが可能です。ぜひこの段階で、食生活の見直しや適切な治療を受けていただきたいと思います」
たとえば、弁膜症は、心臓の弁の開閉がうまくいかなくなる病気だ。心臓は弁で血液の逆流を防ぎ、全身に血液を送り出している。弁の開閉がうまくいかなくなると、血液の流れは悪くなり、心臓に負荷をかけ続けることで心不全に至る。しかし、よほど進行しないと自覚症状に乏しい。聴診器で心臓の音を聞いたときに雑音が混ざることで、弁膜症の早期発見につながる。
「弁膜症の進行を止めるには、生活習慣病予防に加え、適度な運動が効果的です。理由はわかりませんが、適度な運動習慣を持つことによって、中等度の弁膜症では進行がある程度止まるのです。運動習慣を持つようにしましょう」と原田副院長はアドバイスする。
11/24(金) 19:28 長崎文化放送
「犬を飼っている高齢者は認知症を発症するリスクが40%低い」という調査結果がこのほど発表されました。
地方独立行政法人「東京都健康長寿医療センター」の研究チームが10月、研究論文を科学誌に発表しました。ペットの飼育と認知症の発症の関連性を明らかにした発表は初めてとしています。
それによりますと犬を飼っている高齢者は、飼っていない高齢者と比べ、認知症を発症するリスクが40%低いことが分かりました。また犬を飼っている高齢者のうち、犬の散歩などの運動習慣のある人や、散歩中、人と触れ合うなど社会的に孤立していない人の方が認知症の発症リスクが低い傾向にあることも分かりました。
一方、「猫を飼っている高齢者と飼っていない高齢者の間には、意味のある認知症発症リスクの差はみられなかった」としています。
「日常的に犬を世話することによる飼育者の身体活動や社会参加の維持が、飼育者自身の認知症の発症リスクを低下させていると考えられる」としています。
調査は東京都の65歳以上の男女1万1194人を対象に、2016年から20年までのデータを分析したもので、研究対象者の平均年齢は74.2歳でした。
2023年6月24日 8時0分 現代ビジネス
東京都健康長寿医療センター
運動科学研究室長
青冶幸利氏
学校で、職場で、地域のイベントで―。実に60年以上も親しまれてきた「国民的体操」であるラジオ体操。しかし「簡単な運動」と甘く見ていると、ふとした動作で思わぬ負担を身体にかけ、大ケガのもとにもなるリスクが潜んでいることをご存知でしょうか。
前編記事『医師が警告!ラジオ体操は「ひざ」と「腰」を痛めます…「なんとなくひざが痛いなと」「前屈をすると急に」』より続く。
■ラジオ体操…実は「かなりハード」な体操
ちなみにラジオ体操のなかには、きちんと身体を使わなければ、あまり効果がない動作もある。
たとえば、体操第1の「身体を横に曲げる運動」は、しっかりと背骨まで曲げず、肘だけを曲げて身体を傾いているようにしているだけでは、背骨を柔軟にする効果がない。
また体操第1の「身体をねじる運動」も、腕をしっかりと振り上げることができなければ代謝を促進することにはならない。筋肉量が落ちたり、痛みがある部分があったりすると、ついごまかしながらやってしまいがちな動作なのである。
そもそも現在のラジオ体操第1・第2の放送がはじまったのは'51年のこと。この年の平均寿命は、男性60.8歳、女性64.9歳だった。つまり、そもそもラジオ体操の中身は、60歳以上の人が毎日行う前提では作られていないのだ。
また、60代の平均的な肥満度も、当時は男女ともに21前後だったのが、いまは男性24、女性23程度とやや増えている。体重が増加しているぶん、下半身への負担の程度も大きくなっている。
現在放送されているNHKのラジオ体操では、「ラジオ体操の前に筋肉をほぐすウォーミングアップ体操を行いましょう」と推奨している。つまり、高齢者にとってラジオ体操は手軽な運動ではなく、準備体操を要求するほどハードなものと捉えたほうがいいのだ。
ラジオ体操、「朝の時間帯」は特に危ない…
そして特に60歳以上の人の場合、運動する「時間帯」にも気を配ったほうがいい。
著書に『やってはいけないウォーキング』(SB新書)がある、東京都健康長寿医療センターの青冶幸利氏は、「朝の運動は注意するべき」と指摘する。
「朝は脳卒中や心筋梗塞の発症率が一番高い時間帯といわれています。人間は眠っている間に発汗や呼吸をすることで、かなりの量の水分を失っています。つまり寝起きは血中の水分量が少なくなり、血液がドロドロになっている状態なのです。
加齢とともに動脈硬化も進み、血管が詰まりやすくなっていますから、水を飲まずに運動をしはじめると、命取りになりかねません。少なくとも水を飲んでから30分以上は、汗をかくような運動はしないほうがいいのです。
また朝はまだ体温が上がりきっていないので、筋肉がこわばった状態になっています。そのようなタイミングで無理な動きをすると、重大な疾患を引き起こすこともある、と考えたほうがいいのです」
同様に、前出・銅冶氏も早朝の運動にはリスクがあると語る。
「早朝にラジオ体操をされる方が多いと思いますが、できれば避けたほうがいいでしょう。というのも、朝は椎間板が寝ている間に水分を含み、めいっぱい空気を入れたタイヤのように膨れた状態になっているからです。ここで無理な動きをすると、椎間板を痛めやすくなってしまいます」
運動するなら夕方がいい
それでは、いつ運動するのが理想的なのか。前出・青冶氏は、もし身体を動かすならば「夕方」であるとアドバイスする。
「夕方に運動をすることによって、身体のバイオリズムを改善することができます。適度に身体を使うことで夜よく眠れるようになりますし、睡眠の質がよくなれば、脳の活性化を促し、ひいては認知症の予防にまでつながるのです」
もちろん、ラジオ体操すべての動きが身体に支障をきたすわけではない。
前出・橋本氏は次のように語る。
「もともとはきちんと考えて作られているものですから、ラジオ体操には健康上のメリットも当然あります。適切な動作をすることで、血圧や血行を改善したり、仲間と運動することで爽快感を得ることもできる。
ただ、立ってするのが危なければ座ってやる、肩が上がらなければ痛みが出ないところまで、と自分の限界を知っていくことが大切です」
そのようなことを考慮してか、'99年からNHKで放映が開始された「みんなの体操」は、運動量がラジオ体操よりも少なく、また立った状態で行うものと座って行うものと2通りの方法がある。より身体の負担に配慮したメニューになっているのだ。
「高齢者の方が一度膝や腰を痛めてしまうと、急に行動量が減り、運動で血圧や血糖値をコントロールすることが難しくなってしまいます。昨今の健康ブームによって、筋力トレーニングや長時間のウォーキングに挑む人もいますが、『健康のため』と思ってやっていると逆効果になる。
万人に合うような体操や運動というものはありませんから、身体が動けなくなるような部位に関しては、特に気をつけてほしいと思います」(前出・青冶氏)
いくつになっても同じ運動が身体のためになるとは限らない。加齢とともに自分に合った動きをよく見極めるのが肝心だ。
また、骨を強くするのに効果的な体操について関連記事『1日6分やるだけで骨が強くなる!日本整形外科学会が推薦…画期的効果を生む「ダイナミック・フラミンゴ体操」ってなんだ?』もぜひあわせてお読みください。
青栁幸利 あおやぎ・ゆきとし
- 1962年群馬県生まれ。トロント大学大学院医学系研究科修了、医学博士取得。カナダ国立環境医学研究所、奈良女子大学、大阪大学を経て現職。群馬県中之条町住民を対象とした長期にわたる調査活動から「病気にならない歩き方」を導き出す。『一日一万歩はやめなさい!』(廣済堂健康人新書)、『やってはいけないウォーキング』(SB新書)ほか著書多数。
2/24(金) 12:55 医療介護CBニュース
東京都健康長寿医療センター研究所はこのほど、同センター研究所と大阪大、慶応大の共同研究チームが、糖尿病性認知症に特徴的な血中タンパク質糖鎖を発見したと発表した。
糖尿病合併症としての認知症は、患者とその家族の生活の質(QOL)をさらに低下させるため、早期に発見することが求められている。今回の研究成果を基に糖尿病性認知機能低下のバイオマーカー(指標)が策定できれば、「糖尿病患者とその家族に光明をもたらすものと期待される」としている。
タンパク質の翻訳後修飾(タンパク質生合成後に付加される修飾)の糖鎖修飾は、老化や病気など健康状態の変化を反映して構造が変わり、がんなどさまざまな疾患のバイオマーカーとなることが知られている。また、血中タンパク質のほとんどが糖鎖修飾を持っているため、血液を用いて糖尿病性認知症のバイオマーカー候補となる糖鎖修飾を探索することは有用であると考えられている。
今回の研究では、血中タンパク質を消化酵素(タンパク質分解酵素)により、ペプチドにした検体について、液体クロマトグラフィー質量分析装置(LC-MS)と多変量解析(OPLS)を用いて分析。認知機能の低下によって変化する血中タンパク質由来の糖ペプチド(糖鎖修飾を持つペプチド)を探索した。
縦断調査(同じ人に対する数年ごとの追跡調査)に参加した人で、糖尿病に罹患していて認知機能が低下した人の認知機能低下前と低下後の血液を比較したところ、認知機能低下により、クラスタリン、α2マクログロブリン、ハプトグロビン由来糖ペプチドの高分岐(3から4分岐)でシアル酸を含む糖鎖が減少した。逆にトランスフェリン由来糖ペプチドの3分岐で3シアル酸を含む糖鎖が増加することが明らかになった。
これらの特徴的な糖ペプチドについては、「糖尿病性認知症のバイオマーカー候補となる可能性があると考えられ、今後、多検体で検証していく」としている。
12/7(水) 12:30 日刊ゲンダイDIGITAL
東京都健康長寿医療センター
元副院長・桑島巌先生
グルメな俳優の突然の訃報に驚いた人は少なくないだろう。先月28日に亡くなった俳優渡辺徹さんだ。一般には耳慣れない敗血症で、61年の生涯に幕を閉じたが、その急変ぶりは決して他人事ではないという。
渡辺さんに異変が生じたのは先月20日。所属した文学座によると、発熱や腹痛などの症状が現れたため、都内の病院で検査を受けたところ、細菌性胃腸炎と診断されて入院。
その後、敗血症を起こし、入院からわずか8日後に帰らぬ人となってしまった。
細菌性胃腸炎は、いわゆる食中毒だ。それが敗血症に至るのは、なぜなのか。東京都健康長寿医療センターの元副院長・桑島巌氏が言う。
「体に細菌やウイルスなどの病原体が感染すると、それらから身を守る免疫反応が生じたり、傷口が修復されたりします。その生体メカニズムが適切に制御されていれば問題ありませんが、制御不能となって臓器障害を引き起こした状態が敗血症です。感染経路は、肺炎や尿路感染症が多く、細菌性胃腸炎をはじめとする腸管感染症や、手足の傷口などからの感染もある。年間10万人が亡くなり、重症化因子は糖尿病、肝臓病、がん、高齢者などです」
厚労省によると、昨年の食中毒発生状況は、全体で717件発生。患者数は1万1080人に上る。
全国の患者数を月別に表したのが表①だ。梅雨に入る6月が多いのは例年通りだが、昨年は4月が6月を上回っている。昨年4月は、岡山で提供された弁当給食がノロウイルスに汚染されていて2545人が、愛知でも給食のノロ汚染によって158人が食中毒に。これらが例年以上の感染者数の要因だが、食中毒はほかの月も確実に発生している。患者数はともかく、食中毒の件数は例年、6月前後より年末の方が多い傾向だ。
2021年原因施設別発生状況(左)と原因食品別発生状況
調理済みにも多発、持ち帰り総菜は注意
どんなものを、どこで口にして、食中毒になることが多いのか。昨年は富山で汚染された牛乳で大きな被害が出たことで乳製品の患者数が多いが、魚介類や肉類、野菜類などは満遍なく被害が発生している。注目は複合調理品で、被害の詳細を見ると、火を通した総菜などが原因食品になっていることが珍しくない。決して生魚や生肉だけではないのだ。
その点で発生施設を見ると、飲食店がトップ。不衛生な店は論外だが、家庭で多発しているのも事実で、生ものだけでなく、持ち帰った総菜なども注意すべきだろう。
お腹を下して嘔吐や下痢を繰り返すのは、つらい。感染による高熱も重なると、なおさらだが、それでも感染前に健康な人なら数日で回復するだろう。実際、昨年の感染者数は1万人を超えても、死者数は2人のみ。例年、その程度だ。
ところが、渡辺さんは食中毒から敗血症を起こし、命を失った。それも61歳の若さで、だ。最悪の転帰をたどったのは、なぜなのか。桑島氏は、「あくまでも報道から推測されることですが」と断った上でこう言う。
「報道によると、渡辺さんは30代で糖尿病を発症されていて、50代からは腎機能の低下によって人工透析を受けていたといいます。糖尿病と腎不全の影響は、とても大きいでしょう。一般に糖尿病の人は免疫力が下がりやすく、感染リスクが高くなります。血糖コントロールが悪い人はなおさらで、そんな人が何かの手術を受けるときは、術中の感染リスクを下げるため血糖値を下げてから行われますから。さらに腎不全で、人工透析を医療機関で受ける場合、月水金など週3回が原則で、透析との間隔が1日か2日空きます。その間、尿は排出できず、体にたまった状態。人工透析は、敗血症が重症化しやすいのです」
人工透析の2大原因は糖尿病と高血圧
渡辺さんの悲劇が、決して他人事でないのは、まさにここ。生活習慣病の一つである糖尿病がベースにあって、それをこじらせたことが影響していると思われるためだという。
「糖尿病には、末梢神経の感覚がマヒする神経障害、失明のリスクになる網膜症、そして腎不全を起こす糖尿病性腎症が3大合併症。渡辺さんが腎不全で人工透析を余儀なくされたのも、糖尿病の悪化と考えられます」
「国民健康・栄養調査」(2016年)によると、糖尿病の人は予備群を含めて2000万人。
同じ調査で患者数は4300万人とされる高血圧も、治療をおろそかにすると腎臓に悪影響を及ぼすことが分かっていて、慢性糸球体腎炎が悪化すると人工透析が必要になることが少なくない。
「人工透析の導入要因となる病気はいくつかありますが、2大因子が糖尿病性腎症と慢性糸球体腎炎です。つまり、糖尿病や高血圧がある人は、しっかりと治療を受けて持病を悪化させず、腎臓を守ることが大切。腎不全になる前の段階で治療を受けていれば、人工透析の導入を免れることができますが、腎不全と診断されると、人工透析が避けられませんから」
■「2分の1の法則」が浮き彫りになる現状
糖尿病と高血圧は、今や国民病。いずれかに当てはまる人は、渡辺さんの死を教訓に病気と向き合って、しっかりと治療を受けるべきだが……。
「企業健診などで糖尿病や高血圧などを指摘されても、自覚症状がないため、治療を受けずに放置する人がとても多いのが現状です。その現状を如実に示すのが、高血圧治療の『2分の1の法則』で、高血圧患者のうち治療しているのは大体全体の半分で、治療しているグループのうち血圧基準を達成しているのがその半分。つまり、治療していても、半分は未達ということ。一方、治療していないグループのうち、およそ半分は高血圧の認識があり、残りの半分は認識がありません」
なるほど、16年の「国民健康・栄養調査」の結果も、およそ桑島氏の指摘通りの結果だ。まず治療群は全体の56%で、目標達成が27%、未達が29%とほぼ半々。残りの未治療群44%は半々とはいかないが、それでも高血圧の認識アリ11%、認識ナシ33%となっていて、全体で見ると「2分の1の法則」が当てはまるといっていい。
「治療もせず認識もない人は検診を受けて治療すること。治療中で未達の人、未治療でパスしている人は、とにかくなるべく血糖値や血圧などの数値を下げることが大切です。たとえ腎不全にならなくても、心筋梗塞や脳卒中など死に直結する合併症を招く恐れがあります」
渡辺さんは亡くなる直前まで毎日のようにSNSを更新。グルマンだけにその写真は、おいしいものであふれる。人工透析患者とは思えないほどだが、その更新がストップしたのが先月19日。その翌日に細菌性胃腸炎で入院した。わずか8日後の急逝は家族を苦しめ、妻の郁恵さんは憔悴しているという。今回の訃報に驚いた人は、自分のためにも家族のためにも食事などに気をつけながら受診することだろう。
夕刊フジ 1/26(土) 16:56
東京都健康長寿医療センター研究所老化制御研究チーム
高山賢一研究員
健康寿命を延ばすためには、活動的な毎日を過ごしたい。だが、加齢とともに体力は低下し、趣味などへの興味が薄れてしまうことがある。それに関わる大きな要因のひとつがホルモンだ。ホルモンの種類は数多く、血圧調整や酵素の働きなどさまざまな役割を担っているが、とくに男性にとって重要なホルモンといえば、男性ホルモンのアンドロゲンである。
女性ホルモンは閉経後の急激な減少で、骨粗鬆(こつそしょう)症や生活習慣病の後押しをすることが広く知られている。近年、男性ホルモンの減少も老化に関わることがわかってきた。
「アンドロゲンは、生殖以外に骨や筋肉、脳の機能に関わります。それぞれの臓器の細胞には、アンドロゲンを受け取る受容体があり活用しています。アンドロゲンは男性の活力を支えており、アンドロゲンが減少すると、骨や筋肉、脳などの機能が低下してしまうのです」
こう説明するのは、東京都健康長寿医療センター研究所老化制御研究チームの高山賢一研究員。悪性度の高い前立腺がんの遺伝子レベルのメカニズムを研究する一方、ホルモンと老化の研究にも力を注いでいる。
高山氏は、約2年半前に現職となる前、東京大学医学部附属病院老年病科で、骨粗鬆症や認知症などの老化に関わる病気の診断・治療を行った経験を持つ。そのとき感じたのが、男性ホルモンや女性ホルモンと老化の関わりだったという。
「たとえば、退職後に自宅で過ごす時間が増えて内向的になり、外出する機会が減って骨粗鬆症や認知症などになってしまう方がいます。女性は骨粗鬆症になりやすいことは知られていますが、男性でもなります。気分の落ち込みや身体的な活動量の低下が病気につながり、それを男性ホルモンの減少が後押しします」
高山氏によれば、アンドロゲン受容体を人為的に欠損させたマウスの実験では、骨粗鬆症を引き起こし、筋力は弱く、脳の機能も妨げられたと報告されている。一般に男性ホルモンの低下は、男性更年期障害とも言われ、ホルモン補充療法も行われている。老化を防ぐためにどうすればよいのか。
「運動習慣を持ち、趣味などで楽しいことに取り組むことが役立つと思います。男性ホルモンの減少に伴い筋肉や脳などの働きが低下しますが、筋肉や脳を動かすことで補うことが可能と考えられるのです」
認知症の予防でも、運動や趣味などが一助となることが知られている。それらは、男性ホルモンの低下に伴う機能低下を補い、活性化することにも関わっているのだ。
「男性ホルモンの低下で筋肉が萎縮すると、筋肉のアンドロゲン受容体もうまく働かなくなります。特に若い年代から運動によって筋力を高め、活動的に生活する習慣を身につけることが、加齢による病気の予防に大切だと思います」
高山氏が勧める男性ホルモンアップ法を別項に掲げたので参考にしていただきたい。運動は生活習慣病予防だけでなく、男性ホルモンの維持、ひいては老化予防にもつながるのだ。(安達純子)
■「男性ホルモン」アップ法
□楽しいと思えるような趣味を持つ
□ゴルフやウオーキングなどの無理のない運動習慣を継続する
□運動習慣のない人は、室内での体操、速歩や階段の上り下りなど、こまめに体を動かす
□定年退職後も毎日外出するなどして、脳への刺激を心掛ける
□笑顔になるように家族や友人との会話を楽しむ
□睡眠を十分とり規則正しい生活を心掛ける
12/6(火) 9:06 日刊ゲンダイDIGITAL
厚労省研究事業の推計では、ヒートショックとみられる入浴中の死亡者は年間1万9000人ほど。東京都健康長寿医療センターも1万7000人の近似値を出している。事故は寒波が訪れる12~2月に集中。WHO(世界保健機関)は室内温度を「18度以上」に保つよう勧告しているが、暖房費の高騰、そして国の節電要請もあり、専門家からは懸念の声が上がっている。
■灯油代が2年前から5割以上の値上がり
暖房の需要期を迎え、全国で灯油価格が上昇している。北海道の今年11月の店頭価格(税込み・18リットル)は2151円。2020年同月に比べ5割以上の値上がりとなった。
宮城県生活協同組合連合会は、村井知事宛てに「都市ガス代金が(前年比)25.5%、電気代が21.5%の上昇となっています。多くの人は物価高で家計を切り詰めざるをえず、その上1缶2000円以上もの灯油代の負担は大変」だとし、冬場を安心して暮らせる灯油の数量確保と価格抑制を要請している。すでに高齢者施設で暖房費を抑える動きが出ており、入居者のヒートショックを心配する声もある。
それに加えて国による「節電要請」だ。12月1日から3月末まで、経産省は無理のない範囲での協力としているが、「予備率3%以上を確保しているものの、厳しい見通し」「大規模な発電所のトラブルが発生した場合、安定供給ができない可能性」「ロシアのウクライナ侵略により、燃料を取り巻く情勢は予断を許さない」と、ここぞとばかりに脅し文句が並んでいる。真面目な高齢者が暖房のスイッチを切ってしまいそうだ。
■WHOは室内を「18度以上」にするよう勧告
ヒートショックは、寒暖の差で血圧が乱高下することによって起こる健康被害のこと。心筋梗塞や不整脈、脳梗塞を引き起こす。暖房の効いた暖かい部屋から、暖房のない脱衣場・浴室やトイレに移動した際などに起こり、入浴時中の失神で溺れて死亡するのは典型的なケース。着替え中に立ちくらみしたり、心臓が締め付けられたりした経験のある人はよほど気を付けなくてはいけない。
WHOは室内の最低温度を「18度以上」にするように注意喚起しているが、高齢者や小児はさらに暖かい温度が推奨されている。国交省の調査でも、室温が18度未満の住宅に住んでいると、総コレステロール値が基準範囲を超える人、あるいは心電図の異常所見のある人が有意に多いことが分かっている。
つまり、どういうことかというと、寒冷な環境では高血圧になりやすい。高血圧の状態が続けば血管の壁が傷つき、その傷にコレステロールが沈着することで動脈硬化が進んでしまう。要するに、光熱費を惜しんで暖房を切ったり、部屋間の温度差が大きくなると、ヒートショックの危険性も高まると考えられるのだ。
生活機器メーカーのリンナイが「冷え・ヒートショック」に関する意識調査を行ったところ、やはり約7割の人が「光熱費が高い」と答えた。アンケートを監修した早坂信哉医師・東京都市大学人間科学部教授がこう言う。
「光熱費高騰で暖房を控え気味にすることが多いかもしれません。入浴前には脱衣所の暖房、浴室のお湯は湯船のふたをしない、入浴前にシャワーを2~3分かけ流しするなどしましょう」
地域別灯油価格(店頭価格/18リットル)(C)日刊ゲンダイ
温暖な県ほど危険性は高い
ヒートショックは寒い地域に偏るかというと、実はそうでもない。東京都健康長寿医療センターが調べた高齢者1万人当たりのCPA(入浴中心肺停止状態)の件数は、最も少ないのが「沖縄県」(1.78件)というのは分かるが、次に少なかったのは「北海道」(2.03件)だった。この北海道を含め、「青森県」や「宮城県」の“寒冷な県”は意外と少ない。
一方、CPAの発生が多い県は、上から「香川県」(7.16件)、「兵庫県」(6.45件)、「滋賀県」(5.83件)と比較的“暖かい県”とされる地域に偏っている。この3県に次いで多いのが、「東京都」(5.83件)だ。
北海道や宮城県に住む人たちのCPAが少ないのは、普段から冬場の寒さ対策を講じている成果とも考えられるが、光熱費の高騰や節電要請がリスク要因になるかもしれない。
高齢者1万人当たりのCPA件数(C)日刊ゲンダイ
医師がすすめる入浴中のポイント
では、入浴中は特にどんなことに注意すればいいのか? 早坂医師がポイントを解説する。
①高血圧や脂質異常症(高脂血症)、糖尿病の人は気を付ける
「これらの病気があると動脈硬化が進み、血圧の急上昇で脳出血を起こすなどのリスクが高まります」
②入浴(前)に水分を取る
「脱水は血液の粘り気を増し、血の塊ができやすくなり、ヒートショックによって起こる心筋梗塞などを引き起こしやすくします」
③家族に声をかけてから風呂に入る
「ヒートショックが怖いのは意識を失いお風呂で溺れてしまうこと。異変に気付いてもらいやすいよう、家族で声をかけ合うようにしましょう」
④かけ湯をしてから湯船に入る
「血圧の急激な上昇を防ぐことができます」
⑤熱い湯船につからない
「体温が上がりすぎて意識障害に陥る可能性があります。冬でもお湯の温度は40度まで。時間は10分程度にしましょう」
冷え性のため、眠れなくなるという人は、就寝の90分前に入浴するようにすると質の良い睡眠ができる。また、炭酸系の入浴剤を使うと末端の細い血管が広がり、血流の改善効果がある。もしお湯がぬるいと感じたら、追いだきで一時的に温度を上げるのもいい。
「睡眠時に靴下をはいて寝るのは、冷え性の方がよくやる間違い。電気毛布などで一晩中温めすぎると、体温が低下せず、眠れなくなる可能性があります。布団を温めたい場合は、自然にぬるくなる湯たんぽがおすすめです」(早坂医師)
持病のある人や高齢者は特に気を付けたい。
11/18(金) 8:00日刊スポーツ
東京都健康長寿医療センター
循環器内科医 原田和昌副院長
季節の変わり目 体調不良をリセット<24>
仕事や行楽でいつものように外出したら、「ハアハア」と息が切れる。脚もなんだかむくんでだるい。このような症状は、一般的に「太りすぎ」や「運動不足」で起こるといわれる。
「息切れやむくみ、疲れやすいといった症状は、心不全でも起こります。特に高血圧を抱えるご高齢の方は起こしやすいので注意しましょう」と、東京都健康長寿医療センターの原田和昌副院長。循環器内科医で、心不全や高血圧の診療・臨床研究を数多く行う。
心不全とは、文字どおり心臓機能が著しく低下した状態だ。心臓の血管が詰まる心筋梗塞や、心臓ポンプの弁が狭くなって血液を送り出せなくなる弁膜症など、さまざまな原因が隠れている。中でも、「息切れ、脚のむくみ、倦怠(けんたい)感」などの症状に関わるのが、「収縮機能が保たれた心不全」(HFpEF/ヘフペフ)。
「心臓は、収縮して血液を送り出し、拡張したときに心臓に血液が流れ込む仕組みがあります。収縮する機能は保たれているのに、心臓の壁が厚くなって硬くなり、うまく拡張できないため血液を送り出せないのが『ヘフペフ』です」
ヘフペフは健康診断では見つかりにくいが、全身の血流が悪くなり、息切れ、倦怠感、脚のむくみといった症状につながる。
「高血圧の状態が長らく続くと、加齢とともにヘフペフのリスクは上がります。秋から冬にかけて寒暖差で血圧変動が起こりやすいため、血圧の管理をしっかりしましょう」と原田副院長は呼び掛ける。
(東京都健康長寿医療センター 原田 和昌医師)
循環器内科 ・重症心不全(拡張型心筋症など) の名医
東京都健康長寿医療センター 副院長
専門: 心不全、冠動脈疾患、高血圧
11/7(月) 17:00夕刊フジ
東京都健康長寿医療センター
荒木厚副院長
【健康寿命 75歳の壁を乗り越えよう】
今回は、要介護の大敵である「メタボによるフレイルリスク」について、東京都健康長寿医療センターの荒木厚副院長に聞いた。
■肥満でフレイルに
秋はつい食べ過ぎて体重が増えやすい。運動不足が重なると肥満領域の体重に突入する。BMI(体格指数=体重kg÷身長mの2乗)で「25」以上は肥満とされ、身長170センチの人なら体重73キロ以上に相当する。
太っていて身体ががっちりしていれば、痩せている人よりも体力がありそうなメージを持つ人もいるだろう。しかし、肥満の人もフレイル(心身の虚弱)に陥りやすく、健康寿命を縮め、要介護リスクを上げてしまう。
「痩せている人は体力が低下しやすいのですが、太っている人も、腰痛や膝痛などで身体活動能力が低下するとフレイルに陥りやすいのです」
こう話す荒木副院長は、東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科の外来で長年、肥満やメタボな患者を数多く診ている。
■予防のギアチェンジ
「肥満や糖尿病などを合併したメタボリックシンドロームの方は減量のために運動習慣と食事制限が欠かせません。ところが、フレイル予防では体重を維持してタンパク質などを含め、食事をしっかりとることが求められます。つまり、予防が相反しているのです」
肥満やメタボは痩せなければいけないが、フレイルは体重が減ってやせてしまうと悪化する。フレイル予防のために食べ続けて運動不足のままでは、当然のことながら、肥満やメタボは解消しにくい。肥満&メタボとフレイルを同時に予防するのはとても難しいのだ。
「肥満やメタボはフレイルリスクがあることを意識して、中年期の早い段階で改善・予防に努めましょう。65歳未満と65~74歳のプレ高齢者の一部が肥満やメタボ対策をしっかり行う。75歳以上はフレイル対策に切り替えることが重要です」
■2型糖尿病治療薬で改善
そもそもメタボは、心筋梗塞や脳梗塞などの心血管疾患を発症するリスクが、そうでない人と比べて約3倍といわれる。フレイルは要介護のリスクを上げるが、脳卒中も認知症に次いで要介護の原因の第2位に位置する。また、中年期の肥満が認知症のリスクを上げるとも報告されている。つまり、メタボを改善するとフレイル、認知症、心血管疾患の3つの要介護リスクを下げることにつながるのだ。
「現在、2型糖尿病の治療薬は、食欲を抑えながら体重も落とすことができるものがあり、血糖値コントロールに取り組みやすくなっています。メタボも解消しやすい。健康診断で異常値を指摘された場合は、放置せずに適切な治療を受けていただきたいと思います」
肥満やメタボを改善して75歳の壁を乗り越える。健康長寿を伸ばしたならば、さらに高齢期の健康維持のためにフレイル予防に励む。それが、生涯続く健康寿命に寄与する。
「2型糖尿病の治療で75歳の壁を乗り越え、現在、90歳以上で元気に過ごされている患者さんはたくさんいます。元気に長生きを実現するため、メタボは放置しないようにしましょう」と荒木副院長はアドバイスする。
■荒木厚(あらき・あつし)
東京都健康長寿医療センター副院長、フレイル予防センター長兼務。
1983年京都大学医学部卒。英国と米国留学などを経て現職。
主な専門分野は、老年医学、糖尿病、病態栄養。
10/25(火) 17:00夕刊フジ
東京都健康長寿医療センター
荒木厚副院長
【健康寿命 75歳の壁を乗り越えよう】
心身の虚弱を意味するフレイルは、要介護の一歩手前、健康長寿の大敵だ。ここでの予防法が老後を大きく左右する。東京都健康長寿医療センターの荒木厚副院長に対処法を詳しく聞いた。
■コロナ自粛で2倍以上
フレイルは、健康な状態と要介護状態の中間に位置する。身体的・精神的・社会的な3つのフレイルが重なることで、要介護のリスクが高くなり、健康寿命を縮めてしまう。(1)身体的なフレイルは筋力が衰え、疲れやすく、歩くことが遅くなり、身体活動量が低下。(2)心理的なフレイルは、認知機能の低下、気分の落ち込みや気力の低下など。(3)社会的フレイルは、閉じ籠もりや孤立などで社会とのつながりが薄くなる状態のことだ。
高齢になるにつれ3つのフレイルに陥りやすいが、コロナ自粛がそれに拍車をかけてしまった。
「毎年、高齢者の6%程度がフレイルに陥っていましたが、昨年は約16%。コロナ自粛に伴い外出機会や社会交流の減少、身体活動の低下、栄養不足などの要素が絡み合い、フレイルに陥りやすい環境でした」
こう話す荒木副院長は、フレイル予防センター長を兼務し、「フレイルサポート医」の研修を行うなど、自治体と連携しながら総合的なフレイル対策に取り組む。
■〝コロナ萎縮〟
3年にも及ぶコロナ自粛で生活が一変したのは老若男女を問わない。特に1年目は運動不足や体重増加に伴う生活習慣病の悪化、不安定な精神状態などを抱えて、体調不良に陥りやすい状況だった。昨年にはワクチン接種がスタートし治療薬も登場した。感染予防を心掛けながらも少しずつ行動範囲を広げ、運動不足解消やストレス発散に取り組んだ人はいる。だが、高齢者は自粛を続けた人が少なくなかったと考えられる。
「高齢者は重症化しやすいことから自粛を進めた国の施策が浸透し、ワクチン接種後も一切外出をしない、社会交流を持たない人がいるのです」
感染拡大のときには、〈高齢者は重症化しやすいので外出を控える〉よう促された。基礎疾患を持つ人も重症化リスクが高いとして、人混みを控える傾向があっただろう。この状況が、ずっと今も続いているのだ。つまり、自粛というより〝コロナ萎縮〟である。
■意識を変えよう
「ご自身が感染して重症化すれば家族に迷惑をかけると考える人もいます。しかし、フレイルが進行して要介護になっても、ご家族に迷惑をかけるでしょう。マスクや手洗の感染予防は行いつつ、ぜひフレイル予防にも取り組んでいただきたいと思います」
高齢者は、3つのフレイルに陥らないように意識することが大切。当たり前のことだが、身体を動かす運動習慣、バランスのよい食事、友人などとのおしゃべりなど社会交流によってフレイル予防を心掛けることがなにより。引きこもった高齢者の外出を促すには、家族のサポートも必要だ。
「65~74歳のプレ高齢者(準高齢者)の方もフレイルに陥るリスクは高いので注意していただきたい。特にメタボな方は、リスクが高いので改善を心掛けましょう」
■荒木厚(あらき・あつし)
東京都健康長寿医療センター副院長、フレイル予防センター長兼務。1983年京都大学医学部卒。英国と米国留学などを経て現職。主な専門分野は、老年医学、糖尿病、病態栄養。
10/15(土) 17:00夕刊フジ
東京都健康長寿医療センター研究所
老化制御研究チーム分子老化制御の石神昭人研究部長
【健康寿命 75歳の壁を乗り越えよう】
健康長寿や病気予防に役立つビタミンCの上手な摂り方について、東京都健康長寿医療センター研究所の石神昭人研究部長に聞いた。
■ポテトチップス&フライドポテト
筋肉量・もち肌維持などの老化防止や、病気予防などによる健康寿命の延伸に大いに役立つビタミンCは、体内で消耗しやすいため、毎日とることを意識しなければならない。ビタミンCを多く含む食材といえば、野菜や果物。旬を迎えた柿などにも、ビタミンCが多く含まれる。
「手頃にとれる食品としては、ポテトチップスがお勧めです。ビタミンCは加熱で減少しますが、ジャガイモのビタミンCは、加熱後も比較的多く含まれるのです。ポテトチップスは、おやつにも、お酒のおつまみにもなるので、お子さんから大人まで活用しやすいでしょう」
フライドポテトにも、ビタミンCは多く含まれている。とはいえ、ポテトチップスもフライドポテトも食べ過ぎは塩分やカロリー取り過ぎにつながるので注意が必要だ。
■レモンサワーやオレンジサワー
ポテトチップスをつまみに飲むと、アルコール代謝でもビタミンCは使われる。飲んだ後のシメのラーメンも、麺類の糖代謝でビタミンCは消費される。なので、酒のサカナのポテトチップスだけでは、ビタミンCの補充は十分といえない。
「レモンやオレンジなど柑橘類を絞って、サワーなどに加えるとビタミンCを補いやすいと思います。ビタミンCは、代謝や活性酸の除去、コラーゲンの産生など、いろいろなところで使用されるので、食材だけでなくサプリメントも活用するとよいでしょう」
石神博士お勧めの摂取量は1日1000ミリグラム。生のレモン100グラム中におよそ100ミリグラムのビタミンCが含まれるが、1日10個レモンを食べるのは無理だろう。ビタミンCのことだけ考えて野菜や果物に偏れば、タンパク質や脂質が不足して逆効果になりかねない。そこで活用したいのがサプリメントだ。
■1日3回が目安 飲料も活用を
「サプリメントは、価格に関わらず活用してみてください。ビタミンCは消費されやすいので、1日3回程度、こまめにとるようにしましょう」
石神博士も、朝晩はサプリメントのビタミンCをとり、昼間の外出中は、ビタミンCの飲料を飲んでいるという。
「もちろん、ビタミンCを含有した食材を意識することは大切ですが、健康寿命を延ばすためには、サプリメントも役立ちます。また、皮膚の健康を維持するために、化粧水も活用していただきたいと思います」
肌のハリなどを維持するコラーゲンは、ビタミンCがないと産生されず、紫外線で発生する活性酸素の抑制にも、ビタミンCが欠かせない。だが、サプリメントなどでビタミンCをとっても、皮膚の表面には届きにくいという。
「皮膚のビタミンC補給には、ビタミンC10%含有の化粧水を活用しましょう。価格に関わらず、ビタミンCの含有量をチェックして選んでみてください。外出前に顔や腕など、紫外線にあたりやすい部分に塗るのがお勧めです」
食材、サプリ、化粧水。男女問わず、老化を退けるため、毎日、ビタミンCを意識しよう。 (取材・安達純子)
■石神昭人(いしがみ・あきひと)
東京都健康長寿医療センター研究所老化制御研究チーム分子老化制御研究部長。1990年東邦大学薬学部大学院卒(薬学博士)。米国国立衛生研究所、米国国立老化研究所客員研究員などを経て、2011年東京都健康長寿医療センター研究所分子老化制御研究副部長、12年東京都立大学教授(兼任)。14年から現職。
東京都健康長寿医療センター研究所
老化制御研究チーム分子老化制御部
石神昭人研究部長
【健康寿命 75歳の壁を乗り越えよう】
ビタミンC不足は、老化現象や病気など全身の老化に関与するという。どれぐらい摂取すればいいのか。東京都健康長寿医療センター研究所の石神昭人研究部長=写真=に聞いた。
■遺伝子不調修復できず
年を重ねると顔にシミやシワが生じやすくなる。細胞が傷つき、肌の組織が変性した結果だ。こうした老化にビタミンC不足が関わり、さらに全身の老化にも関与することがわかってきた。
「私たちは皮膚の表皮とビタミンCの研究を行っています。ビタミンCは、強い紫外線の細胞へのダメージを防ぐことができます。その理由は活性酸素の除去や炎症の抑制だけでなく、細胞の傷ついた遺伝子の修復にも関わっていたのです」
紫外線を浴びた皮膚では、活性酸素が一気に増える。活性酸素は細胞や組織を傷つけるため、シワ、シミ、動脈硬化、がんなど、さまざまな老化現象や病気に関わる。活性酸素の動きを抑制するのがビタミンCなどの抗酸化物質。特にビタミンCは強い抗酸化作用で知られるが、傷ついた細胞のケアでも欠かせない。
■細胞老化&がん化も
「遺伝情報が正常に転写されないと、細胞はダメージを受けて、老化やがんなどの病気につながります。転写に不具合が生じ、酵素(Tet)が正常に戻すときに、ビタミンCが必要不可欠なのです」
ビタミンCがないと、遺伝情報の転写に不具合が起きても、酵素が働くことができず修復できない。結果として、細胞の老化は進み、細胞のがん化など病気につながる。しかも、寿命が短くなる可能性もあるという。
「ビタミンCが不足すると寿命も縮まることは、私たちの研究で明らかにしています。たとえば、通常のマウスの寿命は24カ月ですが、ビタミンC不足のマウスの寿命は6カ月でした」
ビタミンCが足りないだけで、通常の食事や運動の機会が与えられても、マウスは寿命を全うすることができなかった。体内でビタミンCを合成できない人間も、ビタミンCを意識してとることが重要になる。
■1日1000mg目安
「厚労省が日本人の食事摂取基準で推奨しているビタミンC100mg/日では健康長寿のためには十分とはいえません。ビタミンC不足で起こる壊血病予防に役立つレベルといえます」
壊血病はビタミンC不足が続くことで、粘膜や歯肉などが出血しやすくなるなど、さまざまな症状を引き起こす。1日100mgのビタミンCは、壊血病予防には役立つが、老化やがんなどの病気予防では、さらにとることが必要だという。
「私は健康長寿のために、ビタミンCを1日1000mgは摂取していただきたいと思っています。食べ物だけでは難しいので、サプリメントやビタミンC含有の飲料なども活用するとよいでしょう」
ビタミンCは水溶性なので、余分なものは汗や尿から排泄される。また、全身のコラーゲンや骨などの生成、糖質などの代謝、細胞の遺伝子修復、さらには、体内で爆発的に増える活性酸素の処理で、ビタミンCは常に多量に使われている。
「野菜や果物を食べていても、ビタミンCは不足しがちなのです。それを認識していただきたいと思います」
次週は、ビタミンCの上手な摂り方を紹介する。
■石神昭人(いしがみ・あきひと) 東京都健康長寿医療センター研究所老化制御研究チーム分子老化制御研究部長。1990年東邦大学薬学部大学院卒(薬学博士)。米国国立衛生研究所、米国国立老化研究所客員研究員などを経て、2011年東京都健康長寿医療センター研究所分子老化制御研究副部長、12年東京都立大学教授(兼任)。14年から現職。