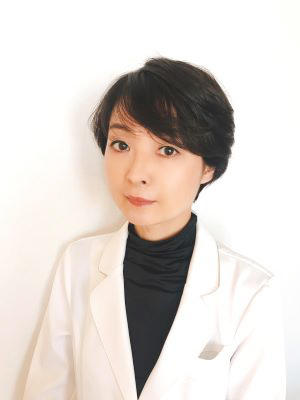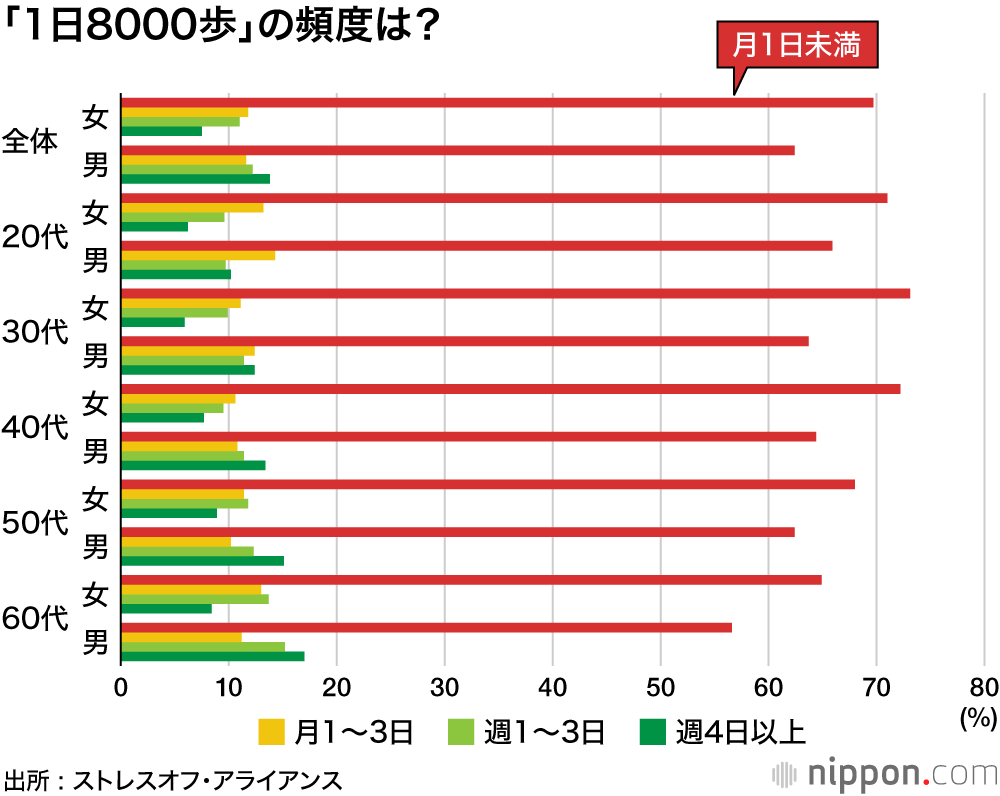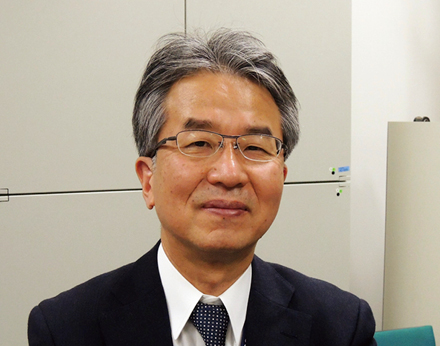9/26(月) 7:01FNNプライムオンライン
主食の“重ね食べ”という言葉をご存じだろうか?
“ラーメン”と“ごはん”、“うどん”と“おにぎり”といったように、炭水化物を主とするご飯、麺、パンなどを2品以上、同時に食べることをいう。この主食の重ね食べする人は、しない人と比べて歯周病を発症する人が1.2倍多いことが研究でわかった。
東京都健康長寿医療センター研究所が調査したもので、2017年に福岡県のバス会社に勤める男性バス運転手540人(平均年齢47.9歳)を対象に実施。
研究チームは「複数の主食を同時に食べること」を重ね食べと定義し、540人のうち、80人(全体の14.8%)が主食の重ね食べをしていた。そして、重ね食べするグループとしないグループの歯を比較したところ、歯周病とされる4mm以上の歯周ポケットを持つ歯の数が重ね食べするグループのほうが1.2倍多かったのだ。
また、重ね食べする人は、1日2回以上のブラッシングの頻度と歯間ブラシの使用頻度が、重ね食べしない人に比べて低いことがわかった。
主食の重ね食べと歯周病の関連は明らかとなっていなかった
「重ね食べが肥満になる」といったリスクは知られているようにも思うが、それだけではなく、歯周病にも関わっているようなのだ。では、なぜ重ね食べすると、歯周病になりやすいのか? 調査を行った東京都健康長寿医療センター研究所の岩崎正則研究副部長に詳しく話を聞いてみた。
――これまでにわかっている重ね食べのリスクにはどんなものがあった?
2015年大阪版健康・栄養調査の結果では主食の重ね食べの頻度が高いことと肥満の関連が報告されています。疾病のリスクについては分かりません。
なお、炭水化物は、主にエネルギー源として利用される大切な栄養素ですが、その多量摂取は肥満、糖尿病などのリスクとなること、また種々の炎症性疾患による死亡リスクが上昇することが示されています。
――ではなぜ今回、重ね食べの歯周病リスクを調査することにした?
野菜類やビタミン類に着目した栄養素・食事摂取状況と歯周病の関連はこれまでに研究されてきていますが、炭水化物を多量に摂ることとなる主食の重ね食べと歯周病の関連は明らかとなっていません。
私たちは一企業で行われる定期健康診断にあわせて歯科検診、食事調査、質問紙調査を実施する機会を得ました。そこで今回、男性労働者を対象に、主食の重ね食べの状況と歯周病の関連を明らかにすることを目的とする研究を実施しました。
――例えば、ラーメンをたくさん食べるよりも、ラーメンとごはんの重ね食べのほうがリスクは高いの?
研究の中で調べていないため、分かりません。
対策はセルフケア、プロフェッショナルケア、定期健診、禁煙
――重ね食べしていたグループが歯周病の割合が高かった理由は?
炭水化物に含まれる糖質は、その多量摂取が食後の高血糖状態を引き起こします。食後の高血糖状態が繰り返されると歯ぐきの炎症や歯を支える骨の吸収につながる物質が多く生産されます。そうしたことが関連していると考えられます。
――岩崎さんは、歯が多く残っている人ほど死亡リスクが低いという論文も過去に発表されている。具体的にどれくらい死亡リスクは低い?
ご自身の歯をきちんと維持されていた群は、歯が少なくなる群と比較して、死亡リスクが約半分でした。
――今後も重ね食べと歯周病についての研究はしていく?
具体的な計画はありませんが、今回対象となっている研究は現在のところ学会発表したレベルでしかなく批判的な吟味を受けていません。只今、論文化の作業中です。
――最後に歯周病にならないためのアドバイスをお願いしたい。
セルフケア(歯磨きなど)とプロフェッショナルケア(歯科医師・歯科衛生士によるケア)、禁煙などの生活習慣の改善、そして、かかりつけ歯科医を持ち定期検診を受けることが重要かと思います。
なお取材では、「重ね食べの中でどんな組み合わせが歯周病になりやすい?」「主食1つでおかずをたくさん食べるのは歯周病になりやすい?」なども質問したが、現段階では調査していないためわからないとのことだった。いずれにせよ、重ね食べは肥満だけでなく、歯周病のリスクもありそうだ。日常的に重ね食べしている人は気を付けたほうがよさそうだ。