Why a World State is Inevitable
ALEXANDER WENDT
昔、カントが、永遠の平和へとかいう論文で、
で、論文の最初のほうでは、方法論についてグダグダ述べる。アリストテレスはものがかくある理由として4通りの説明方式を用意した。この机を説明するのに、何から出来ているか(物質因)、誰が作ったか(作用因)どのような設計か(形相因)何のために出来たか(目的因)がある。いままでの国際関係論の説明には目的因による説明を意図的に排除してきたが、終局的収束相がない説明方式は不完全である、と指摘する。相互承認への対立・闘争を通じて、終局的には世界規模の国家が形成されるというのである。
自己とは他ならない自己であるが、その他者と異なる自己、ということを前提に、身の安全のためにお互いがお互いを承認していく過程でお互いが共通のルールで自己規制しながら「われわれ」という自己意識を形成していく。現代社会は核兵器や弾道ミサイルの恐怖によって競争よりもむしろ協力への方向性を示している。
ホッブスの想定するような全くの混沌状態は承認のない世界で不安定だから、各国は協約を結んでお互いの権利と義務を認めるようなロック的世界になるが、そうした世界でもいざ戦争となれば人民は犠牲となるから、各国は紛争を平和的に解決する国際社会を形成する。もっともこの国際社会でもならず者国家が出現があり得るから安定しているとは言えない。そこで、ひとりはみんなのために、みんなはひとりのためにという積極的相互援助を義務とするような、集団的自衛体制で、「われわれ」がならず者を制裁するような体制が合理的である。ここで、大国は別段小国への援助をする動機に欠けるようにも思えるが、しかし、そうしていれば、小国各国が逆に協力しはじめ大国の存亡を脅かすから、、むしろ、そうした小国を承認して体制に組み込んだほうが合理的であり、終局的には上記世界規模の国家体制が樹立される、というのである。
これは、歴史的にこうだ、とかいつこうなる、というわけではなくて、これが論理的なシナリオである、というのである。
武力の恐怖による絶えざる闘争というリアリストのシナリオよりも明るい未来だけども、やはり、ツメが甘いような気もする。あるいは、おれの理解力、ないし、想像力が不足しているのかもしれん。
もっとも、カントは、恒久平和への構想で
、
とかいって、日本ではそれをマジで信じちゃっている人がいるが、そんな非現実的なことはいっていない。むしろ熾烈な武力競争が逆に協力しあう関係を形成する、という点で、現実的ではある。
また、日本では集団的自衛への参加を戦争の泥沼への一歩のようにいわれることがあるが、、それはむしろ平和的国際社会の形成には必須である、と論じている点が注目に値する。その意思決定方式に問題ははらんでいる。しかし、国際的な「われわれ」から島国的な「われわれ」が取り残されないためにも、そして、平和的国際社会の実現という観点からもっと、この問題を論じる必要があるのである。
また、この観点からすれば、安倍・麻生のリムランド同盟構想もそのレトリックは別にして、真剣に考慮されてしかるべきであろう。
中国の無法に眼をつむる世界の傾向を肝に銘じて粛々と日本も地固めしておくべきだ。
ALEXANDER WENDT
昔、カントが、永遠の平和へとかいう論文で、
永遠の平和に進んでいくための第2確定条項とかいって世界連邦構想をした。世界連邦じゃないけど、世界の国々は世界的規模の一つの国家になるんだ、というのが上記論文の構図。彼の言う国家とは、構成員(=各国)が協働し、正当なる合同的力の行使を独占する組織である。
国際法は自由国家の連邦制を基本にして創設すること
で、論文の最初のほうでは、方法論についてグダグダ述べる。アリストテレスはものがかくある理由として4通りの説明方式を用意した。この机を説明するのに、何から出来ているか(物質因)、誰が作ったか(作用因)どのような設計か(形相因)何のために出来たか(目的因)がある。いままでの国際関係論の説明には目的因による説明を意図的に排除してきたが、終局的収束相がない説明方式は不完全である、と指摘する。相互承認への対立・闘争を通じて、終局的には世界規模の国家が形成されるというのである。
自己とは他ならない自己であるが、その他者と異なる自己、ということを前提に、身の安全のためにお互いがお互いを承認していく過程でお互いが共通のルールで自己規制しながら「われわれ」という自己意識を形成していく。現代社会は核兵器や弾道ミサイルの恐怖によって競争よりもむしろ協力への方向性を示している。
ホッブスの想定するような全くの混沌状態は承認のない世界で不安定だから、各国は協約を結んでお互いの権利と義務を認めるようなロック的世界になるが、そうした世界でもいざ戦争となれば人民は犠牲となるから、各国は紛争を平和的に解決する国際社会を形成する。もっともこの国際社会でもならず者国家が出現があり得るから安定しているとは言えない。そこで、ひとりはみんなのために、みんなはひとりのためにという積極的相互援助を義務とするような、集団的自衛体制で、「われわれ」がならず者を制裁するような体制が合理的である。ここで、大国は別段小国への援助をする動機に欠けるようにも思えるが、しかし、そうしていれば、小国各国が逆に協力しはじめ大国の存亡を脅かすから、、むしろ、そうした小国を承認して体制に組み込んだほうが合理的であり、終局的には上記世界規模の国家体制が樹立される、というのである。
これは、歴史的にこうだ、とかいつこうなる、というわけではなくて、これが論理的なシナリオである、というのである。
武力の恐怖による絶えざる闘争というリアリストのシナリオよりも明るい未来だけども、やはり、ツメが甘いような気もする。あるいは、おれの理解力、ないし、想像力が不足しているのかもしれん。
もっとも、カントは、恒久平和への構想で
、
「常備軍は段階的に完全撤去すること」
とかいって、日本ではそれをマジで信じちゃっている人がいるが、そんな非現実的なことはいっていない。むしろ熾烈な武力競争が逆に協力しあう関係を形成する、という点で、現実的ではある。
また、日本では集団的自衛への参加を戦争の泥沼への一歩のようにいわれることがあるが、、それはむしろ平和的国際社会の形成には必須である、と論じている点が注目に値する。その意思決定方式に問題ははらんでいる。しかし、国際的な「われわれ」から島国的な「われわれ」が取り残されないためにも、そして、平和的国際社会の実現という観点からもっと、この問題を論じる必要があるのである。
また、この観点からすれば、安倍・麻生のリムランド同盟構想もそのレトリックは別にして、真剣に考慮されてしかるべきであろう。
中国の無法に眼をつむる世界の傾向を肝に銘じて粛々と日本も地固めしておくべきだ。











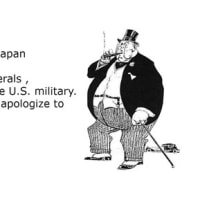
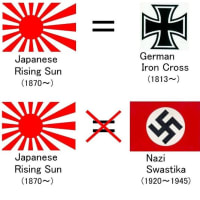
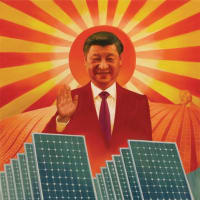
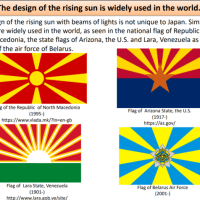




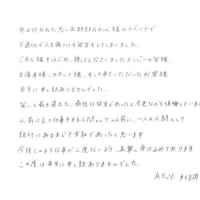
仮に常備軍がなくなっても、警察とか海上警備隊みたいな暴力装置は残るんですよね。
上の文章のような哲学的考察ではなくて、ほんとに素朴な疑問(笑)なんですが、そういう暴力装置があればやはり“戦争”は残るのでは、と思ってしまう。国境付近のいざこざなどを原因として。 だって、ごくごく単純に考えても、ショットガンや狙撃銃や高度な通信網を供えた今の警察とかって、18世紀くらいの軍隊並みに“強い”んじゃないですかね? 槍や弓の時代でも戦争が起きたんだから、いわゆる軍隊(アメリカ軍とか自衛隊とか)を無くしてもそれだけでは戦争の可能性はなくならないと思います。
日本で反自衛隊をマジで叫んでいるのは「あんなこといいな、できたらいいな」の世界の住人でしょうね。