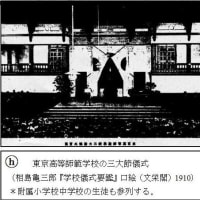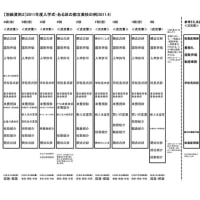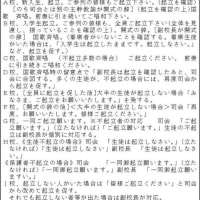◎「片言隻句を捉へて反逆者とは何事」
尾崎士郎『天皇機関説』(文藝春秋新社、1951)から、「凡例」を紹介している。本日は、その二回目。文中の(前略)(下略)は、原文にあったものである。
一、去年(二十五年)の十一月、銀座裏の旗亭で、機関説問題に関係のある学者、政治家、法律家の小集が行はれ、実情について親しく聴取する機会を得た。私的な集合としては実に内容の充実した貴重な時間であつたことを特に銘記しておきたい、出席を賜つた方々の名前を記録して謝意を表したいと思ふ。(順不同)小原直〈オハラ・ナオシ〉、金森徳次郎、大内兵衛〈ヒョウエ〉、宮澤俊義、美濃部亮吉〈ミノベ・リョウキチ〉、田中次郎、戸澤重雄、馬場義続〈ヨシツグ〉。(以上八氏)
その後、数回にわたつて、私はこれ等の諸氏を訪問し、幾度び〈イクタビ〉となくノートをとつた。就中、時代環境を認識するためにもつとも重要な素材となつたものは宮澤博士から貸与された天皇機関説問題についての報道記事(新聞雑誌)の切抜である。これは五つの綴込に分れてゐる浩瀚〈コウカン〉な内容をもつもので、私はこれを一枚一枚はぐし〔ママ〕ながら読みすすんでゆくうちに動き去る時代の波が大きなうねりをうって色彩豊かに逆巻き流れてゐるのをまざまざと見る思ひがした。文学者の心象に映じ来るものは現実であって歴史的事実ではない。此処に一例をとつてみれば宮澤博士の集録されたものは「朝日」「毎日」「読売」の記事を主体としたものであるが、当時の情況から忖度すれば、すべての新聞の発表方法は大同小異であつたらうと思はれる。昭和十年〔1935〕から以降十年間の日本が、いかに「天皇機関説」によつて動いてゐたかといふことを証拠立てるために、その年代的変化を、初期の新聞記事によつて示すと、その進展はおよそ三つの段階に分れる。その火ぶたを切つたものは、「片言隻句〈ヘンゲンセキク〉を捉へて反逆者とは何事」(二月二十六日)と題する朝日新聞の記事で所謂、天皇機関説問題は此処に端を発する。これは貴族院においての最初の機関説攻撃、菊池武夫男爵の質問演説中、美濃部博士の学説及び著書を引用して博士を反逆者、謀反者、学匪と呼んだことに関し、一身上の弁明をなす必要ありとして、二十五日貴族院本会議の席上において行つた弁明である。この演説が、いかに理路整然、満堂の聘衆を感激させたかといふことは、特に慎重を期した次の博士の言葉を引用した新聞記事によつても明白であらう。
「(前略)菊池男は私の学説は議会が天皇の命に従はぬと書いてゐると論難されたやうであるが、これは同男が私の書物を熟読されないがための誤解である。立法、予算の協賛、上奏、建議、質問等の議会の独立の権限は、これが君命によつて行ふものではない。元老院、枢密院は天皇の機関であるが衆議院は天皇の機関ではない。伊藤〔博文〕公の憲法義解においても、「議院は全国の公機を代表す」と認めてゐる。以上は法律学において誰しも認めるところであり私も三十年来唱へてゐる一貫した学説である。云々」――と、推理整然、所信を述ぶれば満場粛としてこれに聴き入る。約一時間にわたり雄弁を振ひ降壇すれば貴族院にはめづらしく拍手起る。(朝日新聞)
同日の毎日新聞(当時の「日日新聞」)の論説は博士に対して満腔の敬意と同情を寄せ、大略次のごとく説明してゐる。「二十五日の貴族院における美濃部博士の、「一身上の弁明」は一般に異常なる刺戟をあたへた。博士の意見には三十年来の歴史がある。その博士の意見が、最近議会の問題となり、一面には一方の権威と認められてゐる学界の長老が、自ら「耐へがたい侮辱」であると感ずるやうな非難を浴びるにいたつたといふことは、まことに悲しむべきことと言はねばならない。(下略)〈230~232ページ〉【以下、次回】