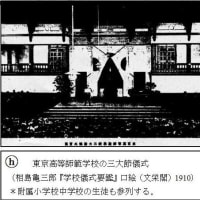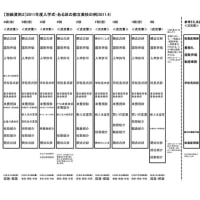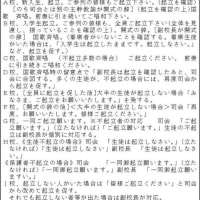◎尾崎士郎の小説『天皇機関説』(1951)について
ここのところ、ずっと、「天皇機関説」について関心を持ち続けている。
戦後になって、最初に、この事件の重要性に気づいたのは、おそらく作家の尾崎士郎(1898~1964)であろう。尾崎士郎は、1951年(昭和26)という早い段階で、『天皇機関説』(文藝春秋新社、1951年10月12日)を発表している。これは、基本的に「小説」だが、周到な調査研究をおこなった跡がある。「小説」だけに、その時代の雰囲気をよく再現している。
尾崎士郎の『天皇機関説』の末尾には、小説には珍しく、「凡例」というものが付いている。著者みずから、この本が成立した事情について、かなり詳しく解説した文章である(229~237ページ)。同書を読まれる方は、まず、この「凡例」から読まれるとよいだろう。
当ブログでは、この「凡例」を、このあと何回かに分けて紹介してみたと思う。
凡 例
一、昭和十年から二十年にわたる十年間は日本歴史の上に民族の悲劇を決定的な方向にみちびいた時代である。われわれの民族が急速度に没落していつた動機と原因についてはこれを検討するための雑多な立場と方法があるであらう。これを一つの政治的失敗として片づける人たちにとつては軍閥の跳梁とか、政治力の衰退といふやうな表面的な現象だけで処理のつく問題である。しかし、歴史の冷厳の事実の上に示された大きな誤謬は、民族それ自体の宿命であつて、これに一応の政治的解釈を加へることによつて処理のつく問題ではない。誤謬は因果の法則によつてあたらしい方向へ展開してゆく。私はこの歴史的悲劇に文学者としての純粋な感性によつて直面しようと試みた。この動蕩〈ドウトウ〉する時代の動きを把握するために「天皇機関説」に重点を置いたことは此処に昭和の動乱を認識するための、もつとも大きな鍵があると信じたからである。素より、美濃部達吉博士の伝記を書くことが目的でないことはいふまでもない。況んや〈イワンヤ〉、憲法論において対立する上杉〔慎吉〕博士と美濃部博士の論争について批判を加へるがごときは私の任ではない。
一、第一部、第二部、共に天皇の言葉に対してだけ特定な註釈が加へられてゐるのは事実の正確を期するがためであることはもちろんであるが、故人の遺言によって門外不出の嫌とされた本庄〔繁〕侍従武官長の日記を私が無断で借用したことに対する責任を明かにするがためである。このやうな事実の究明については既に小説の限界をはなれてゐるとも言へよう。当時の宮廷内部の事情について私はまつたく知るところがないので小説的空想を加へる余地がなかつた。これが幸ひにして法律問題にもならず、第一部が発表された後、本庄大将未亡人から人を介して厚意にみちた助言を寄せられたことは作者のふかく感謝するところである。〈229~230ページ〉【以下、次回】