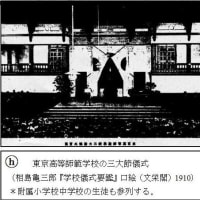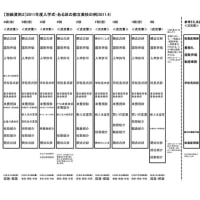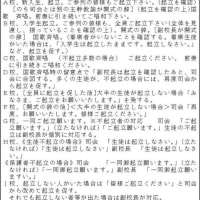◎山本悌二郎の発起により有志議員六十余名が集合
尾崎士郎『天皇機関説』(文藝春秋新社、1951)から、「凡例」を紹介している。本日は、その三回目。文中の(前略)(下略)は、原文にあったものである。
この報道によつて衆議は喧々轟々として湧き返つた。賛否両論の分岐するところは、わが國體は万古〈バンコ〉比類なき万世一系の國體である、といふ信念に立つ意見と、冷徹なる憲法説との対立である。この両者の立場にいささかの関連がないと同じ意味において、機関説の論者が一国民としての信念において千古不滅の國體を信ずることと矛盾するところはない、――といふ考へ方が当時の輿論を支配してゐた。これとは別の立場から、同月二十七日、徳富蘇峰翁は同じ新聞の「日日だより」において、「老書生の陳言〈チンゲン〉」と題して、次のやうな言説を発表してゐる。「(前略)記者〔蘇峰〕は未だ美濃部博士の法政に対する著作を読まない。故に今ここにその所説については語らない。唯、世間が「天皇機関説」を公問題とするに際し、操觚者〈ソウコシャ〉の一人として、その所信だけは明白にすべき義務があると信ずるが故に敢て一言する。記者はいかなる意味においてすらも天皇機関説の味方ではない。苟も〈イヤシクモ〉日本国史の一頁にても読みたらんには、かかる意見に与する〈クミスル〉ことは絶対に不可能だ。その解釈は姑らく〈イバラク〉置き、第一, 天皇機関説などといふ、その言葉さへも、記者はこれを口にすることを日本臣民として謹慎すべきものと信じてゐる。(下略)
大新聞の同じ政治面に、日を隔てずして相〈アイ〉対する社説的言説が発表されたことは、当時の輿論の混沌たる動きを示すものである。それから約一年間、機関説論議は新聞報道面の上で次第に政治的色彩を帯びてくる。江藤〔源九郎〕代議士による告発から転じて両院有志の会合となり、宮田、山岡、山本(悌)、大竹、等、両院各派の代議土が集合して、超党派的立場から、徹底的糾明と排撃を申合せた。翌年〔1936〕に到つて、陸軍部内から起つた反対運動の猛烈さと比べると当時の軍の態度は、緩慢であり、曖昧模糊としてゐた。軍としては寧ろ政党にひきづられて動いたかたちで、三月四日、新聞に発表された首脳部の綜合的意見は「純粋な憲法論として果して美濃部節が正しいかどうかはおのづから他に検討するものがあるであらうが、陸軍としては「天皇機関説」なる用語そのものが妥当でないと思ふ。美濃部博士が単に憲法学者として一つの学説を説いてゐるなら多く意とするに足らぬ。唯これを議会において堂々と説明することになると軍隊教育上面白くない」といふ程度の消極説に一致してゐた。上院下院を通じて、もつとも強硬な反撃的態度を示したのは政友会であつて、三月五日、顧問、山本悌二郎の発起により鈴木〔喜三郎〕総裁以下、久原、川村、宮田、岡、菅原の各顧問をはじめ、主だつた有志議員六十余名が芝三縁亭〈サンエンテイ〉に集合して全員一致、政府の責任としてこの問題を追究し、本会議で政府の処理を促すことに決定した。〈232~234ページ〉【以下、次回】
ここに、山本悌二郎という名前が出てくる。その当時、台北高等商業学校の講師だった成宮嘉造(なるみや・かぞう)は、衆議院議員・山本悌二郎によって「機関説論者」とされたために、職を失うことになった。当ブログ、2024年4月14日の記事「日本憲法概論と云う書物かあります(山本悌二郎)」を参照されたい。