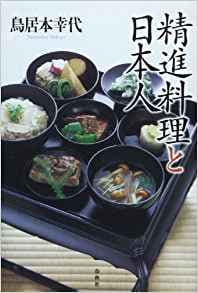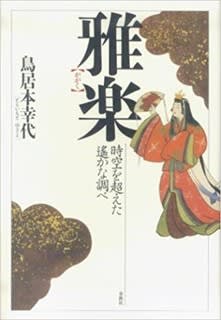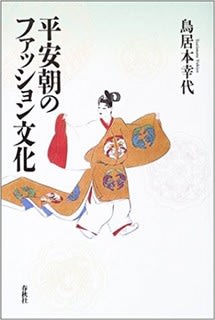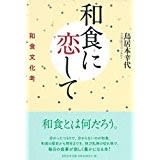「終活」とは、死にゆく準備の事、
という理解で良いのでしょうか?
もしもの時 人は自分で自分に対処する事ができません。
私たちは 自分の死に際して 周囲の人を巻き込む必要があります。
たとえそれが嫌だとしても、必要なのです。
時間をかければ 人は骨になるようですが、
それでは時間がかかり過ぎ。
少なくとも、誰かに火葬場に持って行ってもらい、
火葬場の職員に 荼毘に付してもらうしかなさそうです。
ならば、始めから そういうものだという事で
周囲の人に 了解しておいてもらう方が良いのではないでしょうか。
ならば、縁者には 前もって
「よろしくね」と言っておくべきではないですか?
「了解」には 「暗黙の了解」というのもありますが、
後に残される人のためには、
ある程度の<覚悟>は 持っていてもらった方が
縁者にとっての心の負担は 軽くなるのではないでしょうか?
なぁんて、深く考えもせずに重い事を書いたのは、
お彼岸だからかもしれません。
お盆やお彼岸が近づくと、
お墓だとか 終活だとかの話題が増えます。
「迷惑をかけたくない」という話を聞くと、そのたびに、
「迷惑、かけたっていいにのなぁ」と思う座敷ネズミです。
お彼岸に入る前、16日の読売新聞の夕刊に
垣谷 美雨(かきや・みう)という小説家のお話が出ていました。
その中で、柿谷さんは
「健康のために スポーツジムにも通っています。
難しいかもしれないけど、死ぬまで元気に仕事をして、
たまに旅行を楽しんで、
ころっと亡くなるのが理想ですね。」
そこを読んだ時の、私の感想。
ああ!!!!! その通りだ!(笑)
もっとも、私は「コロリ」と死ぬのは周囲の迷惑だから、
少しは寝付いてからにして、
と思っているのですが(笑)、
死ぬまでは なるべく元氣でいたい。
そして 何かしら 仕事をしていたい。
いえ、仕事といっても、何でもいいんです。
庭の草取りだとか、食事作りだとか、お掃除だとか、窓拭きだとか。
あら、今と同じねぇ。
そして、たまには旅行を楽しむ。 いいねぇ。
あ、ジムに通ってもいいですか?(笑)
お彼岸の入りの日の朝刊には、
前川清さんのお話が載っていました。
「痛いのは嫌だから、苦痛を和らげる薬は使ってほしい。
でも それ以上のことはしなくていい。
直前まで仕事をして、人と関わっていたい。」
この方の仕事は、歌手です。
「歌手という仕事さえもできない状態になった時は、
人生が終わる時」
とおっしゃっています。
<仕事>というのは、<収入>とは別に考えても、
人が生きるための<糧>であるように思います。
そこに自分自身の<価値>や <自分らしさ>や <生きる張り合い>
を見出す事ができるからです。
そして そこに <人との関わり>が生まれるからです。
前川さんがおっしゃった<人と関わる>という事は、
キーポイントのひとつですね。
人は人を支え、人に支えられて、
初めて 人であり続けることができます。
「生きるって、人と関わることなんだと 僕は感じました。」
「外とのつながりが何にもなくなってしまったら、
その状態で何年も生きたいとは思わないだろうな。」
そうですね。
そう思います。
私、<人が好き>ですから。
人と関わって 生きていきたいですから。
QOL【quality of life】(人生の質、生活の質)
という言葉があります。
お彼岸ですので、QOD【Quality of Dying and Death】、
死生観についても ちょっと書いてみました。
前川清さんの記事と同じページに
社会学者の言葉として、
QODについて、
「死の瞬間だけでなく、死を意識するようになってからの生き方や
悲しみからの遺族の立ち直りまでも含めた一連の死のプロセス」
の質を高めることが大切、
とあります。
死生観も人それぞれ。
とりあえず私は 終活の第一歩として
身の周りの整理整頓に取り掛からなければならないのですが。。。。。。

雨が降って肌寒いお中日です。
青い空の去年の画像を置いときます。



 可愛い。
可愛い。


 可愛い。
可愛い。