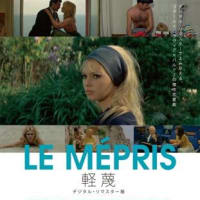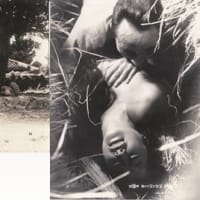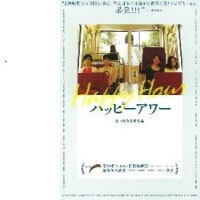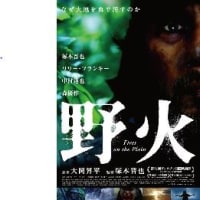「僕たちは希望という名の列車に乗った」 2018年 ドイツ

監督 ラース・クラウメ
出演 レオナルド・シャイヒャー トム・グラメンツ
ロナルト・ツェアフェルト ヘルマン・レムケ
ブルクハルト・クラウスナー レナ・クレンケ
イシャイア・ミヒャルスキ
ストーリー
まだベルリンの壁が建設される前の冷戦が続く1956年の東ドイツ。
スターリンシュタット(現在のアイゼンヒュッテンシュタット)にあるエリート高校に通い、青春を謳歌していたテオとクルト。
ある日、西ベルリンを訪れ、映画館に入った2人は、ニュース映像でハンガリーの民衆蜂起を知る。
市民に多くの犠牲者が出たことに心を痛めた彼らはクラスメイトに呼びかけ、授業中に2分間の黙とうを敢行する。
自由を求めるハンガリー市民に共感した彼らのささやかな行動だったが、ハンガリーと同じくソ連の影響下にある東ドイツでは、たちまち社会主義国家への反逆とみなされ、政府が調査に乗り出すほどの大問題へと発展してしまう。
当局の調査が入り、人民教育相自ら生徒たちに一週間以内に首謀者を明かすよう宣告。
従わない者は全員退学と宣告されてしまうのだった。
大切な仲間を密告してエリート街道を進むか、信念を貫き進学を諦めて労働者として生きるか、生徒たちは人生を左右する大きな決断を迫られる。
寸評
僕たちは言論の自由と思想の自由を当然のこととして受け止めているが、それを維持することは実は大変なのだと思わされるし、民族が一つの国家で過ごせることは幸せなことなのだと感じさせる映画だ。
日本も先の大戦中には言論統制を受けていたのだし、間違えば北海道が占領されて民族が分断されていたかもしれないのだ。
30年目を迎えた天安門事件も思い出す。
1956年のベルリンではまだ壁は出来ておらず、検閲が厳しいものの東西ベルリンは行き来が出来ていたようだ。
テオとクルトは西ベルリンに行きハンガリー暴動のニュース映画を目にする。
ハンガリー暴動は1956年にソ連のスターリン批判後にハンガリーで起こった自由化を求める暴動である。
ソ連軍によって弾圧され、指導者ナジ=イムレは処刑され、この動乱で数千人が死に、20万人が難民となって亡命したと言われている。
彼等は若者の純真さで犠牲者に哀悼の気持ちから黙とうをささげるが、それが当局から国家への反逆だとみなされ、首謀者を追及される羽目になり、かれらの動揺と対応ぶりが描かれていくのだが、同時に父親たちの闇の部分もあぶりだされていく。
それを見るとドイツ国民にとって一度はヒトラーを指示したことがあると言う事実の呪縛があるのだなと思わされる。
テオは労働者の家庭で育ち、父親は製鋼所で働いている。
国民教育大臣と面識があった父親は、息子を守るために直談判に行くが、彼らのやりとりからは、父親が1953年の市民暴動に関わっている不満を抱えた労働者とみなされていることがわかる。
1953年のことと何度か語られるが、それは1953年6月に冷戦時代の東ドイツの東ベルリンで、ソ連のスターリンの死をきっかけに自由を求めて起こった市民暴動のことだ。
ソ連軍が出動し鎮圧したが、1400人ほどが投獄され、約20人が処刑されたと言われている。
父親は体制に反抗する息子の気持ちがわかるが、家族の悲願である進学の機会を失ってほしくないという気持ちがある。
やがてテオは、父親が劣悪な環境で酷使されていることを知る。
西へ一緒に行こうとテオは言うが、父親は故郷を捨てることが出来ない。
僕はこの父親の気持ちは分かる。
クルトの父親は市議会議長で、息子が西ベルリンに墓参りに行くことを快く思っていない。
そこに眠るのは母方の祖父で、彼がナチスの武装親衛隊だったからだなのだが、彼はそのことで母親まで蔑視している。
彼にはナチスという悪との間に一線を引くことで自己を正当化しようとする姿勢が垣間見える。
そんな家族の関係はやがて崩れていくのだが、この家族関係は映画としてはよくある関係だ。
母親の子供への強い愛を感じる。
最後に親子が固い握手を見せ父親の愛も感じさせるが、その後父親の母親への態度は変わったのだろうかと思った。
エリックは体制寄りで、級友たちと距離を置いているところがある。
父親はこの世になく、母親は聖職者と再婚している。
亡くなった父親はドイツ共産党の準軍事組織RFB(赤色戦線戦士同盟)の一員だったので、エリックにとっては英雄でもあるその父親を心の拠り所にしている。
だが、冷酷な郡学務局員からある真実を告げられ、自分を見失い暴走していく。
彼が一番の犠牲者かもしれない。
そして取り調べるソ連側の人間もかつてナチスによって拷問を受けた経験を持っている。
彼等にとってはドイツ人は全てナチの生き残りだと見えたのだろうと想像させる。
子供たちとその親たちが、切迫した状況のなかで過去と向き合い、それぞれがそれぞれの行動を選択していく様は、まさに「過去の克服」だったのだと感じる。
子供たちの反逆だけだったら薄っぺらな作品になっていたと思うが、父親たち過去を描くことで考えさせられる作品に昇華している。
僕はテオが可愛がっている弟たちと別れていくシーンが泣けた。
いつの時代にあっても肉親との別れはつらいものがある。