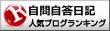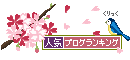こんばんはー!!
今日は吹奏楽部でよく聞く「ハイッ!!」ていう返事について書いてみようかと思います。
思い返せば、自分にもあったあんな頃やこんな頃…(≧∀≦)
燃える吹奏楽キッズだった頃には、疑いもなく威勢のいい「ハイッ!!」をかましていた気がします。
で、キミマロ風に、あれから30年…
気がつけば今も脈々と全国でこういう返事が受け継がれてますよねー。
上位の学校のキレのある「ハイッ!」なんかは聞いててもスカッと気持ち良かったり。
でも時々「盲目的に」「ハイッ!」を連発してる学校(あるいは団体)も見かけますよねー。
するってーと、「普通の」音楽家&演奏家である外部講師の中には、何だか軍隊みたいで不気味だな…と嫌悪感感じる人もいたり。私も時々不気味な気持ちになったりもします。
さりとて、、、さりとてですよ!!
何を言ってもウンでもスンでもない、ハンチクな表情でノーリアクションってのもコワイですよ。相当不気味です。
んじゃー、どっちにも文句言うならどーなのよッ!!てなるんだけど、今日急に気がついたんですよ。
まずね、
まあ一応、プロとかの話じゃなくて、アマチュアと指導者(指揮者でもいい)っていう関係性を考えた時、
これね、指導者ってまあ一応言っちゃうから、するってーと相手の立場は生徒ってことになるんで、どうしても指示が「指導的」「注意」「ダメ出し」「命令」って方向になりやすい。
でも、ここでそれは「教育」なのか「コーチング」なのか、っていう問題にもぶち当たるワケですよ。
この「教育」と「コーチング」っての、これ先日も書いた苫米地博士の受け売りですけど、「教育」ってのは「本人以外の(社会の)ため」、「コーチング」は「100%クライアント(この場合「生徒」)のため」ってことで、ベクトルが逆を向くワケだけど、
多分、演奏をする目的は「音楽を演奏して世の中に何かしらの光を届ける的な?!」かなーと。その手段として、演奏技術の向上とか、アンサンブルの技術なんかが必要ってな感じ?!
で、その過程に、
協調性、忍耐力、自主性、積極性、感情の豊かさ、統率、規律、上下関係、礼儀…などなどが求められたり、あるいは副産物として得られたりするのかなーと。
だから「音楽で世の中に…」的な部分が教育されるべきところで、演奏技術みたいなところがコーチングされるべきとこなのかなーと。
コーチングってのが、100%生徒のためってことになると、いかにその子の(持っている)能力を引き出すかってことになるのかなと。
するとだよ、、
レッスンや合奏指導でかけるべき言葉ってのは、どーなんだろ?!まあひとつには絞れないけど、「こうやってみるってのはどうだ?!」「これにチャレンジしてみよう」的なモノであっていいんじゃないかなと。
んでだよ、そういう指導者の提案に対して、「それにチャレンジしてみるよ!」「お!!その意見に乗った!やってみれるよ!!」的なリアクションとしての、「ハイッ!」っていう、そういう関係だといいんじゃないかと。
指導っていうと、ついなんでもトップダウンで、「ここが合ってない!!」「これはこうして!!」となりがちだし、そういうのが人生に染み付いてるから、生徒(クライアントとしての先生も含めて)の方もそれ求めてるし、そして何より手っ取り早い。
効率こそ重要、みたいな風潮もあるから「手っ取り早い」はこれまた重要。
でも、そうやって自分の頭使わない、想像も創造もしない状態に慣れちゃうのは、奴隷的&盲目的人間を増やすことになりかねない。音楽への愛着とかがあんまり育ってない可能性もある。
もちろんどこもかしこもとかって話でも、またどこか特定のところをイメージして言ってるわけでもないよ。
風潮って話ね。
そういう意味で、時々物凄く柔軟な学校もあって、コンクールなどでの結果にはまだまだ反映されてないけど、「あー、いい活動してるな」って思ったりする。ステキだ。
というわけで、観点がちょっと多いかもだけど、私としてのキモは、コーチングって観点で考えた時の生徒への言葉かけの方向性と、それをやってみるかやってみないかの意思表明としての「ハイッ!」ってのは、どうじゃろな?ってことですたい。
でも、読んでくださったみなさんはみなさんで自分の自由な観点で読み取ってくだされば嬉しいですヨン。そこからまた別な、さらに進んだアイデアが生まれたりしたらもっと嬉しいですなッ。