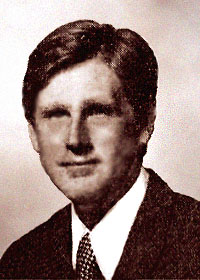14箇所ある‘親木’という訳語が最初に見えるのは、52節ですが、英文では、原語と思われる‘ mother tree ’は、その節にないわけで・・・・54節、56節。そして60節に2回の計4度のみ。
まずは、52~56節あたりですが、
「52 そして、わたしが果樹園のいちばん低い場所に植えておいたこれらの木の枝を取り、親木に接ぎ返そう。いちばん渋い実のなる枝を何本か親木から切り落とし、代わりに親木の元の自然の枝を接ぐことにしよう。
53 わたしがこうするのは、親木を枯らさないためである。こうすれば、わたし自身のためにその根を残せるかもしれない。
54 また見よ、わたしが良いと思う所に植えた親木の自然の枝の根は、まだ生きている。これらの根もわたし自身のために残せるように、この親木の枝を取って、これらの根に接ごう。まことに、これらの根にその親木の枝を接げば、わたし自身のためにそれらの根も残すことができ、根が十分に強くなるとわたしのために良い実を結べるようになる。そうすれば、わたしは果樹園の実によって、まだ栄えを得ることができる。」
55 そして二人は、すでに野生のようになった自然の親木から枝を取り、これまたすでに野生のようになった自然の木にそれらを接いだ。
56 また二人は、すでに野生のようになった自然の木の枝を取り、それらを親木に接いだ。 」
たまWEB風英文に基づいての試訳はですね、
52節は、
“52 そ して、わたしが果樹園のいちばん低い場所に植えておいたこれらの木の枝を取り、元の木に接ぎ返そう。いちばん渋い実のなる枝は木から切り落とし、代わりに自然の枝を元の木に接ぐことにしよう。 ”
となりましょうか。
んで、この意味・解釈としては、リーハイの子孫である末日のレーマン人/アメリカ先住民に彼らの真の出自を、先祖がイスラエルの聖約の民であったことを悟らしめ、言い換えますれば、モルモン書を通じて回復された福音に改宗し贖い主に信仰を持つことでもう一度聖約の民となれるようにしようといった感じ。渋い実は、行いが悪いと聖約の民にはなれないみたいな・・・・
或いは、“低い場所に植えておいたこれらの木の枝”は先住民ではなく異邦人を指すのかな?!?!
この低い場所の木が、48節の高くそびえている木ということであれば・・・・そのようでありますなぁ。この低い場所の木は異邦人のことと解釈できましたかぁ。
この‘元の木’というのも意訳でして、やって来たところの木が原文忠実で、由来・出自となる元々の木の意味なわけです。これは新約の時代、原始キリスト教会以降(背教が起こる以前)の、聖約の民としての異邦人教会を指してるということになりましょうか。
で、高くそびえるとは、学問等により高慢となって、シンプルで分かりやすくて貴い真理を価値の無いものとして退け、捨てて、代わりに彼らの学問の多寡や社会的地位や権威に置き換えてつまずいてしまうといったふうに解する研究がありましたかぁぁ。
「48 そこで、僕は主人に言った。「それは果樹園の木が高くそびえているからではありませんか。そのために、木の枝が良い根を負かしたのではありませんか。枝が根を負かしたために、枝が根の力以上に生長し、勢力を奪ったのです。まことに、果樹園の木がだめになった原因はこれであると、わたしは申し上げます。」 」
よってもって、52節の内容は、第1ニーファイ13:34以下に近いかな。で、改宗した異邦人をイスラエルの聖約の民として数えられるようにしようと。
「13:34・・・・異邦人が甚だしくつまずいた後、』小羊はこう言われ、さらに『その日わたしは異邦人を憐れみ、力をもって、わたしの福音の中の分かりやすくて貴い多くの部分を彼らに明らかにしよう』と小羊は言われる。 」 (第1ニーファイ)
53節以下の訳は
‘53 わたしがこうするのは、木を枯らさないためである。こうすれば、わたし自身のためにその根を残せるかもしれない。
54 また見よ、わたしが良いと思う所に植えた木の自然の枝の根は、まだ生きている。これらの根もわたし自身のために残せるように、この木の枝を取って、これらの根に接ごう。まことに、これらの根にその親木の枝となるように接げば、わたし自身のためにそれらの根も残すことができ、根が十分に強くなるとわたしのために良い実を結べるようになる。そうすれば、わたしは果樹園の実によって、まだ栄えを得ることができる。」
55 そして二人は、すでに野生のようになった自然の木から枝を取り、これまたすでに野生のようになった自然の木にそれらを接いだ。
56 また二人は、すでに野生のようになった自然の木の枝を取り、それらを親木に接いだ。’
となりましょう。(‘親木 mother tree’ は2箇所のみ)
で、この親木は、聖約(の民)としての回復を可能にした・するところの、末日聖徒イエスキリスト教会・モルモン教会と解せるというわけなんですよねぇぇ!!!
54節以下の自然の木の枝というのはリーハイの子孫、アメリカ先住民のことになりましょう。
55節は無くてもOK、56節で改めたんではないか、55節消し忘れた??金版に刻んでしまって消せないと??或いは両節で、回復された福音への改宗のケースとして、異邦人のそしてリーハイの子孫であるところの先住民の、二つをいわんとしたのかも。
日本人も基層は南方系ありということで、異邦人というよりは先住民的扱いでしょうかぁぁ??
日本語モルモン書で訳者さん(グループ?)が、親木を14回訳出したように、この辺はいろいろ異見が出てくる箇所なんでしょう。一応、英語圏の研究情報から再構築してみるのもいいのかもね・・・・
55節以降が、4回目の訪れ/福音の回復以降の事柄・出来事ということになりますかぁぁ・・・・ 「オリーブの木のたとえ」 http://www5b.biglobe.ne.jp/~shu-sato/lds/mormon04.htm
http://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&p=Is%20it%20not%20the%20loftiness%20of%20thy%20vineyard
〝52 Wherefore, let us take of the branches of these which I have planted in the nethermost parts of my vineyard, and let us graft them into the tree from whence they came; and let us pluck from the tree those branches whose fruit is most bitter, and graft in the natural branches of the tree in the stead thereof."