全日本手をつなぐ育成会発行 元気の出る情報・交流誌
「手をつなぐ」5月号が届きました。

今月の特集は「地域にひろがる学校へ」です。
≪P5引用します。≫
≪ここまで≫
この部分を読んだだけで、「あぁそうかも・・・」と
思ってしまいました。
ウチの息子が養護学校を卒業してから丸二年が経ちますので
今現在はどういう状況かははっきり言えませんが、
そうそう変わっていなのではないでしょうか。
ウチの息子が在学中は、現場実習先は親が探してくる。
そして、そこで実習をさせてもらったら、卒業後はそこで
引き受けていただけるように親が働きかけをするように!
というような学校側からの話しがありました。
そして、それがなかなかうまく進まない場合には
学校と保護者と事業所、それに場合により本人の居住地の
役所の担当者とで、「ケース会議」を持つ、というような
感じで進んでいたと思います。
ですので、福祉事業所側としては、本人の情報は
保護者からの話と、ほんの1~2週間の現場実習の様子
からしか得ることができない状態が多かったと思います。
まあ、このように保護者主体になった理由には、
子どもの進路を全て学校に任せっきりにして自分は何もしないという
保護者もいたから というような話も聞いてはいましたが、
というような話も聞いてはいましたが、
そうなると、やはり学校と福祉の連携というものは
取りにくい状態になってしまいますよね。
子どもは、親の前でみせる顔と、学校で見せる顔は
必ずしも同じということはないと思います。
むしろ、まったく違う顔を見せている場合も多いかもしれません。
ですので、卒業後に福祉事業所の方では
「えっ! こんなことをするって聞いていないよ!」
こんなことをするって聞いていないよ!」
というような事がおこったりするのではないでしょうか。
いろいろと考える事が多い内容になっているようですし
その他の話題も興味深いものばかりです。
県内へは、準備が整い次第発送いたしますので
しばらくお待ちください(F)
「手をつなぐ」5月号が届きました。

今月の特集は「地域にひろがる学校へ」です。
≪P5引用します。≫
「障害のある子どもの成長を支えるために、
福祉と教育が手を携えてほしい」
そうした声は、あちこちで聞かれます。
学校での経験が将来の生活の幅をひろげる事に
学校側の認識が浸透しない一方、
学校の持つノウハウや情報などを福祉側が
充分に取り込みきれていないというのが、
多くの地域での現実ではないでしょうか。
それでも一部では、「学校と地域の橋渡し」となる
積極的な取り組みがなされています。
そうした実践などから、教育と福祉の連携について考えます。
福祉と教育が手を携えてほしい」
そうした声は、あちこちで聞かれます。
学校での経験が将来の生活の幅をひろげる事に
学校側の認識が浸透しない一方、
学校の持つノウハウや情報などを福祉側が
充分に取り込みきれていないというのが、
多くの地域での現実ではないでしょうか。
それでも一部では、「学校と地域の橋渡し」となる
積極的な取り組みがなされています。
そうした実践などから、教育と福祉の連携について考えます。
≪ここまで≫
この部分を読んだだけで、「あぁそうかも・・・」と
思ってしまいました。
ウチの息子が養護学校を卒業してから丸二年が経ちますので
今現在はどういう状況かははっきり言えませんが、
そうそう変わっていなのではないでしょうか。
ウチの息子が在学中は、現場実習先は親が探してくる。
そして、そこで実習をさせてもらったら、卒業後はそこで
引き受けていただけるように親が働きかけをするように!
というような学校側からの話しがありました。
そして、それがなかなかうまく進まない場合には
学校と保護者と事業所、それに場合により本人の居住地の
役所の担当者とで、「ケース会議」を持つ、というような
感じで進んでいたと思います。
ですので、福祉事業所側としては、本人の情報は
保護者からの話と、ほんの1~2週間の現場実習の様子
からしか得ることができない状態が多かったと思います。
まあ、このように保護者主体になった理由には、
子どもの進路を全て学校に任せっきりにして自分は何もしないという
保護者もいたから
 というような話も聞いてはいましたが、
というような話も聞いてはいましたが、そうなると、やはり学校と福祉の連携というものは
取りにくい状態になってしまいますよね。
子どもは、親の前でみせる顔と、学校で見せる顔は
必ずしも同じということはないと思います。
むしろ、まったく違う顔を見せている場合も多いかもしれません。
ですので、卒業後に福祉事業所の方では
「えっ!
 こんなことをするって聞いていないよ!」
こんなことをするって聞いていないよ!」というような事がおこったりするのではないでしょうか。
いろいろと考える事が多い内容になっているようですし
その他の話題も興味深いものばかりです。
県内へは、準備が整い次第発送いたしますので
しばらくお待ちください(F)






















 第6次総合化産業を推進します。
第6次総合化産業を推進します。 (F)
(F) クリックをどうぞ
クリックをどうぞ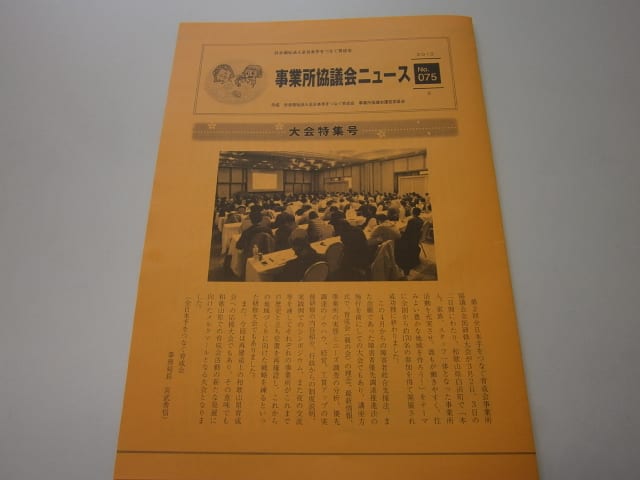

 ほろ酔い気分で)
ほろ酔い気分で)


 制度に乗っかったフワフワした事業所経営はダメ
制度に乗っかったフワフワした事業所経営はダメ
 「仮想事業計画」は楽しめた。
「仮想事業計画」は楽しめた。 今回の研修大会は、事業所の経営者さんや職員さん向けの
今回の研修大会は、事業所の経営者さんや職員さん向けの 遠くはるばるたくさんの方々に白浜まで来て頂き、
遠くはるばるたくさんの方々に白浜まで来て頂き、
 で驚きました。
で驚きました。 桜の花が開いてから、あんなに雪が降ったことは
桜の花が開いてから、あんなに雪が降ったことは モンテディオのホーム戦も、スタジアムに積もった雪を
モンテディオのホーム戦も、スタジアムに積もった雪を

 とても引っかかりを感じた言葉がありました。
とても引っかかりを感じた言葉がありました。 冷たい言葉に感じてしまいました。
冷たい言葉に感じてしまいました。