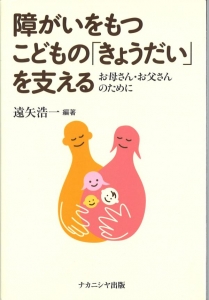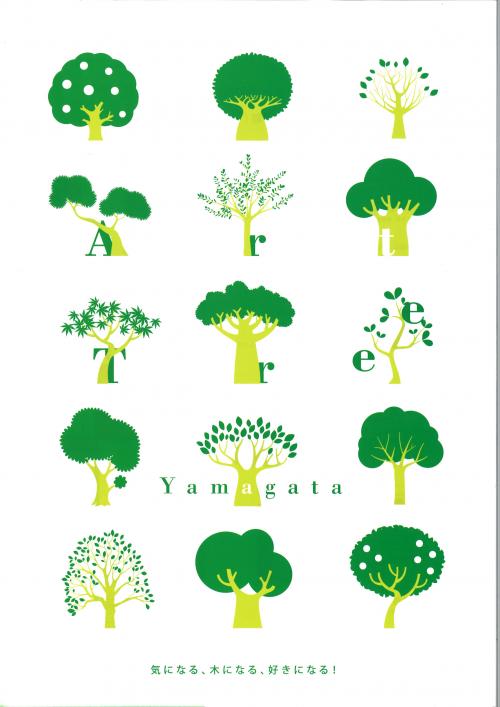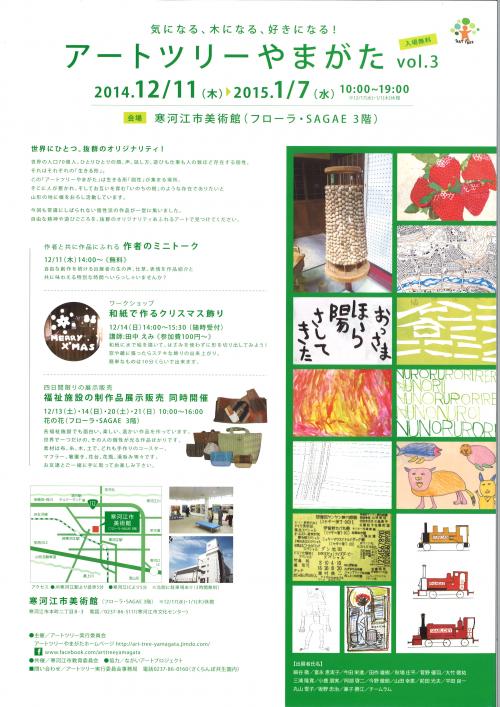先日から、障がいのない“きょうだい”についてのことに触れています。
前々回、研修会の勢いで資料を見せながら障がいのない長男に対し、
これまでの気持ちなどを聞けた事を書きました。

講師の有馬先生にも、その事をメールでお伝えしたのですが、
とても喜んでくださいました。
資料を「ハイ」を返してきた時に「どうだった?」と踏み込んだのが良かった、
聞かれないと答えにくいという事がありますから(特に男性は)といっていただきました。
親亡き後のこと、障がいのある弟の将来のことを気にしてきた事を
私(親)に言えたことが、長男にとっては大きなことで、
きっとホッとしたのではないかと思いますよ。との事でした。
きっとそうなのだと思います(^^)
息子さんが精神的なお辛さ(生きづらさ)を感じていなかったことは何よりです。
それは、Fさんとのコミュニケーションが元々よくて安定感があったからだと思います。
とも言ってくださいました。
そして有馬先生は、私に対して
『私はこんな風にやったよ!』と皆さんにお伝えしていただくと、説得力がありますね!
とアドバイスをいただいたので、研修会にも来てくれた知り合いママ数名にメールをしてみました。
みなさんお返事をくれたのですが、その中のお1人の内容です。
「ウチも障がいのあるきょうだいがいることで、看護、それも精神分野を選んだとおもう。
そういう”きょうだい”のホンネを聞いてみたい!社会に出たから見えてきたものもあるだろうし
小さいころ辛かったこともあるだろうし・・・
帰ってきたら話してみたいと思います。
私も話すタイミングをもらった気分。
研修会と〇〇ちゃんママ←(これ私)に感謝m(__)m」
と書いてあり、私もとっても嬉しくなりました。
手をつなぐ育成会は、障がいのある子を授かった母親たちが作った会です。
障がいのある子を産んだ母親の気持ちは同じ立場の人にしか理解できません。
育成会(親の会)だからこそ、同じ立場の親たちの気持ちに寄り添った研修会をやりたい。
でっかい規模の素晴らしい研修会は他の団体にお任せしてでも、
障がいのある子がいることで母親たちが抱えている戸惑いや生きづらさなどに寄り添い
ちょっとしたヒントが得られ、少しでも前向きになれるような優しい研修会をやりたい。
それこそが、育成会(親の会)だからこそできる役割なのではないかと強く思います。
ご訪問ありがとうございます(F)
前々回、研修会の勢いで資料を見せながら障がいのない長男に対し、
これまでの気持ちなどを聞けた事を書きました。

講師の有馬先生にも、その事をメールでお伝えしたのですが、
とても喜んでくださいました。
資料を「ハイ」を返してきた時に「どうだった?」と踏み込んだのが良かった、
聞かれないと答えにくいという事がありますから(特に男性は)といっていただきました。
親亡き後のこと、障がいのある弟の将来のことを気にしてきた事を
私(親)に言えたことが、長男にとっては大きなことで、
きっとホッとしたのではないかと思いますよ。との事でした。
きっとそうなのだと思います(^^)
息子さんが精神的なお辛さ(生きづらさ)を感じていなかったことは何よりです。
それは、Fさんとのコミュニケーションが元々よくて安定感があったからだと思います。
とも言ってくださいました。
そして有馬先生は、私に対して
『私はこんな風にやったよ!』と皆さんにお伝えしていただくと、説得力がありますね!
とアドバイスをいただいたので、研修会にも来てくれた知り合いママ数名にメールをしてみました。
みなさんお返事をくれたのですが、その中のお1人の内容です。
「ウチも障がいのあるきょうだいがいることで、看護、それも精神分野を選んだとおもう。
そういう”きょうだい”のホンネを聞いてみたい!社会に出たから見えてきたものもあるだろうし
小さいころ辛かったこともあるだろうし・・・
帰ってきたら話してみたいと思います。
私も話すタイミングをもらった気分。
研修会と〇〇ちゃんママ←(これ私)に感謝m(__)m」
と書いてあり、私もとっても嬉しくなりました。
手をつなぐ育成会は、障がいのある子を授かった母親たちが作った会です。
障がいのある子を産んだ母親の気持ちは同じ立場の人にしか理解できません。
育成会(親の会)だからこそ、同じ立場の親たちの気持ちに寄り添った研修会をやりたい。
でっかい規模の素晴らしい研修会は他の団体にお任せしてでも、
障がいのある子がいることで母親たちが抱えている戸惑いや生きづらさなどに寄り添い
ちょっとしたヒントが得られ、少しでも前向きになれるような優しい研修会をやりたい。
それこそが、育成会(親の会)だからこそできる役割なのではないかと強く思います。
ご訪問ありがとうございます(F)