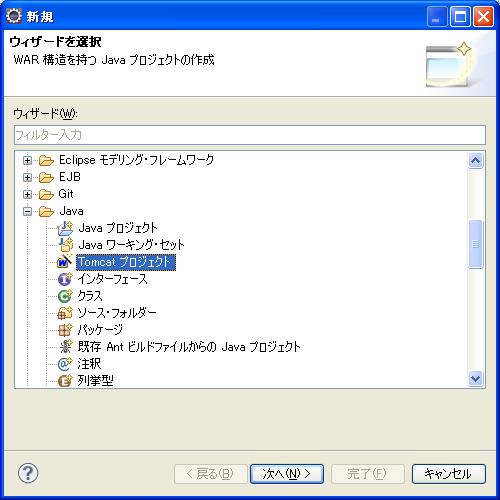2011年4~12月期決算、テレビをやっている、ソニー、シャープ、パナソニックは、軒並み、巨額赤字という事態になりました。
テレビは、地デジ化移行する前に、みんな買い替えてしまったから、当分需要は起こりませんよね。
なにか、大きなイノベーションでもしない限り・・・
とはいえ、個人市場は、もうみんな買ってしまっただろうから、まあ、ここへの投入は難しい。
となると、まだテレビが入っていない、会社ってことになるだろうね。
新しいものというと、テレビとインターネットを結び付けるというのは、みんな考えているけど、
そこから先、それを結び付けて、何するの?っていうところが、不明だよね・・・
で、そう考えると、やっぱり、ひとつの方向としては、スカイプのような方向、
簡易版のテレビ会議みたいなものが考えられるよね。
スカイプそのものでもいいんだけど、テレビ会議ソフトをつくって、インターネット経由で、テレビと、Webカメラを使って、テレビ会議ができるというもの。
会社には、テレビ会議しシステム入っているけど、「あんな大規模なものは必要ない!」っていう会社(SOHOとか)で使いそうだよね!それと、個人でもいいかもしれない。家族がテレビで見れるというのは・・・
パソコンと違ってテレビのほうが、こういうのは、いいんじゃないかな?
32型のテレビ会議システムっていうのは、ありだと思うけど、
32型のパソコンディスプレイは、ちょっと仕事で使うには・・・どうなんでしょう?
あと、もうひとつは、キャンパスTV(大学の場合)や、会社TVですよね。
これは、テレビ移行後の空き周波数にやるという話もあるかもしれないけど、
インターネットで放送するなら、今でもアリですよね。
キャンパスTVの場合、その大学に通っている人だけでなく、受験生も見そう。
会社TVの場合、従業員だけでなく、就活生も見そう。
テレビ局も、テレビ離れが進むと、暇になってくるだろうから、テレビ局が、番組制作をしたりして、
小銭を稼ぐとか・・
ソニーとか、とくに、簡易版のテレビ会議とか、すぐに作れそうな気がするんだけど、
どうだろう・・
こんな、あたらしいテレビの使い方を考えないと、
ちょっと、テレビによる営業不振は抜け出せないのじゃないかな?
テレビは、地デジ化移行する前に、みんな買い替えてしまったから、当分需要は起こりませんよね。
なにか、大きなイノベーションでもしない限り・・・
とはいえ、個人市場は、もうみんな買ってしまっただろうから、まあ、ここへの投入は難しい。
となると、まだテレビが入っていない、会社ってことになるだろうね。
新しいものというと、テレビとインターネットを結び付けるというのは、みんな考えているけど、
そこから先、それを結び付けて、何するの?っていうところが、不明だよね・・・
で、そう考えると、やっぱり、ひとつの方向としては、スカイプのような方向、
簡易版のテレビ会議みたいなものが考えられるよね。
スカイプそのものでもいいんだけど、テレビ会議ソフトをつくって、インターネット経由で、テレビと、Webカメラを使って、テレビ会議ができるというもの。
会社には、テレビ会議しシステム入っているけど、「あんな大規模なものは必要ない!」っていう会社(SOHOとか)で使いそうだよね!それと、個人でもいいかもしれない。家族がテレビで見れるというのは・・・
パソコンと違ってテレビのほうが、こういうのは、いいんじゃないかな?
32型のテレビ会議システムっていうのは、ありだと思うけど、
32型のパソコンディスプレイは、ちょっと仕事で使うには・・・どうなんでしょう?
あと、もうひとつは、キャンパスTV(大学の場合)や、会社TVですよね。
これは、テレビ移行後の空き周波数にやるという話もあるかもしれないけど、
インターネットで放送するなら、今でもアリですよね。
キャンパスTVの場合、その大学に通っている人だけでなく、受験生も見そう。
会社TVの場合、従業員だけでなく、就活生も見そう。
テレビ局も、テレビ離れが進むと、暇になってくるだろうから、テレビ局が、番組制作をしたりして、
小銭を稼ぐとか・・
ソニーとか、とくに、簡易版のテレビ会議とか、すぐに作れそうな気がするんだけど、
どうだろう・・
こんな、あたらしいテレビの使い方を考えないと、
ちょっと、テレビによる営業不振は抜け出せないのじゃないかな?