4 そのかわりまたからすがどこからか、たくさん集まってきた。昼間見ると、そのからすが、何羽となく輪を描いて、高い鴟尾の周りを鳴きながら、飛び回っている。ことに門の上の空が、夕焼けで赤くなるときには、それがごまをまいたように、はっきり見えた。からすは、もちろん、門の上にある死人の肉を、ついばみに来るのである。――もっとも今日は、刻限が遅いせいか、一羽も見えない。ただ、所々、崩れかかった、そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上に、からすの糞が、点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段のいちばん上の段に、洗いざらした紺の襖のしりを据えて、右のほおにできた、大きなにきびを気にしながら、ぼんやり、雨の降るのを眺めていた。
Q4 「からす」の表現効果を説明せよ。
A4 羅生門の不気味さを強調する働きをもつ。
Q5 「大きなにきびを気にしながら」という表現から、下人がどういう存在であることが読み取れるか。2点指摘せよ。
A5 (1)まだ若い存在 (2)容姿を気にするふつうの若者
5 作者はさっき、「下人が雨やみを待っていた。」と書いた。しかし、下人は雨がやんでも、格別どうしようという当てはない。ふだんなら、もちろん、主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは、四、五日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の町はひととおりならず衰微していた。今この下人が、永年、使われていた主人から、暇を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波にほかならない。だから「下人が雨やみを待っていた。」と言うよりも「雨に降りこめられた下人が、行き所がなくて、途方に暮れていた。」と言うほうが、適当である。そのうえ、今日の空模様も少なからず、この平安朝の下人のSentimentalismeに影響した。申の刻下がりから降り出した雨は、いまだに上がる気色がない。そこで、下人は、何をおいても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとして――いわばどうにもならないことを、どうにかしようとして、とりとめもない考えをたどりながら、さっきから朱雀大路に降る雨の音を、聞くともなく聞いていたのである。
Q6「どうにもならないこと」について、
(a)「どうにもならないこと」とは何か。6字で抜き出せ。
(b)なぜ「どうにもならない」のか。15字以内で述べよ。
(c)「主人に暇を出されたこと」を別の言葉でなんと表現されているか。10字で抜き出せ。
(d)「この衰微」とはどの衰微か。簡潔の記せ。
A6(a)明日の暮らし
(b)主人から暇を出されたから。
(c)この衰微の小さな余波
(d)京都全体の衰微
6 雨は、羅生門を包んで、遠くから、ざあっという音を集めてくる。夕闇はしだいに空を低くして、見上げると、門の屋根が、斜めに突き出した甍の先に、重たく薄暗い雲を支えている。
Q7「見上げると」の主語は?
A7 下人
Q8 この風景描写の役割はどういうものか。
A8 暮らしの目処が立たず途方に暮れ、感傷に浸っている下人の心情が象徴的に表されている。
小説における風景描写はすべて作者が作り出したものです。何月何日のこの場所はこんなでしたという客観的風景が記されているのではありません。さらに、ここでは「下人の視点」でこの風景が捉えられている、つまり下人にはそう見えるということです。それは下人の心情が投影されているということです。風景描写は、ドラマや映画におけるBGMのはたらきをします。
「 A 心情 = A' 風景 」










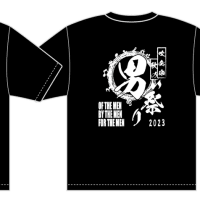






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます