堀江敏幸「送り火」(センター2007年)③
陽平さんにそれを話すと、墨はね、松を燃やして出てきたすすや、油を燃やしたあとのすすを、膠(にかわ)であわせたものでしょう、膠っていうやつが、ほら、もう、生き物の骨と皮の、うわずみだから、絹代さんが感じたことは、そのとおり、ただしい、と思いますよ、と真剣な顔で言うのだった。生きた文字は、その死んだものから、エネルギーをちょうだいしてる。重油とおなじ、深くて、怖い、厳しい連鎖だね。
大人になれば、ものの見方は変わります。
さまざまな経験を積み、新しい知識を手に入れるからです。
陽平さんは、絹代さんにとって、ものの見方を変えてくれる存在です。
「主役(主人公)」と「対役」は、敵対関係でとらえるよりも、主役を変化させうる存在、主役に影響を与える存在が「対役」だととらえるといいと思います。
物語のパターンで説明すると、陽平さんは「賢者」とか「贈与者」とよばれる存在なのです。
対役によって主役が変化することを、基本的に「成長」とよびます。
なぜだろう、絹代さんはそのときはじめて、陽平さんのこれまでの人生を、あれこれ聞いてみたいとつよく思った。ほとんど毎日顔を合わせて食事をしているこの不思議な男の人の過去と未来を知りたい気持ちがどんどんふくらんで、それを押しとどめることができなくなっていった。どこで生まれて、どこで育って、どんな子ども時代、どんな青年時代を送ったのか。教室を閉めたあと、無理に頼んで持ってきてもらった古いアルバムを居間で開きながら飽きもせずに質問を重ねていると、これまで陽平さんを知らずにいたことがとても信じられなかった。絹代さんの横顔にときどき視線を投げながら、陽平さんは遅くまで、質問のひとつひとつに、あまりにまじめすぎて逆にはぐらかされているのではないかと聞き手が不安になるほど丁寧な説明をくわえた。そういう陽平さんの顔を、今度は絹代さんが見つめているのだった。
自分にないものをもっている存在、自分にないものを与えてくれる存在に、人はこころ惹かれます。
惹かれはじめると、もっと知りたくなります。
西田幾太郎という、日本で一番えらいクラスの哲学者が、「愛は知の極点である」と言いました。「愛と知は決して別種の精神作用ではない」と。
誰かのことが気になる、もっと知りたい、どんなことでも知りたいという思いが愛につながる感覚は理解できますね。
絹代さんの気持ちが固まったのは、翌年、あんなに楽しそうに子どもたちと接していた母親が心臓発作で急死して、その喪が明けたさらに翌年の正月のことだ。全員参加の書き初め大会が教室で開かれ、四文字以内で好きな言葉を清書し、それをみんなに披露しながらひとりずつ新年の抱負を述べたとき、陽平さんは最後にすっくと立ちあがって一同を見渡し、当時大変な人気があったテレビ番組にひっかけて「絹への道」と書いた紙を掲げると、シル、ク、ロード、です、これが、ぼくの、今年の、抱負、です、と例の口調でそう読みあげておおいに笑いを取ったのだが、子どもたちには洒落(しゃれ)にしか聞こえない話で陽平さんがなにを言おうとしているのか、「初日の出」だなんてありきたりな言葉でお茶をにごした飛び入り参加の絹代さんにはすぐに理解できた。頬(ほお)が少しほてった。D有名な女優さんとおなじだねえと大人たちからいくら褒められても嬉しくなかった名前を、陽平さんは、あたたかい、人肌に触れるために生まれてきたなめらかな布地に、一瞬で変えてくれたのである。
問5 傍線部D「有名な女優さんとおなじだねえと大人たちからいくら褒められても嬉しくなかった名前を、陽平さんは、あたたかい、人肌に触れるために生まれてきたなめらかな布地に、一瞬で変えてくれたのである」とあるが、ここに至るまでの「絹代さん」の心の動きはどのようなものと考えられるか。
正解選択肢が、本文に直接書かれていない言葉が用いられているので、難しい設問と言えるでしょう。
与えられた情報、つまり小説の描写から、主人公の心情を想定するという作業が必要です。
「ここに至るまでの『絹代さん』の心の動きはどのようなものと考えられるか」という問われ方に注意してください。
まず、「ここ」をまとめましょう。
「絹代さんの気持ちが固まったのは … 正月のことだ」とありますね、何があったのですか。
みんなで書き初めをする。
陽平さんは「絹への道」としたため、「今年の目標だ」とみんなの前で宣言する。
絹代さんは、自分への求婚だと一瞬にして気づく。
そして、蚕を連想させるために、たとえ「田中絹代(知らないよね?)と同じじゃないか、素敵な名前だねぇ」と言われたところで、今ひとつ好きになれなかった「絹代」の「絹」が、なめらかな生地としての「絹」にイメージが変わったと絹代さんは感じるのです。
もちろんそれは、この時点で、二人の間に愛情が育まれていたからでもあります。
直前の部分の、墨の由来やら陽平さんの来し方を語り合っている場面でそれはわかります。
自分にないものを与えてくれる人に人はひかれる。
知りたいという強い思いが愛を生む、という場面。
その前提がなかったら、「絹への道」が求婚だとは言い切れなくなりますよね。
「勝手に何書いてんの? きもっ!」て。
ちなみに、子供達は誰も気づかなかったのでしょうか。
これはまったく想像にすぎませんが、普段から二人の様子を見ていて、「絹への道」という書き初めを見て頬を赤らめている絹代さんに気づいたら、小学校高学年の女子なら、「ははあん、やっぱりね」となるのではないでしょうか。男子はぜったい無理でしょうが。
「絹への道」 … ぼくの、今年の、抱負、です、
↓
自分への求婚だと気づく
↓
頬(ほお)が少しほてった
↓
気持ちが固まった
∥
「絹代」… 蚕に結びつく・有名な女優と同じと言われてもとくにうれしくない
↓
「絹代」… (あなたは)あたたかい、人肌に触れるために生まれてきたなめらかな布地
↓
頬が少しほてった
↓
気持ちが固まった
という構造です。なので、非常にエロチックに解釈しようと思えば可能な表現でもありますね。
さすがにそういう選択肢は書けませんが。
①「陽平さんが墨の由来とともに名前の意味を教えてくれ、 … シルクロードになぞらえた愛情告白をしてくれたため」×
② 墨の匂いに関連した生き物の死と人間の営みとのつながりを教えてくれた陽平さんから、
書き初めに託された愛情表現を受けたことで、
好きになれなかった名前とともに自分のことも肯定的に受け止められるようになり、
陽平さんと一緒に生きていこうと考えている。〈 正解 〉
③「陽平さんの … 書き初めによって、悠久の歴史を想起させるシルクロードとも結びつくものだと気づき」×
④「陽平さんのまっすぐな生き方を知ることによって」×
⑤「ようやく自分の名前の意味を肯定的に受け止めることができるようになったので」
問5を間違える人は、次の3つが原因です。
1、本文の因果関係を読み取れない場合
2、選択肢の構文を把握できない場合
3、言い換えがわからない場合
問6 この文章における表現の特徴について説明したものとして適当なものを、次の①~⑥のうちから二つ選べ。
表現についての問いは、三つのチェックポイントがあります。
a どのような内容が
b 何という表現技法によって
c どう効果的に表現されているか
です。a・b・cのどこかがおかしければ間違いです。
またはそれぞれのつながり方がおかしければ間違いです。
① 「比喩表現を用いて描写されることによって」b○、「『絹代さん』の特異な感性が」a×
② 「感覚に訴える表現が多用されることによって」b○、「絹代さんの実感が」a○、「巧みに表現されている」c○
③ 「かぎ括弧を用いずに会話の内容が示されることによって」b○、「現実感が生み出され」c×、「人物が生き生きと描き出されている」b→c×
④ 「回想の形で語られる中に現在形の表現が挿入されることによって」b○、「臨場感が強められ」c○、「登場人物の心理状態と行動との結びつきが明示されている」b→c×
⑤ 「読点で区切りながら陽平さんの話し方が描写されることによって」b○、a「その人物像が」「浮かび上がるように工夫されている」c○
⑥ 「人物同士がふだん呼び合っている名称」a×、「平仮名書きが多用されることによって」b△、「大人の世界に子どもの視点が導入され」c×、「物語が重層的に語られている』c×。
よって、②と⑤を選びます。
表現の問題を解くためには、表現技法の知識が必要です。
たとえば「擬人法」とは何かを知らなければ、どういう効果があるのかもわからないですよね。
次のような観点をまず意識してみましょう。
1 視点・語り手 2 比喩・象徴 3 時系列 4 文体
個々についてはこれから随時勉強していきます。
陽平さんにそれを話すと、墨はね、松を燃やして出てきたすすや、油を燃やしたあとのすすを、膠(にかわ)であわせたものでしょう、膠っていうやつが、ほら、もう、生き物の骨と皮の、うわずみだから、絹代さんが感じたことは、そのとおり、ただしい、と思いますよ、と真剣な顔で言うのだった。生きた文字は、その死んだものから、エネルギーをちょうだいしてる。重油とおなじ、深くて、怖い、厳しい連鎖だね。
大人になれば、ものの見方は変わります。
さまざまな経験を積み、新しい知識を手に入れるからです。
陽平さんは、絹代さんにとって、ものの見方を変えてくれる存在です。
「主役(主人公)」と「対役」は、敵対関係でとらえるよりも、主役を変化させうる存在、主役に影響を与える存在が「対役」だととらえるといいと思います。
物語のパターンで説明すると、陽平さんは「賢者」とか「贈与者」とよばれる存在なのです。
対役によって主役が変化することを、基本的に「成長」とよびます。
なぜだろう、絹代さんはそのときはじめて、陽平さんのこれまでの人生を、あれこれ聞いてみたいとつよく思った。ほとんど毎日顔を合わせて食事をしているこの不思議な男の人の過去と未来を知りたい気持ちがどんどんふくらんで、それを押しとどめることができなくなっていった。どこで生まれて、どこで育って、どんな子ども時代、どんな青年時代を送ったのか。教室を閉めたあと、無理に頼んで持ってきてもらった古いアルバムを居間で開きながら飽きもせずに質問を重ねていると、これまで陽平さんを知らずにいたことがとても信じられなかった。絹代さんの横顔にときどき視線を投げながら、陽平さんは遅くまで、質問のひとつひとつに、あまりにまじめすぎて逆にはぐらかされているのではないかと聞き手が不安になるほど丁寧な説明をくわえた。そういう陽平さんの顔を、今度は絹代さんが見つめているのだった。
自分にないものをもっている存在、自分にないものを与えてくれる存在に、人はこころ惹かれます。
惹かれはじめると、もっと知りたくなります。
西田幾太郎という、日本で一番えらいクラスの哲学者が、「愛は知の極点である」と言いました。「愛と知は決して別種の精神作用ではない」と。
誰かのことが気になる、もっと知りたい、どんなことでも知りたいという思いが愛につながる感覚は理解できますね。
絹代さんの気持ちが固まったのは、翌年、あんなに楽しそうに子どもたちと接していた母親が心臓発作で急死して、その喪が明けたさらに翌年の正月のことだ。全員参加の書き初め大会が教室で開かれ、四文字以内で好きな言葉を清書し、それをみんなに披露しながらひとりずつ新年の抱負を述べたとき、陽平さんは最後にすっくと立ちあがって一同を見渡し、当時大変な人気があったテレビ番組にひっかけて「絹への道」と書いた紙を掲げると、シル、ク、ロード、です、これが、ぼくの、今年の、抱負、です、と例の口調でそう読みあげておおいに笑いを取ったのだが、子どもたちには洒落(しゃれ)にしか聞こえない話で陽平さんがなにを言おうとしているのか、「初日の出」だなんてありきたりな言葉でお茶をにごした飛び入り参加の絹代さんにはすぐに理解できた。頬(ほお)が少しほてった。D有名な女優さんとおなじだねえと大人たちからいくら褒められても嬉しくなかった名前を、陽平さんは、あたたかい、人肌に触れるために生まれてきたなめらかな布地に、一瞬で変えてくれたのである。
問5 傍線部D「有名な女優さんとおなじだねえと大人たちからいくら褒められても嬉しくなかった名前を、陽平さんは、あたたかい、人肌に触れるために生まれてきたなめらかな布地に、一瞬で変えてくれたのである」とあるが、ここに至るまでの「絹代さん」の心の動きはどのようなものと考えられるか。
正解選択肢が、本文に直接書かれていない言葉が用いられているので、難しい設問と言えるでしょう。
与えられた情報、つまり小説の描写から、主人公の心情を想定するという作業が必要です。
「ここに至るまでの『絹代さん』の心の動きはどのようなものと考えられるか」という問われ方に注意してください。
まず、「ここ」をまとめましょう。
「絹代さんの気持ちが固まったのは … 正月のことだ」とありますね、何があったのですか。
みんなで書き初めをする。
陽平さんは「絹への道」としたため、「今年の目標だ」とみんなの前で宣言する。
絹代さんは、自分への求婚だと一瞬にして気づく。
そして、蚕を連想させるために、たとえ「田中絹代(知らないよね?)と同じじゃないか、素敵な名前だねぇ」と言われたところで、今ひとつ好きになれなかった「絹代」の「絹」が、なめらかな生地としての「絹」にイメージが変わったと絹代さんは感じるのです。
もちろんそれは、この時点で、二人の間に愛情が育まれていたからでもあります。
直前の部分の、墨の由来やら陽平さんの来し方を語り合っている場面でそれはわかります。
自分にないものを与えてくれる人に人はひかれる。
知りたいという強い思いが愛を生む、という場面。
その前提がなかったら、「絹への道」が求婚だとは言い切れなくなりますよね。
「勝手に何書いてんの? きもっ!」て。
ちなみに、子供達は誰も気づかなかったのでしょうか。
これはまったく想像にすぎませんが、普段から二人の様子を見ていて、「絹への道」という書き初めを見て頬を赤らめている絹代さんに気づいたら、小学校高学年の女子なら、「ははあん、やっぱりね」となるのではないでしょうか。男子はぜったい無理でしょうが。
「絹への道」 … ぼくの、今年の、抱負、です、
↓
自分への求婚だと気づく
↓
頬(ほお)が少しほてった
↓
気持ちが固まった
∥
「絹代」… 蚕に結びつく・有名な女優と同じと言われてもとくにうれしくない
↓
「絹代」… (あなたは)あたたかい、人肌に触れるために生まれてきたなめらかな布地
↓
頬が少しほてった
↓
気持ちが固まった
という構造です。なので、非常にエロチックに解釈しようと思えば可能な表現でもありますね。
さすがにそういう選択肢は書けませんが。
①「陽平さんが墨の由来とともに名前の意味を教えてくれ、 … シルクロードになぞらえた愛情告白をしてくれたため」×
② 墨の匂いに関連した生き物の死と人間の営みとのつながりを教えてくれた陽平さんから、
書き初めに託された愛情表現を受けたことで、
好きになれなかった名前とともに自分のことも肯定的に受け止められるようになり、
陽平さんと一緒に生きていこうと考えている。〈 正解 〉
③「陽平さんの … 書き初めによって、悠久の歴史を想起させるシルクロードとも結びつくものだと気づき」×
④「陽平さんのまっすぐな生き方を知ることによって」×
⑤「ようやく自分の名前の意味を肯定的に受け止めることができるようになったので」
問5を間違える人は、次の3つが原因です。
1、本文の因果関係を読み取れない場合
2、選択肢の構文を把握できない場合
3、言い換えがわからない場合
問6 この文章における表現の特徴について説明したものとして適当なものを、次の①~⑥のうちから二つ選べ。
表現についての問いは、三つのチェックポイントがあります。
a どのような内容が
b 何という表現技法によって
c どう効果的に表現されているか
です。a・b・cのどこかがおかしければ間違いです。
またはそれぞれのつながり方がおかしければ間違いです。
① 「比喩表現を用いて描写されることによって」b○、「『絹代さん』の特異な感性が」a×
② 「感覚に訴える表現が多用されることによって」b○、「絹代さんの実感が」a○、「巧みに表現されている」c○
③ 「かぎ括弧を用いずに会話の内容が示されることによって」b○、「現実感が生み出され」c×、「人物が生き生きと描き出されている」b→c×
④ 「回想の形で語られる中に現在形の表現が挿入されることによって」b○、「臨場感が強められ」c○、「登場人物の心理状態と行動との結びつきが明示されている」b→c×
⑤ 「読点で区切りながら陽平さんの話し方が描写されることによって」b○、a「その人物像が」「浮かび上がるように工夫されている」c○
⑥ 「人物同士がふだん呼び合っている名称」a×、「平仮名書きが多用されることによって」b△、「大人の世界に子どもの視点が導入され」c×、「物語が重層的に語られている』c×。
よって、②と⑤を選びます。
表現の問題を解くためには、表現技法の知識が必要です。
たとえば「擬人法」とは何かを知らなければ、どういう効果があるのかもわからないですよね。
次のような観点をまず意識してみましょう。
1 視点・語り手 2 比喩・象徴 3 時系列 4 文体
個々についてはこれから随時勉強していきます。










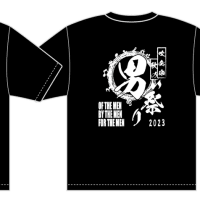




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます