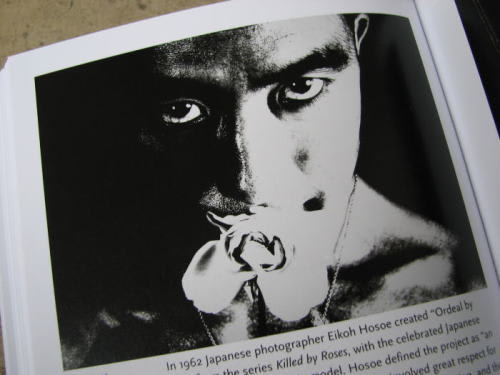今日の天声人語で“ツイッギー”が還暦になったことを知った;
《過日の本紙別刷り「be」で懐かしい英国人に会った。小枝のような体形とミニスカートで一世を風靡(ふうび)したモデル、ツイッギーだ。1967年秋、来日時の装いは噂(うわさ)のひざ上20センチではなく、ひざが隠れるキュロット姿だった。だが、翌日の記者会見にはひざ上30センチで現れる▼カーブの後の豪速球である。その短さがすっきり映えるのは足が長いからだと、当時の写真を見て思った。歳月流るるごとしで、英和辞典に名をとどめる彼女も還暦という》(天声人語引用)
ぼくにとって“ツイッギー”というのは、特別に思い出(思い入れ)のあるひとではない。
しかしそれは、1960年代終わりというぼくの青年時代を喚起する“記号”のひとつではある。
この1960年代終わりという“時期”について、むしろ最近ぼくは“思い出す”のである。
それはぼくの高校から大学時代という、“青春”という恥ずかしい時期であったため、それを“特権化”することを、ぼくはむしろ避けてきた、と思う。
しかし(たとえば)今日日付が変わったころ書いた<引用>は、1970年に自決した、ひとりの日本作家についての文章および彼自身の言葉の引用であった。
すなわち“三島由紀夫”もまた、あの時代を喚起する<記号>であった。
ぼくが、<現在>、三島由紀夫に関する言説を引用するからとて、ぼくが<右翼>に転向した(笑)とかんちがいしていただいては、困る。
なによりも、ぼくは<右翼>でないだけでなく、<体育会系>ではないからである。
もちろん三島由紀夫も“体育会系”でなかった。
だからこそ、“自衛隊の軍事訓練”体験に、コロリと“いかれた”のだ。
しかし、現在のぼくは、このような三島を、馬鹿にしては、いない。
三島が自決した当時、ぼくは彼を馬鹿にしていた。
三島の死にはびっくりしたが(彼の生首が転がっている写真!)、かれの“行為”には何の共感も触発もなかった。
しかしそれから、40年、ぼくの“感じ方”は、変わった。
もちろん、現在においても、三島由紀夫に“共感する”わけではない。
しかし、たしかにこの<事件>についての<情報>も不足していた。
引用した内田隆三『国土論』には、自決直前の三島由紀夫の武田泰淳等3人との対談からの引用があった、そこでの発言;
★ 僕はいつも思ふのは、自分がほんとうに恥づかしいことだと思ふのは、自分は戦後の社会を否定してきた、否定してきて本を書いて、お金をもらつて暮らしてきたといふことは、もうほんたうに僕のギルティ・コンシャスだな。
この発言は、対談の場で“とっさに”発言された“思いつき”ではない、三島は同じことを言いつづけている;
★ でもね。僕、耐へられないのは、たとへば僕の680円の本を出す。それを買つてくれる人がゐる。68円僕の懐ろに入る。そうすると68円はどういうふお金かと思ふんだよね。(略)この人たちから68円もらふといふことは、やつぱりこの人たちをつまり生かしておくためだらう。そしてその人たちはそれがなかつたら生きられないかといふと、なくても生きられることは確かだらう。その瞬間に、おれはやつぱりいやになつちやふんだな、ほんとうに。なにをやつてるんだおれは、といふことね。(三島由紀夫発言)
なんという発言であろうか!
これは、“資本主義”否定である(笑)
いや<資本主義>などという“観念語”を、ここでの三島は用いていない。
いったい現在“だれが”このように率直な発言を、なしえるか!
もちろん、上記の発言は、“馬鹿げている”。
現在、この言葉を、鼻先でせせら笑うひとは、多いだろう。
だからこそ、<この発言>は輝く。
もちろんぼくもこのような発言を、なし得ない。
つまり“1960年代後半には”は、このように“気狂いじみたひと”が<いた>のである。
たとえば、<現在>、“気狂い”、“気違い”という<言葉>さえ変換できない。
ぼくは最近のこのブログで<ロックンロール・ニガー>を提起した。
ぼくが書きえた最高のブログと自己評価する。
ぼくは“基本的に謙虚”なので(爆)、自己主張をしていない(“引用”ばかりしているのだ)
ジミ・ヘンドリックスについての“ロックンロール・ニガー”宣言こそ、ぼくの主張である。
“ジミ・ヘンドリックス”もまた、1960年代後半の記号であった。
ぼくは先ほど、<右翼>という言葉を使った。
しかし、“右翼”と“左翼”と“リベラル”の区別こそ、笑うべきものである。
問題は、“一億総保守化“である。
すなわち、“保守的なひと”と、“保守的でないひと”が<いる>。
“区別”は、それだけである。
天声人語は、保守的な言説の“サンプル”である;
▼ 以来、スカートの流行は伸びたり縮んだり。60年代の急成長をしのんでか、景気がいい時は縮むとの説がある。昨今、ひざ上がどうしたと論じることもないが、家庭では別らしい▼東洋大が募る今年の「学生百人一首」に、選外の傑作があった。埼玉県の高1が詠んだ〈朝早くスカート丈で押し問答母に短し私に長し〉。登校前のひともんちゃくが楽しい。バブル世代のお母さんは、若き日のボディコンを棚に上げて説教する▼服装史は男女とも、東洋はズボン、西洋はスカート型で始まるそうだ。欧州の男性が活動的なズボンに移行しても、地位が低かった女性はスカートに取り残されたという。片や「女らしさ」を求められた日本女性。農民以外はズボン型を捨て、明治以降も着物に封じられた▼和洋、男女の垣根が消えた街に「スカート男子」が出没する世。女子には、母娘の妥協の産物か、レギンスやジーンズの上にミニといういでたちがある。服に縛られぬ世は幸せだ。ただしその幸せはいつも、自己責任と「重ね着」になる。(今日天声人語後半)
天声人語にとっては、この世界の<出来事>すべてが、母娘の会話に、“おとしこまれる”。
この“みじめな(痴呆的な)”家族主義人間の<自己責任>に解消される。
ぼくは何度も言っているが、“家族という関係のなかの人間同士”が関係できるか否かの重要性は(それを<愛>といってもいい)、“家族主義”の対極にある。
この一点においても、天声人語的ヒューマニズムは、まったくの<空語>(からっぽの言葉)である。
ある時代の<記号>や<ファッション>に、“その存在の重さ”があったか否かを、判定するのは、現在のぼくらの<認識>である。
現在において、ぼくは、“そのようなひと”を発見することに、喜びを見出す。
♪ ジミ・ヘンドリックス ロックロール・ニガー
二ガー、ニガー、ニガー、ニガー ロックンロール・ニガー ♪