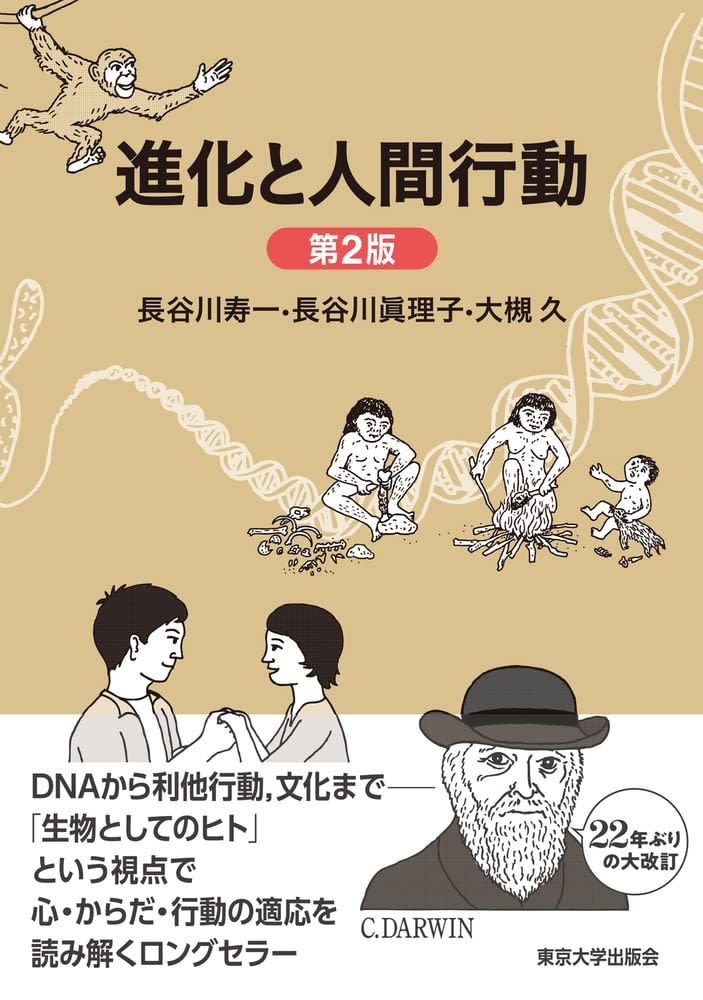
進化心理学、あるいは人間行動進化学の教科書的な本が読みたいと思って探したところ、本書の第1版に行き着いたのだけれど、出版が2000年とやや古い。そうこうしているうちに、改訂されて第2版が出るという情報を得たので、待っていたら2022年4月についに出たのが本書である。待ったかいのあった、良い本であった。とくに「第9章 血縁に寄らない協力行動の進化」の内容は、非常に勉強になったし、血縁のない他者との協力行動がここまで科学的に説明ができるようになったのかという感慨を持つことができた。本書の章立てと、注目した内容をまとめておきたい。
第1章 人間の本性の探求
第2章 古典的な進化学
第3章 現代の分子進化学
第4章 「種の保存」の誤り
第5章 霊長類の進化
第6章 人間の進化
第7種 ヒトの生活史戦略
第8章 血縁淘汰と家族
第9章 血縁によらない協力行動の進化
第10章 雄と雌:性淘汰の理論
第11章 ヒトにおける性淘汰
第12章 ヒトの心の進化へのアプローチ
第13章 ヒトにおける文化の重要性
[まえがき]この20年間の人間行動進化学の大きな進展が三つ挙げられている。①進化的基盤を持つ人間の本性と文化的影響の交絡が、様々な研究によって解明されるようになった。20年前に協調されていたヒューマン・ユニヴァーサルズ(人間行動の普遍性)や通文化性に対して、文化的ゆらぎが大きいことが再認識されるようになった。②協力行動や利他行動の進化に関する研究が理論・実証の両面で大きく進展した。数理生物学や実験社会科学との交流により、特に間接互恵性に関する研究が進んだ。③隣接領域である進化人類学と認知神経科学(脳科学)の発展により、人間行動の進化基盤と神経基盤の解明が進んだ。前者としては、アルディピテクス・ラミダスの詳細な解析、ホモ・サピエンスとネアンデルタール人・デニソワ人との交配の事実などがあり、後者としては、行動と認知の神経基盤について、他の動物との共通性と相違点について多くの事実が明らかになったことがある。
[第1章 人間の本性の探求]エドワード・ウィルソンは、1975年の著書「社会生物学」において、心理学、社会学、文化人類学、法学、倫理学などの人文・社会系の学問は、社会生物学という名のもとに、遺伝子レベルの淘汰の理論で統一されるだろうと予言した。さすがにそれは誤りであったが、1990年代以降くらいから、伝統的な心理学、社会学、文化人類学、言語学、法学、経済学、美学、倫理学、哲学などの分野から、人間性の進化的基盤を探求する研究がたくさん現れてきた(デネット、スパーバー、スカイムス、ホジソン、アレクサンダー、ペトリノヴィッチ、ピンカー、スコット-フィリップス、トマセロなど)。
[第3章 現代の分子進化学]行動が、遺伝によっているのか学習によっているのかは議論のあるところだが、人間以外の動物では遺伝による部分が大きいようである。例えば、ボタンインコ属に属するルイゴシボタンインコとコザクラインコは、巣材の運び方に違いがある。前者は葉の切れ端などの巣材をくちばしに一つずつくわえて運ぶのに対し、後者は体の後ろの羽毛の間に巣材をいくつかはさみこみ運ぶという行動を見せる。これら2種の交雑個体の行動を調べたとところ、くちばしでくわえて運ぶか羽にはさみこんで運ぶか、それらの間を決めかねるような行動を示した。数カ月が過ぎると、より高い頻度でくちばしで運ぶようになったが、巣材を羽の間にはさみこもうとするそぶりも見せた。そして、このようなそぶりをほとんど見せなくなるには、3年もの期間を要した。おそらくは3年間の学習の成果と考えられるが、遺伝的な要素がいかに行動に影響を与えるかを示す一例となっている。
[第4章 「種の保存」の誤り]現在、個体淘汰によって行動は進化してきたという考え方が主流になっている。しかし、群淘汰での説明が人々には好まれる。自己の利益だけに基づいた個体淘汰の説明は、話としては非常に利己的に聞こえる。なわばり行動を「自己の利益のため」と言うよりは、「皆で資源を均等に使うため」と説明するほうが、聞いている人の耳には心地よいだろう。協力や助け合いといった行動が私たちヒトの身近に存在し、生きていくのに必須な行動で、親からもしっかりと教育される行動である。私たちヒトが、他者との協力に依存して暮らしている種であることは、また別の説明がされている。
[第5章 霊長類の進化]心理学では、他者の心的状態(意図や欲求、信念など)を推測する能力を「心の理論」(theory of mind)と呼ぶ。「心の理論」は、心理学者のデイヴィッド・プレマックが最初に提唱した心の機能で、プレマックは類人猿が「心の理論」を有するかを問題にした。なぜ「心の理論」が心的能力かと言えば、他者にも心というものが宿っていると見なせるか、すなわち他者にも自分と同様に「心という内的理論体系」があるとみなせるかどうかについての能力だからである。ヒヒの群れでは「戦術的欺き」が観察されるが、これが本当に他者の心的状態を推測していることなのかどうかを実証するのは困難である。別の機会に「条件づけ」として学んでいるだけかもしれない。
[第6章 人類の進化]リチャード・ランガムは、人類における火の利用と調理の開始は通説よりはるかに古く初期ヒト属までさかのぼると考察し、火の利用の開始が人類進化上の画期的な出来事だったと論じた。火の利用により、様々な利点がもたらされたが、加熱調理により効率的なエネルギー摂取が可能になり、脳の進化が促されたと論じている。男女の絆の強化と家族(夫婦)の成立も火の賜物だという。現代のキャンプファイアーや暖炉でもそうだが、火にはヒトの心をおだやかにする機能もあり、共同体生活がうながされたとも考えられている。ちなみに、私は当初、バーベキューのために炭に火をおこすことができなくて、妻にずいぶんバカにされたことがある。火をおこせる能力なんて趣味人か昔の人の技術だと思っていたのだけれど、実は現代においても、男性の(生きていくための)能力として女性から重要視されるものなのだということを、これを読んで納得した。
[第8章 血縁淘汰と家族]「利他行動」という言葉を最近よく見かけるが、なんなのかきちんとわかっていないような気がする。単に他人の役に立つことをするのが「利他行動」ではない。「利他行動」とは、自らの行為によって自分の適応度(利益)が減少し、他者の適応度が増加することである。自分は損をする行動なのだ。ここでは、ある行動を、①自己の適応度が増加したか否か、②他者の適応度が増加したか否かの二つの側面で、4種類に分類している。自己も他者も適応度が増加するのが相互扶助行動、自己の適応度は増加するが他者の適応度は減少するのが利己行動、自己も他者も適応度が減少するのが意地悪行動、自己の適応度は減少するが他者の適応度が増加するのが上記した利他行動となる。最近、頻繁に事件が起きている、他人を巻き添えにして自分も死ぬというテロリズムは意地悪行動に該当するのだろう。
自分と同じ遺伝子を持つ他者、つまり血縁者に対して利他的行動を行うことは自分の遺伝子を広げることにつながるので進化してきたという考え方が、現在主流の血縁淘汰説である。では、生物はどうやって自らの血縁と非血縁を認識しているのだろうか。一つ目は「表現型マッチング」で、見た目、匂い、音など、知覚できる何らかの手がかりを使って自分と相手のそれが似ているかを判断し、似ていれば血縁者であろうと判断する方法である。しかし、この方法のためには、優れた感覚器とそれを利用するための優れた神経基盤を持っていなくてはならず、ヒトではこの方法による血縁認識はとても難しいと考えられている。よく、娘が父親を臭いというのは、近親婚を避けるために、個人ごとに異なりかつ遺伝するタンパク質であるHLAの匂いを嗅ぎ分けているのかもしれないなどと言われることがあるが、単なる俗説なのかもしれない。二つ目は、「物理的近縁性」で、親子やきょうだい、および血縁者はしばしば物理的に近い場所に存在する傾向がある。「物理的に近くにいること」が「血縁者であること」を示唆し、血縁認識をすることができる。三つ目は、ヒト特有であり、ヒトにおいて最も重要な血縁認識の方法である「親族呼称」である。私たちの言語には、自己と血縁者との関係性を詳細に表す単語ー父親、姉、息子、おじ、おい、祖母、いとこ、大おじ、などーがたくさん存在する。これらの呼称を繰り返し用いることで、ヒトは明示的な血縁認識をしている。
[第9章 血縁によらない協力行動の進化]血縁によらない協力行動を進化させる仕組みは、リチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子」にも説明されていたが、血縁選択性の陰に隠れてしまってあまり印象に残っていない。本書ではこのような仕組みとして、直接互恵性、裏切り者検知、間接互恵性が明示的に示されている。直接互恵性は、互恵的利他行動とも呼ばれ、ロバート・トリヴァースが示したロジックである。XとYの間で、互いに利他行動を行うことで、コストより利益のほうが大きければ、両者の適応度の上昇に結びつき、このような行動は進化するというものである。友人とのものの貸し借りや隣人との助け合いなどが、直接互恵性の好例である。しかし、ヒト以外の動物で直接互恵性が存在するかどうかは否定的な見解が多いという。
レダ・コスミデスとジョン・トゥービーは進化心理学という学問の名づけ親である。彼らは、直接互恵性が強い淘汰圧となった結果、ヒトの心は裏切り者検知がとても得意なように進化したはずだと考えた。「裏切り」とは、対価となるコストを支払わずに、利益だけ得る行為である。「利益を受けるものは必ずその対価を支払っていなければならない」というルールが、社会契約の基本であり、ヒトは裏切り者に対して特別に敏感に反応する性質を有していることは、実験などでも実証されている。
直接互恵性のような当事者同士の二者間の仕組みと違い、協力の受け手以外の第三者が協力者にお返しをすることで行われる協力の受け渡しのしくみを、間接互恵性と呼ぶ。間接互恵性において協力を提供した人物は、社会からよい評判を得て、またその評判によって自分が困ったときに社会の誰かから助けてもらうことができる。リチャード・アレクザンダーは、間接互恵性こそ私たちの道徳システムの起源であろうと述べている。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます