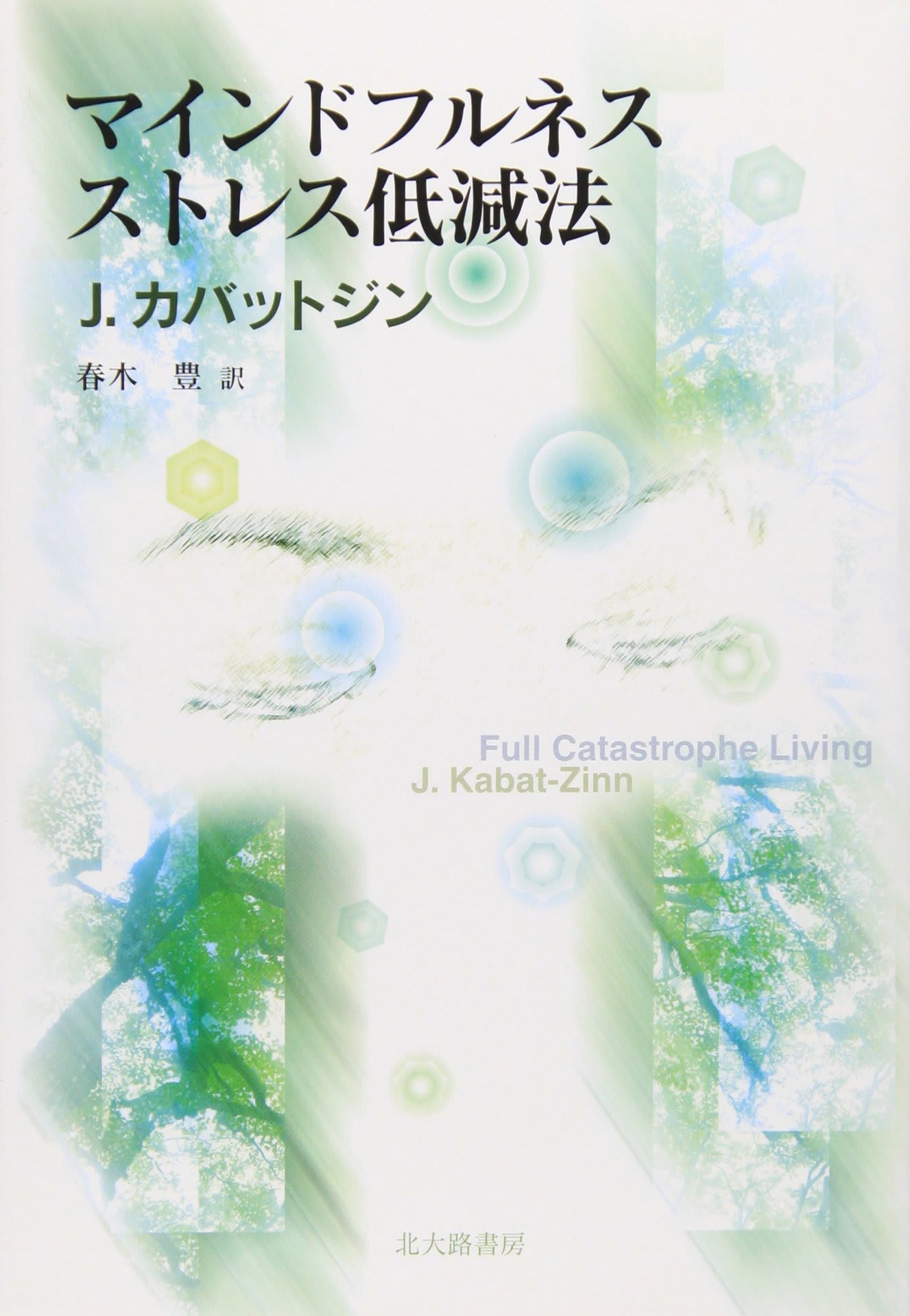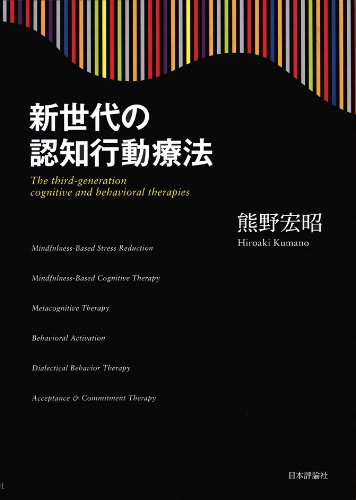アドラー心理学は、心理療法というより、子どもの教育法としての面が強い。今注目されているEQ、あるいは非認知スキルを高める教育法に近いと思う。この本は筆者たち夫婦による子育ての成功談を述べた自慢話だという評もあるが、アドラー心理学の専門家がアドラー心理学に則って自分たちの子育てを行ったら、理想的な人間に育ったという実例があるからこそ、他人にも勧められるわけで、子育てが成功したことを示してもらうことは無意味なことではない。この本の内容の多くは、著者の奥さんの育児日記を元にしている部分が大きい。常識的な子育てとは一線を画しているが含蓄のある、アドラー心理学による教育法を参考にして、取り入れられることは取り入れるつもりで読んでみるのもわるくないと思う。
・この本の全体を貫く子育ての4つのキーワードは、尊敬、共感、信頼、勇気である。
・子どもの行動には、適切な行動と不適切な行動があるが、大部分は適切な行動をとっていると言える。不適切な行動をするのは、適切な方法を知らなかったからということもある。そんな時には、頭ごなしに怒るのでなく、この場でそれをするのはよくないよと教えてあげればいい。不適切な行動の多くの場合、注目されたいという目的がある。そういう時はその行動に注目しないようにする。不適切な行動以外の当たり前のことにこそ注目する。
・子どもに何かを頼むときは命令口調ではなく、お願い口調でする。たとえ人生経験が少なく未熟な子どもであっても、一人の人間としての尊敬は大人と変わりないのである。協力してくれたら、ありがとうと感謝する。
・親が子どもの行動に怒りを爆発させたくなる時、怒りという二次感情の裏に、心配、不安、落胆などの一時感情が隠れているものだ。だから、子どもには怒りをぶつけるのではなく、その裏にある一時感情を伝えるといい。それは、大人同士、夫婦間や職場での役に立つ考え方である。子どもにもそういう表現の仕方を教えると、主張的な表現ができるようになったり、感情処理が上手になったりする。
・子どもは、失敗を繰り返しながら成長していく。失敗をするから、違うやり方を考えたり、今度こそはと工夫を加えたりすることで新たな意欲を持つからだ。子どもを尊敬、共感、信頼しているのなら、失敗したときこそ子供を勇気づける言葉をかけてあげる。
・アドラー心理学の教育法は、ほめない、しからない、でよく知られている。ほめることと勇気づけることは違っている。ほめることは、外発的動機づけに属し、子どもが内発的動機づけで自ら取り組もうとする意欲を失わせる。ほめることで成功しても、ほめることをしなくなれば、子どもは課題に取り組まなくなる。ただし、まだ内発的動機づけの心の装置が確立されていない、乳児・幼児の時期は、ほめることが効果的であることは認めている。しかし、子どもが内発的動機づけで自分を動かせるようになったら、勇気づけの出番である。
・子育ての最終目標は、「社会性」「創意工夫力」「臨機応変力」を育てることであり、それが育つよう「自立心」「責任感」「貢献感」を子どもが身につけられるよう支援することである。親が子どもに接する際は、いつも「親が・・・すると、子どもは何を学ぶか?」の判断基準を持っていること。社会性に関して、アドラー心理学が対人関係で実践しているメソッドが「友人に対して使うとその友人が交際を断ちたくなる言葉は、誰に対しても使わない」というのがあり、これは親子関係にも当てはまる。親と子は上下関係ではなく、役割が違っていても対等の関係にあるからだ。
・子育て中の親の夫婦関係として、妻の心理ケアのために夫は妻の話を聴くこと、それも助言、解釈、肩代わりを加えずに、とにかく聴くことを提唱している。それが妻への勇気づけになる。また、夫婦の役割分担は、それぞれの夫婦間で取り決めることが大事で、時間や労働量で均等にすればよい、というものではない。それはよく話し合って決める。