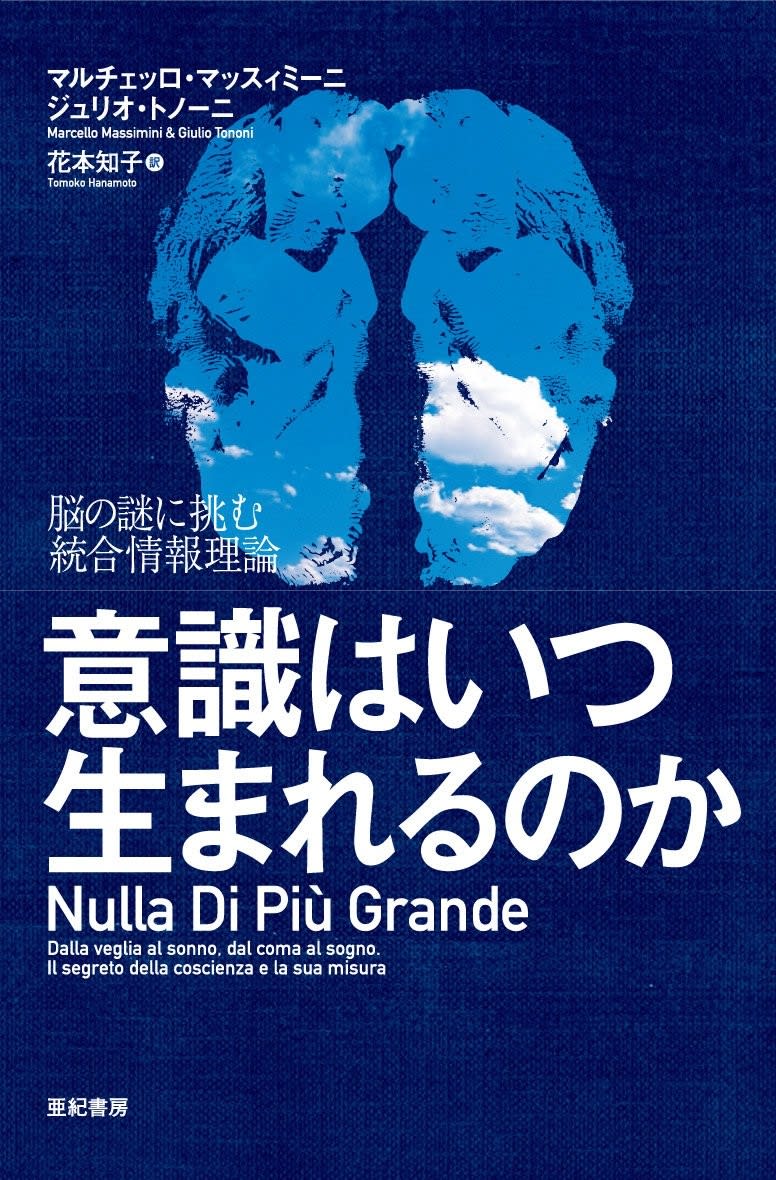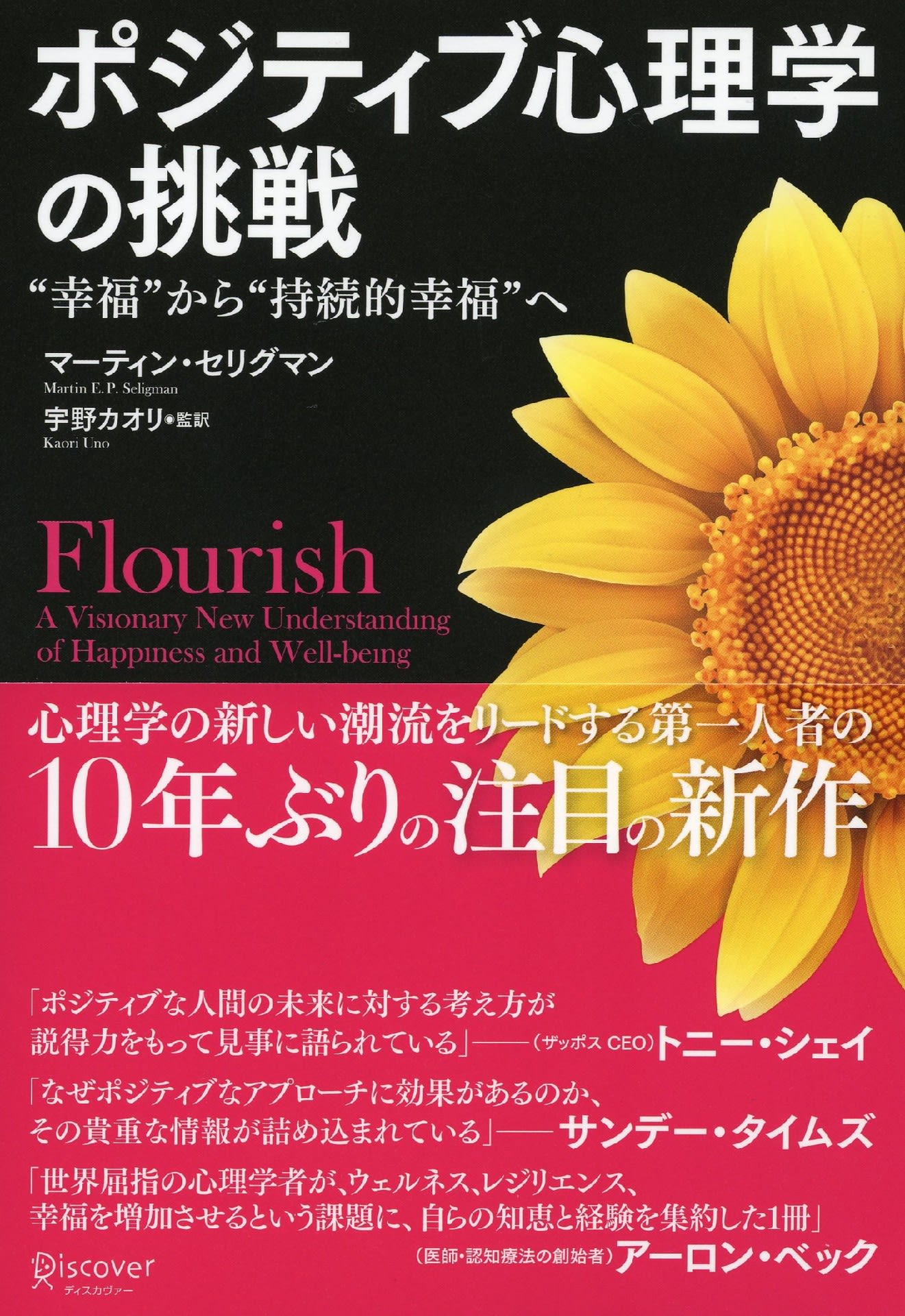
ポジティブ・シンキングと混同しやすいが、ポジティブ心理学は全くちがう概念である。そして、おもに医師が担っている精神疾患の治療を目的とした精神医学とも違っていて、おもに心理学者が担っている病者以外の人の心をより良くすることを目的としたプラクティスの一つがポジティブ心理学である。しかし、うつ病やPTSDなどの患者が対象範囲に含まれる場合もある。著者のマーティン・セリグマンはポジティブ心理学の創始者であり、アメリカ心理学会会長も歴任している。本書は、米国で2011年、日本で2014年に出版された、この分野では最新、最良のテキストだと思われる。しかし、内容は教科書的ではなく、著者たちによるこの新しい心理学分野の普及に向けた挑戦のエピソードを織り交ぜながら書かれているので、読みやすくできている。
現在、医学分野での精神療法・心理療法としては認知行動療法が主流となり、その派生であるマインドフルネスが医療だけでなく広く産業界も含めて活用されていて、私も生活の一部に取り入れている。しかし、そこから少し離れて、脳の中でポジティブな記憶とネガティブな記憶が互いに拮抗しているという生物学的な発見や、過敏性への対処のためにポジティブ心理学の有効性が示唆されていること(「過敏で傷つきやすい人たち」岡田尊司著)などから、前から気になっていて読んだのが本書である。
各章ごとに要点をまとめてみた。
第1章・ウェルビーイングとは何か?
・幸せの1つの要素「エンゲージメント」=「フロー」状態を得るために重要なのは、自分の最高の強みを見つけて、それらの強みを頻繁に活用することを学ぶことである。強みを見つけるための「VIA・強みテスト」は「ポジティブ心理学 ペンシルベニア大学公式サイト」(日本語版あり)で無料受検できるし、本書の巻末に簡略版の「強みテスト」が付録として付いている。
・かつてのポジティブ心理学のテーマは、「幸せ」であり、「幸せ」の判断基準は「人生の満足度」であった。しかし現在は、ポジティブ心理学のテーマは「ウェルビーイング」であり、「ウェルビーイング」の判断基準は「持続的幸福度(flourishing)」と考えられている。
・ウェルビーイング理論は、5つの要素「ポジティブ感情」、「エンゲージメント」、「意味・意義」、ポジティブな「関係性」、「達成」からなる。これら5つの要素の頭文字を取って「PERMA」と表される。「ポジティブ感情(P: Positive emotion)」の中の単なる一要素が、主観的尺度である幸福感と人生の満足度という位置づけになっている。「エンゲージメント(E: Engagement)」は、主観によってのみ測定される「自分にとって時は止まっていたか?」「自分は仕事に完全に没頭していたか?」「自分は没我状態にあったか?」などが含まれる。「意味・意義(M: Meaning)」は、自分よりも大きいと信じる存在に属して仕えることであり、主観的な判断だけではなく、公正かつ客観的な判断も含まれる。「達成(A: Achievement)」は、そのもののよさのために追及されるものだ。「関係性(R: Relationships)」は、他者との関わり、他人に親切にすることである。
・幸福理論を人生の指針とすると、自分の老いた両親を放置してしまったり、夫婦は子どもを持たないという選択をするかもしれない。一方、ウェルビーイングが意味と関係性を含むものとして視野を広げると、なぜ夫婦が子どもを持つことを選ぶのか、なぜ自分の老いた両親を世話することを選ぶのか、理由が明らかになる。
第2章・幸せを創造するーポジティブ心理学エクササイズ
・「うまくいったことエクササイズ」毎晩寝る前の10分間で、今日うまくいったことを3つ書き出して、それらがどうしてうまくいったのかを書く。日記でもパソコンでもなんでもいいが、書いたものの物理的な記録を残しておくことが大事である。3つの出来事は重大なことでもそうでなくてもよい。これを続けると、6ヵ月後には、落ち込むことが少なくなり、幸せになるという。
・「特徴的強みエクササイズ」自分の特徴的強みを新しい方法で、かつ頻繁に活用することで、その強みを自分のものにするように働きかけることが目的だ。特徴的強みの活用で得られるものは、当事者意識と本来感(本当の自分らしさ)、高揚感・喜び・活力・恍惚感、学習曲線の急上昇、新しい方法を見つけたいという渇望感、活用することへの必然性の感覚などがある。やり方としては、上記の「VIA・強みテスト」を受けて、自分の強みの上位5位を見つける。テストの後、今週決まった時間を設け、職場か、自宅か、余暇で、一つかそれ以上の自分の特徴的強みを新しい方法で活用する。その時、強みを使う機会を決めておく。例えば、自分の強みが「創造性」の場合、脚本の執筆を始めるために、ある晩に2時間取ってみる。また、自分の強みが「審美眼」の場合、通勤に20分余分にかかるとしても、職場との行き帰りに遠回りの、美しい道を選んでみる、などだ。そのエクササイズの前、最中、後でどう感じたか、自分の経験を書いてみる。
第3章・薬とセラピーの”ばつの悪い秘密”
・「積極的-建設的反応のエクササイズ」自分が大切に思う人たちは、彼らの勝利や成功や好ましい出来事についてよく話してくれるものだ。それに対して、こちらがどのように反応するかで、相手との関係性を築くか壊すかが決まる。反応する方法は、積極的か受動的か、また建設的か破壊的かによって、4つの組み合わせがある。そのうち、積極的×建設的な反応だけが相手との関係性を築く方向に作用する。エクササイズとして、1週間、自分が大切に思う相手の身に起きたよい出来事について、相手が自分に話してくれるたびに、注意深く耳を傾け、積極的に、かつ建設的に反応する努力をしてみる。そして、「相手の出来事」「自分の反応」「自分に対する相手の反応」を毎晩記録する。これが得意でない場合は、最近見聞きしたポジティブな出来事を書きとめ、自分がどのように反応すべきであったかを書き出してみる。あるいは、朝目覚めたとき、5分間、今日出会う人たちがどんなよいことを話してくれるか思い浮かべ、積極的×建設的な反応をする準備をしてみる。こうしたことは自然に習得されるものではないので、勤勉に努力しながら習慣化されるまで訓練を重ねていく。
・大部分のパーソナリティ特性は強力な生物学的基盤があるものだ。人は悲しみや不安、宗教性などの強い傾向を遺伝的に受け継いでいる可能性がある。だから、現実的なアプローチは、悲しみや、不安や、怒りの只中にあっても、うまく機能することを学ぶこと、つまり、ネガティブ感情とつき合うことである。リンカーンもチャーチルも重度のうつ病患者であったが、彼らは憂うつ症や自殺願望と付き合いながら大変よく機能した人間である。こうした人たちの課題は、このような感情と闘いながらも堂々と生きることである。
・セリグマンにとって大きな転機は、1970年から71年まで、アーロン・ベック(認知療法の創始者)の下で精神医学の研修を受けたときである。ベックのアドバイスによって、動物実験を行う実験心理学者から、現実の人間に向き合う応用心理学者に転身したのである。
第4章・ペンシルベニア大学MAPPプログラム
・セリグマンは、ポジティブ心理学を習得するためのコースをいくつか作ってきた。その一つが、ペンシルベニア大学MAPPプログラム(応用ポジティブ心理学修士課程)である。その教授陣の一人で、ポジティブ感情研究の第一人者であるバーバラ・フレドリクソンは、ロサダ比を提唱している。ロサダ比とは、ポジティブな発言対ネガティブな発言の比率のことである。例えば、会社の経営は、2.9:1の比率を上回ると良好で、下回ると悪化している。結婚生活は、2.9:1では離婚を招く、愛情に溢れた結婚生活には5:1が必要だという。
・労働(ジョブ)、仕事(キャリア)、天職(コーリング)という区別がある。人はお金のために労働をする。お金がストップすれば働くことをやめる。昇進のために仕事を続ける。昇進がストップするか頭打ちになれば、仕事をやめるか日和見主義の抜け殻となる。それとは対照的に、天職は、それ自体の目的のために完遂される。給料や昇進なしでも従事するものだ。天職とは、選んで行動するのではなく、選ばれて・向うから呼ばれて(コーリング)行動することである。
第5章・ポジティブ教育ー学校でウェルビーイングを教える
・ウェルビーイングを学校で教えることで、抑うつ患者の急増に対する特効薬となり、人生の満足度を向上させ、よりよい学習や創造的な思考を促す助けになる。学校向けのプログラム「ペン(ペンシルベニア大学)・レジリエンシー・プログラム」(PRP)において、効果を実証してきた。
第6章・知性に関する新理論ー根気、徳性、達成
・人間は過去(環境、遺伝)に突き動かされる存在なのか、未来(自由意志)に引き寄せられる存在なのかという2つの考え方がある。従来の心理学は前者であったが、ポジティブ心理学は後者の立場に立つ。多くの場合、人は自らの行動に責任がある。そして、人の不運な選択は自らの徳性に起因している。責任と自由意志は、ポジティブ心理学においては必要なプロセスである。ポジティブ心理学では、劣悪な環境を解消していくだけでなく、自らの悪い徳性もよい徳性もともに特定した上で方向づけていくことで、世界をよりよい場所へと作り変えていくことが可能となると考える。
・「達成=スキルX努力」の基本方程式が成り立つ。この中のスキルとは認知的情報処理過程であり、その要素には、スピード、スローネス、学習率(知性の加速度)がある。一方、努力は非認知的要素であり、徳性、自制心(自己鍛錬)、自己コントロール(自己制御)、根気(GRIT)といった言葉でも表わされる。本書には「根気テスト」(GRIT尺度)が付いているので、自分で根気のレベルが測定できる。
第7章・アーミー・ストロングー総合的兵士健康度プログラム
・50年間、人間は基本的に利己的な存在であると考えるのが進化論における流行であった。リチャード・ドーキンスによる「利己的な遺伝子」によれば、血縁による利他的行動は説明ができるが、無関係の人への利他心は説明がつかない。セリグマンは、ダーウィンの群選択という考え方で説明ができるとして、こう述べている。「彼は、一つの集団(遺伝的に無関係な個人からなる)が競争集団よりも長く生存するか、または多く生殖する場合、勝ち組の遺伝子プール全体が増えると仮定した。協力行動、そしてそれを支える愛情、感謝、賞賛、ゆるしといった群居感情が、その集団の生き残りに有利に働いたことを想像してみるとよい」
・セリグマンは、陸軍の総合的兵士健康度プログラム(CSF)に協力してきた。軍隊において精神的な健康の鍵となるのは、レジリエンス(精神的回復力)である。社会的レジリエンスとは、ポジティブな社会的関係を促進させ、そこに全面的に関わり、維持させる力、ストレスや社会的孤立感に耐え抜き、立ち直る力である。社会面のレジリエンスとして、「共感」に重きが置かれている。他人が感じている感情を特定できる能力だ。
第8章・トラウマを成長に変える
・心的外傷後ストレス障害(PTSD)はよく知られているが、極端な逆境を経験した後で、激しい抑うつや不安、PTSDを示した後、人が成長し、以前より高いレベルで心理的に機能するようになる「心的外傷後成長」(PTG)が存在する。心理テストを行ったところ、人生でひどい出来事を経験した人は経験したことがない人に比べて強靭な強さ(ウェルビーイング度の高さ)を備えていた。さらに、ひどい出来事の数が多い人ほどそれは強かった。
・イラクとアフガニスタンでの戦争は、「携帯電話を持ち、戦闘の最前線からでも自分の奥さんに電話をかけられる初めての戦争」となった。イラク戦争の退役軍人の一人は「簡易爆発物を警戒するのは結構厄介ですが、食器洗いの分担や、子供の学校での成績のことでつまらないケンカをするのはもっと厄介ですよ。我々兵士の抑うつや不安の多くは、家で起きていることに原因があるのですよ」と述べている。家族内の人間関係はそうとうストレスの原因になるということである。
・苦境に立ったときに、リアルタイムで「破滅的な思い込み」に立ち向かうためのストラテジーは3つある。反証を集めること、楽観を使うこと、バランスと取れた見方をすることだ。例えば、妻とメールで連絡が取れなくなったとき、3段階モデルのバランスの取れた見方をしてみる。最悪のケース「家内が浮気している」、最高のケース「彼女は忍耐力もあって強い人だ。1秒たりとも心が揺らいだりすることはないさ」、最もあり得そうなケース「彼女は友人と出かけているんだな。今夜か明日にでも私にメールしてくれるだろう」を考えることで、破滅的な考え方「彼女は私のもとを去ったんだ」に対して反論する。
・セリグマンは陸軍に協力してきたことの心情を明かしている。「私はアメリカ合衆国を、ヨーロッパで死に至らしめる迫害を受けた自分の祖父母に、自分の子どもや孫たちが繁栄を築けるような安全な避難所を与えた国だと考えている。アメリカ陸軍のことは、私とナチスのガス室の間に立って闘ってくれた軍隊であると考えている」
第9章・ポジティブヘルスー楽観性の生物学
・セリグマンらは、1960年代半ばに「学習性無力感」を発見したことでも有名である。学習性無力感とは、最初に自らの力ではどうすることもできない不快な出来事を経験するやいなや受動的になり、困難に直面すると諦めてしまうことである。これは、動物実験によって発見された。そして、学習性無力感に陥ると、移植した腫瘍による死亡率が高まることを、1982年にサイエンス誌で発表したが、これが、彼が関与した最後の動物実験となった。その理由は、自分自身が動物好きであるため動物を苦しめることに大変な抵抗を感じていたこと、動物よりも人間を対象とするほうが興味を持つ問いに対して直接的なアプローチができること、動物実験を人間に当てはめようとすることには限界があるという外的妥当性の問題があるからであった。
・「学習性無力感」にはだれでもなるわけではない。およそ3分の1の人と動物は決して無力にならなかった。また、およそ10分の1の人と動物は最初から無力であった。ここで決して無力にならなかったのは、人生の妨げとなる出来事の原因が、一時的で、変わりやすく、局所的なものであると考える人たちであることがわかった。こうした人たちを楽観主義者と呼ぶ。反対に、いつも悲観的に考えてしまう人たちを悲観主義者と呼ぶ。
・ウェルビーイングの身体的健康に対する影響は調査結果から次のように考えられる。「楽観性は心血管の健康に、悲観性は心血管の危険性に強く関係している」「ポジティブな気分は風邪やインフルエンザの予防に、またネガティブな気分は風邪やインフルエンザに対するより大きな危険性に関係している」「非常に楽観的な人はガンになる危険性が低い可能性がある」「健康な人で、良好な心理的ウェルビーイングにある人は、全死因死亡に対する危険性が少ない」
・楽観性と同じように、運動も機能的な健康資産となる。軍医総監の2008年度の報告書では、成人が1日につき1万歩歩くのに相当する運動をする必要性が明記されている。歩く以外に、水泳、ランニング、ダンス、重量挙げ、ヨガなど、どんな方法でもよい。セリグマンは自ら、万歩計をつけた歩行者による同好会を立ち上げ、毎日ウォーキングを継続しているという。