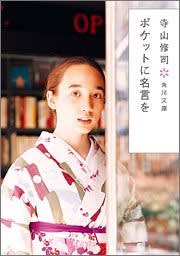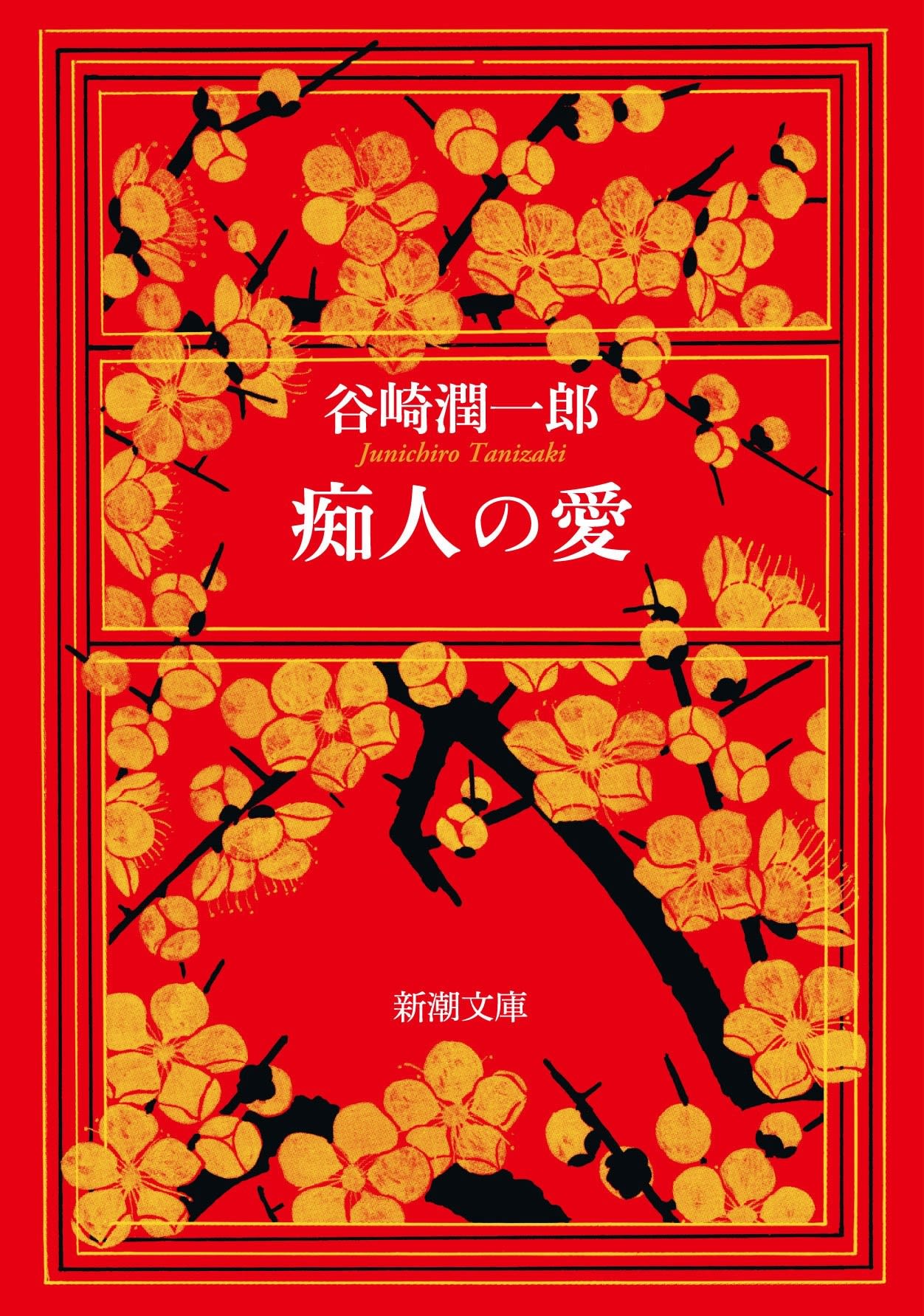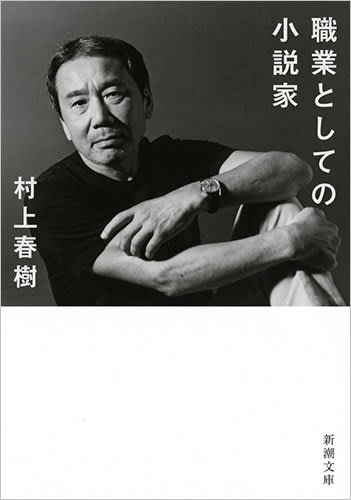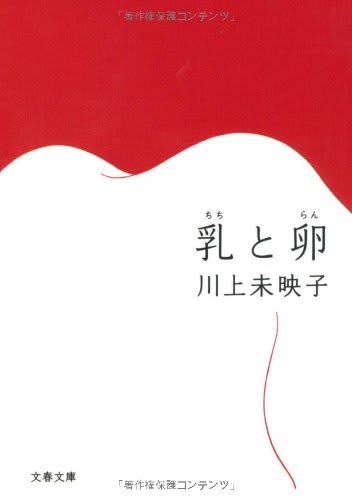ポーランドのSF作家スタニスワフ・レムの作品ソラリスは1961年に発表され、日本のSFファンによる人気投票では今でも必ず上位に入る人気作品だという。1972年にはアンドレイ・タルコフスキーによって、2002年にはスティーヴン・ソダーバーグによって映画化されている。私は両方とも映画を見ていて、かなり感動したことをよく覚えているが、原作はまだ読んでいなかった。本書では、レムによる原作とタルコフスキーによる映画の違いを述べていて、それはかなり本質的なことのようなので、やはり小説を読んでみないといけないのだろう。
各回のポイントを抽出してみた。
第1回:未知なるものとのコンタクト
近現代の文学作品で名作として名高いものには、解釈の多様性を許すという共通点があり、様々な読み方が可能である。ソラリスもそうであり、様々の批評家が様々な解釈をしてきた。(ちなみに私が映画を見て強く感じたのは、過去のことが再び現れるとしてもそれはイリュージョンのようなものであり、けっして本当の意味でのやり直しはできない。そのことの哀しみ、無常観であった)この小説の一つの大きなモチーフは、心の中のトラウマが実体化された存在、「お客さん」とか「幽体F」と呼ばれるものの出現と彼らとのかかわりである。
第2回:心の奥底にうごめくもの
人間の深層にあるトラウマや人間関係などに焦点を当てる精神分析にも似ているが、この小説は人間に回帰しない。人間の理性を越えた、ソラリスという惑星の「海」という完全に不可解なるものとのかかわりが主題だという。
第3回:人間とは何か 自己とは何か
主人公のクリスの前に、自殺をしたかつての恋人ハリーが「お客さん」として現れる。クリスは悲劇に終わった関係をもう一度やり直したいという思いにとりつかれ、切ないラヴ・ロマンスの様相を呈してくる。この恋愛小説の要素がなかったら、「ソラリス」はこれほどの世界的ベストセラーにはならなかっただろうといわれている。ソダーバーグの映画はこのラヴ・ロマンスの部分に焦点を当てていたが、レムはそれに不満だったという。
第4回:不完全な神々のたわむれ
ハリーはクリスを愛するがゆえに自殺する。しかし、クリスは地球には帰らず、ソラリスの海という絶対的他者と向き合い続けるという選択肢を選ぶ。そして海を「欠陥のある神」ととらえる。一方、タルコフスキーの映画では、クリスは地球という懐かしいものへと帰っていくという描かれ方をしている。ここにもレムは大変不満で、議論の末タルコフスキーとけんか別れしている。映画と比べて原作は結末が難解になっているのかもしれないが、やはり読んで確かめてみる必要がありそうだ。
宇宙を感じさせる音楽を作り続けてきたのはこの人をおいて他にいないだろう。SF映画の主演をいくつもやっているが、生前「ブレードランナー2049」へのキャスティングも計画されていたという。さて、この曲とPVは、暗鬱でわけの分からないところが「ソラリス」のようだ。
David Bowie - Blackstar