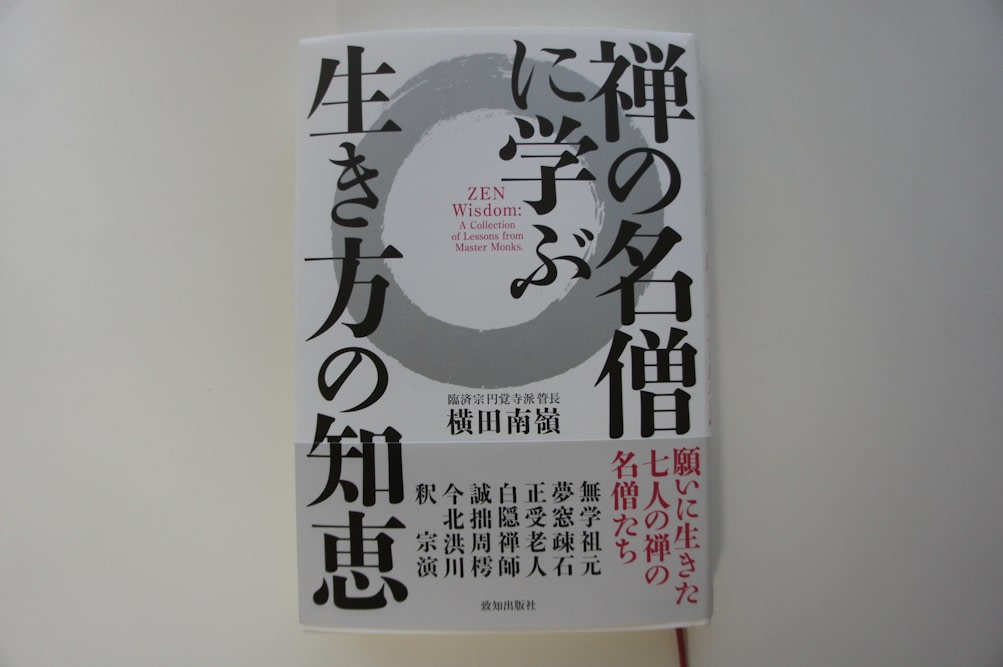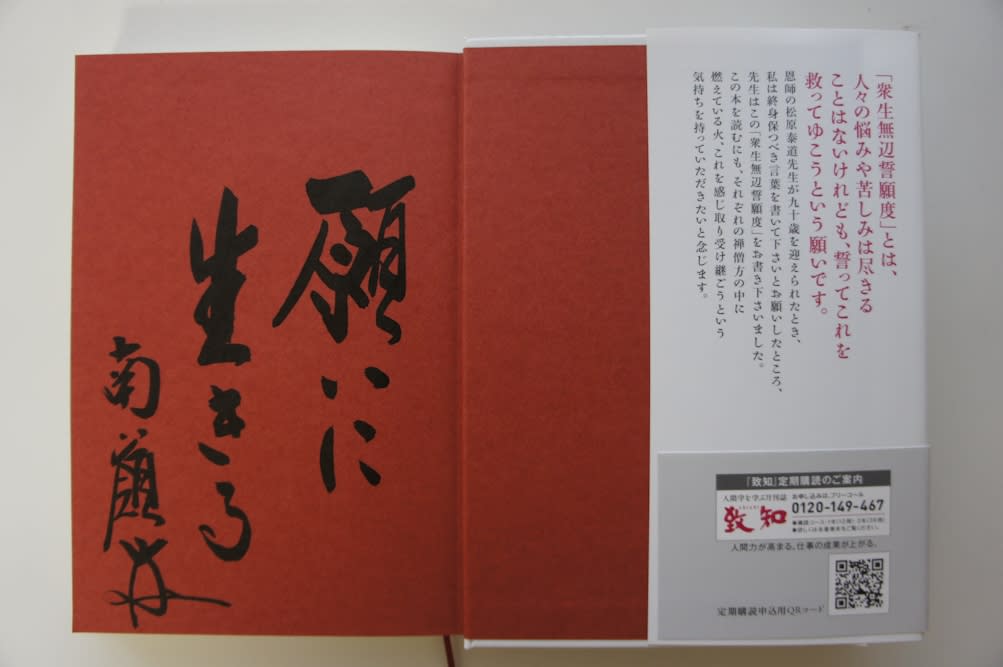最近脚光をあびているマインドフルネス瞑想という心理療法があります。私も最近取り組み始めました。もとは、東南アジアで伝統的に受け継がれている上座部仏教(原始仏教)が行ってきた瞑想法を現代の医学に取り込んだものです。その創始者であるジョン・カバットジンの著書(マインドフルネスストレス低減法」北大路書房)には「日本の読者の皆さんへ」の中で、鈴木大拙、鈴木俊隆、道元といった日本の禅師たちに大きな影響を受けたことが述べられています。だから、このマインドフルネス瞑想法の中には、「呼吸法」、あるいは「呼吸に集中する静座瞑想法」という坐禅にとても近いエクササイズがあるのは不思議なことではありません。そこでは、雑念の扱い方についてじつに明確な説明がされています。
「自分の心が呼吸から離れたことに気がついたら、そのたびに呼吸から注意をそらせたものは何かを確認してから、静かに腹部に注意を戻し、息が出たり入ったりするのを感じとってください。心が呼吸から離れてほかのことを考え始めるたびに、呼吸に注意を引き戻すのがあなたの仕事です。どんなことに気をとられようとも、そのたびに注意を呼吸に引き戻してください。」(呼吸法のエクササイズ1-正式なトレーニング、p.89)
雑念が浮かんだら呼吸に注意を戻すことが呼吸法の重要な作業だということで、臨済宗で言われていることと基本的に同じことが勧められています。
「心の中を常にさまざまな思いがよぎっていること、そして、その思いは自分が意識的に考えようとして生じてきたものではないということがわかれば、その思いは瞑想をさらに深めていくための大きな一歩になるはずです。」(心にわいてくる思いをどう扱うか、p.101-102)
「自分の思いを手放すというのは、おし殺すという意味ではありません。瞑想とは自分の思いや感じを閉めだすことだと思いこんでいる人もいますが、これはまちがいです。何かを考えてしまうことが“悪い瞑想”で、何も考えないことが“良い瞑想”である、というふうに考えてはいけません。思い違いをしないように強調しておきますが、瞑想中に何かを考えるのは、悪いことでも望ましくないことでもありません。問題は、考えていることに気がつくかどうかということ、そして気がついた時点でどうするかということなのです。」(心にわいてくる思いをどう扱うか、p.103-104)
瞑想中に雑念が浮かんでくることは悪いことではなく、それに気づいて雑念を手放して呼吸への集中に戻れることが重要であると言われています。そして、その雑念は自分が意識して考えたことではないこと、自分の考えではないということに気づくことが大切だと述べられています。その雑念とは自動思考とか無意識といってもいいのかもしれません。それに気づくこと、重要視しないこと、受け流すこと、そこにマインドフルネスの根本があるように思います。(完)
「自分の心が呼吸から離れたことに気がついたら、そのたびに呼吸から注意をそらせたものは何かを確認してから、静かに腹部に注意を戻し、息が出たり入ったりするのを感じとってください。心が呼吸から離れてほかのことを考え始めるたびに、呼吸に注意を引き戻すのがあなたの仕事です。どんなことに気をとられようとも、そのたびに注意を呼吸に引き戻してください。」(呼吸法のエクササイズ1-正式なトレーニング、p.89)
雑念が浮かんだら呼吸に注意を戻すことが呼吸法の重要な作業だということで、臨済宗で言われていることと基本的に同じことが勧められています。
「心の中を常にさまざまな思いがよぎっていること、そして、その思いは自分が意識的に考えようとして生じてきたものではないということがわかれば、その思いは瞑想をさらに深めていくための大きな一歩になるはずです。」(心にわいてくる思いをどう扱うか、p.101-102)
「自分の思いを手放すというのは、おし殺すという意味ではありません。瞑想とは自分の思いや感じを閉めだすことだと思いこんでいる人もいますが、これはまちがいです。何かを考えてしまうことが“悪い瞑想”で、何も考えないことが“良い瞑想”である、というふうに考えてはいけません。思い違いをしないように強調しておきますが、瞑想中に何かを考えるのは、悪いことでも望ましくないことでもありません。問題は、考えていることに気がつくかどうかということ、そして気がついた時点でどうするかということなのです。」(心にわいてくる思いをどう扱うか、p.103-104)
瞑想中に雑念が浮かんでくることは悪いことではなく、それに気づいて雑念を手放して呼吸への集中に戻れることが重要であると言われています。そして、その雑念は自分が意識して考えたことではないこと、自分の考えではないということに気づくことが大切だと述べられています。その雑念とは自動思考とか無意識といってもいいのかもしれません。それに気づくこと、重要視しないこと、受け流すこと、そこにマインドフルネスの根本があるように思います。(完)