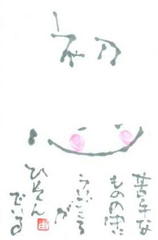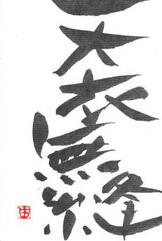「おとぎばなし」
「御伽(おとぎ)とは、身分の高い人の寝床に入って、
お相手をすることでした。戦国時代以降になると、
御伽衆といわれる職ができ(男性)、諸国の情報を伝えたり
雑談の相手をしたりするのが仕事でした。子供相手の話を
意味するようになったのは、明治時代以降のことだそうです。
大切な人の枕元で、交わされた、さまざまな言葉が御伽噺の
はじまり。子供に読んで聞かせる絵本や、お話の内容だけが
御伽噺ではなく、お母さん、お父さんの、一言一言が御伽噺
なのでしょうね。」(本文より抜粋)
寝る前に絵本を読んでやる。。。あまりしなかったです。
「おやすみ」「おやすみなさい」これも大切ですよねぇ~~
もう一度、育児を最初からやりたい(笑)
「御伽(おとぎ)とは、身分の高い人の寝床に入って、
お相手をすることでした。戦国時代以降になると、
御伽衆といわれる職ができ(男性)、諸国の情報を伝えたり
雑談の相手をしたりするのが仕事でした。子供相手の話を
意味するようになったのは、明治時代以降のことだそうです。
大切な人の枕元で、交わされた、さまざまな言葉が御伽噺の
はじまり。子供に読んで聞かせる絵本や、お話の内容だけが
御伽噺ではなく、お母さん、お父さんの、一言一言が御伽噺
なのでしょうね。」(本文より抜粋)
寝る前に絵本を読んでやる。。。あまりしなかったです。
「おやすみ」「おやすみなさい」これも大切ですよねぇ~~
もう一度、育児を最初からやりたい(笑)