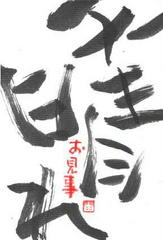「うらごい」
「昔は心のことを、「うら」といいました。表面に出ている顔などを
「面」というのに対して、隠れている内面は、「うら」とか、「下」という
言葉で表したのですね。~~~中略~~~心恋は、心の中で、恋しく
思うこと。まだ恋を意識しはじめたころの、あまく淡い想いです。
~~~後略~~~それにしても、心の裏をかく人や、下心のある人が
増えて、「うら」も「した」も、印象のいい言葉ではなくなってしま
いましたね。」 (本文より)
ほんとですね~ 「心恋」文字だけ見ていたら、ほんわか綺麗♪
ところが、声にだして、読むと。。。さえないです(笑)
「うらごい」が綺麗な言葉に聞こえる世の中にしないとねぇ~
「昔は心のことを、「うら」といいました。表面に出ている顔などを
「面」というのに対して、隠れている内面は、「うら」とか、「下」という
言葉で表したのですね。~~~中略~~~心恋は、心の中で、恋しく
思うこと。まだ恋を意識しはじめたころの、あまく淡い想いです。
~~~後略~~~それにしても、心の裏をかく人や、下心のある人が
増えて、「うら」も「した」も、印象のいい言葉ではなくなってしま
いましたね。」 (本文より)
ほんとですね~ 「心恋」文字だけ見ていたら、ほんわか綺麗♪
ところが、声にだして、読むと。。。さえないです(笑)
「うらごい」が綺麗な言葉に聞こえる世の中にしないとねぇ~