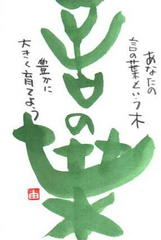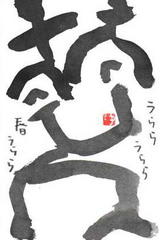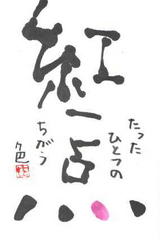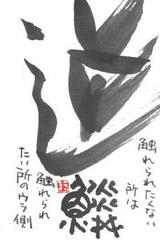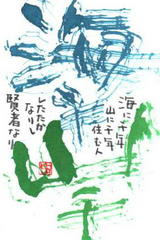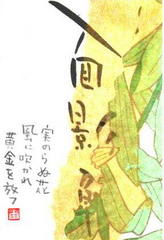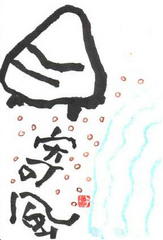「ありがとう」
「ありがとうは、「有り難し」が変化したものです。
「難し」は、難しいという意味ですから、「有り難し」は
「存在するのが難しい」・・・つまり、「めったにない」
という意味です。~~中略~~考えてみれば、私たちの周り
は奇跡に満ち溢れています。生まれてきたことも、生きて
いることも、出会いも、何もかもが、すべて奇跡です。
どんなにありがとうと言っても、決して及ぶことは
ないでしょう。」(本文より抜粋)
本、「美人の日本語」は今日、3月31日で終わりとなっています。
ところが、私がこのブログを始め、描きだしたのが4月23日から
なのです。そういう訳で、もう少しおつき合い下さいd(^_^o) ネッ
「ありがとうは、「有り難し」が変化したものです。
「難し」は、難しいという意味ですから、「有り難し」は
「存在するのが難しい」・・・つまり、「めったにない」
という意味です。~~中略~~考えてみれば、私たちの周り
は奇跡に満ち溢れています。生まれてきたことも、生きて
いることも、出会いも、何もかもが、すべて奇跡です。
どんなにありがとうと言っても、決して及ぶことは
ないでしょう。」(本文より抜粋)
本、「美人の日本語」は今日、3月31日で終わりとなっています。
ところが、私がこのブログを始め、描きだしたのが4月23日から
なのです。そういう訳で、もう少しおつき合い下さいd(^_^o) ネッ