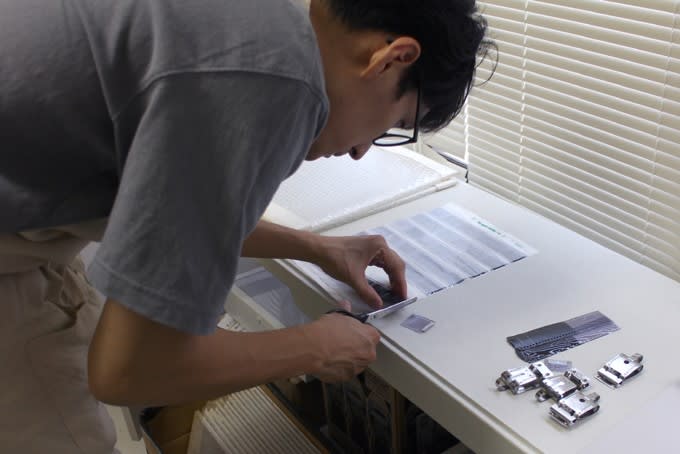2018年度の銀塩写真講座は3期に分けました。
Step1は暗室作業の基礎実習
Step2は写真史の学びから、自身が写真に関わる意義の研究
Step3はバライタ印画紙を使用する写真作品の制作
・・・という流れで進みます。
今回の講座レポートはStep2の初日の報告です。
*
Step2では写真史を知ることから始めます。
しかし、単に歴史を知るのではなく
体験を伴う理解を目指した内容です。
初日は写真誕生前から創成期のアレコレについて。
下の写真は
体験を伴う理解のために持ち出したTIPAオリジナル教材です。
昔、某美術館でのワークショップで開発したカメラオブスクラ。
黒の取っ手を抜くとレンズが存在します。
内部で虫眼鏡を貼り付けています。
裏面のカバーを開くと・・・
大型カメラのように
上下左右逆さの画像を見ることができる仕様です。
この教材は像を観察するだけでなく写し撮ることもできます。
感光紙を内部に貼り付け
撮影した後はアイロンで熱現像。
すると
・
・
・
青い湾曲した世界が仕上がります。
虫眼鏡レンズの歪が現実味をなくし
もう一つの世界の扉を開けたような写真です。
*
後半はナダールが撮影した肖像写真についての説明の中で
下の資料を紹介しました。
実際に手に取って写真を観察する中で気が付いたことがあります。
この写真を手にした感覚はスマートフォンと同じである!
手に収まるサイズの
なくてはならない存在ということですね。
記:徳永好恵
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
徳永写真美術研究所
大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。 ![]()

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・