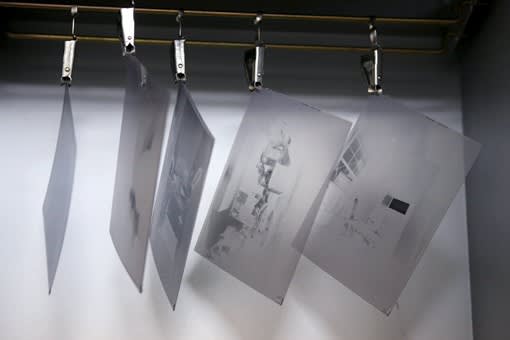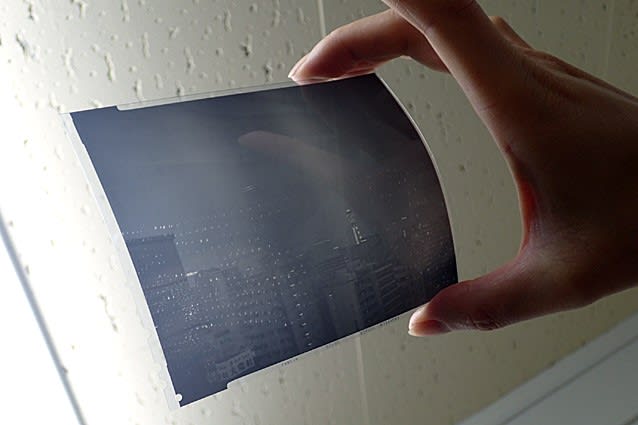2019年度の銀塩写真講座、初日のレポートです。
*
まずは写真の原理を知ることから。
今回
像を結ぶ現象を観察するために
3つのカメラオブスクラを準備しました。
カメラオブスクラとは
暗い部屋という意味です。
詳しくはWikiにて確認下さい。
最もシンプルな構造のカメラです。
ボール紙をコの字に折って孔をあけただけですが
おぼろげながらも画像を認識できます。
次は筒状
画像の投影面を動かせる仕組みです。
筒を覗いて見える画像がコチラ
左右上下反転画像が見えます。
↓
最後は・・・
虫眼鏡のレンズを取り付け
45度の傾斜をつけた鏡を内部に入れています。
レンズを使うことで
ピントを合わせる動作が必要となりますが
針孔よりも鮮明な画像を認識できます。
*
一通りの観察を終えたのち
次のピンホールカメラ撮影実習に使う
カメラを作りました。
作り方はカンタン。
六切印画紙が入るサイズの箱を用意し
内部を黒く塗ります。
そして
孔をあけた板を箱に取り付け・・・
印画紙を固定するためにペーパーセメントを塗り・・・
内部に光が入らぬように隙間テープを貼り・・・
黒布ガムテープでシャッターを作って完成。
次回は
このカメラを用いて撮影
そして
暗室での現像実習をおこないます。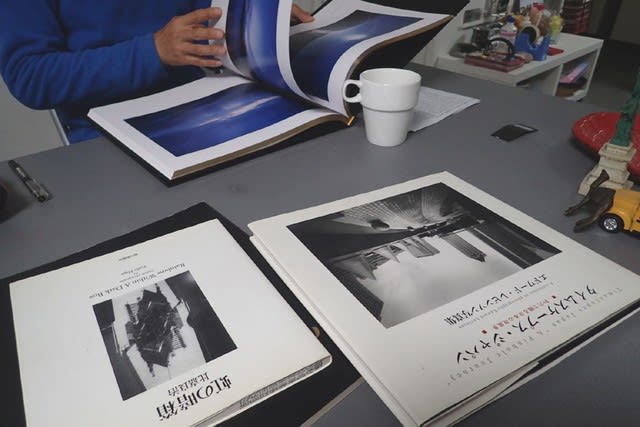
ティータイムでは
ピンホール写真作品集を見ながら
撮影計画を立てました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
徳永写真美術研究所
大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。