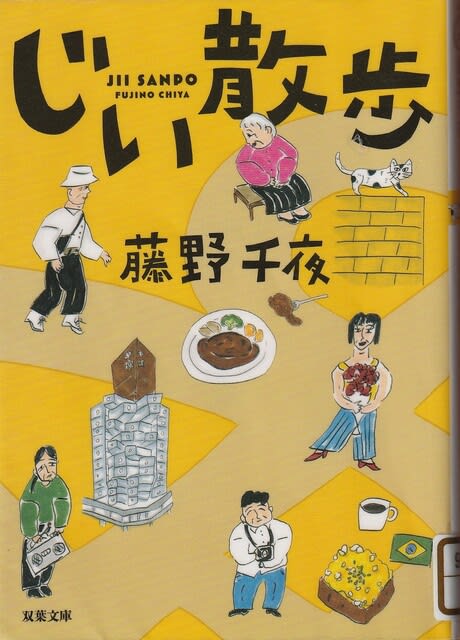図書館から借りていた、葉室麟著 「あおなり道場始末」(双葉社)を読み終えた。
本書は、九州豊後の架空の小藩、坪内藩の城下町の剣術道場のひとつ、青鳴(あおなり)道場の権平(ごんべい)、千草、勘六、三兄弟の絆を心温く描いた長編時代小説だった。

読んでも読んでも、そのそばから忘れてしまう老脳。
読んだことの有る本を、うっかりまた借りてくるような失態を繰り返さないためにも、
その都度、備忘録として、ブログ・カテゴリー「読書記」に、書き留め置くことにしている。
▢目次
(一)~(二十四)
▢主な登場人物
青鳴権平(あおなりごんべい、神妙活殺流、青鳴道場主、20歳)・千草(17歳)・勘六(12歳、竹丸)、
青鳴一兵衛(あおなりいちひょうえ)、
柿崎源五郎(新当流、柿崎道場主)、尾藤一心(無念流、尾藤道場主)・由梨、
熊谷鉄太郎(雲弘流、熊谷道場主)、戸川源之亟(心影流、戸川道場主)、
和田三右衛門(柳生流、和田道場主)
羽賀弥十郎(坪内藩剣術指南役)、稲富兵部(藩主側用人)
坪内信貞(坪内藩藩主)、お江与の方(藩主の正室)・松丸(新之助信春)、
お初の方(藩主の側室)・竹丸(勘六)、闇姫(小篠の方、藩主の側室)
▢あらすじ等
青鳴道場主だった父親青鳴一兵衛が、酔って神社の石段で足を滑らせ亡くなったとされる
不名誉な死に方をしてから1年が経ったが、その跡を継いだ長男権平は、昼行燈のような性格で
「あおなり先生」等と呼ばれ、妹千草は、兄に勝る剣術の腕前で、男装を好む美貌の持ち主、
荒稽古をしてのけ、「鬼姫」と呼ばれ、弟勘六は神童の誉が高い秀才で「天神小僧」と
呼ばれていたものの、次々と門人が去り、ついに誰もいなくなり、道場は、存続危機に陥る。
「兄上、いったいどうなさるおつもりですか・・・」
「父の仇を捜すために、道場破りをいたす」
父一兵衛の死には、不審な点があり、城下の五つの流派の道場主達が関わっているのでは
ないかという疑念を持つ三兄弟。
父の仇を探すという大儀名分を持って、城下の道場ひとつひとつに、「道場破り」を仕掛け、
看板料を稼ぎながら、生計を立てる策に打って出るのだが・・・、
果たして、父一兵衛は、誰に殺されたのか、ミステリー仕立て、
本作のキーワードは、「神妙活殺(しんみょうかっさつ)」の技、
藩のお世継ぎ抗争が根に有るストーリーではあるが、終始、権平、千草、勘六、
三兄弟の兄弟愛が描かれており、青少年向けの小説の如く、痛快、爽やかな仕立ての
作品になっている。
千草が急に元気を取り戻して、
「それから、わたし、江戸に着いたらお願いがございます」
「なんだ、また、道場破りをするのか」
「いいえ、道場の看板ですが、仮名で「あおなり道場」と書いたら
どうかと思うのです。・・・・」