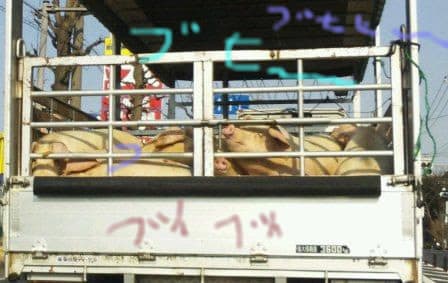2年半くらい前に、直腸の良性腫瘍をとってから、年に一度はCF(大腸ファイバー)をやっています。
でも、前処置が面倒で、先延ばしにして、やっと今日行ってきました。
大腸の中をファイバーでのぞくので、腸の中をきれいにしておかなくてはなりません。
そのため、前日は低残渣食を食べるのですが、最近は一日分のレトルト食品があり、それを買ってきて食べるのが一番楽です。
朝は、卵のお粥、昼は職場に持参して鮭のお粥と肉じゃが、夜は7時までにクラッカー5枚とクリームシチューでした。
 お昼これだけは、ちょっとさみしい・・。
お昼これだけは、ちょっとさみしい・・。
しかも、昨日は退職されるヘルパーさんがいたので、みんなでケーキタイムもあり、私は見ただけで我慢でした。
夜には、マグコロールPと、ラキソベロン半分(下剤です)を飲み、どんどん出すわけですが、私はかなりの便秘体質なので、事前にマグミットでかなり調整していたので、今回はスムーズにきれいになっていきました。
そして、今朝も空腹をこらえつつ町田内視鏡クリニックへ。
町田マキヨ先生は、陽気なおばちゃん先生で、実はかなりの天然キャラなのですが、内視鏡の腕は抜群なので、人気の先生です。
ここから前処置の本番です。
ニフレックという腸のお掃除をする塩味のプラスティックみたいな液を、約1時間かけてがぶがぶ飲みます。
今日は4人のCFの患者さんがいたので、ここからは「腸がきれいになった人競争」となり、はやく検査をしてもらいたくて、必死にトイレに通うのです。
ニフレックを飲みながら、立って腰を回したり、お腹の体操をしたり、飛んだりしているとじっと座っているより速く、便意をもよおします。
結局、お年寄りが優先されたので、私は3番目でしたが、もう一人の男性は出が悪くて、なんと洗腸されていました。可愛そうに。
検査は、鎮痛剤件鎮静剤と、お腹の動きを止める薬を点滴から入れて行います、
なので、検査中はかなり朦朧としながらとなり、昔みたいに痛いことはほとんどなく、ぼわーんとしたまま終わります。
ちなみに、検査後の食事を楽しみにしていた私は、S状結腸にポリープを発見され、ポリペクトミーという処置により、ポリープの切除を行ったために、今日も絶食!!水分のみとなってしまいました。
お腹へったよ~。
甘い紅茶を飲みながら、今夜は我慢です。
明日は、お粥か素うどんだって。
我慢できる気がしない私です・・・・、
でも、前処置が面倒で、先延ばしにして、やっと今日行ってきました。
大腸の中をファイバーでのぞくので、腸の中をきれいにしておかなくてはなりません。
そのため、前日は低残渣食を食べるのですが、最近は一日分のレトルト食品があり、それを買ってきて食べるのが一番楽です。
朝は、卵のお粥、昼は職場に持参して鮭のお粥と肉じゃが、夜は7時までにクラッカー5枚とクリームシチューでした。
 お昼これだけは、ちょっとさみしい・・。
お昼これだけは、ちょっとさみしい・・。しかも、昨日は退職されるヘルパーさんがいたので、みんなでケーキタイムもあり、私は見ただけで我慢でした。
夜には、マグコロールPと、ラキソベロン半分(下剤です)を飲み、どんどん出すわけですが、私はかなりの便秘体質なので、事前にマグミットでかなり調整していたので、今回はスムーズにきれいになっていきました。
そして、今朝も空腹をこらえつつ町田内視鏡クリニックへ。
町田マキヨ先生は、陽気なおばちゃん先生で、実はかなりの天然キャラなのですが、内視鏡の腕は抜群なので、人気の先生です。
ここから前処置の本番です。
ニフレックという腸のお掃除をする塩味のプラスティックみたいな液を、約1時間かけてがぶがぶ飲みます。
今日は4人のCFの患者さんがいたので、ここからは「腸がきれいになった人競争」となり、はやく検査をしてもらいたくて、必死にトイレに通うのです。
ニフレックを飲みながら、立って腰を回したり、お腹の体操をしたり、飛んだりしているとじっと座っているより速く、便意をもよおします。
結局、お年寄りが優先されたので、私は3番目でしたが、もう一人の男性は出が悪くて、なんと洗腸されていました。可愛そうに。
検査は、鎮痛剤件鎮静剤と、お腹の動きを止める薬を点滴から入れて行います、
なので、検査中はかなり朦朧としながらとなり、昔みたいに痛いことはほとんどなく、ぼわーんとしたまま終わります。
ちなみに、検査後の食事を楽しみにしていた私は、S状結腸にポリープを発見され、ポリペクトミーという処置により、ポリープの切除を行ったために、今日も絶食!!水分のみとなってしまいました。
お腹へったよ~。
甘い紅茶を飲みながら、今夜は我慢です。
明日は、お粥か素うどんだって。
我慢できる気がしない私です・・・・、















 焼き芋。
焼き芋。



 。
。



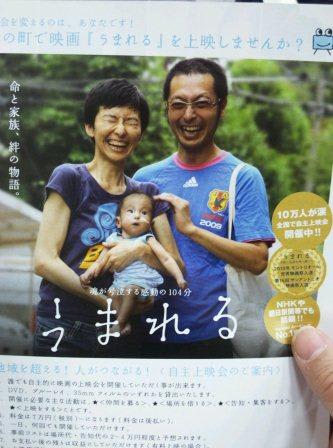



 。展開がすごいです。
。展開がすごいです。 から
から にブレそうになります。
にブレそうになります。










 」
」