先週の閲覧数が予想外に多かったことに驚きを感じています。
1日200PV以上の訪問者。
あまり書く事も無く、困って書いた内容なのですが・・。
本日の内容は、
『本当に江戸の浪人は傘張りの内職をしていたのか?』と
『江戸の卵は1個400円!』
からの抜粋とその感想です。
江戸時代の若者の憧れの就職先は銭湯(湯屋)だったそうです。
街中を歩いて廃材を探して、それを運ぶ「木拾い」、
そして1日中地獄のような暑さの中での「釜だき」で10年以上の修行。
それから客の背中のアカ擦りをする「三助」。
「番台」に座ることにも少々憧れますが、
長い修行に私は耐えられそうにもありません。
幕末、提灯用の短いロウソクの値段は一本240円だったそうです。
夜暗くなれば、早寝したことは容易に理解できます。
無駄に深夜電力を利用して夜更かししている現代とは明らかに違っているようです。
貸本屋は新しく出版された本のあらすじを説明して客の気を引いたそうです。
ちなみに江戸時代、新刊本は「封切り」といい、映画の公開を封切りの語源だそうです。
庶民が着ている木綿の着物の価格は約10万円。
庶民は古着を買って着ていたそうです。
客が帰る時、雨が降り出したら、
日本橋の大丸呉服店と越後屋呉服店の屋号や家紋が入っている「番傘」を無料で貸出したそうです。
客は濡れずに喜び、百貨店は広告効果と傘の返却に再来店する客に喜ぶので両者ウィンウインの関係ですね。
越後屋(三越)、大丸屋(大丸)、白木屋(東急)などの江戸の呉服店の従業員は全員独身男性だったそうです。
理由は12歳位で就職して、江戸店に配属、下ったそうです。
15歳で元服。入店後9年ぐらいで関西への里帰りが許されたそうです。(「初登り」)その後、手代というハウスマヌカンに昇格してご婦人との商談にあたったそうです。
幕末には全国に寺子屋が15506塾。
現在の小学校数は22476校ですから、その数の多さが目立ちます。
私学経営の厳しさは、江戸時代でも同様だったようです。
歌舞伎役者は紅や鬢付け油などの化粧品店を販売する店を経営していたそうです。
「成田屋」「音羽屋」「大和屋」などと屋号で呼ぶのは、
この時代に店を構えていた名残りだそうです。
その他の江戸時代の主な物価
ゆで卵400円 / たくあん300円 / 握り寿司160円 / 蕎麦320円 / 奈良茶漬1000円
居酒屋の飲み代 700~1400円 / いなり寿司80円 / 鰻の蒲焼4000円 / カステラ9000円 /
以上です。











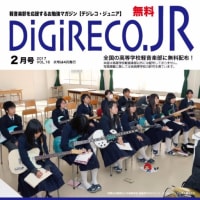





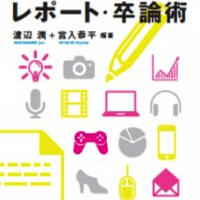






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます