12月7日午前7時55分発のANAで、小春、ふーちん、りえぼんの3人を宮崎空港で見送って、上演がすべて終り、2009年が終り、今日は1月5日である。この一ヶ月の時間の経過に実感がない。なにか読書中の本をパタリと閉じて終った感じである。なにか起きたのかさへ漠然としている。
そう、ほっといていた虫歯を抜いた。ぐらぐらして鈍い痛みのまま3週間ほどほっといていたら、もう抜き取るしか処置のしようがないということだった。それでやっと29日に抜き、30日口から痛みが消えていた。しかし、翌日の午後から左側の犬歯が揺れだした。揺すると鈍い痛みがする。その夜、年越しそばに餅を入れて食べだすと、痛みは餅を噛むごとに、ずきずきとはっきりと反応しだした。またかあといやな予感がするのであったが、我慢して食べ終わって、数分もしないうちに、かなづちで歯をたたくような重たい痛みが脈打ちだしたのだ。
幸い、抜歯したときのボルタリンが2錠のこっていたので、1錠飲むと,痛みは収まりだした。そして元旦の朝となり、雑煮を食べだした、そして当然、おなじ経過で痛みが正確無比に戻ってきた。2日目は、新春コンサートを日高プロショップに聴きに行った。このあと、もうボルタリンはなくなった。3日目は朝から夜まで、歯の痛みのため、お粥で過ごした。やっと4日になったが、痛みは治まらず、またお粥、不思議に空腹感はないのであった。その夜から痛みはだんだん遠のき、5日の今現在に至っている。午後1時半に診療してもらえることになった。生まれてこのかた、元旦から3日間、歯痛みで、お粥しか食えなかった正月とは初めてである。正月とはいったいなんであろうか。近所も中心市街地でも注連飾りも消えてしまった。正月らしき気配はまったくどこにも感じられなくなった。そして歯痛みである。これで、季節感などは吹き飛んだ。
さて、小春/マイノリティオーケストラ公演の幸運について話をつづけよう。彼女らの滞在3日間に宮崎の自然が、これほど宮崎らしい装いを示したのは、ぼくにも驚きであったが、彼女らへのインパクトは、さらに強烈であったようだ。初めて宮崎市に来たという20歳そこそこの彼女らに、宮崎市は夢のような土地と、彼女らに思ってもらえたようだ。ちょっと効果あり過ぎというべきか。自然はなにを考えたのであろうか。
そして、もう一つの幸運は、上演はヘブンアーティストをいう大道芸としての楽しみを越え、聴衆を感動させる深みがあったということである。これは幸運というより、ぼくが事前に予測できなかっただけの話で、うれしすぎる誤算でもあったのだ。
もともと、小春のアコーディオンと、そのバンドに期待したことは、聴衆を区分けせずにだれでも惹きつけること。演奏者は演奏だけに没頭し、聴くものは聴くだけに集中しているだけ、そんな演奏会場にはあきあきしていたぼくは、両者は同じ場に立ち、同じ地平を見晴かしているステージはないのかと思っていたのだ。そんなステージを実現したかった。そして昨年5月上旬にユーチューブで見つけたアコーディオン奏者の小春こそはこの期待の奏者と思ったのであった。街角で群集を引き付けている演奏、その技量、プロフェッショナル性こそ期待に添えると判断したのだ。
演奏を終ってみると、そこには楽しさだけがあったのではなかった。なによりも、感動があった。演奏者たちと、自分と、まわりの人たちとの共感が沸き起こり、自分と世界を再認識させたのだ。小春とバンドの音楽には、きわめて明快なメッセージがあった。それは個人という弱者への愛情であり、その個人を抑圧する不正や悪への抵抗である。去年の春、村上春樹が、イスラエル賞の授賞式で述べた、個人という卵をつぶす壁がある。その壁がいかなる正義をのべようと、私は卵の側に立つ、それが書くという意味だといったことと、ぴたりと通じているのである。もちろん、彼女らに社会主義や革命やイデオロギーなどの反乱の言動などはなく、ごく日常の感情として自然に溢れていることに、ぼくはなによりも共感できたのであった。
小春が、ユーモラスに、ヘリクダルか、やや自虐的にのべるバンド紹介「ヘンテコジプシー音楽団」歌とアコーディオンのユニット「チャラン・ポランタン」が上演する「ヘンテコ・ブンチャカ・コンサート」いうタイトルに、音楽のまっとうな本質があるとは、だれも想像できないだろう。しかし、それがあるのだと、私たちは再認識する必要がある。
上演は小春の作曲「消えたモーゼ」から開幕になった。これは彼女らが上野公演の広場で演奏するときに、いつも近寄ってきたホームレスのモーゼのような顎鬚を生やした老いたる乞食のことで、かれが差し出すへろへろのプラスチックの中の弁当を口にもっていくのが大変だったと語る。ある日突然、彼の姿は消えたしまった。ついに再会できず、この曲がうまれたという。ユーモアと不思議な躍動感のある曲で、決して暗くも憂鬱でもない。このあと、彼女らの日常が曲によって展開していく。大衆芸の楽しさと明るさ、なによりも個性と独創性があり、たぶんヘンテコという自称も、常識を超えたということでは当たる。その個性の激しさはチャラン・ポランタンでモモちゃん(小春の実妹)の歌声で度肝を抜かれる。
その愉快な流れは、最終曲によって、突然、すべてが集約される。この曲はアルゼンチンの歌手ビクトールハラが1973年チリのクーデダーにより
連行されてきた多くの市民を励まそうと革命歌ベンセレーモスを歌ったところ、ギターを取り上げられ、「二度とギターを弾けないように」と両手を撃ち砕かれ、それでも歌いやめなかったため射殺されたと伝えらた、かれの偉業を歌った「不滅の民」の演奏になったのだ。これまでの笑いや軽さは一転して音楽の可能性、その可能性に寄せる彼女の思いが切々と語られ、聴衆は衝撃を受けたのだ。
このホームレスに寄せる思いから、アルゼンチンの革命家へとこの構成は、まるで、ぼくの思いを推し量ったようなプログラムであったが、もちろん、彼女と交換したのは、ほとんどが事務的なものにすぎなかった。また孫ほどに若い彼女らにぼくの思いがとどけられるはずもないとも思っていたし、そんな野暮なことなどやって笑われたくなかったのだ。にもかかわらず、彼女はぼくの思いを見事に掬いとっていたのだ。もっとも、それは彼女には彼女の思いがあったためであろう。それが重なるところが、不思議である。
あるいは、彼女の鋭い勘、状況判断が働いたのかもしれない。いずれにしても、彼女らの音楽は、音楽が歴史とともに嵌め込んで描こうとするパズル絵画のパズルの一片として、存在していることは、間違いないと思えたのである。
それにしても小春(21歳)は、写真やそのブログでの印象とはまさに別人であったのだ。マイノリティ・オーケストラもヘンテコ・ブンチャカ・こんサートもまた然りである。
そう、ほっといていた虫歯を抜いた。ぐらぐらして鈍い痛みのまま3週間ほどほっといていたら、もう抜き取るしか処置のしようがないということだった。それでやっと29日に抜き、30日口から痛みが消えていた。しかし、翌日の午後から左側の犬歯が揺れだした。揺すると鈍い痛みがする。その夜、年越しそばに餅を入れて食べだすと、痛みは餅を噛むごとに、ずきずきとはっきりと反応しだした。またかあといやな予感がするのであったが、我慢して食べ終わって、数分もしないうちに、かなづちで歯をたたくような重たい痛みが脈打ちだしたのだ。
幸い、抜歯したときのボルタリンが2錠のこっていたので、1錠飲むと,痛みは収まりだした。そして元旦の朝となり、雑煮を食べだした、そして当然、おなじ経過で痛みが正確無比に戻ってきた。2日目は、新春コンサートを日高プロショップに聴きに行った。このあと、もうボルタリンはなくなった。3日目は朝から夜まで、歯の痛みのため、お粥で過ごした。やっと4日になったが、痛みは治まらず、またお粥、不思議に空腹感はないのであった。その夜から痛みはだんだん遠のき、5日の今現在に至っている。午後1時半に診療してもらえることになった。生まれてこのかた、元旦から3日間、歯痛みで、お粥しか食えなかった正月とは初めてである。正月とはいったいなんであろうか。近所も中心市街地でも注連飾りも消えてしまった。正月らしき気配はまったくどこにも感じられなくなった。そして歯痛みである。これで、季節感などは吹き飛んだ。
さて、小春/マイノリティオーケストラ公演の幸運について話をつづけよう。彼女らの滞在3日間に宮崎の自然が、これほど宮崎らしい装いを示したのは、ぼくにも驚きであったが、彼女らへのインパクトは、さらに強烈であったようだ。初めて宮崎市に来たという20歳そこそこの彼女らに、宮崎市は夢のような土地と、彼女らに思ってもらえたようだ。ちょっと効果あり過ぎというべきか。自然はなにを考えたのであろうか。
そして、もう一つの幸運は、上演はヘブンアーティストをいう大道芸としての楽しみを越え、聴衆を感動させる深みがあったということである。これは幸運というより、ぼくが事前に予測できなかっただけの話で、うれしすぎる誤算でもあったのだ。
もともと、小春のアコーディオンと、そのバンドに期待したことは、聴衆を区分けせずにだれでも惹きつけること。演奏者は演奏だけに没頭し、聴くものは聴くだけに集中しているだけ、そんな演奏会場にはあきあきしていたぼくは、両者は同じ場に立ち、同じ地平を見晴かしているステージはないのかと思っていたのだ。そんなステージを実現したかった。そして昨年5月上旬にユーチューブで見つけたアコーディオン奏者の小春こそはこの期待の奏者と思ったのであった。街角で群集を引き付けている演奏、その技量、プロフェッショナル性こそ期待に添えると判断したのだ。
演奏を終ってみると、そこには楽しさだけがあったのではなかった。なによりも、感動があった。演奏者たちと、自分と、まわりの人たちとの共感が沸き起こり、自分と世界を再認識させたのだ。小春とバンドの音楽には、きわめて明快なメッセージがあった。それは個人という弱者への愛情であり、その個人を抑圧する不正や悪への抵抗である。去年の春、村上春樹が、イスラエル賞の授賞式で述べた、個人という卵をつぶす壁がある。その壁がいかなる正義をのべようと、私は卵の側に立つ、それが書くという意味だといったことと、ぴたりと通じているのである。もちろん、彼女らに社会主義や革命やイデオロギーなどの反乱の言動などはなく、ごく日常の感情として自然に溢れていることに、ぼくはなによりも共感できたのであった。
小春が、ユーモラスに、ヘリクダルか、やや自虐的にのべるバンド紹介「ヘンテコジプシー音楽団」歌とアコーディオンのユニット「チャラン・ポランタン」が上演する「ヘンテコ・ブンチャカ・コンサート」いうタイトルに、音楽のまっとうな本質があるとは、だれも想像できないだろう。しかし、それがあるのだと、私たちは再認識する必要がある。
上演は小春の作曲「消えたモーゼ」から開幕になった。これは彼女らが上野公演の広場で演奏するときに、いつも近寄ってきたホームレスのモーゼのような顎鬚を生やした老いたる乞食のことで、かれが差し出すへろへろのプラスチックの中の弁当を口にもっていくのが大変だったと語る。ある日突然、彼の姿は消えたしまった。ついに再会できず、この曲がうまれたという。ユーモアと不思議な躍動感のある曲で、決して暗くも憂鬱でもない。このあと、彼女らの日常が曲によって展開していく。大衆芸の楽しさと明るさ、なによりも個性と独創性があり、たぶんヘンテコという自称も、常識を超えたということでは当たる。その個性の激しさはチャラン・ポランタンでモモちゃん(小春の実妹)の歌声で度肝を抜かれる。
その愉快な流れは、最終曲によって、突然、すべてが集約される。この曲はアルゼンチンの歌手ビクトールハラが1973年チリのクーデダーにより
連行されてきた多くの市民を励まそうと革命歌ベンセレーモスを歌ったところ、ギターを取り上げられ、「二度とギターを弾けないように」と両手を撃ち砕かれ、それでも歌いやめなかったため射殺されたと伝えらた、かれの偉業を歌った「不滅の民」の演奏になったのだ。これまでの笑いや軽さは一転して音楽の可能性、その可能性に寄せる彼女の思いが切々と語られ、聴衆は衝撃を受けたのだ。
このホームレスに寄せる思いから、アルゼンチンの革命家へとこの構成は、まるで、ぼくの思いを推し量ったようなプログラムであったが、もちろん、彼女と交換したのは、ほとんどが事務的なものにすぎなかった。また孫ほどに若い彼女らにぼくの思いがとどけられるはずもないとも思っていたし、そんな野暮なことなどやって笑われたくなかったのだ。にもかかわらず、彼女はぼくの思いを見事に掬いとっていたのだ。もっとも、それは彼女には彼女の思いがあったためであろう。それが重なるところが、不思議である。
あるいは、彼女の鋭い勘、状況判断が働いたのかもしれない。いずれにしても、彼女らの音楽は、音楽が歴史とともに嵌め込んで描こうとするパズル絵画のパズルの一片として、存在していることは、間違いないと思えたのである。
それにしても小春(21歳)は、写真やそのブログでの印象とはまさに別人であったのだ。マイノリティ・オーケストラもヘンテコ・ブンチャカ・こんサートもまた然りである。











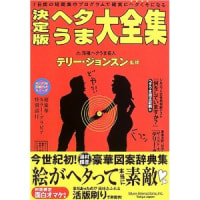












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます