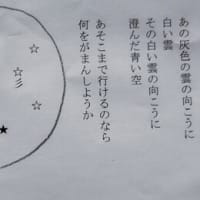安水稔和「道の辺の」、佐々木幹郎「静止点」(「現代詩手帖」2014年12月号)
安水稔和「道の辺の」(初出『有珠』2014年10月)は菅江真澄の足跡を追いつづける。菅江は何をしたか。(引用ではルビを省略した。)
その土地で草がどう呼ばれているかを尋ねて、それを記録した。そういうことを安水はどんな批評もくわえず、ただ書き記している。確かめている。
このとき、安水は「菅江」になっているのか、その土地の人になっているのか。「菅江」になって、土地の人に聞いている。「菅江」の耳を反芻している。単純に考えると、そうなるのだが、私はときどき、そこから逸脱してしまう。
「菅江」になって草の名前を聞き取りながら、次第次第にその「土地の人」になっていく。「シケツプ、カバル、シルナキ、ビシビシ」と繰り返していると、見なれた草が新しく生まれ変わっていく。その「土地の人」になって、草を見つめていることに気づく。「土地の人」に「なる」というのは「土地」になること、その「土地」がへてきた時間そのものに「なる」ことだ。
「土地」「人」と一緒に、「土地」「人」を超え、「時間」になるとき、「風」はもうその土地という限定を超えている。「日が傾く」というのはどの土地でも起きる。その傾きは土地土地によって違うけれど、「日が傾く」という動きは同じ。それと同じように「風が立つ」という動きも土地の限定を超える。そして、「名前をつける(名前で呼ぶ)」ということも、その「土地」「人」と一緒にありながら、「土地/人」を超える。「人間」という存在の普遍的な「動詞」となる。
普遍の風と光のなかで、ことばが動く。
普遍の「人間」になりながら、安水はまた、「菅江」になり、土地の人になり、土地そのものになっていく。その往復。そんな姿を感じる。止まることのない静かな、そして強い「動詞」が隠れている。
*
佐々木幹郎「静止点」(初出「イリプス Ⅱnd」14、2014年11月)。
「スクティ」と呼ばれる羊の干し肉を舐めながら標高五千メートルの土地を歩いている。スクティの描写が簡潔で美しい。
どこの土地とは書いていないのだが、私はネパールとかヒマラヤとか、アジアの山岳地帯を想像した。
後半は、スクティを舐めると滲み出てくるものが「肉体」のなかに入って、そこでことばになって動く感じがする。
私は「魂」というものが自分のなかにあると感じたことがないし、自分の外にも感じたことがない。「魂」ということばをつかって何かを書こうと思ったことはないのだが、自分というものが「破れる」と感じたことはある。「肉体」がぱっと破れて、四方に開かれる。「肉体」が消えるという感じ。
佐々木は「魂」と書いているのだが、私は、そこに書かれている「破れる」を手がかりに、自分の感覚を重ねてみた。そういう「こと」、そういう「瞬間」はたしかにある。
そういうこと、そういう瞬間というのは……
この部分。自分ではないものの「声」が突然襲ってきて、私を「破る」。
誰の声?
佐々木は、ここでは「白と黒の羊たち」と書いているが、羊は日本語を話すわけではない。
佐々木の、自覚できなかった声、無意識の声。そして、その声は羊と出合ったとき、突然、聞こえた。佐々木が羊になっている。羊になっているから、羊の「ことば」がわかるのだ。
「人間」である佐々木が破れた。「人間」が破れた。その「人間」を佐々木は「魂」と呼んでいる。
「魂」が破れるとき「辛い」かすかな音がするのは、佐々木の舐めている「スクティ」の香辛料の味が「辛い」からだろう。佐々木は、佐々木を取り囲んだ「羊」と一体になっているだけではなく、その羊がその後なるだろうスクティにもなっている。羊の「一生」になって、生きている。その「一生」は死んで食べられるというのではなく、食べられて誰かの「肉体(魂)」になる、というところまで含んでいる。
「羊」になったあと、佐々木は、さらに変わっていく。
砂嵐のなかで「目をつぶる」、そのとき「馬」も「目をつぶる」。馬に乗っていたのかもしれないが、砂嵐に襲われて、佐々木は馬から下りて立っているかもしれない。「四つ足を垂直にして」というのは馬の描写だが、このとき佐々木は二本の足を垂直にしている、ふんばっているのだろう。「足を垂直にして立つ」「目をつぶる」という「動詞」のなかで「肉体」が馬と同化する。一体になる。そして、馬と一体になった佐々木は、そのとき「自然」そのものとも一体になる。風になる。羊→馬→自然(風)。この自然は「宇宙」と言いかえることができる。
「魂」が「破れ」、「風」に溶ける(風と区別のつかないもの、風そのものになる)ことで、佐々木は、「宇宙」に「なる」。
こういう瞬間を、この村の人たちは……
という具合に言っていた。(引用の順序が逆になってしまった。)
「人間」という「枠」をとっぱらう。「人間」という「枠」にこだわらない。「いま/ここ」に「ある」。「ある」とき、人は何かになっている。何になるか、こだわらず、「なる」が自在に動くとき、そこに「宇宙」があらわれる。動物とひとつづき、連続している、動物と一体であるというのは、それだけ「宇宙」に近い。だから「誇り」である。
いいなあ。
詩のタイトルは「静止点」。この「静止」は、止まっているというよりも、どこへでも動けるという「静止」だ。「自在」をささえる「静止」、ある動き(ベクトル)にこだわらない感じ、こだわりを「破る」瞬間だ。「点」であるけれど「宇宙」全体でもある。遠心と求心が合体した瞬間としていの「点」だ。
アンソロジーの最後をしめくくるのに最適な詩だ。
「谷川俊太郎の『こころ』を読む」はアマゾンでは入手しにくい状態が続いています。
購読ご希望の方は、谷内修三(panchan@mars.dti.ne.jp)へお申し込みください。1800円(税抜、郵送無料)で販売します。
ご要望があれば、署名(宛名含む)もします。
安水稔和「道の辺の」(初出『有珠』2014年10月)は菅江真澄の足跡を追いつづける。菅江は何をしたか。(引用ではルビを省略した。)
有珠を立ち
道々。
道の辺の草々を手に
その名を問えば。
萩 シケツプ
芒 カバル
藜 シルナキ
木賊 ビシビシ
その土地で草がどう呼ばれているかを尋ねて、それを記録した。そういうことを安水はどんな批評もくわえず、ただ書き記している。確かめている。
このとき、安水は「菅江」になっているのか、その土地の人になっているのか。「菅江」になって、土地の人に聞いている。「菅江」の耳を反芻している。単純に考えると、そうなるのだが、私はときどき、そこから逸脱してしまう。
「菅江」になって草の名前を聞き取りながら、次第次第にその「土地の人」になっていく。「シケツプ、カバル、シルナキ、ビシビシ」と繰り返していると、見なれた草が新しく生まれ変わっていく。その「土地の人」になって、草を見つめていることに気づく。「土地の人」に「なる」というのは「土地」になること、その「土地」がへてきた時間そのものに「なる」ことだ。
風が立ち
日が傾き。
道の辺の立木を仰ぎ
重ねて問えば。
柳 シユシユニ
榛 ホウケルケニウチ
黄檗 シケンべ
山胡桃 ニシコ
「土地」「人」と一緒に、「土地」「人」を超え、「時間」になるとき、「風」はもうその土地という限定を超えている。「日が傾く」というのはどの土地でも起きる。その傾きは土地土地によって違うけれど、「日が傾く」という動きは同じ。それと同じように「風が立つ」という動きも土地の限定を超える。そして、「名前をつける(名前で呼ぶ)」ということも、その「土地」「人」と一緒にありながら、「土地/人」を超える。「人間」という存在の普遍的な「動詞」となる。
普遍の風と光のなかで、ことばが動く。
普遍の「人間」になりながら、安水はまた、「菅江」になり、土地の人になり、土地そのものになっていく。その往復。そんな姿を感じる。止まることのない静かな、そして強い「動詞」が隠れている。
*
佐々木幹郎「静止点」(初出「イリプス Ⅱnd」14、2014年11月)。
「スクティ」と呼ばれる羊の干し肉を舐めながら標高五千メートルの土地を歩いている。スクティの描写が簡潔で美しい。
歯で齧らず 舐めている
枯れきった肉に溶けているもの
ターメリック コリアンダー 唐辛子
どこの土地とは書いていないのだが、私はネパールとかヒマラヤとか、アジアの山岳地帯を想像した。
後半は、スクティを舐めると滲み出てくるものが「肉体」のなかに入って、そこでことばになって動く感じがする。
何度も山道で
突然湧き出てきた白と黒の羊たちに取り囲まれた
「人間など やめちまえ!」
「どうせ死ぬだけだ」
角を突き立て 口々に羊たちはわめき
流星のように走り去り
残されたわたしは
スクティを舐めた
魂が破れる 辛い かすかな音がして
私は「魂」というものが自分のなかにあると感じたことがないし、自分の外にも感じたことがない。「魂」ということばをつかって何かを書こうと思ったことはないのだが、自分というものが「破れる」と感じたことはある。「肉体」がぱっと破れて、四方に開かれる。「肉体」が消えるという感じ。
佐々木は「魂」と書いているのだが、私は、そこに書かれている「破れる」を手がかりに、自分の感覚を重ねてみた。そういう「こと」、そういう「瞬間」はたしかにある。
そういうこと、そういう瞬間というのは……
「人間など やめちまえ!」
「どうせ死ぬだけだ」
この部分。自分ではないものの「声」が突然襲ってきて、私を「破る」。
誰の声?
佐々木は、ここでは「白と黒の羊たち」と書いているが、羊は日本語を話すわけではない。
佐々木の、自覚できなかった声、無意識の声。そして、その声は羊と出合ったとき、突然、聞こえた。佐々木が羊になっている。羊になっているから、羊の「ことば」がわかるのだ。
「人間」である佐々木が破れた。「人間」が破れた。その「人間」を佐々木は「魂」と呼んでいる。
「魂」が破れるとき「辛い」かすかな音がするのは、佐々木の舐めている「スクティ」の香辛料の味が「辛い」からだろう。佐々木は、佐々木を取り囲んだ「羊」と一体になっているだけではなく、その羊がその後なるだろうスクティにもなっている。羊の「一生」になって、生きている。その「一生」は死んで食べられるというのではなく、食べられて誰かの「肉体(魂)」になる、というところまで含んでいる。
「羊」になったあと、佐々木は、さらに変わっていく。
崖の下から熱い砂嵐が襲ってくる
目をつぶると
馬も耳を垂れ 四つ足を垂直にして
目をつぶる
地上から 浮いていることがわかる
馬とともに
崖の上の山道で わたしは風に溶けた
砂嵐のなかで「目をつぶる」、そのとき「馬」も「目をつぶる」。馬に乗っていたのかもしれないが、砂嵐に襲われて、佐々木は馬から下りて立っているかもしれない。「四つ足を垂直にして」というのは馬の描写だが、このとき佐々木は二本の足を垂直にしている、ふんばっているのだろう。「足を垂直にして立つ」「目をつぶる」という「動詞」のなかで「肉体」が馬と同化する。一体になる。そして、馬と一体になった佐々木は、そのとき「自然」そのものとも一体になる。風になる。羊→馬→自然(風)。この自然は「宇宙」と言いかえることができる。
「魂」が「破れ」、「風」に溶ける(風と区別のつかないもの、風そのものになる)ことで、佐々木は、「宇宙」に「なる」。
こういう瞬間を、この村の人たちは……
村人たちはみな
祖先が猿であることを誇っている
という具合に言っていた。(引用の順序が逆になってしまった。)
「人間」という「枠」をとっぱらう。「人間」という「枠」にこだわらない。「いま/ここ」に「ある」。「ある」とき、人は何かになっている。何になるか、こだわらず、「なる」が自在に動くとき、そこに「宇宙」があらわれる。動物とひとつづき、連続している、動物と一体であるというのは、それだけ「宇宙」に近い。だから「誇り」である。
いいなあ。
詩のタイトルは「静止点」。この「静止」は、止まっているというよりも、どこへでも動けるという「静止」だ。「自在」をささえる「静止」、ある動き(ベクトル)にこだわらない感じ、こだわりを「破る」瞬間だ。「点」であるけれど「宇宙」全体でもある。遠心と求心が合体した瞬間としていの「点」だ。
アンソロジーの最後をしめくくるのに最適な詩だ。
 | 明日 |
| 佐々木 幹郎 | |
| 思潮社 |
 | 谷川俊太郎の『こころ』を読む |
| クリエーター情報なし | |
| 思潮社 |
「谷川俊太郎の『こころ』を読む」はアマゾンでは入手しにくい状態が続いています。
購読ご希望の方は、谷内修三(panchan@mars.dti.ne.jp)へお申し込みください。1800円(税抜、郵送無料)で販売します。
ご要望があれば、署名(宛名含む)もします。