豊原清明「34歳ノート・後編」(「白黒目」30、2011年07月発行)
豊原清明「34歳ノート・後編」は「短編映画シナリオ」である。いつものことだが、このシナリオがとてもおもしろい。
「ぐちゃぐちゃの部屋」に「ああ…。」という声がかぶさることろが、とてもいい。ひとは映っていないのだ。ただ部屋があり、それに声がかぶさる。その部屋の荒れた感じと、声の距離感。
眼鏡をはずした顔から、荒れた部屋へのカメラの切り返し。
なぜ部屋が「ぐちゃぐちゃ」なのか、何の説明もないが、その説明のなさが「意味」をはぎ取って、詩、そのものになっている。
次のシーンもとても好きだ。
このシーン。私なら、「僕」の姿を映さない。「僕」の姿を映さずに、ただ部屋の明暗、電燈の点滅の変化、カーテン越しの夕日の光というものだけをスクリーンに拡げてみたい。
光の変化、闇の変化、それにともなってみえるぐちゃぐちゃの部屋の変化--その変化そのものが「僕の肉体」なのだ。
「僕の肉体」と「部屋」そのものの「肉体」が光の変化のなかで「ひとつ」になる。
豊原の映画には、いつも「僕」が登場する。そして、その「僕」は「僕」なのだけれど、輪郭が破れている--というと語弊があるけれど、なにか「僕」を超えて、はみだすものがある。そのはみだしたものは、何かに触れて、その何かと「ひとつ」になる。そういう感じがある。それがとてもおもしろい。
ここには「意味」はない。日常の、「意味」から除外された「存在」がある。「空気」がある。
この繰り返しは、深い過去をもっている。過去があるから、「いま」が繰り返される。「希望を持って」というのだから「未来」が繰り返されるといってもいいが、その繰り返しによって「時間」が濃密になる。
「時間」が存在として浮かび上がってくる。
それは、その次のお茶の一気飲みで、違った形で繰り返される。
お茶の「一気飲みはあかん。」というのは、「僕」が何度も何度もきかされてきたことばである。何度もきかされているけれど、やっぱり、知らずに一気飲みをしてしまう。その「僕」の顔、僕の姿に、父の声が重なる。
このとき「僕」がいて「父」がいて「父の声」がするのだが、スクリーンの上では「僕の顔」に「父の声」が重なり、「僕」と「父」が「ひとつ」になる。
違った存在が「ひとつ」になるとき、そこに「時間」がエッジをもって浮かびあがってくる。
これはいいなあ。
私は映画のカメラというものを持ったことがないが、豊原のシナリオを読む度に、映画をとってみたくなる。そこに書かれていることばを映像にしてみたくなる。
詩も、俳句もいいが、映画のシナリオはそれをはるかに超越しておもしろい。
*
今月のお薦め。
河邉由紀恵『桃の湯』(思潮社)
池井昌樹「無事湖」
吉浦豊久「白い光景」
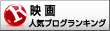
豊原清明「34歳ノート・後編」は「短編映画シナリオ」である。いつものことだが、このシナリオがとてもおもしろい。
○ 僕の顔
眼鏡をはずし、呟く。
僕「今は六月二十二日。誕生日は今週の土曜日。来週の日曜日、教会に行ったら、
誕生カードを渡すという。」
○ ぐちゃぐちゃの部屋を映す。
声「ああ…。」
溜息、嘆き声。
「ぐちゃぐちゃの部屋」に「ああ…。」という声がかぶさることろが、とてもいい。ひとは映っていないのだ。ただ部屋があり、それに声がかぶさる。その部屋の荒れた感じと、声の距離感。
眼鏡をはずした顔から、荒れた部屋へのカメラの切り返し。
なぜ部屋が「ぐちゃぐちゃ」なのか、何の説明もないが、その説明のなさが「意味」をはぎ取って、詩、そのものになっている。
次のシーンもとても好きだ。
○ ぐちゃぐちゃの部屋(夕)
声「祈らないと。祈らないと。」
カーテンを閉めて、真っ暗にする。
点滅する、電気。やがて、消し、真っ暗になる。
暗闇の部屋に、夕日が射す。カーテンを少し、開ける。
祈り終わって、立ち上がり、電気をつける。
このシーン。私なら、「僕」の姿を映さない。「僕」の姿を映さずに、ただ部屋の明暗、電燈の点滅の変化、カーテン越しの夕日の光というものだけをスクリーンに拡げてみたい。
光の変化、闇の変化、それにともなってみえるぐちゃぐちゃの部屋の変化--その変化そのものが「僕の肉体」なのだ。
「僕の肉体」と「部屋」そのものの「肉体」が光の変化のなかで「ひとつ」になる。
豊原の映画には、いつも「僕」が登場する。そして、その「僕」は「僕」なのだけれど、輪郭が破れている--というと語弊があるけれど、なにか「僕」を超えて、はみだすものがある。そのはみだしたものは、何かに触れて、その何かと「ひとつ」になる。そういう感じがある。それがとてもおもしろい。
○ 居間(夕)
誕生日の粗末なケーキ。暗い部屋の貧乏さ。
父の顔「33歳、たいへんやったなあ。」
僕の顔「もう一度、挑戦してみるわ。」
父の顔「希望を持って。」
僕の顔「希望を持って。」
お茶を一気飲みする、僕。
父の声「一気飲みはあかん。」
僕「あっ。」
父の声「お茶はちびちび飲む。」
茶をコップに入れて、飲む。
ここには「意味」はない。日常の、「意味」から除外された「存在」がある。「空気」がある。
父の顔「希望を持って。」
僕の顔「希望を持って。」
この繰り返しは、深い過去をもっている。過去があるから、「いま」が繰り返される。「希望を持って」というのだから「未来」が繰り返されるといってもいいが、その繰り返しによって「時間」が濃密になる。
「時間」が存在として浮かび上がってくる。
それは、その次のお茶の一気飲みで、違った形で繰り返される。
お茶の「一気飲みはあかん。」というのは、「僕」が何度も何度もきかされてきたことばである。何度もきかされているけれど、やっぱり、知らずに一気飲みをしてしまう。その「僕」の顔、僕の姿に、父の声が重なる。
このとき「僕」がいて「父」がいて「父の声」がするのだが、スクリーンの上では「僕の顔」に「父の声」が重なり、「僕」と「父」が「ひとつ」になる。
違った存在が「ひとつ」になるとき、そこに「時間」がエッジをもって浮かびあがってくる。
これはいいなあ。
私は映画のカメラというものを持ったことがないが、豊原のシナリオを読む度に、映画をとってみたくなる。そこに書かれていることばを映像にしてみたくなる。
詩も、俳句もいいが、映画のシナリオはそれをはるかに超越しておもしろい。
*
今月のお薦め。
河邉由紀恵『桃の湯』(思潮社)
池井昌樹「無事湖」
吉浦豊久「白い光景」
 | 夜の人工の木 |
| 豊原 清明 | |
| 青土社 |































