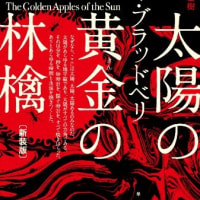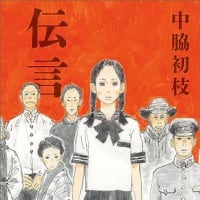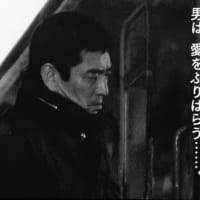豪雨と土砂崩れ
過去に発生した台風被害
台風21号が接近し、日本列島を縦断するらしい。
「記録的大雨 警戒」と今朝の新聞は警鐘を鳴らす。
歴史の発掘は、
実証主義で過去の出来事がどの資料(古文書)によって
証明されるかを示さなければ研究として認められない。
「武士の家計簿」を書いた磯田道史氏もよく草の根をかき分けるようにして資料を発見し、
それを一般の人にも分かりやすく書いてくれる。
その中の一冊に、土砂崩れに関する記述があったので紹介します。
『天災から日本史を読み直す 先人に学ぶ防災』
磯田道史著 中公新書刊 2014.11初版

第三章 土砂崩れを紹介します。
伊豆神津島の土砂災害。
1907(明治40)年7月8日、死者16名、負傷者31名、全壊家屋35戸、半壊家屋6戸。
『(前日7日)正午近くから大雨となり、
夜中中降りつづけ、
8日午前2時ごろより4時ごろまでの間に於いて、
諸所に山崩れ起こりたり、
その当時は盆を覆すがごとき強雨なりし』
神津島に降った豪雨は、
14時間ほどで土砂災害が発生した、
ことを当時の報告書は伝えている。
その原因を報告書は神津島の火山島としての地層にあることを指摘している。
この島は、伊豆大島と同じ火山島で、
溶岩の上に積もった火山灰は、雨水を浸透しやすい。
しかも、雨水は地中深く浸透できず、
溶岩の上を水道水のような勢いで流れ、
火山灰層を押し流し、
土砂となって崩れていく。
このような場所には家を建てるなと報告書は警鐘を鳴らす。
磯田氏は警告する。
このような場所に建てた住宅に住む人は、
明るいうちの早めの避難を心がけるのが一番。
前兆を見逃すなとも。
地鳴りや異臭を察知したら躊躇せずに逃げる。
大切なことは、
自分が住んでいる場所が災害に対して、
どのような場所なのか
(雨に弱いのか、地震に弱いのか、津波に弱いのか)を把握しておくことなのでしょう。
こうした事例を報告書や古文書にもとめて、磯田氏は提示している。
『地震に救われた家康』、『伏見地震・豊臣政権崩壊の引き金に』、『宝永地震が招いた津波と富士山噴火』、『津波から生き延びる知恵』、『東日本大震災の教訓』随時紹介します。
(2017.10.22記) (読書案内№113)