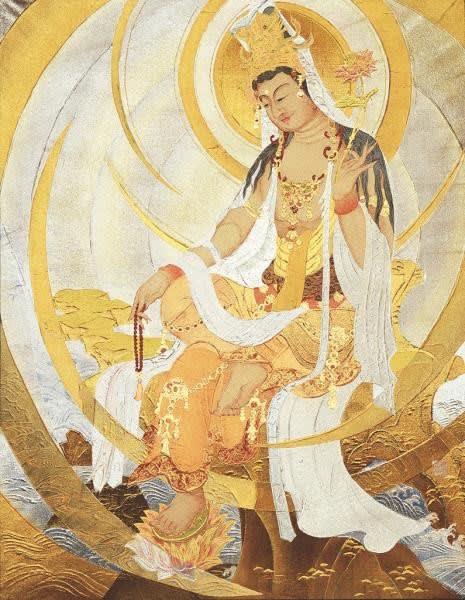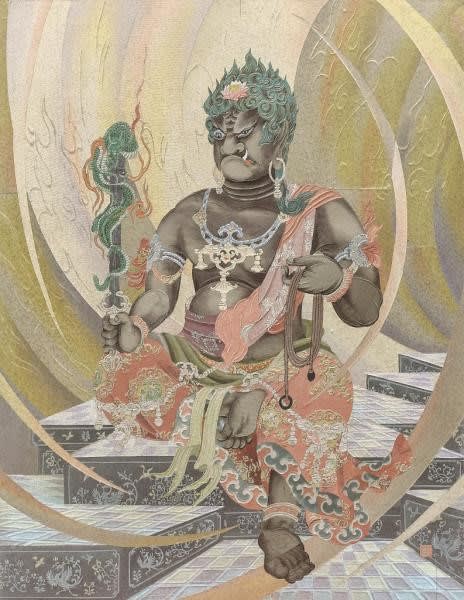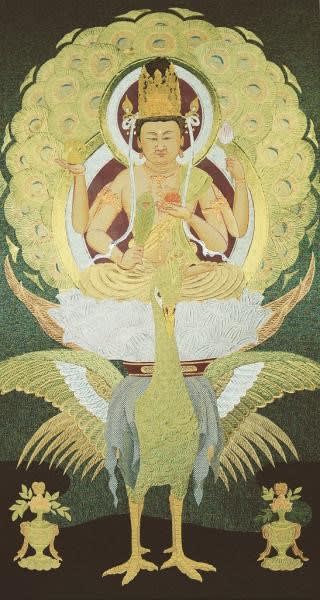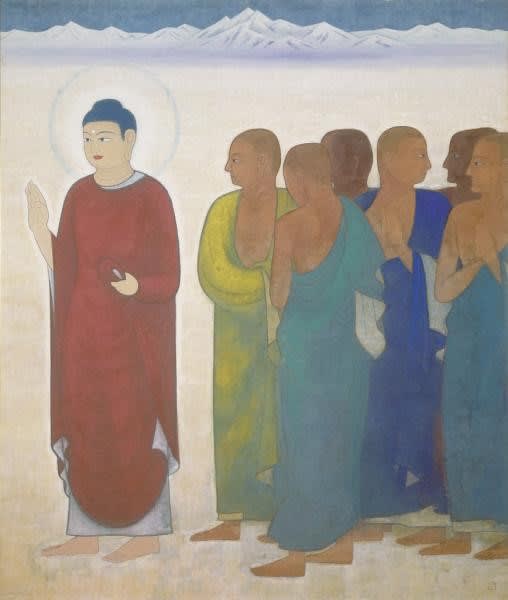新型コロナウイルス
⑤ 100年前のパンデミック スペイン風邪
新型コロナ
世界の感染者数 531万4625人……500万人を超えたのが
4月 3日に100万人を超え
15日200万人に
28日300万人
5月10日400万人……そして5月21日、ついに500万人を超えた。
わが国では25日、新規感染者が減少傾向にあることを受けて、
緊急事態宣言の全域解除になった。
国内の感染者数(24日午後9時半現在) 1万7369人
死者 851人
歩んでいくトンネルの先に、わずかな光が差してきた。
しかし、新型コロナウイルスを巡っては、
全身の血管に炎症が起きる「川崎病」と似た症状との関連が疑われるなど、
新たな報告も出ています(WHO)。
感染の過程でウイルスが変容したのか。
要はこのウイルスに関してはいまだに、不明な点が多い。
特効薬さえ開発されていない。
感染拡大を抑え、感染者を隔離するのが、当面の対策なのだろうか。
新型コロナウイルスの概要を見て来ましたが、
100年前の「スペイン風邪」の状況を見てみましょう。
100年前(1918~1920年) スペイン風邪・パンデミック
発生はスペインではなく、
アメリカ・カンザス州にあるファンストン陸軍基地の兵営からだとされています。
当時は第一次世界大戦の真っ最中で、
アメリカは欧州に大規模な派遣軍を送ることになる。
欧州に派遣されたアメリカ兵とともに「スペイン風邪 」も
世界中にばらまかれたといわれてます。
歴史を顧みればトランプ氏が、「中国が新コロナウイルスをまき散らした」などと
自分への非難の矛先をかわすような中国批判などできるわけがないのです。
さて、アメリカ・カンザス州から発生した「A型インフルエンザウイルス」がなぜ、
「スペイン風邪」といわれるようになったか。
1918年は第一次大戦のさなかであり、
欧州各国やアメリカなど大戦参加国では報道管制が敷かれていました。
そのため当時中立国であった「スペイン」を経由して、
報道が「スペイン発」として発信されていました。
アメリカ陸軍がばらまいた感染症ウイルスがいつの間にか、
「スペイン風邪」と称されるようになったといわれています。
正確には「アメリカ風邪」というべき所を報道の発信元スペインの名が冠されたのです。
スペイン側からすれば理不尽なことなのでしょうが、
当時の国際間の国力の力関係もあって戦のどさくさに紛れて、「スペイン風邪」と
なってしまったようです。
ただし、当時の日本での俗称は、「流行性感冒」として報道されていました。
(スペイン風邪に罹患したアメリカ・カンザス州の陸軍病院・ウィキペディアより)
そのスペイン風邪。
全世界で死者 …… 2000万~4500万人
日本国内の死者 …… 40万とも45万人ともいわれています。
最初に示した「新型コロナウイルス」の規模と比べ、感染拡大の規模が
桁違いであることがお分かりと思います。
当時の報道は次のように伝えています。
感冒のため一村全滅 (福井県九頭竜川上流山間部)
各病院は満杯となり、新たな「入院は皆お断り」(朝日新聞)
商工業は休業。学校は休校 (岩手日報)
処理能力を超えた火葬場 (神戸)
啓発ポスターは次のようなものがありました(朝日新聞4/24)。
テレビやンターネットのない時代、新聞やラジオ啓発ポスターという方法で情報を流しました。




悪性感冒・ 汽車電車人の中ではマスクせよ 「テバナシ」に咳をされては
病人はなるべく別の部屋に 恐るべし「ハヤリカゼ」のバイキン 堪えない 「ハヤリ カゼ」はこん
なことからつる
外出の後はうがい忘れるな
マスクをかけぬ命知らず!
新聞報道は次のようにも伝えています。
患者に近寄るな 咳などの飛沫から伝染 今が西班牙(スペイン)風邪の絶頂(1918.10.25付・朝日)
航海中に死者続出(米国から日本へ向かう船内での感染を伝える記事)
政府が呼びかけた対策は、マスク着用、うがい励行、室内の喚起や掃除の徹底、等々。
「芝居、寄席、活動写真には行かぬがよい」
「電車などに乗らずに歩く方が安全」
なんだか、100年前の「スペイン風邪」は、
現在の「新型コロナウイルス」感染拡大対策とほとんど同じようです。
日本では一次流行期 …… 1918年8月~19年7月
二次流行期 …… 19年9月~20年7月
三次流行期 …… 20年8月~21年7月
国内の罹患者は約2380万人 死者は48万人と推定されています。
100年で世界は当時と比べ、地球規模でグローバル化が進み、 科学技術や医学技術は格段に進歩しているが、基本的な対策は当時と大差のないことが分かります。
ワクチンの進歩をのぞけば、感染症対策はほぼ変わらないですね。
緊急事態宣言が全国で解除され、私たちの生活も、
経済活動も徐々にではあるが回復の道を歩み始めた。
しかし、専門家の間では、
「新型コロナのワクチンができるか、多くの人が感染することで集団免疫を獲得するまでは、終息は難しい」のではないかと、警鐘を鳴らす人もいる。
全面解除されたとはいえ、
私たち一人ひとりが感染予防者であるという自覚を持つことが必要なのではないか。
(つれづれに…心もよう№106) (2020.5.26記)




















 (トイレットペーパーがなくなる)
(トイレットペーパーがなくなる)