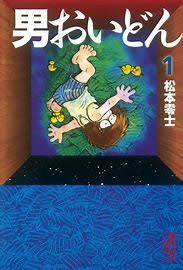海に消えた対馬丸・学童疎開の悲劇 ④
学童疎開船『対馬丸』 撃沈に至る経緯 ②
真珠湾奇襲攻撃 1941(昭和16)年12月
ミッドウェイ海戦 1942(昭和17)年6月 この海戦で日本は多くの犠牲を余儀なくされ、戦況は
劣勢になっていく
サイパン陥落 1944(昭和19)年7月 (学童疎開船「對馬丸」出港・撃沈まで1年)
1944(昭和19)年7月7日、サイパンの日本軍が陥落した。
本土防衛の「防波堤」である絶対防空圏の一つであるサイパンが米軍の手に落ち、
日本本土はB29・重爆撃機の爆撃圏内に入った。
サイパンが陥落すると各地に派兵された兵隊が、米軍上陸に備え沖縄に進駐してきた。
当時、人口49万人の沖縄に10万の兵隊が集まってきた。
59万人に膨れ上がった沖縄の人々にとって不足するものは何か?
小さな島では食料の生産性も極めて低く、本土からの食料の移送もままならず、
沖縄決戦を推進するにはあまりにも脆弱な食料体制だ。
本土防衛のための最後の砦となる沖縄に集められた兵隊たちの食料確保は、
何としても実現しなければならない最重要事項であった。
以上の戦況のもとで、
日本政府はこれから戦場になる沖縄から、九州に8万人、台湾に2万人の疎開が計画された。
命を守るための疎開政策の裏に、
食糧難の状況を打破するために計画された「学童集団疎開」計画が立案された。
※ 台湾疎開について
台湾は1683~1895年までは清国の支配下にあったが、1895年日清戦争に勝利した日
本が台湾の統治権を得た。以後約50年間(1895~1945)、台湾は日本の支配下にあっ
た。日本の支配下で、道路、鉄道、上下水道、電気などのインフラ整備も行われ、
教育は日本語で行われた。植民地の台湾への疎開が計画されたわけです。
植民地支配は第二次世界大戦で日本は敗戦国となり、統治権を放棄した。
(つづく)
(語り継ぐ戦争の証言№28) (2023.7.22記)