
エッセイ 料理を愉しむ
美味しい料理を食べて楽しむ。そして美味しい料理をつくることを楽しむ。この両面から、このエッセイを書きました。
われらが池波正太郎には、「鬼平犯科帳」や「剣客商売」といった名編がある。しかし、こと料理に関して、はなんと云っても「仕掛け人・藤枝梅安」であろう。全七巻の小説の至るところに美味そうな小料理の話が仕込まれている。
(貝柱飯)はしらめし
”やがて彦次郎が帰ってきた。「貝柱のいいのがあったよ。梅安さん。それに豆腐と、子もちの鯊(はぜ)を買ってきた」。「それで十分だよ」
「どうしなすった。にやにやと妙な笑いをしなさるじゃあねえか。「うふふ、ふふ、・・・こんなことは私もはじめてだよ」「札差の元締めが、そんなに妙な仕掛けをたのみに来なすったのかえ?」「そうとも、そうともさ、彦さん。まあ、聞いておくれ」
それからしばらくして、二人は膳を囲み、酒を酌み交わしていた。さっと煮付けた子持ちはぜに、湯豆腐である。貝柱は後で、炊きたての飯へ山葵醤油とともにまぶしこみ、焼海苔をふりかけて、たっぷりと食べるつもりであった。”
~「春雪仕掛針」から
ちなみに梅安は大根が好物。彦次郎は豆腐が好物である。
ここに出てくる貝柱は、いうまでもなく青柳のそれである。本名は馬鹿貝。バカガイ科の二枚貝。青柳をさっと熱湯かけて霜降りにしたものを、酢の物かぬたで賞味する。青柳と豆腐の小鍋立てというのも、いい。材料は他には独活とか春菊でもあればいい。青柳は淡い塩水で振り洗いした後、水気切っておく。豆腐は焼き豆腐がいい。独活は皮をむいて短冊に切る。春菊は葉先だけを摘み取っておく。材料を全部ざるに盛っておいて、小さな土鍋で出汁を煮立て、少しずつ煮ながら食べる。
奮発して小柱(バカ貝の貝柱のこと)を買ってきたら、二つに分け、半分は池波正太郎流の貝柱飯*(はしらめし)にする。もう半分は分葱と一緒に強火でさっと炒めて酒の肴にする。胡麻油で分葱を炒め、次に小柱をいれ、酒と淡口醤油で味を整え、最後に七味をふる。手早くすること。静岡(檜の木)の料理人・西堀高市の創案による。
(*貝柱飯・・はしら飯。貝柱を醤油、おろし山葵で和え、炊きたてのご飯にかき回し合わす。器に盛り、もみ海苔をのせる)
小柱のことがでてきたので、小柱のかき揚げについて、そのコツを紹介しておく。末尾を参照されたい。 これまた余談になるが、東京の新幹線品川駅では、「貝づくし弁当」を販売している。はまぐり、しじみ、アサリ、貝柱、びっしりと敷き詰められている。貝柱は、小さい小柱のようなものが沢山入っている。これを買って、新幹線の車内で食べるのが、昨今の楽しみの一つである

(兎汁)・・・豚のバラ肉の薄切りで代用する。兎汁より遥かに美味い。
”ゆったりと歩を運び、芝口橋を渡ったとき(そうだ、ひさしぶりに・・・)思いついたことがある。それは、京橋の東詰めを北へ行った大根河岸にある「万七」という小体な料理屋のことだ。「万七」の名物は、兎汁である。そこの兎汁は、生姜をきかせ、巧妙に葱をあしらったもので、これが藤枝梅安の大好物なのだ。小さな火鉢が梅安の前におかれ、そこへ小ぶりな鉄鍋をかけ、女中が出汁をそそぎ、客の目の前で兎汁をつくる。淡白な兎肉の脂肪が秘伝の出汁に溶け合い、”いつもながら、うまいな”と梅安が舌鼓を打ったとき、となりの座敷へ客が入ってくる気配がした”
~「梅安蟻地獄」から
今日、梅安の好きな兎汁を再現することはむずかしい。だからといってがっかりすることはない。どこにでもあって値段の安い豚の三枚肉(いわゆるバラ)の薄切りを買ってきて、兎汁としてつくればよい。味は兎汁より遥かにうまい。土鍋に昆布出汁をいれ、醤油・塩・酒で味を好きなように整える。火にかけ、まず豚肉をいれ、浮き上がってきたアクをすくい取り、食べる直前に水菜のざく切りを入れる。水菜は歯あたりのシャキッとしてるのが値打ちなので、いれたらすぐ食べる。酒は、やや甘口の酒があう。淡麗な吟醸酒はむしろ合わない。
(焼きむすび)
”(ふうん・・・梅安さん。しゃれた家に住んでるなあ)八畳と六畳の二間。玄関を入って土間。廊下も何もなく、土間と二つ部屋の間に、長四畳の板の間がある。彦次郎は、この板の間の天井板を外しておいてから、蝋燭を灯し、手にした風呂敷包みを開いた。その他には脇差が一つ。にぎりめしに醤油をつけて焼いたものが五個。これは竹の皮に入っている。”
~「殺しの四人」から
こめの飯くらいうまいものはない。とにかく米はうまい。米の良否を見分けるには、まずひとつまみ掌に取り、匂いを嗅ぐ。つきたての米には一種独特の芳香がある。米粒が丸く充実したものが成熟したよい米である。乾燥が十分であるか否かは噛んで食べる。乾燥のよい米はパリパリとして噛むのに一苦労するはずである・・・と。今は亡き辰巳浜子が『料理歳時記」の中で教えている。 注)辰巳浜子の娘さんが辰巳芳子。『味覚日乗』などの料理についての名著がある。
米のうまさがしみじみわかるのは、なんといってもにぎりめしである。にぎりめしには、握った人の愛情も一緒ににぎりしめられている。だから、うまい。にぎりめしもちいさく一口の大きさにすれば酒の肴になる。ちょっと知恵を働かせれ、ありあわせの材料ですぐ十種類や十五種類のにぎり飯ができる。コ胡麻、ちりめんじゃこ、たらこ、塩鮭、味噌、醤油、たくあん、梅干し、青じそ、野沢菜、焼海苔、削り節、ふりかけ、佃煮、桜の花の塩漬け、瓶詰めの雲丹、わさび漬け、塩昆布。どこの家にも必ずあるものばかり。それを中にいれたり、まぶしたり、塗ったり、焼いたりすればいいだけのことである。
ちなみに、最近では肉巻きおにぎりというのがある。小ぶりのおにぎりに、牛薄切り肉を巻いて、フライパンに胡麻油をいれて加熱し、火が通ったら焼き肉のたれとコチュジャンを加えて、煮絡める。弁当として、乙なものである。
(蝦蛄の煮つけ)
”元締めに座を子分の藤五郎へゆずりわたし、今は目黒の碑文谷に古女房と暮らしている亀右衛門が帰ろうとするのへ、 「ま、もう少しお待ちなさい。先刻、いい蝦蛄がとどいてね、今ちょっと煮付けるから、それで久しぶりにお酒を・・・」「へえ、嬉しゅうございますねえ、先生。かまいませんかえ?」「もうね、すっかり弱くなっちまって・・・五合(ごんごう)くらいなら、おつきあいさせて頂きましょうよ」
~「梅安鰹飯」から
蝦蛄は煮付けに限る、とまでは言わないが、煮付けの味が好ましい。殻付きのまま甘辛く醤油で煮たものを、箸を尻尾の方から差込み、指でしっぽを抑えながら箸を持ち上げるようにすると、きれいに殻が剥がれる。
東京は外神田にある池波正太郎行きつけの料亭「花ぶさ」では、「シャコめし」を出す。
注)今は、シャコ飯はないようだ。
余談になるが、関西の日生では、蝦蛄は畑の肥やしと云われ、だれも食べなかったらしい。いつぞや、日生の港からフェリーで頭島へ渡ったことがある。スケッチ旅行であった。そこの民宿では、山と盛られたしゃこの塩ゆでをだされた。殻を剥いて、次から次へとぱくついた。その美味いことうまいこと。それに安いものだ。関東の人は、蝦蛄は高級品と思っているのであろう。寿司種に出てくるくらいである。茹でたものを寿司に載せる。きっと高くつくだろう。可哀相だ。
(秋茄子の塩もみ)
”夜更けて、から雨がやんだ。障子の桟に止まった茶立虫が、小さな音をたてているのを、梅安が指差して、「あの音はね、虫のやつがあごで叩いているのだよ」「へえ、本当に梅安さんは、もの知りだねえ」「ときに彦さん、そそそろ江戸へ帰ろうか・・・?」「梅安さんの心まかせだ」二人は茶碗酒を酌み交わしている。肴は、女中が寝しなにもってきてくれた秋茄子の塩もみへ、水辛子をそえただけのものであった。「こいつは、たまらなくうまい。と彦次郎が舌鼓をうった。”
~「秋風二人旅」から
茄子の塩もみといっても、なすに塩をふって、すぐにぎゅっぎゅっと手で強くもみ込だけのことなので、その説明はおいておき、新しい茄子の賞味法をご紹介しよう。NHKのベテランアナウンサーの羽佐間正雄氏の夫人の羽佐間温子さんの「茄子かやき」という料理である。夫人の語るところでは、
”私や弟が大きくなりました山口県のお茄子は、東京のと違いまして20センチから25センチもあります長茄子です。その皮をむき、そぎ切りにして、水につけてアク抜きしておきます。鮭缶を少し奮発して二缶、汁ごと浅鍋にあげまして、ほんのわずか水を足します。それに、お醤油をたらして茄子を煮るときくらいの味加減にし、テーブルの上に出したガスコンロで、茄子を煮ながらいただきます。”
真夏で「茄子かやき」で、こんなにおいしいものはないという。残った茄子の皮は、刻んだ唐辛子と一緒に胡麻油で炒めて食べると美味しいそうだ。
(豆腐の葛あんかけ)
”昨日の夕暮れであったが・・・。浅草の外れの塩入土手下にあるわが家に帰ってきた彦次郎は、土間に押し込まれている結び文を拾い上げた。「手すきのときに、顔をみせてください たま屋」としたためてある。・・・
朝のうちに買っておいた豆腐を土鍋に入れて煮ながら、彦次郎は別の小さな鉄鍋で葛餡をこしらえた。行灯に火をいれてから、酒をあたため、豆腐に熱い葛餡をかけまわした一鉢と大根の切漬けだけで、彦次郎は五合ほど呑んだ。”
~「梅安流れ星」から
彦次郎は豆腐に葛餡をかけて食べる。「豆腐をやや大型に切り、たっぷりと水を加えて食塩ひとつまみを入れ、煮加減をすくい揚げて 湯を切り、深い器に取った上から煮立てた葛餡をどろりとかけて、おろし生姜・さらし葱・もみ海苔だどを添える。葛餡は煮出し汁に醤油・味醂などでややこっくりと味をつけ、煮立たせたところへ水溶きした葛を適宜加えて煮る。」(本山萩舟 『飲食辞典』
彦次郎はよほど豆腐が好きなのである。湯豆腐、冷奴に次ぐ食べ方と思っている。
(根深汁つき大根浅漬)
”梅安は、もう夕餉の支度をととのえてあった。濃い目に仕立てた根深汁に、生卵と梅干し、大根の浅漬だけのものだが、その熱い根深汁を一口すすりこんだ彦次郎と小杉十五郎が、「おや・・・?」「これは妙だ」と、顔を見合わせた。「うまいかねね?」と梅安。「うまい。こんな根深汁ははじめてだが・・・」いいさした彦次郎が椀の中をじっと見て、「ははあ・・・」「わかったか?」「胡麻の油を少し、落としなすったね?}「うむ。ほんの少し」
~「梅安針供養」の中「地蔵堂の闇」から
池波正太郎は実に葱が好きなのである。『味と映画の歳時記』の十二月の一節から。
”ところで、葱も旨くなる。大根と同様に、葱の応用も多種多用だが、鶏の皮を少々いれた葱の味噌汁や吸い物は、このひと椀で酒も飯もすませてしまうことができるほど、私の好物なのだ。品質のよい葱の、太い白根のところをぶつ切りにし、胡麻油を塗ってコンロの網で焙り、柚味噌や塩食べるのもよい。”
この鶏の皮というのが、今日手に入るのだろうか? 少し前は、「パントリーというすぐ近くの食料品スーパーで売っていたのだが・・・。これを小さなフライパンで、カリカリ成るまで焼いて、塩を振ると、ウイスキーの最高のつまみになるのだが・・。
(大根と油揚げの鍋仕立て)
”それから尚、二日を「井筒」に泊まり、日中はどこかへ出歩いていた藤枝梅安は、いったん雉子の宮の我が家へ帰った。夕暮れから降りはじめた雪はやむことなく、翌朝、梅安が目覚めてみると、すでに厚く積もっていた。百姓の女が帰ってしまった昼過ぎになってから、梅安はようやく起き出した。居間に切ってある囲炉裏へ、うすく出汁を張った鉄鍋を掛け、中へ輪切り大根と油揚げを細く切ったものをいれ、これがぐつぐつ煮えだすのを小皿にとって、さもうまそうに食べつつ、梅安は酒をのみはじめた。”
~「おんなごろし」から
大根の葉もいいものだ。強火でさっと炒め、醤油と唐辛子で味付けしたのを、飯のおかずにしたり、酒の肴にする。いい大根があり、新しい酒粕があり、寒鰤があったら、ぶり大根がいい。ブリは出刃包丁でぶつ切りにし、水洗いする。大根は厚い輪切りにし、皮は厚くむき、たっぷりの米の研ぎ汁で茹で、柔らかくなったら、一度水洗いして出汁の中へブリと共に入れる。三時間程とろ火で煮るとブリの骨まで柔らかく成るから、そこで酒粕と塩少々を加え、さらに一時間ほど煮る。煮上がる少し前に、四つ切にした椎茸をいれ、味がしみるまで煮て、仕上げにそいだ柚子を散らす。
余談になるが、大根の葉っぱについて辰巳浜子が、『料理歳時記』の中で、次のように書いている。
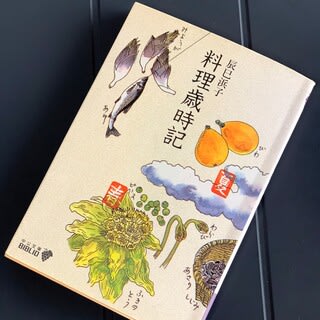
”大根の葉の栄養価の高いことは白い部分の幾倍と聞いては、とてものことに捨てることはできません。青い葉の部分をしごいて、さっと湯通しして、細かく刻んで塩味をして菜めしにしましょう。茎は糠味噌に入れたり、刻んで大のしっぽや皮を混ぜて大阪漬けにします。青い葉を温度の低い油で真青にからりと揚げて箸で細くつぶし、大根おろしに混ぜ合わせ、二杯酢または三杯酢で和えます。酢はゆず、レモン、すだちなどを使えば理想的な栄養食なります。葉も茎もともに細くきざみ、胡麻油で炒め、砂糖・醤油でやや濃い目に味付けをしてから、からからに煎りつけ、七味唐辛子をふりかけると、温かいご飯にうってつけで、まことに食欲をそそります”
(大根鍋)
”とっぷりと暮れてから、梅安を彦次郎は、居間の長火鉢へ土鍋をかけ、これに出汁を張った。ざるに、大根を千六本に刻んだのを山盛りにし、別のざるには浅蜊の剥き身が入っている。
鍋の出汁が煮えてくると、梅安は大根の千六本を手づかみでいれ、浅蜊もいれた。刻んだ大根は、すぐさま煮えあがる。それを浅蜊とともに引き上げて小皿にとり、七色唐がらしを振って、二人とも、汁と一緒にふうふうう言いながら口に運んだ。「うめえね、梅安さん」「冬がくると、こいつ、いいものだよ」酒は茶碗でのむ。・・・「彦さん・・・」「え・・・?」箸をとめて藤枝梅安は 「とうとう白いものが落ちてきたようだね」といった。”
~「梅安晦日蕎麦」から
(浅蜊と大根ー小鍋立て)
”その夜。梅安は、ひとり遅い夕餉の膳に向かっていた。春の足音は、いったん遠のいたらしい。毎日の底冷えがきつく、ことに今夜は、雪になるのでははいかと思われた。
梅安は、鍋へうす味の出汁を張ってコンロにかけ、これを膳のかたわらへ運んだ。大皿へ、大根を千六本に刻んだものが山盛りになってい、浅蜊の剥き身もたっぷりと用意してある。出汁が煮立った鍋の中へ、梅安は手づかみで大根をいれ、浅蜊をいれた。千切りの大根はすぐ煮える。煮えるそばから、これを小鉢に取り、粉山椒をふりかけ、出汁とともにふうふう言いながら食べるのである。このとき、酒は冷のまま。
~「梅安最合傘」から
(鯛)
”梅安は、積もった雪の中を、あちこちと治療に出歩き、夕暮れになってから帰ってきた。雪は、昼過ぎにやんでいる。・・・梅安は、堀本桃庵が届けてくれた鯛をさばきにかかった。まず、刺し身にし、残る片身は塩焼きにしておいた。鯛の刺身で、たっぷり酒をのんだ梅安は、濃い目にいれた煎茶へぱらりと塩をふって吸い物がわりにし、残った飯を四杯も食べた。”
~「闇の大川橋」から
鯛ぐらいありがたい魚は他にはない。頭からしっぽの先まで、捨てるところが一つもない。頭はかぶと焼き、かぶと汁、潮汁。もちろんチリ鍋にも使える。頬の肉に食らいつく時の幸福感は魚好きなら説明無用だろう。目玉(目のまわりの肉)となると、もう喧嘩腰で早いもの勝ちということになる。
刺し身は皮を引かずにさっと熱湯をかける「鹿の子づくり」が洒落ている。皮を引いて平づくりにした時も、皮を捨てるなどとんでもないことで、これは極上に箸洗いにもなるし、和え物にも得難き材料である。肝や子は炊合せがよく、中骨その他はアラ煮とし、文字通り骨までしゃぶり尽くさねばならぬ。身を取った残りの中骨は白焼きにするという手もある。白焼きにしてから、さらにくっついている細い身を丹念にこそげ落とし、これをそのままおろし和えにしたり、酢の物にしたり、また味噌と煮込んで鯛味噌にせよ・・・と懐石名人の辻嘉一が教えている。
大鯛が無理でも小鯛というものがある。若狭名物の小鯛の笹漬けは、昔は京都四条富小路の「わかさや」で売っていたが、今はなくなった。もちろん、若狭から取り寄せることができる。酒のあてになるし、炙って飯のおかずにもなる。
「小柱のかき揚げ」についていうと、これが結構むずかしい。小柱の水気をしかかりとることと、揚げる油の温度管理。東京は築地にある懐石料理の名店「つきじ田村」の料理長、田村隆のいうところを紹介しておく。
”①ホタテ小柱は布巾などで水気をしっかり取る。三つ葉を2センチ程度の長さに刻む。
②ボウルに小柱と三つ葉を入れ、薄力粉少々を加えて和える。全体にまんべんなくかぶさるくらいの量の基本の衣を加え、箸でさっくり混ぜる
③揚げ油を160~170度に熱し、網杓子の上にのせて油の中に静かに入れる。4等分が目安。あれば、紅葉の葉を衣と一緒に揚げる。
④衣がほとんどキツネ色になったら、取り出して油をとる。
⑤器に紙をしき、その上に盛る。
三代目の田村隆さんは、この一月に逝去された。まだ63歳という働きざかりの時に。合掌。
~~~~~~~~~~~~~
まだまだあるが、この辺りで、いったんしめることにする。お読みいただいたように、まことに素朴な手料理である。戦後のひもじい時期に生きてきた私にとっては、これで十分である。これより手のこんだ料理となると、料理屋へ行くことになる。本格的な料理を味わいたい時は、京都は高倉御池上がるの「押小路 岡田」に行く。ここは、二年ほど前に開いた本格懐石料理を出す。味は一流、値段は十分手の届く範囲にある。気に入った店なので愛用している。もう少し気張れば、堺町通り下がるの<室町和久傳>に足を運ぶ。
しかしふだん使いということになると、<和食 晴ル>(高倉通綾小路角)に足を運ぶ。ここはちょっと市中の賑やかなエリアからは離れているが、安くて旨い。時には、いい意味で期待を裏切るような料理が出てくる。すこし、そのメニューをみてみよう。
おでんには、大根、赤こんにゃく、浅蜊真丈、ふきのとう真丈など。前菜では、雲子ポン酢、あん肝酒蒸し、和牛すじ煮込み、生麩バターソテー。炭焼は、甘鯛、のど黒、鴨ハンバーグ。揚げ物は、白アスパラフライ、カキフライ、鴨メンチカツ、甘鯛うろこ揚げ。酒肴としては、自家製カラスミ、自家製鴨生ハム、タラコ粕漬け。 ご飯物は、鯖寿司、づけ丼、白魚の玉しめ丼。
さらに黒板には、旬のメニューが書かれている。明石産鯛、北海道毛ガニ、宮津産サヨリ、牡蠣の太白油漬け、牛肉クレソンすき焼き、本鮪と辛味大根、長崎産アオリイカ、ホタルイカ天ぷら、菜の花辛子和え、河豚の唐揚げ、春キャベツのおひたし。などなど、。どれも呑み助にはたまらない。
そして呑助のためにに、いい日本酒を置いてある。純米澤屋まつもと、特純禮泉、純吟黒龍、純米大吟醸尾瀬の雪どけ、などなど。もちろん、芋や麦の焼酎もある。
どうしてこんなに様々なメニューが提供できるのか? 素人目には、不思議に思う。一日、二日くらいしか鮮度が持たないものも少なくない。毎日の積み重ねで、おおよその需要の見当がつくのかも知れない。
ここと似たような店が京都駅近くにある<燕(えん)>という店である。予約を取るのは至難の業だ。メニューにも、共通するようなものがあるが、一方で一捻りしたものが少なくない。一例を上げれば、グアンチャーレ西京焼き(豚トロを塩漬けにして熟成させたイタリアの食材)。グアンチャーレを蕗の薹入りバターで焼いたもの)、アボカドの梅肉おろし。焼きたての鮎の塩焼きもうまい。ここは、しょっちゅう通っている。
この両店は、和久傳の流れを汲むものである。ほかにも和久傳で修行した若い人たちが京都で競い合っているようだ。

この「晴ル」から歩いてさほど遠くないところにバー「ロッキングチェア」がある。御幸町通り、仏光寺下がる。京都にはバーの名店がいろいろあるが、ここほど気軽で洒落たバーはあまり知らない。ご婦人連れで行かれれば、きっと連れのお気に召すこと請け合いである。
(日頃、気に入って料理をしているレシピ)
「レタスのオイスターソース炒め」・・・さる中華料理の店で食べていらい、やみつきになってしまった。ところが、この店が閉店になってしまった。
それでは自分でつくるしかないと、試している。
①レタス(ひと玉)を、ややおおめに手でちぎる。これに塩とオリーブオイル少々を薄くまんべんなく振りかける。
②レンジ用容器に、これをいれて電子レンジで2分30秒加熱する。加熱後取り出すと半ゆで状態になるが、レタスのシャキシャキ感は残っている。これを、ひっくり返して皿にもる。
③耐熱容器に、中華スープ(ガラスープ)の素小さじ1、オイスターソース大さじ1、紹興酒小さじ1、胡麻油こさじ1、(チューブの)にんにく1センチ。これらを水40CCに入れてよくかき混ぜ、電子レンジで50秒ほど加
熱する。これをレタスにかける。
これは、まだ研究中である。オイスターソースを元町中華街の専門店で、あれこれ買ってきて、さらに美味しいものに仕上げたいと思っている。なおこれは、どちらかといえば副菜である。しかるべき主菜との組み合わせが肝要であろう。
豚の薄切りロースを、醤油でさっと煮絡めたものと組み合わせるといいかも知れない。
「蕗味噌」
”春の寒さたとえば蕗の苦味かな” (夏目成美)
この季節になると、様々な山菜が出てきます。その中でも蕗の薹は独特の香りや苦味があって魅力的な一品になります。茹でた蕗の薹を摺って白味噌や赤味噌と混ぜ、砂糖と味醂を加えると酒の肴にもなります。これを、おにぎりにのせ
て焼きおにぎりにすると、まさに春に先駆ける逸品になる。
「材料」
ふきのとう …… 7~8個
味噌・みりん・砂糖……各大さじ3(お好みで加減してください)
胡麻油)…… 適量
「つくりかた」蕗の薹を半分に切り、水にさらしてアクを抜く。水気をとって細かく刻み、油で炒める。味噌・砂糖・みりんを入れ、弱火で練り混ぜながら煮詰める。
酒の肴として、そのまま味わってもいいが、焼きおにぎりにすると軽い食事にもなる。おにぎりに蕗味噌をのせて、トースターで焼き目がつくくらい焼く。
(最後に)今回、このエッセイを書くにあたって、池波正太郎の『仕掛け人・藤枝梅安』の他に『料理歳時記』(辰巳浜子)や、『池波正太郎・鬼平料理帳』(編、佐藤隆介)、さらに佐藤隆介さんの著作『日本口福紀行 がんこの卓上』などなどを参考にさせていただいた。その中で、異色のライターが書いた『システム料理学』(丸元叔生)は、なかなか興味深いものがある。丸元さんは、東京大学仏文科を卒業し、編集の道から作家になった。ところが、何を思ったのか、最新の栄養学にもとづく料理の研究の道に入り、数々の著作をものにしている。『丸本淑生のクックブック』(文春文庫)や
『今、家庭料理を取り戻すには』(中公文庫)などがある。
『システム料理学』では、和食の出汁のもとになる鰹節についての一文がある。興味深いので引用させていただく。
”かつお節と昆布は料理の基礎であり、ほとんどの料理は、これなしにはつくれない。そのかつお節の上等なものは、現在築地の場外市場で1キロ三千円前後、極上品は三千七、八百円で買える。一キロでだいたい三本と思ったらよい。いずれにしろキロ三千円以上のものを買っていれば問題はない。一キロ買っておくと二ヶ月はもつから、月にして千五百円の消費である。それで、味噌汁も、煮物もサラダも、すべてこの上なく美味しいいものとなることを思えば極めて安いものだ。しかし、二千五百円のものを買ってくるとそうはいかない。すべての味が駄目になるからだ。呆れ果てて捨てることになり、そうなればお金をドブに捨てたことにほかならない。
なお、かつお節の表面には薄くカビが生えている。カビによって、変質するのを防ぐ工夫なのだ。このカビは削る際、湿らせた布巾で拭くときれいに落ちる。また、そうやって若干の湿気を与えることで削りやすくる。ところが、京都の錦市場のカツオ節屋を見て驚いた。どれにもカビがない。聞けば、最近の人はカビの生えたものは買わないとのこと。一本のかつお節に、民族の文化が凝縮されている。”
ちなみに、この本の出版されたのは1980年代の初めである。現在は、どうか? 調べてみると鹿児島は枕崎のカツオ本節、5本セットで、およそ5800円。重さが、やく1.1キロだから、それほど変わっていない。これを使って、本格的な出汁をとってみたい。
~~~~~~~~~~~~~
みなさま如何でしたか? ”よし、俺も厨房にたって、うまいものを作ってみよう”と思われましたでしょうか? ”いや、前からやってるよ!”、とおっしゃる諸兄姉は、ぜひ得意のレシピをご紹介ください。お待ちしています。
美味しい料理を食べて楽しむ。そして美味しい料理をつくることを楽しむ。この両面から、このエッセイを書きました。
われらが池波正太郎には、「鬼平犯科帳」や「剣客商売」といった名編がある。しかし、こと料理に関して、はなんと云っても「仕掛け人・藤枝梅安」であろう。全七巻の小説の至るところに美味そうな小料理の話が仕込まれている。
(貝柱飯)はしらめし
”やがて彦次郎が帰ってきた。「貝柱のいいのがあったよ。梅安さん。それに豆腐と、子もちの鯊(はぜ)を買ってきた」。「それで十分だよ」
「どうしなすった。にやにやと妙な笑いをしなさるじゃあねえか。「うふふ、ふふ、・・・こんなことは私もはじめてだよ」「札差の元締めが、そんなに妙な仕掛けをたのみに来なすったのかえ?」「そうとも、そうともさ、彦さん。まあ、聞いておくれ」
それからしばらくして、二人は膳を囲み、酒を酌み交わしていた。さっと煮付けた子持ちはぜに、湯豆腐である。貝柱は後で、炊きたての飯へ山葵醤油とともにまぶしこみ、焼海苔をふりかけて、たっぷりと食べるつもりであった。”
~「春雪仕掛針」から
ちなみに梅安は大根が好物。彦次郎は豆腐が好物である。
ここに出てくる貝柱は、いうまでもなく青柳のそれである。本名は馬鹿貝。バカガイ科の二枚貝。青柳をさっと熱湯かけて霜降りにしたものを、酢の物かぬたで賞味する。青柳と豆腐の小鍋立てというのも、いい。材料は他には独活とか春菊でもあればいい。青柳は淡い塩水で振り洗いした後、水気切っておく。豆腐は焼き豆腐がいい。独活は皮をむいて短冊に切る。春菊は葉先だけを摘み取っておく。材料を全部ざるに盛っておいて、小さな土鍋で出汁を煮立て、少しずつ煮ながら食べる。
奮発して小柱(バカ貝の貝柱のこと)を買ってきたら、二つに分け、半分は池波正太郎流の貝柱飯*(はしらめし)にする。もう半分は分葱と一緒に強火でさっと炒めて酒の肴にする。胡麻油で分葱を炒め、次に小柱をいれ、酒と淡口醤油で味を整え、最後に七味をふる。手早くすること。静岡(檜の木)の料理人・西堀高市の創案による。
(*貝柱飯・・はしら飯。貝柱を醤油、おろし山葵で和え、炊きたてのご飯にかき回し合わす。器に盛り、もみ海苔をのせる)
小柱のことがでてきたので、小柱のかき揚げについて、そのコツを紹介しておく。末尾を参照されたい。 これまた余談になるが、東京の新幹線品川駅では、「貝づくし弁当」を販売している。はまぐり、しじみ、アサリ、貝柱、びっしりと敷き詰められている。貝柱は、小さい小柱のようなものが沢山入っている。これを買って、新幹線の車内で食べるのが、昨今の楽しみの一つである

(兎汁)・・・豚のバラ肉の薄切りで代用する。兎汁より遥かに美味い。
”ゆったりと歩を運び、芝口橋を渡ったとき(そうだ、ひさしぶりに・・・)思いついたことがある。それは、京橋の東詰めを北へ行った大根河岸にある「万七」という小体な料理屋のことだ。「万七」の名物は、兎汁である。そこの兎汁は、生姜をきかせ、巧妙に葱をあしらったもので、これが藤枝梅安の大好物なのだ。小さな火鉢が梅安の前におかれ、そこへ小ぶりな鉄鍋をかけ、女中が出汁をそそぎ、客の目の前で兎汁をつくる。淡白な兎肉の脂肪が秘伝の出汁に溶け合い、”いつもながら、うまいな”と梅安が舌鼓を打ったとき、となりの座敷へ客が入ってくる気配がした”
~「梅安蟻地獄」から
今日、梅安の好きな兎汁を再現することはむずかしい。だからといってがっかりすることはない。どこにでもあって値段の安い豚の三枚肉(いわゆるバラ)の薄切りを買ってきて、兎汁としてつくればよい。味は兎汁より遥かにうまい。土鍋に昆布出汁をいれ、醤油・塩・酒で味を好きなように整える。火にかけ、まず豚肉をいれ、浮き上がってきたアクをすくい取り、食べる直前に水菜のざく切りを入れる。水菜は歯あたりのシャキッとしてるのが値打ちなので、いれたらすぐ食べる。酒は、やや甘口の酒があう。淡麗な吟醸酒はむしろ合わない。
(焼きむすび)
”(ふうん・・・梅安さん。しゃれた家に住んでるなあ)八畳と六畳の二間。玄関を入って土間。廊下も何もなく、土間と二つ部屋の間に、長四畳の板の間がある。彦次郎は、この板の間の天井板を外しておいてから、蝋燭を灯し、手にした風呂敷包みを開いた。その他には脇差が一つ。にぎりめしに醤油をつけて焼いたものが五個。これは竹の皮に入っている。”
~「殺しの四人」から
こめの飯くらいうまいものはない。とにかく米はうまい。米の良否を見分けるには、まずひとつまみ掌に取り、匂いを嗅ぐ。つきたての米には一種独特の芳香がある。米粒が丸く充実したものが成熟したよい米である。乾燥が十分であるか否かは噛んで食べる。乾燥のよい米はパリパリとして噛むのに一苦労するはずである・・・と。今は亡き辰巳浜子が『料理歳時記」の中で教えている。 注)辰巳浜子の娘さんが辰巳芳子。『味覚日乗』などの料理についての名著がある。
米のうまさがしみじみわかるのは、なんといってもにぎりめしである。にぎりめしには、握った人の愛情も一緒ににぎりしめられている。だから、うまい。にぎりめしもちいさく一口の大きさにすれば酒の肴になる。ちょっと知恵を働かせれ、ありあわせの材料ですぐ十種類や十五種類のにぎり飯ができる。コ胡麻、ちりめんじゃこ、たらこ、塩鮭、味噌、醤油、たくあん、梅干し、青じそ、野沢菜、焼海苔、削り節、ふりかけ、佃煮、桜の花の塩漬け、瓶詰めの雲丹、わさび漬け、塩昆布。どこの家にも必ずあるものばかり。それを中にいれたり、まぶしたり、塗ったり、焼いたりすればいいだけのことである。
ちなみに、最近では肉巻きおにぎりというのがある。小ぶりのおにぎりに、牛薄切り肉を巻いて、フライパンに胡麻油をいれて加熱し、火が通ったら焼き肉のたれとコチュジャンを加えて、煮絡める。弁当として、乙なものである。
(蝦蛄の煮つけ)
”元締めに座を子分の藤五郎へゆずりわたし、今は目黒の碑文谷に古女房と暮らしている亀右衛門が帰ろうとするのへ、 「ま、もう少しお待ちなさい。先刻、いい蝦蛄がとどいてね、今ちょっと煮付けるから、それで久しぶりにお酒を・・・」「へえ、嬉しゅうございますねえ、先生。かまいませんかえ?」「もうね、すっかり弱くなっちまって・・・五合(ごんごう)くらいなら、おつきあいさせて頂きましょうよ」
~「梅安鰹飯」から
蝦蛄は煮付けに限る、とまでは言わないが、煮付けの味が好ましい。殻付きのまま甘辛く醤油で煮たものを、箸を尻尾の方から差込み、指でしっぽを抑えながら箸を持ち上げるようにすると、きれいに殻が剥がれる。
東京は外神田にある池波正太郎行きつけの料亭「花ぶさ」では、「シャコめし」を出す。
注)今は、シャコ飯はないようだ。
余談になるが、関西の日生では、蝦蛄は畑の肥やしと云われ、だれも食べなかったらしい。いつぞや、日生の港からフェリーで頭島へ渡ったことがある。スケッチ旅行であった。そこの民宿では、山と盛られたしゃこの塩ゆでをだされた。殻を剥いて、次から次へとぱくついた。その美味いことうまいこと。それに安いものだ。関東の人は、蝦蛄は高級品と思っているのであろう。寿司種に出てくるくらいである。茹でたものを寿司に載せる。きっと高くつくだろう。可哀相だ。
(秋茄子の塩もみ)
”夜更けて、から雨がやんだ。障子の桟に止まった茶立虫が、小さな音をたてているのを、梅安が指差して、「あの音はね、虫のやつがあごで叩いているのだよ」「へえ、本当に梅安さんは、もの知りだねえ」「ときに彦さん、そそそろ江戸へ帰ろうか・・・?」「梅安さんの心まかせだ」二人は茶碗酒を酌み交わしている。肴は、女中が寝しなにもってきてくれた秋茄子の塩もみへ、水辛子をそえただけのものであった。「こいつは、たまらなくうまい。と彦次郎が舌鼓をうった。”
~「秋風二人旅」から
茄子の塩もみといっても、なすに塩をふって、すぐにぎゅっぎゅっと手で強くもみ込だけのことなので、その説明はおいておき、新しい茄子の賞味法をご紹介しよう。NHKのベテランアナウンサーの羽佐間正雄氏の夫人の羽佐間温子さんの「茄子かやき」という料理である。夫人の語るところでは、
”私や弟が大きくなりました山口県のお茄子は、東京のと違いまして20センチから25センチもあります長茄子です。その皮をむき、そぎ切りにして、水につけてアク抜きしておきます。鮭缶を少し奮発して二缶、汁ごと浅鍋にあげまして、ほんのわずか水を足します。それに、お醤油をたらして茄子を煮るときくらいの味加減にし、テーブルの上に出したガスコンロで、茄子を煮ながらいただきます。”
真夏で「茄子かやき」で、こんなにおいしいものはないという。残った茄子の皮は、刻んだ唐辛子と一緒に胡麻油で炒めて食べると美味しいそうだ。
(豆腐の葛あんかけ)
”昨日の夕暮れであったが・・・。浅草の外れの塩入土手下にあるわが家に帰ってきた彦次郎は、土間に押し込まれている結び文を拾い上げた。「手すきのときに、顔をみせてください たま屋」としたためてある。・・・
朝のうちに買っておいた豆腐を土鍋に入れて煮ながら、彦次郎は別の小さな鉄鍋で葛餡をこしらえた。行灯に火をいれてから、酒をあたため、豆腐に熱い葛餡をかけまわした一鉢と大根の切漬けだけで、彦次郎は五合ほど呑んだ。”
~「梅安流れ星」から
彦次郎は豆腐に葛餡をかけて食べる。「豆腐をやや大型に切り、たっぷりと水を加えて食塩ひとつまみを入れ、煮加減をすくい揚げて 湯を切り、深い器に取った上から煮立てた葛餡をどろりとかけて、おろし生姜・さらし葱・もみ海苔だどを添える。葛餡は煮出し汁に醤油・味醂などでややこっくりと味をつけ、煮立たせたところへ水溶きした葛を適宜加えて煮る。」(本山萩舟 『飲食辞典』
彦次郎はよほど豆腐が好きなのである。湯豆腐、冷奴に次ぐ食べ方と思っている。
(根深汁つき大根浅漬)
”梅安は、もう夕餉の支度をととのえてあった。濃い目に仕立てた根深汁に、生卵と梅干し、大根の浅漬だけのものだが、その熱い根深汁を一口すすりこんだ彦次郎と小杉十五郎が、「おや・・・?」「これは妙だ」と、顔を見合わせた。「うまいかねね?」と梅安。「うまい。こんな根深汁ははじめてだが・・・」いいさした彦次郎が椀の中をじっと見て、「ははあ・・・」「わかったか?」「胡麻の油を少し、落としなすったね?}「うむ。ほんの少し」
~「梅安針供養」の中「地蔵堂の闇」から
池波正太郎は実に葱が好きなのである。『味と映画の歳時記』の十二月の一節から。
”ところで、葱も旨くなる。大根と同様に、葱の応用も多種多用だが、鶏の皮を少々いれた葱の味噌汁や吸い物は、このひと椀で酒も飯もすませてしまうことができるほど、私の好物なのだ。品質のよい葱の、太い白根のところをぶつ切りにし、胡麻油を塗ってコンロの網で焙り、柚味噌や塩食べるのもよい。”
この鶏の皮というのが、今日手に入るのだろうか? 少し前は、「パントリーというすぐ近くの食料品スーパーで売っていたのだが・・・。これを小さなフライパンで、カリカリ成るまで焼いて、塩を振ると、ウイスキーの最高のつまみになるのだが・・。
(大根と油揚げの鍋仕立て)
”それから尚、二日を「井筒」に泊まり、日中はどこかへ出歩いていた藤枝梅安は、いったん雉子の宮の我が家へ帰った。夕暮れから降りはじめた雪はやむことなく、翌朝、梅安が目覚めてみると、すでに厚く積もっていた。百姓の女が帰ってしまった昼過ぎになってから、梅安はようやく起き出した。居間に切ってある囲炉裏へ、うすく出汁を張った鉄鍋を掛け、中へ輪切り大根と油揚げを細く切ったものをいれ、これがぐつぐつ煮えだすのを小皿にとって、さもうまそうに食べつつ、梅安は酒をのみはじめた。”
~「おんなごろし」から
大根の葉もいいものだ。強火でさっと炒め、醤油と唐辛子で味付けしたのを、飯のおかずにしたり、酒の肴にする。いい大根があり、新しい酒粕があり、寒鰤があったら、ぶり大根がいい。ブリは出刃包丁でぶつ切りにし、水洗いする。大根は厚い輪切りにし、皮は厚くむき、たっぷりの米の研ぎ汁で茹で、柔らかくなったら、一度水洗いして出汁の中へブリと共に入れる。三時間程とろ火で煮るとブリの骨まで柔らかく成るから、そこで酒粕と塩少々を加え、さらに一時間ほど煮る。煮上がる少し前に、四つ切にした椎茸をいれ、味がしみるまで煮て、仕上げにそいだ柚子を散らす。
余談になるが、大根の葉っぱについて辰巳浜子が、『料理歳時記』の中で、次のように書いている。
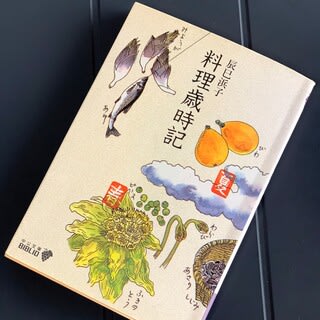
”大根の葉の栄養価の高いことは白い部分の幾倍と聞いては、とてものことに捨てることはできません。青い葉の部分をしごいて、さっと湯通しして、細かく刻んで塩味をして菜めしにしましょう。茎は糠味噌に入れたり、刻んで大のしっぽや皮を混ぜて大阪漬けにします。青い葉を温度の低い油で真青にからりと揚げて箸で細くつぶし、大根おろしに混ぜ合わせ、二杯酢または三杯酢で和えます。酢はゆず、レモン、すだちなどを使えば理想的な栄養食なります。葉も茎もともに細くきざみ、胡麻油で炒め、砂糖・醤油でやや濃い目に味付けをしてから、からからに煎りつけ、七味唐辛子をふりかけると、温かいご飯にうってつけで、まことに食欲をそそります”
(大根鍋)
”とっぷりと暮れてから、梅安を彦次郎は、居間の長火鉢へ土鍋をかけ、これに出汁を張った。ざるに、大根を千六本に刻んだのを山盛りにし、別のざるには浅蜊の剥き身が入っている。
鍋の出汁が煮えてくると、梅安は大根の千六本を手づかみでいれ、浅蜊もいれた。刻んだ大根は、すぐさま煮えあがる。それを浅蜊とともに引き上げて小皿にとり、七色唐がらしを振って、二人とも、汁と一緒にふうふうう言いながら口に運んだ。「うめえね、梅安さん」「冬がくると、こいつ、いいものだよ」酒は茶碗でのむ。・・・「彦さん・・・」「え・・・?」箸をとめて藤枝梅安は 「とうとう白いものが落ちてきたようだね」といった。”
~「梅安晦日蕎麦」から
(浅蜊と大根ー小鍋立て)
”その夜。梅安は、ひとり遅い夕餉の膳に向かっていた。春の足音は、いったん遠のいたらしい。毎日の底冷えがきつく、ことに今夜は、雪になるのでははいかと思われた。
梅安は、鍋へうす味の出汁を張ってコンロにかけ、これを膳のかたわらへ運んだ。大皿へ、大根を千六本に刻んだものが山盛りになってい、浅蜊の剥き身もたっぷりと用意してある。出汁が煮立った鍋の中へ、梅安は手づかみで大根をいれ、浅蜊をいれた。千切りの大根はすぐ煮える。煮えるそばから、これを小鉢に取り、粉山椒をふりかけ、出汁とともにふうふう言いながら食べるのである。このとき、酒は冷のまま。
~「梅安最合傘」から
(鯛)
”梅安は、積もった雪の中を、あちこちと治療に出歩き、夕暮れになってから帰ってきた。雪は、昼過ぎにやんでいる。・・・梅安は、堀本桃庵が届けてくれた鯛をさばきにかかった。まず、刺し身にし、残る片身は塩焼きにしておいた。鯛の刺身で、たっぷり酒をのんだ梅安は、濃い目にいれた煎茶へぱらりと塩をふって吸い物がわりにし、残った飯を四杯も食べた。”
~「闇の大川橋」から
鯛ぐらいありがたい魚は他にはない。頭からしっぽの先まで、捨てるところが一つもない。頭はかぶと焼き、かぶと汁、潮汁。もちろんチリ鍋にも使える。頬の肉に食らいつく時の幸福感は魚好きなら説明無用だろう。目玉(目のまわりの肉)となると、もう喧嘩腰で早いもの勝ちということになる。
刺し身は皮を引かずにさっと熱湯をかける「鹿の子づくり」が洒落ている。皮を引いて平づくりにした時も、皮を捨てるなどとんでもないことで、これは極上に箸洗いにもなるし、和え物にも得難き材料である。肝や子は炊合せがよく、中骨その他はアラ煮とし、文字通り骨までしゃぶり尽くさねばならぬ。身を取った残りの中骨は白焼きにするという手もある。白焼きにしてから、さらにくっついている細い身を丹念にこそげ落とし、これをそのままおろし和えにしたり、酢の物にしたり、また味噌と煮込んで鯛味噌にせよ・・・と懐石名人の辻嘉一が教えている。
大鯛が無理でも小鯛というものがある。若狭名物の小鯛の笹漬けは、昔は京都四条富小路の「わかさや」で売っていたが、今はなくなった。もちろん、若狭から取り寄せることができる。酒のあてになるし、炙って飯のおかずにもなる。
「小柱のかき揚げ」についていうと、これが結構むずかしい。小柱の水気をしかかりとることと、揚げる油の温度管理。東京は築地にある懐石料理の名店「つきじ田村」の料理長、田村隆のいうところを紹介しておく。
”①ホタテ小柱は布巾などで水気をしっかり取る。三つ葉を2センチ程度の長さに刻む。
②ボウルに小柱と三つ葉を入れ、薄力粉少々を加えて和える。全体にまんべんなくかぶさるくらいの量の基本の衣を加え、箸でさっくり混ぜる
③揚げ油を160~170度に熱し、網杓子の上にのせて油の中に静かに入れる。4等分が目安。あれば、紅葉の葉を衣と一緒に揚げる。
④衣がほとんどキツネ色になったら、取り出して油をとる。
⑤器に紙をしき、その上に盛る。
三代目の田村隆さんは、この一月に逝去された。まだ63歳という働きざかりの時に。合掌。
~~~~~~~~~~~~~
まだまだあるが、この辺りで、いったんしめることにする。お読みいただいたように、まことに素朴な手料理である。戦後のひもじい時期に生きてきた私にとっては、これで十分である。これより手のこんだ料理となると、料理屋へ行くことになる。本格的な料理を味わいたい時は、京都は高倉御池上がるの「押小路 岡田」に行く。ここは、二年ほど前に開いた本格懐石料理を出す。味は一流、値段は十分手の届く範囲にある。気に入った店なので愛用している。もう少し気張れば、堺町通り下がるの<室町和久傳>に足を運ぶ。
しかしふだん使いということになると、<和食 晴ル>(高倉通綾小路角)に足を運ぶ。ここはちょっと市中の賑やかなエリアからは離れているが、安くて旨い。時には、いい意味で期待を裏切るような料理が出てくる。すこし、そのメニューをみてみよう。
おでんには、大根、赤こんにゃく、浅蜊真丈、ふきのとう真丈など。前菜では、雲子ポン酢、あん肝酒蒸し、和牛すじ煮込み、生麩バターソテー。炭焼は、甘鯛、のど黒、鴨ハンバーグ。揚げ物は、白アスパラフライ、カキフライ、鴨メンチカツ、甘鯛うろこ揚げ。酒肴としては、自家製カラスミ、自家製鴨生ハム、タラコ粕漬け。 ご飯物は、鯖寿司、づけ丼、白魚の玉しめ丼。
さらに黒板には、旬のメニューが書かれている。明石産鯛、北海道毛ガニ、宮津産サヨリ、牡蠣の太白油漬け、牛肉クレソンすき焼き、本鮪と辛味大根、長崎産アオリイカ、ホタルイカ天ぷら、菜の花辛子和え、河豚の唐揚げ、春キャベツのおひたし。などなど、。どれも呑み助にはたまらない。
そして呑助のためにに、いい日本酒を置いてある。純米澤屋まつもと、特純禮泉、純吟黒龍、純米大吟醸尾瀬の雪どけ、などなど。もちろん、芋や麦の焼酎もある。
どうしてこんなに様々なメニューが提供できるのか? 素人目には、不思議に思う。一日、二日くらいしか鮮度が持たないものも少なくない。毎日の積み重ねで、おおよその需要の見当がつくのかも知れない。
ここと似たような店が京都駅近くにある<燕(えん)>という店である。予約を取るのは至難の業だ。メニューにも、共通するようなものがあるが、一方で一捻りしたものが少なくない。一例を上げれば、グアンチャーレ西京焼き(豚トロを塩漬けにして熟成させたイタリアの食材)。グアンチャーレを蕗の薹入りバターで焼いたもの)、アボカドの梅肉おろし。焼きたての鮎の塩焼きもうまい。ここは、しょっちゅう通っている。
この両店は、和久傳の流れを汲むものである。ほかにも和久傳で修行した若い人たちが京都で競い合っているようだ。

この「晴ル」から歩いてさほど遠くないところにバー「ロッキングチェア」がある。御幸町通り、仏光寺下がる。京都にはバーの名店がいろいろあるが、ここほど気軽で洒落たバーはあまり知らない。ご婦人連れで行かれれば、きっと連れのお気に召すこと請け合いである。
(日頃、気に入って料理をしているレシピ)
「レタスのオイスターソース炒め」・・・さる中華料理の店で食べていらい、やみつきになってしまった。ところが、この店が閉店になってしまった。
それでは自分でつくるしかないと、試している。
①レタス(ひと玉)を、ややおおめに手でちぎる。これに塩とオリーブオイル少々を薄くまんべんなく振りかける。
②レンジ用容器に、これをいれて電子レンジで2分30秒加熱する。加熱後取り出すと半ゆで状態になるが、レタスのシャキシャキ感は残っている。これを、ひっくり返して皿にもる。
③耐熱容器に、中華スープ(ガラスープ)の素小さじ1、オイスターソース大さじ1、紹興酒小さじ1、胡麻油こさじ1、(チューブの)にんにく1センチ。これらを水40CCに入れてよくかき混ぜ、電子レンジで50秒ほど加
熱する。これをレタスにかける。
これは、まだ研究中である。オイスターソースを元町中華街の専門店で、あれこれ買ってきて、さらに美味しいものに仕上げたいと思っている。なおこれは、どちらかといえば副菜である。しかるべき主菜との組み合わせが肝要であろう。
豚の薄切りロースを、醤油でさっと煮絡めたものと組み合わせるといいかも知れない。
「蕗味噌」
”春の寒さたとえば蕗の苦味かな” (夏目成美)
この季節になると、様々な山菜が出てきます。その中でも蕗の薹は独特の香りや苦味があって魅力的な一品になります。茹でた蕗の薹を摺って白味噌や赤味噌と混ぜ、砂糖と味醂を加えると酒の肴にもなります。これを、おにぎりにのせ
て焼きおにぎりにすると、まさに春に先駆ける逸品になる。
「材料」
ふきのとう …… 7~8個
味噌・みりん・砂糖……各大さじ3(お好みで加減してください)
胡麻油)…… 適量
「つくりかた」蕗の薹を半分に切り、水にさらしてアクを抜く。水気をとって細かく刻み、油で炒める。味噌・砂糖・みりんを入れ、弱火で練り混ぜながら煮詰める。
酒の肴として、そのまま味わってもいいが、焼きおにぎりにすると軽い食事にもなる。おにぎりに蕗味噌をのせて、トースターで焼き目がつくくらい焼く。
(最後に)今回、このエッセイを書くにあたって、池波正太郎の『仕掛け人・藤枝梅安』の他に『料理歳時記』(辰巳浜子)や、『池波正太郎・鬼平料理帳』(編、佐藤隆介)、さらに佐藤隆介さんの著作『日本口福紀行 がんこの卓上』などなどを参考にさせていただいた。その中で、異色のライターが書いた『システム料理学』(丸元叔生)は、なかなか興味深いものがある。丸元さんは、東京大学仏文科を卒業し、編集の道から作家になった。ところが、何を思ったのか、最新の栄養学にもとづく料理の研究の道に入り、数々の著作をものにしている。『丸本淑生のクックブック』(文春文庫)や
『今、家庭料理を取り戻すには』(中公文庫)などがある。
『システム料理学』では、和食の出汁のもとになる鰹節についての一文がある。興味深いので引用させていただく。
”かつお節と昆布は料理の基礎であり、ほとんどの料理は、これなしにはつくれない。そのかつお節の上等なものは、現在築地の場外市場で1キロ三千円前後、極上品は三千七、八百円で買える。一キロでだいたい三本と思ったらよい。いずれにしろキロ三千円以上のものを買っていれば問題はない。一キロ買っておくと二ヶ月はもつから、月にして千五百円の消費である。それで、味噌汁も、煮物もサラダも、すべてこの上なく美味しいいものとなることを思えば極めて安いものだ。しかし、二千五百円のものを買ってくるとそうはいかない。すべての味が駄目になるからだ。呆れ果てて捨てることになり、そうなればお金をドブに捨てたことにほかならない。
なお、かつお節の表面には薄くカビが生えている。カビによって、変質するのを防ぐ工夫なのだ。このカビは削る際、湿らせた布巾で拭くときれいに落ちる。また、そうやって若干の湿気を与えることで削りやすくる。ところが、京都の錦市場のカツオ節屋を見て驚いた。どれにもカビがない。聞けば、最近の人はカビの生えたものは買わないとのこと。一本のかつお節に、民族の文化が凝縮されている。”
ちなみに、この本の出版されたのは1980年代の初めである。現在は、どうか? 調べてみると鹿児島は枕崎のカツオ本節、5本セットで、およそ5800円。重さが、やく1.1キロだから、それほど変わっていない。これを使って、本格的な出汁をとってみたい。
~~~~~~~~~~~~~
みなさま如何でしたか? ”よし、俺も厨房にたって、うまいものを作ってみよう”と思われましたでしょうか? ”いや、前からやってるよ!”、とおっしゃる諸兄姉は、ぜひ得意のレシピをご紹介ください。お待ちしています。
























紹介されたレシピの食材はありふれたものですが、美味しく食べるには、根気のある技量と酒と友人を含めた舞台装置がほしいような気がすします。コロナの早かな収束を祈るばかりである。
なお、レタスのオイスターソースいためのレシピですが、私は野菜のフライパン炒めにマヨーネーズを油代わりに使います。マヨネーズはサラダ油と卵からできていますが、これで野菜を炒めます。塩を足すかどうかはお好み次第。ハーフマヨネーズより普通のマヨネーズの方をお勧めします。レンジでレタスを程よく蒸すのは難しいです。マヨネーズで炒めながら、使う箸の感触と目視でレタスの歯ごたえの絶妙な頃合いを見図ります。
気のむくままに書き散らしたようなエッセイをお読みいただきありがとうございました。 ”紹介されたレシピは、以外と料理仕上げるのは難しい”とのご指摘ですが、そうかも知れませんね。昨今のレシピで、調味料の量を大さじ1,小さじ1などと細く書かれていますが、それは食材次第。適当にトライアル&エラーでやるほうが、いいかなと思います。
また、よき食材を手に入れるのは、スーパー全盛の今日、返ってむずかしいように思います。通販のほうが、いいものが手に入るのではないでしょうか。問題は、量が多いことです。
レタスのオイスターソース炒めにマヨネーズをつかうというアイデアはいいですね。早速試してみます。
緊急事態宣言が終了したら、「例の会」で集まって料理談義に花を咲かせたいものです。
ただただ空腹を満たし、栄養価を確かめるぐらいのわが身からすれば、ゆらぎ様の世界は、粋と気風に満ちた世界を見る思いです。
小生の厨房との係わりは、普段のカレー作りと年末のごまめと黒豆つくりぐらいです。家内は、この3点は手を出しません。小生の任務となっています。
またまた得意の分野の池波他の一流料理研究家、藤枝梅安に語らせるところが憎いですね。
いずれも興味が湧きますが、わが台所で直ぐと言うわけにいきません。
コロナ下で振出しに戻って、NHKの料理番組を毎日見、テキストを買ってきて二人でやってます。
最近よかったのは、
① 大根を一口大の乱切り、豚肉を塩コショウ。いオイスタソースで味付ける。
鍋にゴマ油、しょうが、にんにく、唐辛子を刻み熱して大根豚肉を炒める。火が通ったらだし汁(鶏ガラ)を入れ、煮込む。味付けは砂糖、しょうゆ、酢
カタクリでとろみで完成。
NHKのオリジンからアレンジした。
②人参、大根細切り、ゴマアブラでいため、だし汁で少し煮る。砂糖、しょうゆ、酢で味付ける。とろみをつける。
これを、湯豆腐、厚揚げ、鱈、とり団子などを単独に、別にゆでて準備し、とろみの人参・大根をかける。
最近甘酢が口当たりがよい。
全てお遊びです。
「美味しい話」というタイトルのコメントを頂きましたが、お名前がありませんでした。が、葉有露様のものと推測されますので、ここにコメントバックさせていただきます。 拙文をお読みいただきありがとうございました。
”普段のカレー作りと年末のごまめに黒豆づくり”、とありますが、小生はどちらも取り組んでおりません。一手、ご指南をいただきたいところです。
お仲がよろしいようで、恐れ入ります。(笑)
駄文をお読みいただきありがとうございました。NHKNの「料理教室」をご覧になり、お二人で料理をしておられるとのこと。うーん、参りました!
「大根をオイスターソースで味付けし、豚肉と一緒に炒める」というのは美味しそうですね。一度、ためしてみます。ご教示ありがとうございました。