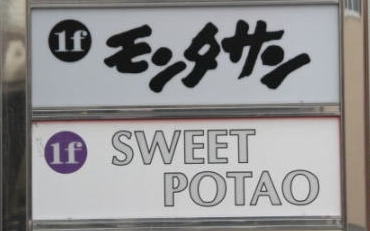写真は先日撮ったものと、以前冬場に撮ったものとがあるので比較して観てもらいたい。
御所ヶ谷神籠石(ごしょがたにこうごいし)は、福岡県行橋市の南西部のホトギ山
(御所ヶ岳、標高246.9メートル)山頂から山麓一帯にかけ外周3キロメートルに亘って
花崗岩の切り石と土塁をめぐらせた古代の山城跡で、国の史跡となっている。
調査・研究史
御所ヶ谷山中の石塁や礎石群の存在は江戸時代から知られており、
元禄7年 ( 1694年 ) の貝原益軒の 『 豊国紀行 』 にも記されている。
その後、伊藤常足 『 太宰管内史 』 、西田直養 『 柳村雑記 』 、 『 筱舎漫筆 』、
高田右近 『 豊前国史 』 、渡辺重春 『 豊前史 』 らが、この遺跡について言及している。
その多くは、この遺跡を 『 日本書紀 』 に見える景行天皇の長峡県の行宮と考えていたが、
だが、伊藤常足だけはこれに否定的であった。
この遺跡を神籠石遺跡の一つとして認識し、学界に紹介したのは伊東尾四郎である。
明治43年 ( 1910年 ) 1月には、喜田貞吉、伊東尾四郎、宮崎栄雅が御所ヶ谷神籠石を踏査し、
新たに門や列石を確認している。
その後、昭和初期に文化財指定申請のため実測調査が行われた。
平成2年に行橋市において御所ヶ谷神籠石周辺地域の史跡自然公園化構想が浮上したが、
御所ヶ谷神籠石はそれまで発掘調査が全く手付かずで遺跡の範囲も不明確な状況であった。
そこで史跡の実態を把握する目的で平成5年から同市教育委員会によって発掘調査が行われた。
概要
景行天皇が熊襲征伐の際に、この地に立ち寄ったと伝えられ、景行神社が鎮座している。
古代に築造された山城で、「日本書紀」「続日本紀」に記載がなく、
遺構でしか存在の確認できないものを神籠石(こうごいし)、
または神籠石式山城(-しきやましろ)と呼ぶ。
古代山城(朝鮮式山城)とされることもあるが、築造主体など建設の経緯は一切不明である。
そのため、多くの研究がなされており、様々な学説がある。
門跡七ヶ所(東門・中門・西門・第二の西門・東北門・南門・南西門)、
列石十ヶ所、梁行三間×桁行四間の総柱礎石郡などが確認されており、
神籠石の中でも、規模と保存状態が良い。
門跡の中でも中門の規模は特に大きく、水門は高さ7.5メートル、長さ18メートルの二段の石塁である。
石材は全て花崗岩である。
山頂部を底辺北側の谷を頂点とする三角状の範囲
(東西[底辺]900メートル、南北[高さ]600メートル、比高差170メートル)が列石と土塁によって囲まれ、
その推定外周は約3キロメートルにもおよぶ。なお一部列石が二重になっている。
所在地:福岡県行橋市大字津積および京都郡みやこ町勝山大久保・犀川木山地区に跨る。
アクセス
行橋市中心部から車で約15分の位置にあり、
福岡県道58号椎田勝山線の津積交差点より南約1キロメートル。
みやこ町側からのアクセスはできない。