防災カレンダー
16日。新月週間。
16日。新月週間。
18歳の小銃により2名の方がお亡くなりになりました。心からの御冥福と、負傷された1名の方の御見舞を申し上げます。
この事件もまたこれから日本が迎える時代の一つの警告であるように思いました。
100人のうち99人は穏やかで優しい方々となる反面、1人は普通の人の100倍キレやすい。そういう社会。
陰と陽のバランス。振り子の揺れ戻し。
社会全体が優しくなることの反動。
このバランスについての考察はいろいろ書きたいこともありますが、とりあえずはまず私たちの身近な社会のこととして。
99人が優しい穏やかな人であっても。100人に1人は100倍キレやすい。
これから、運が悪ければそういう人に遭遇する危険性がある。
運転をしている時でも、人混みで買い物している時でも、駅のホームや電車の中でも、そして仕事先の人間関係でも。
あれ。この人ちょっと空気感???と思った場合は、静かに距離を置いてみることは大切になっていくかも。
昭和時代のオジサンオバサンのお節介ノリが伝わらない人は、100人に1人はいるかも。
私たちの社会。100人中99人はいい人です。
でも残りの1人は。迂闊に近寄って地雷を踏んじゃダメ。逆恨みから新聞沙汰になる事件はこれから増えていく小説があるかもしれません。
ケーキを切れない子供。
昭和時代のように清濁混合の社会の空気の時代から、誰もが優しく物分りが良い社会の空気に変化していくと、数少ない一部の人に残りの闇が集中します。
その方もお気の毒な方です。
ケーキを切れない子供たちは本当に可哀想です。
心の嗅覚。
でもそれと同時に。
私たちは嗅覚を効かせる必要がありそうです。
不必要に恐れる必要はありませんが、頭の片隅に。そういうことが自分の身の回りでも起きるかも。という意識さえあれば。大丈夫。
念のため。
本日の100人に1人のお話は、まだ「現在の日本社会」のことではありません。ただしこの先日本社会に起きる変化の一つとなり得る。そんな可能性の考察です。

『ケーキの切れない非行少年たち』
https://president.jp/articles/-/59176?page=1
おまけ(読者の方によって教えて頂いたこと)
==========
ただそういう技術的な面だけじゃなくて、ヒット曲というのはさまざまなタイミングがピタリとハマったときに生まれるものだし、なにより楽曲そのものに、人を惹きつける理屈ではない「なにか」あってこそのもの、だと思っています。この「なにか」というものは、意図的に作り出せるものではないらしい。
→ 神様から与えられたタイミング。光のスポットですね。
==========
ワクチンの後遺症対策を教えて頂ければ幸いです。
まだ、自覚する後遺症は無いように感じていますが。
3回接種しました。
→ 津波の復興と似ているように思います。数年という期間をかけて自分の身体の生命力で本来の機構に戻していくこと。
自分の身体本来の生命力のために有効なのは
・腸内細菌。
・自分のペースでの運動。
・周囲のために出来ること。
というのが私の仮説です。
==========
親は音大出、高校までピアノを習っていたアニメは好きからのオープニングの印象です。
出だしの「進撃の巨人風」は劇的な幕開けでワクワク。むしろ進撃のほうがショックが大きかった。
転調は数学的調和から発達したドイツ系音楽にはない転調だが、最近の日本の歌にはボチボチ出てきているので驚きはなかったが、こんな最先端な曲を歌ったり演奏するのはちょっとテクがいる、攻めがいのある挑発感のある好印象というのがアニメのテーマ。
リズムの変調はベートーベン後のロマン派以降、凝った大曲にはあること。
だがそれらの曲は弾き手・指揮に合わせてもっとゆとりをもって情緒的に演奏するので、こんなにインテンポではお目にかかれない。
特に後半、早くするのは簡単だが(興奮すると早く演奏できる)、ゆっくりするのは一息ついてからでないと難しいし、たぶん弦楽器なら音(ピッチ)が微妙に下がるのでは?
なので初めて全曲聞いたとき、ゆったりの部分のピッチが下がらず、気持ち悪かった。
アニメのテーマソングは1分30秒に起承(転)結が盛り込まれるから、曲想の変化が激しく、すぐにサビがくる。これは日曜のNHKのど自慢でサビまで行きつくのが難しいことからでもわかると思う。
しかし編集されていない原曲が想像以上に激しい変化をするのは、漫画からのインスピレーションを見事に体現したと思う。
まるぞうさんのように先行映画の1時間半ある1話目の1/3いかずにドロップアウト寸前でした。
でもきちんと見ないで世間・特に若者も原作好きもなぜゾッコンなのかが知りたくて、我慢して1話目終わりまで見て、ストーリーに衝撃を受けました。
→ 感想ありがとうございます。
これからの時代、ますます世界の人の約半分は日本に理由なく惹かれる時代になると思います。これから100あるそういう現象の象徴的な1つだと思います。
==========
今の時代は生きながら、自分の因果と向き合う時代が来たのだとおもいます。怖い気持ちもありますが、死後に向き合うより、生きている時に良心と向き合い反省できるのだから、有難いです。くくりなおしです。
→ 本当に。もの凄い勢いで社会の変化が進んでいると思います。この中で暮らしていると変化は感じにくいですが。
コメントありがとうございます。
==========
まるぞうさん、仰る通り?です。
お能のあと、京都御苑に寄った時、回りのほとんどの御方が外国の人でしたが、更にそのほとんどの方々は西洋人(白人)さんでございました。
まるぞうさんの近未来小説、、
未来でのドキュメントかもです。
→ 日本は責任が大きいです。ミジンコではありますが心の中では密かに身が引き締まる思いです。
===========
おっしゃる通り、都市部災害のやっかいな点は群衆とその心理であります。加えて想定しずらい点も出てきます(豪雨や台風前のスーパーすっからかん想定は容易なんですが)。
もし自分が100年前、関東大震災に遭っていたらどうだったろう、流向こう側に行こうと橋を渡っただろうか、などと浅草界隈を歩きながら思ったり。流言飛語に惑わされなかっただろうか。。。
その時その時の群集心理にはある程度影響される面があるかもしれません。いわば自分も群衆の一員でもあり。逆に群衆に助けられることもあるかもしれない。ただ、完全に巻かれるようなことにはならないよう、いざという時の自分の瞬発力を信じられるよう、その元の羅針盤のメンテナンスはしていこうと思って日常を歩んでいるつもりの自分が55%くらい、ぽやーっと過ごす部分が30%くらい、「絶対あの位置ヤバいよ、EEZ内? 近すぎる」が10%、「いや騒いでどうする、注視するしかない」が5%、の、今日この頃です。
→ 静かに観ていこうと思います。コメントありがとうございます。
==========
==========
ただそういう技術的な面だけじゃなくて、ヒット曲というのはさまざまなタイミングがピタリとハマったときに生まれるものだし、なにより楽曲そのものに、人を惹きつける理屈ではない「なにか」あってこそのもの、だと思っています。この「なにか」というものは、意図的に作り出せるものではないらしい。
→ 神様から与えられたタイミング。光のスポットですね。
==========
ワクチンの後遺症対策を教えて頂ければ幸いです。
まだ、自覚する後遺症は無いように感じていますが。
3回接種しました。
→ 津波の復興と似ているように思います。数年という期間をかけて自分の身体の生命力で本来の機構に戻していくこと。
自分の身体本来の生命力のために有効なのは
・腸内細菌。
・自分のペースでの運動。
・周囲のために出来ること。
というのが私の仮説です。
==========
親は音大出、高校までピアノを習っていたアニメは好きからのオープニングの印象です。
出だしの「進撃の巨人風」は劇的な幕開けでワクワク。むしろ進撃のほうがショックが大きかった。
転調は数学的調和から発達したドイツ系音楽にはない転調だが、最近の日本の歌にはボチボチ出てきているので驚きはなかったが、こんな最先端な曲を歌ったり演奏するのはちょっとテクがいる、攻めがいのある挑発感のある好印象というのがアニメのテーマ。
リズムの変調はベートーベン後のロマン派以降、凝った大曲にはあること。
だがそれらの曲は弾き手・指揮に合わせてもっとゆとりをもって情緒的に演奏するので、こんなにインテンポではお目にかかれない。
特に後半、早くするのは簡単だが(興奮すると早く演奏できる)、ゆっくりするのは一息ついてからでないと難しいし、たぶん弦楽器なら音(ピッチ)が微妙に下がるのでは?
なので初めて全曲聞いたとき、ゆったりの部分のピッチが下がらず、気持ち悪かった。
アニメのテーマソングは1分30秒に起承(転)結が盛り込まれるから、曲想の変化が激しく、すぐにサビがくる。これは日曜のNHKのど自慢でサビまで行きつくのが難しいことからでもわかると思う。
しかし編集されていない原曲が想像以上に激しい変化をするのは、漫画からのインスピレーションを見事に体現したと思う。
まるぞうさんのように先行映画の1時間半ある1話目の1/3いかずにドロップアウト寸前でした。
でもきちんと見ないで世間・特に若者も原作好きもなぜゾッコンなのかが知りたくて、我慢して1話目終わりまで見て、ストーリーに衝撃を受けました。
→ 感想ありがとうございます。
これからの時代、ますます世界の人の約半分は日本に理由なく惹かれる時代になると思います。これから100あるそういう現象の象徴的な1つだと思います。
==========
今の時代は生きながら、自分の因果と向き合う時代が来たのだとおもいます。怖い気持ちもありますが、死後に向き合うより、生きている時に良心と向き合い反省できるのだから、有難いです。くくりなおしです。
→ 本当に。もの凄い勢いで社会の変化が進んでいると思います。この中で暮らしていると変化は感じにくいですが。
コメントありがとうございます。
==========
まるぞうさん、仰る通り?です。
お能のあと、京都御苑に寄った時、回りのほとんどの御方が外国の人でしたが、更にそのほとんどの方々は西洋人(白人)さんでございました。
まるぞうさんの近未来小説、、
未来でのドキュメントかもです。
→ 日本は責任が大きいです。ミジンコではありますが心の中では密かに身が引き締まる思いです。
===========
おっしゃる通り、都市部災害のやっかいな点は群衆とその心理であります。加えて想定しずらい点も出てきます(豪雨や台風前のスーパーすっからかん想定は容易なんですが)。
もし自分が100年前、関東大震災に遭っていたらどうだったろう、流向こう側に行こうと橋を渡っただろうか、などと浅草界隈を歩きながら思ったり。流言飛語に惑わされなかっただろうか。。。
その時その時の群集心理にはある程度影響される面があるかもしれません。いわば自分も群衆の一員でもあり。逆に群衆に助けられることもあるかもしれない。ただ、完全に巻かれるようなことにはならないよう、いざという時の自分の瞬発力を信じられるよう、その元の羅針盤のメンテナンスはしていこうと思って日常を歩んでいるつもりの自分が55%くらい、ぽやーっと過ごす部分が30%くらい、「絶対あの位置ヤバいよ、EEZ内? 近すぎる」が10%、「いや騒いでどうする、注視するしかない」が5%、の、今日この頃です。
→ 静かに観ていこうと思います。コメントありがとうございます。
==========
まる(=・3・=)ぞうのネタ帳。
今後記事にするかもしれないししないかもしれない。気になる情報は、とりあえずここに放り込んであります。
https://twitter.com/J5F6eZXx6YgJP2x
防災意識カレンダー。
Twitterで要注意日の朝6時ごろ配信しております。
https://twitter.com/ohisama_maruzo
本ブログに共感される方はクリックのほどよろしくお願いいたします。
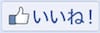
にほんブログ村ランキング
■ブックマーク
備忘録検索(β版)
ゆっくり解説(Youtube)
ゆっくりまるぞう動画(YouTube)
■防災意識リマインダー
防災に注意が必要な期間は、メールやTwitterで防災意識リマインダーを受け取ることができます。詳しくはこちら
■地震雲写真投稿方法
地震雲(飛行機雲のように短時間で消えない立ち上がる雲)を目撃された方は、雲の御写真と目撃情報を下記のメールアドレスにお送り頂ければ幸いです。
ohisama.maruzo@gmail.com
御写真とともに送って頂きたい情報
・目撃された日時(何日何時頃など)
・目撃された場所(県名や地名など)
・目撃された方向(可能なら)
地震雲かわからない方は地震雲の見分け方をご参考になさってください。
(個人情報は厳重に管理し、私以外の第三者に投稿者のメールアドレスなどの個人情報を開示することはありません。また御写真の画像情報や機種情報は消去いたします。人物が特定できる映り込みなどのぼかし加工もこちらで対応いたします。なおお送り頂いた御写真と目撃情報は関連サイトにも掲載させて頂くことがあります。)
■非掲載希望のコメントについて
1.公開を希望しないコメントは投稿しないでください。基本的に投稿されたものは他の読者の方の目にもふれるとお考えください。
2,どうしても公開されたくないメッセージを送りたい方はメールでお願いします。
ohisama.maruzo@gmail.com
3,ただしメールでお送り頂いた内容に対し、私はメールで返信をお送りすることは一切ありません。一方通行となります。
4,上記のようにコメントは原則公開ですが、炎上つながる場合や個人情報が含まれている場合、読者間での私信コメントは、私の判断で非公開とする場合があります。
■引用転載について
本ブログは引用元をあきらかにしていただければ、ブログやSNSでの拡散は許可いたします。









