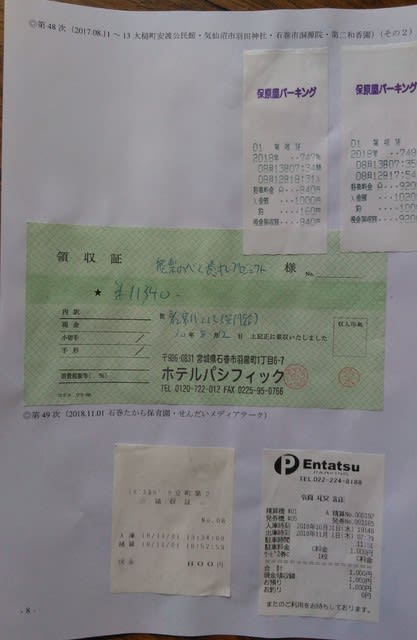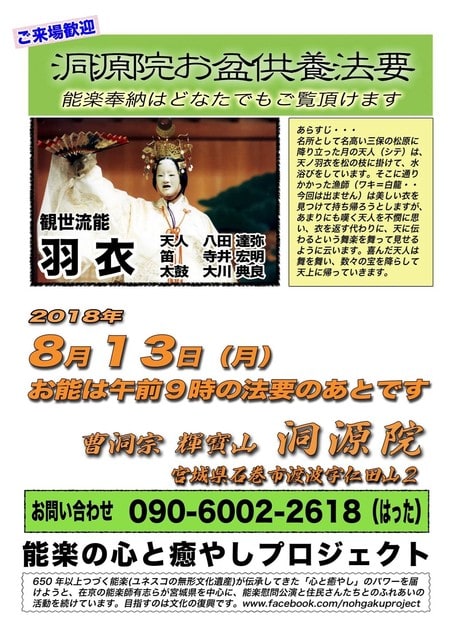住民ボランティアの明友館の千葉さんのご紹介を得て ぬえはその日、湊小学校避難所でお手伝いさせて頂くことになりました。初めて避難所というところに伺うのでドキドキしましたが。。
湊小学校は石巻市の市立小学校で、いわゆる「公設」の避難所です。到着してみると校庭はどろどろにぬかるんでいました。ぬえが伺った頃にはすでに片付けられていましたが、後日 学校のプールに自動車が突っ込んでいる写真を見ることがありました。この避難所も津波の被害を受けていたのです。
そして校庭には巨大な。。サーカス小屋か? と思わせるような大きなテントが威容を現していました。詳しくはあとで触れようと思いますが、これは仮設の浴場だったのです。それから校庭に陣取る何台もの自衛隊の車両。もちろん施設の規模も違うから一概には言えないとしても、「明友館」のような私設の避難所と公設の避難所との支援体制の違いは明らかでした。

もっとも、これも後になって段々と分かってきたことですが、規模が大きく行政の支援が(比較的)整っていた公設の避難所では、それがゆえに小回りの効かないこともあったようで、たとえば200人の避難者がいて199個の物資が届けられた場合、公平の観点から物資そのものが避難者に配布されない、というようなこともあったそうです。その点、逆に私設の避難所では住民ボランティアさんが中心になって自主的に避難所を運営されていたので、そりゃ交渉は大変だったかと思いますが、避難者のニーズを取りまとめて物資を調達することがフレキシブルに行われていた印象があります。聞いたところでは、上記のような理由で大きな避難所に届けられながら避難者に配ることができず、とうとうこっそりと廃棄されそうになった支援物資を、小さな避難所のボランティアさんが駆けつけて引き取ったり。。ということもあったそうな。綱渡りのような作業が日常だったのですね。。
さて湊小学校避難所に到着した ぬえは、千葉さんにご紹介頂いて、ここで避難所を運営するボランティア団体のひとつ「チーム神戸」を訪ねました。当時、公設の避難所でも市役所が直接避難所を運営するのは職員の人数からいっても無理で、市役所とは連絡役のような方が1人程度あるだけで、実質的には民間のボランティア団体が運営を担っていました。湊小学校避難所にも「チーム神戸」のほかに「ピースボート」など大小2~3の団体が入っていたと思います。
彼らは震災直後に被災地に入った人たちで、避難所に住み込んで常駐していました。あとで知ったことですが、ピースボートのような大きな組織では各地から集まったボランティアさんが2~3カ月の交代制でここに住み込み、いわゆる「泥掻き」といわれる瓦礫の片付けなどの重作業を大人数で行っていました。また「チーム神戸」のような小さな団体では、ぬえのように各地から何か被災地の手助けをしたい、と思って駆けつけた若者がスタッフとなっていったようです。
ぬえは「チーム神戸」が設置していた「ボランティア受付」に行き、千葉さんから紹介されたことを若いスタッフさんに恐る恐る伝えました。「明友館」に先に行ったこともあり、すでに「泥掻き部隊」は出動したあとで、そのうえ恥ずかしいことに ぬえは「体力的に泥掻きは無理かもしれません。。何かそれでもお役に立てることがありますか。。?」なんて言いましたね。
その、まだ20歳台の若者は ぬえを上から下までジロジロと見て「ああ。。そうですか。。」と、ちょっと困った様子でしたが、それでも「大丈夫ですよ。それではこの避難所の中の清掃をお願いします」と言ってくれました。
忘れもしない、その後も長くお世話になる「チーム神戸」の若手スタッフの無尽洋平くんとの出会いでした。彼もまた被災地の手助けがしたくて東京から石巻に行き「チーム神戸」の一員となったボランティアさんです。そのほかに同様に京都から来た水島緑ちゃん、そしてチームリーダーで震災直後に神戸から駆けつけた金田真須美さん。「チーム神戸」とはここから長いお付き合いが始まります。
湊小学校は石巻市の市立小学校で、いわゆる「公設」の避難所です。到着してみると校庭はどろどろにぬかるんでいました。ぬえが伺った頃にはすでに片付けられていましたが、後日 学校のプールに自動車が突っ込んでいる写真を見ることがありました。この避難所も津波の被害を受けていたのです。
そして校庭には巨大な。。サーカス小屋か? と思わせるような大きなテントが威容を現していました。詳しくはあとで触れようと思いますが、これは仮設の浴場だったのです。それから校庭に陣取る何台もの自衛隊の車両。もちろん施設の規模も違うから一概には言えないとしても、「明友館」のような私設の避難所と公設の避難所との支援体制の違いは明らかでした。

もっとも、これも後になって段々と分かってきたことですが、規模が大きく行政の支援が(比較的)整っていた公設の避難所では、それがゆえに小回りの効かないこともあったようで、たとえば200人の避難者がいて199個の物資が届けられた場合、公平の観点から物資そのものが避難者に配布されない、というようなこともあったそうです。その点、逆に私設の避難所では住民ボランティアさんが中心になって自主的に避難所を運営されていたので、そりゃ交渉は大変だったかと思いますが、避難者のニーズを取りまとめて物資を調達することがフレキシブルに行われていた印象があります。聞いたところでは、上記のような理由で大きな避難所に届けられながら避難者に配ることができず、とうとうこっそりと廃棄されそうになった支援物資を、小さな避難所のボランティアさんが駆けつけて引き取ったり。。ということもあったそうな。綱渡りのような作業が日常だったのですね。。
さて湊小学校避難所に到着した ぬえは、千葉さんにご紹介頂いて、ここで避難所を運営するボランティア団体のひとつ「チーム神戸」を訪ねました。当時、公設の避難所でも市役所が直接避難所を運営するのは職員の人数からいっても無理で、市役所とは連絡役のような方が1人程度あるだけで、実質的には民間のボランティア団体が運営を担っていました。湊小学校避難所にも「チーム神戸」のほかに「ピースボート」など大小2~3の団体が入っていたと思います。
彼らは震災直後に被災地に入った人たちで、避難所に住み込んで常駐していました。あとで知ったことですが、ピースボートのような大きな組織では各地から集まったボランティアさんが2~3カ月の交代制でここに住み込み、いわゆる「泥掻き」といわれる瓦礫の片付けなどの重作業を大人数で行っていました。また「チーム神戸」のような小さな団体では、ぬえのように各地から何か被災地の手助けをしたい、と思って駆けつけた若者がスタッフとなっていったようです。
ぬえは「チーム神戸」が設置していた「ボランティア受付」に行き、千葉さんから紹介されたことを若いスタッフさんに恐る恐る伝えました。「明友館」に先に行ったこともあり、すでに「泥掻き部隊」は出動したあとで、そのうえ恥ずかしいことに ぬえは「体力的に泥掻きは無理かもしれません。。何かそれでもお役に立てることがありますか。。?」なんて言いましたね。
その、まだ20歳台の若者は ぬえを上から下までジロジロと見て「ああ。。そうですか。。」と、ちょっと困った様子でしたが、それでも「大丈夫ですよ。それではこの避難所の中の清掃をお願いします」と言ってくれました。
忘れもしない、その後も長くお世話になる「チーム神戸」の若手スタッフの無尽洋平くんとの出会いでした。彼もまた被災地の手助けがしたくて東京から石巻に行き「チーム神戸」の一員となったボランティアさんです。そのほかに同様に京都から来た水島緑ちゃん、そしてチームリーダーで震災直後に神戸から駆けつけた金田真須美さん。「チーム神戸」とはここから長いお付き合いが始まります。
(続く)