4、こどもと高齢者が交流できる取組について
(1)現状の取組について伺う
答:現在、こどもと高齢者が交流できる場所は、地域の交流拠点としてニュータウンふくしプラザや総合福祉センター。
両施設とも、町社会福祉協議会に委託。
ニュータウンふくしプラザでは、町の福祉の拠点と位置づけ、専任の担当者を配置し、
日常の困り事など様々な相談を受け、必要に応じて関係機関へつなげる相談支援を行っている。
ふくしプラザでは、お子さんから高齢まで、地域住民が気軽に集まれる場の提供として、
毎週様々な催物を行う楽々サロン会や無理なく健康に筋力アップを図るゆるり体操、
就園前のお子さんと保護者、保育ボランティアとの遊びの広場である
はとっこひろば「にこにこ」を設置。
また、福祉センターでは、常設型サロンを開設し、地域住民の皆さんが気軽に集まれる場の提供や
イベントとして、子育て中のお母さん、お父さんたちの友達づくりの場、情報交換の場として、
鳩山町民生委員・児童委員協議会の協力を得て、子育て支援サロンを年6回開催。
このほか、夏休み学習支援として、夏休み中の5日間程度、小中学生を対象に、
教員経験等のある地域のボランティアの協力を得て、食事や遊びを通じて
地域の皆さんと楽しく交流できる触れ合いの居場所づくりを目的に
子ども食堂も開催しております。
また、夏休みなどに、鳩山小学校内にありますのびのびプラザの利用者が講師となって、
保育室、銀河鉄道’90を利用する児童に囲碁や料理など、交流事業を行っている。
(2)人と人とをつなげていくことで新しい取組を考えられないか
答:近年の急速な人口減少や高齢化により地域活動がさらに難しくなってきている。
地域で安心して暮らしていくためには、人と人のつながりや見守りや支え合いなどが必要。
地域づくり活動は、町と地域が一緒になって相談や活動などの取組が求められている。
町社会福祉協議会では、ボランティアセンターを設置し、ボランティア活動をしたい方と
ボランティア活動をしてほしい方をつなぐ、人と人とをつなげる橋渡しの活動を行っている。
また、登録された団体などには、各種講座などの案内や様々なボランティア情報を提供し、
ボランティア活動の助言やボランティア団体間の連絡調整などを行っている。
町内には、多世代の町民の多様かつ主体的な活動を支援し、交流の輪を広げるための
鳩山町福祉健康多世代交流複合施設や町民に交流の場としての鳩山町泉井交流体験エリア
などもある。
町や町社会福祉協議会が把握している子どもと高齢者の交流を目的に活動されている団体に
呼びかけを行い、各団体などの活動状況や課題などを共有し、各団体の経験などを生かした取組を
行うなど、検討していきたい。
再質問:ひとり暮らしの高齢者が約20%おられます。孤立化した方はおられないですか。
気にかかります。
健康づくりの取組が盛んで、健康寿命も県下でトップクラス、健康長寿のための栄養、運動、社会参加の
3つの柱を掲げている鳩山ですが、こどもを真ん中において、これをさらに進められないかと思う。
いわゆる各地で展開されている子ども食堂を提案したい。
長期休みに子ども食堂を開いてくださっているエニイさんには感謝しております。
ほかにも単発で子ども食堂を開催されている方もおられます。
認定NPO法人全国子ども食堂支援センターむすびえの湯浅誠さんのお話を伺いました。
小学校区に1か所、地域のちゃぶ台として子ども食堂が当たり前にあるとよい、そんなお話。
子どもたちだけではなく、世代間交流し、高齢者の孤立を防ぎ、生きがいづくりに貢献し、
地域づくりにも寄与できる取組ではないかと思います。
継続的に、持続的に取り組むためにはマンパワーと資金が必要です。
いろいろな企業、団体が補助金制度を創設している。
補助金を活用するためには、受皿としてマンパワーの確保ができていないと申請することもできない。
町の状況を見ていて、今必要な取組ではないか。
子どものためだけでなく、高齢者だけのためではなく、地域がつながれるように
町民、学生、町、社協、農業者、事業者が連携して、それぞれのできる力を出し合って
子ども食堂、だれでも食堂の取組を考えられないか。
答:NPO法人全国子ども食堂支援センターむすびえが行った第2回全国子ども食堂実態調査では、
多くのグループが多世代交流や地域づくり、まちづくりを活動目的としており、
実際に約6割近くの子ども食堂が高齢者も参加していると回答があった。
子どもから高齢者まで、地域の多様な方たちが参加される、また世代交流拠点として
運営されているところが多いという結果。
子ども食堂、誰でも食堂について、町や町社会福祉協議会が把握している
子どもと高齢者の交流を目的に活動されている団体などにも呼びかけを行い、
町内で活動されている各団体などの活動状況や課題などを共有するなど、
今後検討していきたい。
再質問:何かできることがあったらやりたいという方が結構いらっしゃる。
点と点をつなぎ合わせられると何かが動き出すと思う。
5年先には状況が変わっている。やるなら今。
昨年12月から越生町でこども食堂を始めたが、その情報はつかんでいるか。
答:食堂を始めたというお話は聞いているが、詳しい内容まで把握できていない。
再質問:準備をしっかりした上で、まず組織づくりをして、それから付随してくるものはいろいろ
お互いに力を出し合ってやっていければ良いと考える。
独り暮らしの高齢者がいっぱい周辺にいらっしゃると。
もう心配で仕方がないけれども、ピンポンして大丈夫ですかと言いに行けない。
だから、そういう人たちもまき込めるような取組、子ども食堂・誰でも食堂をやってほしいと
お手紙をいただいた。前に進めていかないか。
町長答弁:周辺自治体のそういった内容をしっかり研究した上で、
我々のほうも準備を進めていきたい。
むすびえのサイトからコピーしました。詳細はこちらでご覧ください。



















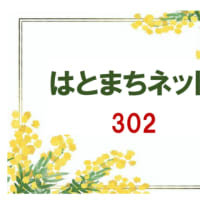




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます