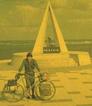<尾瀬ヶ原からの至仏山>


<ナガバノモウセンゴケ> <ハッチョウトンボ>
湿原というと、尾瀬などの大規模なものを頭に浮かべると思いますが、ある種の条件があると、小規模な谷戸のようなところにも、モウセンゴケなどの湿原植生が現れるそうです。
岡山理科大学の波田善夫先生は、湿原が成立する条件を研究されています。(波田先生は、研究だけでなく、開発で消えていく湿原植物の移植も行っています。)
この中で、供給される水が貧栄養であることが挙げられていますが、この水の栄養の度合いをはかる尺度として、波田先生は電気伝導率(上記参照ページ中の表)を使っています。
電気伝導率については、波多先生のページでも解説されていますが、私の言葉で簡単に説明すると、その水がどれだけ電気を通しやすいか(イオン量が全部でどれだけあるか)の尺度ということになります。植物の生育に関係する窒素、リン、カリなどといったものを個別に測定せずに、全部まとめて表してしまおうという考え方です。ここで対象にしている湧水は、「貧栄養」と言われているように、水にあまり多くの物質が溶けていませんので、微妙な差を測るには、電気伝導率という一見大ざっぱな感じのする水質指標が、手ごろで有効だったというわけです。
私は多摩丘陵周辺では、このような小規模湿原を見たことはないのですが、本でみると、多摩ニュータウン開発前の永山にあったようです。また、八王子の鑓水の大谷戸?にもあった可能性があります。
・『大栗川・乞田川 流域の水と文化』小林宏一(2003)p.100
(引用開始)
「永山にあった湿地岩入りの池は、一部の人には重要性が認識されていたが、ニュータウン工事初期の昭和43年、保護意識がまだ高くなかった頃で、きちんとした調査が行われないまま、あっという間に埋め立てられてしまった。トキソウ、サギスゲ、モウセンゴケなどがあった。「ふるさと多摩 一号」」
(引用終わり)
・『絹の道 やり水に生きて』小林栄一 かたくら書店(1992)p.12-14
(引用開始)
「多摩丘陵の中の小さな村落である鑓水の、いたる所にある谷間や沢は、それぞれ異なった地質、地層があって、好奇心の強い少年時代の私は、よく一人で山の中や谷川沿いを歩きまわった。・・・
その中で、一番不思議だと思う所が一ヶ所あった。それは大谷戸の沢の奥で、雑林の生えている約六畳か八畳間ほどの広さがある平坦地で、いつもこの地に足を入れると、心持ち足元がぐらつく様な感じがする。そこは楢やえごの木が生えていて、一見その周辺の山肌と何の変わっているところでもない。だが、その場所へ来て、両足をしっかりと踏んばって腰に力を入れて振って見ると、大地がユラユラと揺れ動く。・・・
戦後、尾瀬の湿原の記事が新聞や雑誌の紙面を賑しテレビでも時々紹介されるようになったが、尾瀬の記事を読み、画面を凝視していると、あの少年の日に、行ってはゆすぶって見た、あの沢の雑木林の土地は、湿原に近い小規模のものでなかったとも想像して見る。」
(引用終わり)
以下は、10年近く前の古いデータですが、私が実測した電気伝導率の値です。波田先生の指標と比べてみると面白いと思います。尾瀬の水は私が今まで測った中では最小値です。
尾瀬(牛首ちかくの池塘1997.8.2) 5μS/cm pH 5.1
雨水(東京都府中市1997.12.31) 10μS/cm
水道水(東京都府中市) 220-230μS/cm
静岡県柿田川最下流(1997.8.10) 170μS/cm
国立市ママ下湧水(1997.8.10) 300μS/cm
下水処理水(北多摩2号1999.12.26) 520μS/cm
(単位μS/cmの読み方:マイクロジーメンス毎センチメートル)