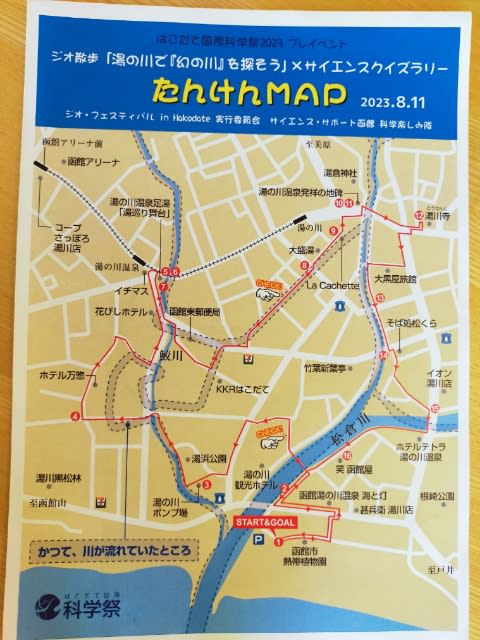2月27日、わが妻が、通勤定期の更新に函館駅前の函館バス待合で通勤定期の更新をした際の話である。
昨年9月1日から本年2月29日までの6カ月間の有効期限の通勤定期だったのだが、さらに6カ月を更新したいと頼んだら、8月28日までの有効期限で出てきたというのである。
妻が「期限がおかいしいのでは?」と言ったら、受付担当者は「通勤定期は1月30日間の換算です。」と返答したというのである。?????
これを真に受けると、3月1日から180日目は8月27日となる。
説明がおかしいいと、詰め寄ると、「あなたのいうとおりにします」と言って8月31日までの定期を出してきたというのである。
初期の目的である6カ月分の定期を買えたので、その場は収めたところではあるが、どうにも納得できないので、高盛町の函館バス本社に行って事の顛末を話した。営業時間外だったので、担当責任者不在で後日電話連絡する由とのこと。翌日の電話による回答を受けて整理してみると
まず、昨年12月に運賃改定があったので、継続更新とはならないとのこと。
よって新規扱いとなるため、開始日は任意となる。
それは理解したうえで、3月1日を始期とすると、やはり、終期が8月28日となるのはおかしい。
購入手続きをした日が2月27日なので、その日を新規扱いとすると終期は8月26日となる。
つまり考えられるのは、本来継続扱ができないのに、更新前の終期が2月28日だったため、その翌日を始期の6カ月としたのではないかと考えられる。
だとすれば、更新扱いができないので、いつを始期とするのかを、確認し手続きをすすめなければならなかったところ、勝手に29日を始期としたのではないかということだ。
この場合こちら側としては、2月27日以降いつでも始期を設定できるので、確認せずに勝手に入力したか、はたまた誤って始期を2月29日にしたかのどちらかである。
そして、クレームを言われて苦し紛れに1月は30日換算などという陳説まで持ち出したとしか考えられない。
駅前のバス案内所で通勤定期を購入する場合は要注意である。