
萩原葉子は、詩人萩原朔太郎の長女である。そんな彼女が本書において描き出す朔太郎像は、一度読んだら忘れられないほどに鮮烈である。その意味で、本書は朔太郎に関心を抱くすべての人々にとって貴重な書物であると言えよう。
萩原朔太郎が日本近代詩人の最高峰であることは、贅言を要すまい。また、その詩群は、いまだに生々しいほどの生命を保っている。言葉がまったく死んでいないのだ。例えば個人的な経験を述べると、気心の知れた少人数でしんみりと酒を呑んでいるとき、不意に記憶の闇の底から、「夜の酒場の壁に穴がある」という『夜の酒場』の一節が生々しく浮かんできたりするのである。
高校時代の現代国語の授業ではじめて彼の名とその詩風を知ったという方がけっこういらっしゃるのではなかろうか。かくいう私もそのひとりである。高校二年生のときの授業で、彼の処女詩集『月に吠える』所収の「竹とその哀傷」に触れて衝撃を受けた。そうして、その詩世界に強い興味を抱き、彼の詩集を紐解くことになった。のみならず、その後も折に触れその詩世界を顧みてきた。どうやら、朔太郎のポエジーは、私の、世界に対する構え方に少なからず影を落としているようなのだ。いささか気障な言い草に響くのかもしれないが、私の身体の奥底にある、厭世観としか名づけようのない心性の種子は、半ば以上、朔太郎の詩を読み込むことで植えつけられたような気がする。坂口安吾が、「文学は毒である」と言ったのは本当のことだといまさらながらに思う。
本書において萩原葉子は、いろいろな意味で特異な存在である朔太郎の娘として生育した自らの宿命と真摯に向き合おうとしている。そうして、その姿勢の底には、父朔太郎への切ない愛情の泉が人知れずこんこんと湧き出しているのが感じられる。その愛情が哀しいのは、普通の意味での父の愛を、彼女がどうやら十分に感じた経験がないからである。彼女は、母の穏やかな愛さえも知らない。父の孤独と同じくらいに娘の孤独は深い。
小見出しを掲載順に挙げておこう。「晩年の父」、「幼いころの日々」、「父の再婚」、「再会」、「折にふれての思い出(一)」、「折りにふれての思い出(二)」。発行は、昭和三四年十一月十五日。私が生まれたのはその前年だから、いまから五四年前のこと。私が購入したのは、紙がすっかり日焼けしてしまったボロボロの初版本なのである。
印象深かったところをいくつか記しておこう。
まずは、「晩年の父」所収の「手品」から。朔太郎の、若い頃からの手品好きは有名である。その片鱗は、次の詩からもうかがわれる。
みよわが賽(さい)は空にあり、
賽は純銀、
はあと(原文、傍点あり)の「A」は指にはじかれ、
緑卓のうへ、
同志の瞳は愛にもゆ。
みよわが光は空にあり、
空は白金、
ふきあげのみづちりこぼれて、
わが賽は魚となり、
卓上の手はみどりをくむ。
(「純銀の賽」より)
本書によれば朔太郎は、晩年の五十二、三歳の頃、阿部徳蔵氏主催の「アマチュア・マジシャン・クラブ」に入会した。そのことがとても嬉しかったようで、その会への出席の日は、祖母(朔太郎にとっては母)が出してくれる真っ白いハンカチをポケットに入れ、威厳を帯びた表情で出かけて行ったという。酔ったときのだらしない姿とは大違いとの由。その会で手に入れた手品の道具は、二階の書斎のいくつも引き出しのある小物入れに鍵をかけて入れてあった。朔太郎の死後、それらの引き出しの鍵が開けられることになった。手品の道具は、どれもこれも安っぽくて、まるで幼児の喜ぶ玩具のようなものばかりだった。
私は父の亡きあと、まもなくひとりで二階にいって、それらの入った引き出しを見た時、唖然として立ちすくんでしまった。私は、そこに父の姿を目の当たり見たように思い、もう父はこの世のどこにもいないのだという激しい悲しみが改めて全身を襲ってきて、泣いた。
なんてことだろうと思った。こんなものが、こんなに大切だった父の心を思うと、しばらくは悲しみのため、そこを動くことができなかった。
ここを目にして、なんの鎧(よろい)も着けないままの、詩人朔太郎の魂の生地を目の当たりにする思いがするのは、私だけではないだろう。
晩年の朔太郎は、同居する母の支配から逃れるようにして、連日のように飲みに出かけたそうだ。身なりに無頓着で、赤い鼻緒の下駄だろうとなんだろうと目に触れたものを履いて外出しようとするので、家の者たちは気が気でなかったという(若いころは、蝶ネクタイにトルコ帽を身につけるような伊達男だった)。その飲み方は度を越した深酒で、深夜心配して父を捜しに外へ出て、その姿をやっと見つけて言葉をかけようとする筆者の存在にさえ気がつかないほどであったらしい。ぼんやり灯っている街灯の下、筆者の方に近づいてくるのでも佇んでいるのでもなく、また歩いているようにも見えない不思議な影として朔太郎の姿は描かれている。ちなみにしらふのときでも、朔太郎の歩き方はとても奇妙で、ふわふわと身体が宙に浮くような早足で歩いたという。そのぎこちなさや非現実感は、まるであやつり人形のようであったらしい。
このくだりを目にしながら、私は、中沢新一『チベットのモーツァルト』のなかの「風の行者」を思い浮かべた。「風の行者」とは、神秘的な風(ルン)の力によって深い瞑想状態のまま石だらけの荒野をすっすっと駆け抜ける、チベット仏教の修行僧である。そのイメージが、不思議な歩き方をする朔太郎の姿とダブるのだ。少なくとも、歩いているときの朔太郎が、しばしば深い瞑想状態に陥ったことは間違いないような気がする。私見によれば、朔太郎の詩は本質的にリアリズムである。リアリズムであることにおいて、それがすっぽりと夢に浸潤されているのである。彼は、幻想的な詩を作ろうなどと意図して詩を作ったことなど、おそらく一度もないのではないかと私は思う。幻想的であることは、彼の宿命であり、本能なのである。その幻想の衣が襤褸(らんる)と成り果てたとき、彼は『氷島』という無残で痛切なスワン・ソングを歌うよりほかはなかった。そのことについては、のちに触れよう。
朔太郎が娘の葉子を喫茶店に誘ったエピソードも忘れがたい。朔太郎がちょっと笑いながら娘に「お前は喫茶店に行ったことがあるか」と尋ねたのである。むろん、葉子にはそんな経験はなかった。そして、新宿に繰り出してある喫茶店に入りすぐにそこを出た後、通りに面した「大衆酒場のような店」の前にさしかかったとき、朔太郎が振り返って「ちょっと寄ってもいいだろう?」と許しを請うように言った(朔太郎は、最初からそういう魂胆だったのだろう。母のお咎めを避けるために娘を誘い出したにちがいない)。扉を開けると女たちが朔太郎のところに近寄ってきて「しばらくね!先生」と声をかけた。
汚いテーブルにはお酒が運ばれ、和服を着た女の人達は、かわるがわる馴れたしなやかな手さばきで、父にぐいぐいお酒を注いだ。父はソフトをかぶったまま、お酒を受けて飲んだ。女の人達も飲んで、瞬くまに空になったお銚子は、テーブルの上に並んでしまった。(中略)父はそのとき顔を挙げると、急に思い出したように、たもとに手をつっこんで大きな口金付の皮のガマ口を出して勘定を払った。それからざらざらとテーブルの上に、残りのお金をみんな空けてしまうように落とした。五十銭銀貨や十銭銅貨が重なり合ってガマ口から落ちた。「みんなで分けてくれ」と父がいうと、まわりに集まった女の人達の「ありがとうございます」という声と一緒に、たちまち白い手がそこに集まり、お金は一瞬にして、テーブルの上から消えてしまった。
朔太郎の愛読者がここを目にするならば、『氷島』所収の「喫茶店 酔月」のなかの
我まさに年老いて家郷なく
妻子離散して孤独なり
いかんぞまた漂泊の悔(くい)を知らむ。
女達群がりて卓を囲み
我れの酔態を見て憫(あわれ)みしが
たちまち罵りて財布を奪い
残りなく銭を数えて盗み去れり
という一節をありありと思い浮かべるにちがいない。端的にいえば晩年の朔太郎は、『氷島』の世界を日々生きていたのである。朔太郎自身、その自序に「この詩集の正しい批判は、おそらく芸術品であるよりも、著者の実生活の記録であり、切実に書かれた心の日記であるのだろう」と書き記している。ここから、例の「氷島問題」が惹起することになった。つまり、日本語で書かれた口語自由詩における前人未到の領域を力強く切り開いた萩原朔太郎が、晩年に到って文語定型詩に「後退」したことを否定的に評価すべきかどうかの是非問題である。ここでその詳細に触れるつもりはないが、この問題は、『氷島』の、作品としての是非という芸術評価的な観点を超えて、日本における近代の本質に触れるものをはらんでいる、とだけは言っておきたい気がする。
と言っただけでは、「なにを思わせぶりな。『日本における近代の本質に触れるもの』とは何か、はっきり言ってみろ」とお叱りを受けても致し方がないとも思われるので、端的に申し上げておこう。「日本における近代の本質」とは、日本近代には中国問題をめぐってアメリカと衝突せざるをえないという文明論的な意味での不可避性が存したこと、である。日本近代は、その不可避性が次第に癌細胞のように肥大化する過程としてイメージすることが可能であると私は考える。言いかえれば、日本近代は二〇世紀の覇権国家としてのアメリカによって完膚無きまでに叩きのめされる宿命にあった。そういう悲痛極まりない帰結を、朔太郎は詩的本能としか名付けようのないものによって、自分自身の私生活の破綻に重ね合わせるようにして、『氷島』における無残なリリシズムとして鋭敏にも先取りしていたのではなかろうか、と私は考えるのである。言語表現の近代化の最前線に長らく独りでぽつんと位置していたからこそ、朔太郎は、いわば身体まるごとで、日本近代の宿命を感知することになってしまったのではないだろうか。ちなみに、『氷島』が刊行されたのは昭和九年、大東亜戦争が火ぶたを切る七年前である。本物の詩人の感性は、それくらいには鋭いのだ。
その「無残なリリシズム」は、『氷島』全編に鳴り響いているともいえるが、とりわけ、次の詩句にいちじるしい。
日は断崖の上に登り
憂いは陸橋の下を低く歩めり。
無限に遠き空の彼方
続ける鉄路の柵の背後(うしろ)に
一つの寂しき影は漂ふ。
(中略)
ああ汝 寂寥の人
悲しき落日の坂を登りて
意志なき断崖を漂泊(さまよ)ひ行けど
いづこに家郷はあらざるべし。
汝の家郷は有らざるべし!
(「漂白者の歌」より)
作中の「漂白者」は、帰るべき家郷をすでに失い、あてもなく彷徨う。そうしてどこへ行くのか。この詩の寒々とした敗残の響きは、彼には破滅よりほかに待ち受けるものがないことを暗示する。私は、作中の「漂泊者」が晩年の朔太郎の自画像であることにおいて、日本近代の帰するところを象徴し、その暗い行く末を詩の響きとその巌のような肌ざわりそれ自体で表現していると感じる。それは、朔太郎が意識していたのかどうかとは、まったく関わりのないことである(誤解を恐れて付け加えるのだが、私はここで、詩人という存在はかけがえのないものである、と言いたいのである)。
最後に、朔太郎の死の場面に触れておこう。
朔太郎が亡くなる前の晩に筆者は悪夢とも幻覚ともつかないものを見る。血の気がなくすでに死んでいる朔太郎が二階の書斎に横たわっている。筆者は危うくその場に倒れてしまいそうなほどに不吉なものを感じて驚き、確かに生きているはずの父を捜しに階下へ逃げるように降りてくる。するとこんどは居間にも同じ姿となった朔太郎が横たわっているのである。筆者は、それをふり払うようにして、急いで自分の部屋に入るとまた同じ姿の朔太郎が横たわっているのだ。筆者は夢のなかで、″これはたしかに夢なのだ″と念じて、必死に目覚めようとあせる。むし暑い夜半、首筋にべっとりと汗がにじみ、夜中の二時を打つ柱時計の音をどこかにぼんやり聞き、また眠りに落ちていく。すると、二階にさっきとまったく同じ姿の朔太郎が今度は二体も横たわっている。筆者が、重い足をひきずりながら急いで階下に下りてくると、そこにも死んだ朔太郎が二体横たわっている。筆者は必死に目覚めようともがき、ふと目が覚めると、暗い部屋の壁にも同じ姿の朔太郎が映っているのである。そうして、そんな状態が明け方まで続く。錯乱状態と隣合わせの精神状態にかろうじて踏みとどまりながら、間近に迫った父の死を全身全霊で受けとめようとする筆者のなまなましい姿が読み手を圧倒する。いよいよ臨終の場面である。
その夜は祖母(朔太郎の母――引用者注)と私と妹の三人が附添っていたが、十二時を過ぎたころまではいくらか呼吸も楽に落ち着いたように思われたが、急に荒いいきづかいになってきて大きく胸を不規則に波立たせ、顔は透きとおるように白く、手足のむくみは激しくなっていた。Y医に急いで電話をかけようとした時だった。ふいに瞳孔の定まらないおそろしいほど大きな目を一瞬見開いてあたりを見たかと思うと、次の瞬間には深く目を閉じ、同時に深い呼吸を一つつき、ふいにそれっきり呼吸が止まったのである。その時私と妹は同時に「お父さま!」と大きな声を挙げて呼んだ。しかし父はもう何も答えてはくれなかった。
昭和十七年五月十一日、かぞえ年で五十七歳だった。
ここで本書は終わっている。上の引用でうまく伝わるかどうか心もとないのではあるが、私はここを目にして、しばし絶句状態に陥り、肉親の最期をこのように書き切った筆者の作家魂に感服するとともに、本書を読み終えたバスの中で不意にこみあげてくるものがあり、それをこらえるのに一苦労したものだった。
インターネットで検索してみてはじめて知ったのだが、映像作家の萩原朔美氏は、著者のご子息であるとの由。骨がらみの表現者の業(ごう)は深い。












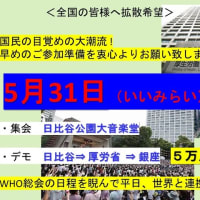














KAZENOUSHIRO21st@gmail.com
心のこもったコメントをどうもありがとうございます。林さまのお役に立てたところがあるようで、書き手冥利に尽きます。私は、文芸評論は潔く心を丸裸にして書くものではなかろうかと考えております。そうすることではじめて、文芸評論はかろうじて文学ジャンルの末席に座ることができるのではなかろうか、と。その思いが林さまにいささかなりとも伝わっていれば、なおさら嬉しゅうございます。