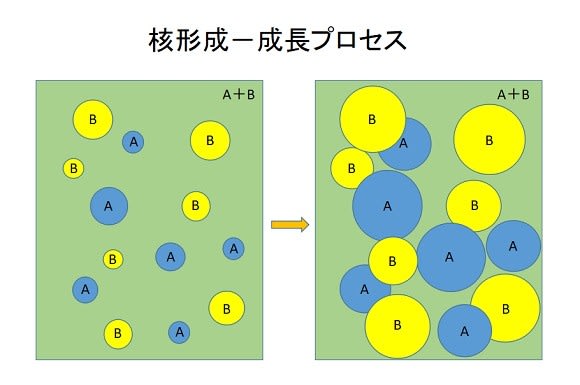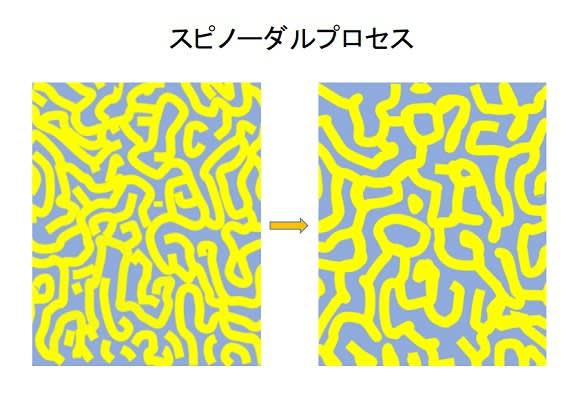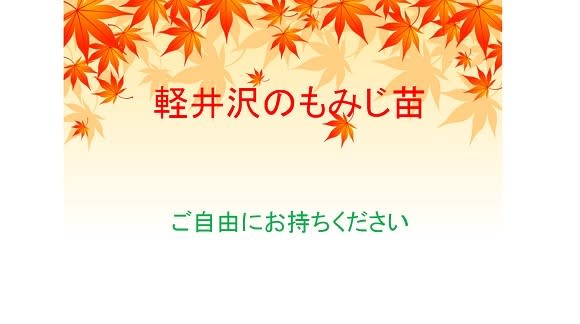今回はオシドリ。雲場池でオシドリを見ることができるとはまったく予想しておらず、テレビの番組で北海道大学の構内で子育てをするオシドリのことを見た時にも、何か特別な遠い存在であるように感じていた。
ところが、妻がツイッターの写真を見ていて、そのオシドリが近くの千ヶ滝地区にある池に来ていると教えてくれたのは4月頃であった。
スマホ画面で見たその写真は素晴らしいもので、これまで私が雲場池で撮影してきた水鳥たちのものとは一線を画する解像度で撮影されていた。やはり、近くに寄ることが難しい鳥類の撮影にはそれなりの機材が必要なのだとこのとき痛感させられたのであった。
そのころ、ブログで写真を紹介している友人のIさんが新たに超望遠レンズ購入し、そのレンズで撮影した写真を紹介し始めており、それらの写真はとてもよく撮れていたし、使い勝手も良いとの感想を書いているのを知り、私も鳥類の撮影用に思い切ってこの同じレンズの購入を決意した。
昨年あたりまでは、主にチョウや山野草の撮影をしていたので、古いニコンD200とタムロンの望遠ズーム18-270mmでも何とかなっていたが、雲場池に散歩に出かけるようになって、撮影対象に鳥類が加わるようになってからは、特に物足りなさを感じていたのであった。
今回購入することにした超望遠レンズは、オリンパス製の100-400mmズームレンズで、オリンパスのボディーと12-40mmズームレンズはすでに持っていた。これはアンティーク・ガラスショップの商品撮影用に購入してあったもので、ボディーは深度合成ができる機種オリンパスOM-D/E-M1である。
Iさんからすでに評価は聞いていたので、カメラショップでの実物確認はスキップしてネットショップで購入することにしたが、調べてみると、1ヶ月以上待たなければならないようであった。しかし、実際に発注してみると数日で商品が届けられた。
千ヶ滝付近の池にオシドリが来ているとの情報をもとに、現地の様子などを調べ始めていたが、先ずは毎朝の散歩で試し撮りをしてみようと、さっそく散歩のお供にニコンD200に替えてこのオリンパスEM-1を持ち出して雲場池に出かけるようになった。
そして、数日が経った頃、雲場池の西側の遊歩道を歩いていて、対岸近くにいる水鳥に気がついた。毎日のように見かけているカルガモではなさそうで、望遠レンズ越しに確認すると、一羽の雄のオシドリであった。

対岸に見つけた雲場池のオシドリ1/2(2021.5.25 撮影)

対岸に見つけた雲場池のオシドリ2/2(2021.5.25 撮影)
早速、撮影を開始したが、オシドリは池の東側にいて、周辺の林の陰になり朝日が差し込まないため暗く、どうしてもシャッター速度が遅くなってしまう。
しばらくそのまま撮影を続けたが、飛び去らないように見えたので、私が池の東側に移動することにした。
今度は、私を意識してか、オシドリは池の中心部方向、朝日が直接当たる場所に移動していった。撮影条件も良くなり、それまでより早いシャッタースピードで撮影できるようになった。
オシドリが雲場池に現われたのは、この日一日だけで、その後の散歩で見かけることはまだない。千ヶ滝方面に撮影に出かけようと思っていた矢先のことで、幸運なできごとであった。
さて、思いがけない出会いのことに、ついつい前置きが長くなったが、いつもの「原色日本鳥類図鑑」(小林桂助著 1973年保育者発行)でこのオシドリについての記述を見ると、次のようである。美しい♂の羽色についての記述がやはりかなり長い。
「形態 ♂の冬羽はきわめて美麗。三列風切内側の一枚は栗色に大きく拡がりいわゆるいちょう羽となる。嘴峰27~32mm、翼長214~250mm、尾長90~109mm、跗蹠33~40mm。♂は頭上金緑色にて後頭の羽毛は長く延び白色と赤栗色とを混じえている。背は暗かっ色で肩羽には藍黒色と白色とを混じえる。眼先は淡かっ黄色、頸側には栗色の細長い羽毛がある。胸は紫黒色で胸側には2条の白帯がある。腹は白。嘴は暗紅色。♀は上面暗かっ色にて眼の周囲から後頭にかけ白い線が延びている。胸は黒かっ色で白はんがあり、上嘴基部両側と喉と腹とは白色。脇は黒かっ色と黄かっ色とのまだら。♂の夏羽はいちょう羽を欠き全体♀に似る。
生態 シベリア東北部・満州・蒙古・中国・朝鮮・日本などに分布繁殖する。欧州でも天然に繁殖しているものが各所にあるが、これは昔東洋から輸入されたものである。水上生活すると共にしばしば高い樹枝上にも止まる。好んでシイの実を食す。山地の水辺に近い高木の天然樹洞に営巣することが多いが、皇居の外ぼり付近や明治神宮などで繁殖するものもある。冬期は群集して山間部の密林に囲まれた池や谷川に生息するものが多い。
分布 北海道・本州・九州で繁殖し冬期は本州中部以南・八丈島・四国・九州・対馬・種子島・奄美大島などに分布する。」
では、以下に対岸に移動後に撮影した写真をごらんいただく。池中央部のよく朝日が当たる場所に移動したときのもので、撮影条件は改善している。

雲場池のオシドリ1/11(2021.5.25 撮影)

雲場池のオシドリ2/11(2021.5.25 撮影)

雲場池のオシドリ3/11(2021.5.25 撮影)

雲場池のオシドリ4/11(2021.5.25 撮影)

雲場池のオシドリ5/11(2021.5.25 撮影)

雲場池のオシドリ6/11(2021.5.25 撮影)

雲場池のオシドリ7/11(2021.5.25 撮影)

雲場池のオシドリ8/11(2021.5.25 撮影)

雲場池のオシドリ9/11(2021.5.25 撮影)

雲場池のオシドリ10/11(2021.5.25 撮影)

雲場池のオシドリ11/11(2021.5.25 撮影)
撮影した写真を見ていると、今回のこのオシドリの♂はまだ若い鳥だろうと思える。図鑑の羽色の説明と見比べてみると、後頭の羽毛が未発達で、「長く延び白色と赤栗色とを混じえている」とは見えない。また、最近の図鑑の写真と比べてみても、眼の周囲から後頭にかけての白い線の延びも短い。さらに、オシドリの特徴であるイチョウ羽もまだ未発達のようである。
全体の印象も、これまで写真で見ていたものとはやや異なり、頭部が小さいと感じる。これは後頭部へと伸びる羽が未発達のせいだろう。
静止した時の姿も、頭部を後ろに引き胸を突き出したように見える写真を見ることが多いが、今回池を泳いで首を前に突き出して餌を食べる姿を見ていると、他のカモ類と同じように見えてほほえましい。
いまのところ、雲場池で姿を目撃できたのは、この1日だけであったが、またいつか出会い、成長した姿を見せてもらいたいものである。オシドリ夫婦という言葉があるが♀を伴った姿もぜひ見せてもらいたい。