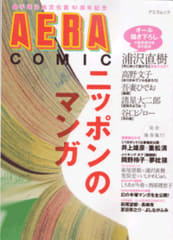(週刊少年サンデー 昭和62年36号~平成8年12号掲載)
近頃、久しぶりにらんまを読み返している。
全38巻なので毎晩寝る前に5冊程読んでいるのだがまだ全部読み終わってない。
有名だと思うのであらすじは省略してもいいよね?
最終回はどんな話だったっけ?と思って最終巻を見ると・・・
あらら!?乱馬とあかねって結婚したっけ~~!!??
あわてて読んだが・・・あ~ナルホドね・・・っていう感じ。
ネタばれが嫌な人がいるかもしれないので、どういう結末かはここに書かない。(手抜き?・・・笑)
この作品、もうかなり古いが今読んでも十分面白い。
こういうギャグっぽいコメディって、古くなるとつまらなく感じるものも多いがこれは違う。
大したものだ・・・と思う。
超個性的なキャラたち。
多くの人たちに受け入れられるだろうと思われる魅力的な絵柄。
顔は可愛いし、動きもいい。
少年漫画のアクションものでは服装がほとんど同じ場合が多いが、
この作品では登場人物たちは実に多彩な服装をしている。
中国風のファッションが多いが、どの服も非常に可愛い!!
設定が実にユニーク!
乱馬は水をかぶると女の子、お湯をかぶると元の男の子に変わる!
こんな発想一体どこから来るんだ~~!!
父の玄馬はナント!・・・パンダだし~~~!!
黒豚、猫、あひる・・・よくまあ考えたものだ・・・。
<1巻カバー裏表紙の言葉より>
恋と涙、拳法と剣道と天道、パンダと人間と男と女が大混乱!!
かる~~く、楽しく読める作品。
ちょっと落ち込んだときなどに気分転換に読むのもいいかもしれない。
近頃、久しぶりにらんまを読み返している。
全38巻なので毎晩寝る前に5冊程読んでいるのだがまだ全部読み終わってない。
有名だと思うのであらすじは省略してもいいよね?
最終回はどんな話だったっけ?と思って最終巻を見ると・・・
あらら!?乱馬とあかねって結婚したっけ~~!!??
あわてて読んだが・・・あ~ナルホドね・・・っていう感じ。
ネタばれが嫌な人がいるかもしれないので、どういう結末かはここに書かない。(手抜き?・・・笑)
この作品、もうかなり古いが今読んでも十分面白い。
こういうギャグっぽいコメディって、古くなるとつまらなく感じるものも多いがこれは違う。
大したものだ・・・と思う。
超個性的なキャラたち。
多くの人たちに受け入れられるだろうと思われる魅力的な絵柄。
顔は可愛いし、動きもいい。
少年漫画のアクションものでは服装がほとんど同じ場合が多いが、
この作品では登場人物たちは実に多彩な服装をしている。
中国風のファッションが多いが、どの服も非常に可愛い!!
設定が実にユニーク!
乱馬は水をかぶると女の子、お湯をかぶると元の男の子に変わる!
こんな発想一体どこから来るんだ~~!!
父の玄馬はナント!・・・パンダだし~~~!!
黒豚、猫、あひる・・・よくまあ考えたものだ・・・。
<1巻カバー裏表紙の言葉より>
恋と涙、拳法と剣道と天道、パンダと人間と男と女が大混乱!!
かる~~く、楽しく読める作品。
ちょっと落ち込んだときなどに気分転換に読むのもいいかもしれない。