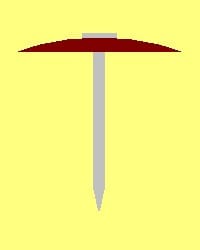機械弄りをするとコンプレッサーがあると便利。オートバイ弄りをしてた一番欲しかった頃、こういう物を買おうなんて思わなかった。恐らく当時はプロ用の大きなのしか無かったんじゃないのかな。それの思わぬ使い方を最近見た。自転車のハンドルについてるグリップをコンプレッサーで簡単に外せるのだ。といってそれだけのために買うのもちょっとねって感じ。
「チェーンソーの掃除にコンプレッサーが良いよ」とこれまた最近聞いた。そのくらいの事は知ってるけど1万円くらいので綺麗になるよ、と。それを聞いて気になったのはその1万円ので自転車のハンドルについてるグリップを外せるかだ。
コンプレッサーを調べてるとタンクの大きさが作業時間に関係してるというのが分かった。他に静音型だとかオイルレスなんてのも。小さいのや安いの買って今一つってのもよく経験したのでタンク容量が20L以上のにしようかと決めかけた。だけど重さが20kgもあって使い勝手が悪そう。修理工場みたいに床が平なコンクリートなら良いけど石ころだらけの凸凹な庭では車輪があっても移動が大変そう。なのでタンク容量10Lという小さなのを買った。
 オイルレスの静音型@タンク容量10L
オイルレスの静音型@タンク容量10L
気になるグリップ外しを試してみた。これがダメだったらガックリだ。写真のようにノズルをグリップの所に挿して2~3回シュシュッとやったら簡単にグリップを外せた。ホッとした。勿論チェーンソーのゴミ吹き飛ばしも出来た。でも大きなゴミはブラシなどである程度落とさないと途中で作業中断になってしまいそうだ。

隣の家が離れてるとはいえやっぱり静かな方が良い。タンクに空気を詰めてる時の音はミシンくらいなので家の中で使える。重さは10kgくらいだからあちこちに持ち歩いて使える。ただ面白がって何度もシュッシュとやってたら直ぐに圧力が無くなった。この辺りが小さなタンク故だけど、ちょっとした事で色々と便利な使い方が出てきそうだ。