【日本史】
『織田信奈の野望』(作・春日みかげ、イラスト・みやま零)6巻読みました。(↓)以前の記事です。
▼『織田信奈の野望』~戦国ラブコメ~信奈とか光秀とか可愛い
(↓)あとペトロニウスさんの『物語三昧』で、引用されていた哲学さんのコメントがとても『面白ろ』かったので、こちらでも貼っておきます。『織田信奈の野望』が6巻に入って、それまで、微妙にして絶妙(?)のバランスで合わせていた史実から、かなり離れてきた感があって「そうすると、歴史に合わせ込んで観る愉しさから離れてしまわないか?…みたいな?感じの話題を上げていたんですよね。
それに対する哲学さんの回答は、なかなか秀逸…というか、僕はこういう『物語』への考え方、好きなんですよね。その物語が好きになり過ぎて「すごい科学で守ります!」みたいな感じになっているのってw
▼物語三昧:『織田奈の野望』について哲学さんのコメントが面白いです。
まあ、ちょっと立ち返った事を言うと、織田信長を美少女にしよう!というコンセプトを得た時、「この子にどうすればハッピーエンドを与えられるか?」という志向になって、織田信長の史実を一つずつ一つずつ、ハッピーエンドの伏線となるような“形”に改変して行く……と、技術的にはそういう話なんですが、それをどう“物語的”に落としこんでゆくのか?というのは、おたくの醍醐味というか、このブログでぼちぼち更新している『物語愉楽論』の一つの到達点の話でもあります。まあ、それは本当にぼちぼち紹介するとして…。
もう一つ『織田信奈の野望』はハッピーエンド志向の他に、もう一つ別のコンセプトがついているようです。これも哲学さんが指摘している、武田信玄と、伊達政宗の台頭です。まあ、これもハッピーエンドの一環というべきなのかもしれませんが“英雄の決戦”とでも言えばいいのか、天下統一を目指しながらも天命無く、その場に至らなかった者たちの決着を着けてやろう…という考え方で歴史が動いてきているように観えます。これも今後の愉しみの一つでしょうね。
そして、その“英雄の決戦”からはおよそかけ離れた存在と言え、かつ織田信長を悪名たらしめている相手、石山本願寺及び一向宗門徒との戦いは『織田信奈の野望』において、お猫様を信仰する本猫寺(ほんにゃんじ?)として扱われ、良晴の交渉によって平和の内に和睦を成し遂げてしまいます。
まあ、これも分かる話。宗教ものという存在自体が、いろいろ扱いづらい面もあるのですが、“英雄の決戦”という軍記物的な華やかな戦さの描きとはおよそかけ離れた戦いとなっていた一向宗門徒はその戦いを描くだけで、まあ、ハッピーエンドのハッピーな気持ちからは遠ざかるよね…という事なのでしょう。
■石山本願寺という存在
しかし、最近、僕は戦国時代において、この石山本願寺という存在をすごく大きなものに捉えようとしています。…といっても、今、何かまとまった説を持っているわけでもないんですけどね(汗)
石山本願寺が織田信長にとって、最大最強の敵である事は……まあ、意見が割れるとも思いますが、そこそこの支持を得られるであろう史観だと思います。ちょっと言うと、織田信長が10年かけて美濃を攻略するワケですが、この時、尾張と美濃を手に入れた時点で、織田信長は、戦国大名としては最強の国力を持ち、一国で彼と総力戦をやれる大名はいなくなったんですよね。
動員兵力について語ると……諸説ありますが、仮に武田信玄のこの時の動員兵力を3万とするなら、信長は6万の兵力を動員できる…というぐらいの差がついている。(信長が「天下布武」を謳うのは時から…という達見を考えると空寒いものがありますが)この国力差は、信長が南近江を手に入れ、上洛を果たすとさらに跳ね上がります。
この信長に対して毛利の支援があったとは言え、特に大きな領土を持つわけでもない石山本願寺が10年間……言ってしまえばタイマンを張り続けたわけです。はっきり言ってこれは他の戦国大名では真似ができなかった事です。
また石山本願寺は武装寺としての信長の対立だけでなく、別の対立もあったと言えるのでは…と僕は思っていて。ちょっと一般的な話をすると、延暦寺や一向宗に対する信長の虐殺行為ってけっこう一緒くたに思われている所があると思うんですけど、延暦寺と一向宗は、信長に逆らった者という観点からは同じでも、対立の意味は違っている所があるんじゃないかと。
いや、よく言われるように織田信長の功績には「旧態勢力の打破」というのがあります。延暦寺はこれにあたると言えそうです。しかし、石山本願寺及び一向宗は戦国時代においては“新興勢力”と言った方がよい存在のはずなんです。
つまり、僕は英雄・織田信長軍団とは別の“新しい勢力”だったのでは?と言いたい。
しかし、本願寺は旧態勢力とはつながっていだろうし、信長ほどそれを一気に片付ける能力があったかと言うと疑わしい。でも、信長だって将軍を利用したり天皇を利用したり別に旧態勢力と敵対ばかりしていたワケではないし、あくまで邪魔なモノを排除しようとしただけで「時代を改革してやろう」とか考えていたか?というとそれは充分に疑えるもので、つまり、その意味において本願寺と大差ないんじゃないの?とも言えます。
石山本願寺は延暦寺のような歴史を持った霊山ではない。また「百姓の治めたる国」と言われた加賀の一向一揆(真に百姓の統治だったかは解釈がありそうですが)などを観ても、別の“新しい勢力”を観てとる事ができると思います。
また『桶狭間戦記』のラジオなんかでも繰り返し述べましたが、戦国時代は、何より武装村落である“惣村”が充分に強い力と主張を持っていた時代であったという史観があり、その惣村の者たちに絶大な支持と信仰を受けたのが石山本願寺であった事には大きな意味があると思います。
戦国時代にキラ星のごとく現れてその名を馳せた戦国大名たちと、その版図の変遷で歴史が語られて~これを仮に版図主義と言いますが~その版図においては“点”に過ぎない石山本願寺のその意味は、まだ充分には掘り下げられていないような………って、僕の話ですけどね。僕がまだ納得できていないと。
『織田信奈の野望』の本猫寺も、ちらっと近い事を言っていましたが、石山本願寺は、版図主義の戦国大名とは全く違った形での“天下統一”を目指していたのではないか?そんな事を考えたりもします。
う~ん、まあ、正直に言うと、そのネタで何か一本小説がかけないかな?とか考えているんですけどね。今は、ぼちぼちゆるゆるとその下調べ中みたいなものです(汗)
 | 織田信奈の野望 6 (GA文庫) |
| みやま 零 | |
| ソフトバンククリエイティブ |
『織田信奈の野望』(作・春日みかげ、イラスト・みやま零)6巻読みました。(↓)以前の記事です。
▼『織田信奈の野望』~戦国ラブコメ~信奈とか光秀とか可愛い
(↓)あとペトロニウスさんの『物語三昧』で、引用されていた哲学さんのコメントがとても『面白ろ』かったので、こちらでも貼っておきます。『織田信奈の野望』が6巻に入って、それまで、微妙にして絶妙(?)のバランスで合わせていた史実から、かなり離れてきた感があって「そうすると、歴史に合わせ込んで観る愉しさから離れてしまわないか?…みたいな?感じの話題を上げていたんですよね。
それに対する哲学さんの回答は、なかなか秀逸…というか、僕はこういう『物語』への考え方、好きなんですよね。その物語が好きになり過ぎて「すごい科学で守ります!」みたいな感じになっているのってw
▼物語三昧:『織田奈の野望』について哲学さんのコメントが面白いです。
一見、織田信奈の物語はひょいひょいハッピーエンドが続いてるように見えますが、これは何周もの歴史ループが裏で繰り返されており、豊臣秀吉が何度も何度も『まどか☆マギカ』の暁美ほむらや『紫色のクオリア』のガクちゃんみたいに歴史ループを繰り返し、ようやく辿り着いたハッピーエンドルートだと仮定すればいいのです。
織田信長の人生はどうしても凄惨なものになるのは確実で、それを修正するにはもう、天皇家を解体して邪馬台国が天下取って卑弥呼の末裔が姫巫女として君臨して姫武将が大量に出るようになって、織田信長も織田信奈と性別改変まで行い、秀吉自身も未来から自分のオルタナティブを呼んで託すことまでしないとトゥルーエンドの歴史へ辿り着けなかった……みたいに考えるのです。
まあ、ちょっと立ち返った事を言うと、織田信長を美少女にしよう!というコンセプトを得た時、「この子にどうすればハッピーエンドを与えられるか?」という志向になって、織田信長の史実を一つずつ一つずつ、ハッピーエンドの伏線となるような“形”に改変して行く……と、技術的にはそういう話なんですが、それをどう“物語的”に落としこんでゆくのか?というのは、おたくの醍醐味というか、このブログでぼちぼち更新している『物語愉楽論』の一つの到達点の話でもあります。まあ、それは本当にぼちぼち紹介するとして…。
もう一つ『織田信奈の野望』はハッピーエンド志向の他に、もう一つ別のコンセプトがついているようです。これも哲学さんが指摘している、武田信玄と、伊達政宗の台頭です。まあ、これもハッピーエンドの一環というべきなのかもしれませんが“英雄の決戦”とでも言えばいいのか、天下統一を目指しながらも天命無く、その場に至らなかった者たちの決着を着けてやろう…という考え方で歴史が動いてきているように観えます。これも今後の愉しみの一つでしょうね。
そして、その“英雄の決戦”からはおよそかけ離れた存在と言え、かつ織田信長を悪名たらしめている相手、石山本願寺及び一向宗門徒との戦いは『織田信奈の野望』において、お猫様を信仰する本猫寺(ほんにゃんじ?)として扱われ、良晴の交渉によって平和の内に和睦を成し遂げてしまいます。
まあ、これも分かる話。宗教ものという存在自体が、いろいろ扱いづらい面もあるのですが、“英雄の決戦”という軍記物的な華やかな戦さの描きとはおよそかけ離れた戦いとなっていた一向宗門徒はその戦いを描くだけで、まあ、ハッピーエンドのハッピーな気持ちからは遠ざかるよね…という事なのでしょう。
■石山本願寺という存在
しかし、最近、僕は戦国時代において、この石山本願寺という存在をすごく大きなものに捉えようとしています。…といっても、今、何かまとまった説を持っているわけでもないんですけどね(汗)
石山本願寺が織田信長にとって、最大最強の敵である事は……まあ、意見が割れるとも思いますが、そこそこの支持を得られるであろう史観だと思います。ちょっと言うと、織田信長が10年かけて美濃を攻略するワケですが、この時、尾張と美濃を手に入れた時点で、織田信長は、戦国大名としては最強の国力を持ち、一国で彼と総力戦をやれる大名はいなくなったんですよね。
動員兵力について語ると……諸説ありますが、仮に武田信玄のこの時の動員兵力を3万とするなら、信長は6万の兵力を動員できる…というぐらいの差がついている。(信長が「天下布武」を謳うのは時から…という達見を考えると空寒いものがありますが)この国力差は、信長が南近江を手に入れ、上洛を果たすとさらに跳ね上がります。
この信長に対して毛利の支援があったとは言え、特に大きな領土を持つわけでもない石山本願寺が10年間……言ってしまえばタイマンを張り続けたわけです。はっきり言ってこれは他の戦国大名では真似ができなかった事です。
また石山本願寺は武装寺としての信長の対立だけでなく、別の対立もあったと言えるのでは…と僕は思っていて。ちょっと一般的な話をすると、延暦寺や一向宗に対する信長の虐殺行為ってけっこう一緒くたに思われている所があると思うんですけど、延暦寺と一向宗は、信長に逆らった者という観点からは同じでも、対立の意味は違っている所があるんじゃないかと。
いや、よく言われるように織田信長の功績には「旧態勢力の打破」というのがあります。延暦寺はこれにあたると言えそうです。しかし、石山本願寺及び一向宗は戦国時代においては“新興勢力”と言った方がよい存在のはずなんです。
つまり、僕は英雄・織田信長軍団とは別の“新しい勢力”だったのでは?と言いたい。
しかし、本願寺は旧態勢力とはつながっていだろうし、信長ほどそれを一気に片付ける能力があったかと言うと疑わしい。でも、信長だって将軍を利用したり天皇を利用したり別に旧態勢力と敵対ばかりしていたワケではないし、あくまで邪魔なモノを排除しようとしただけで「時代を改革してやろう」とか考えていたか?というとそれは充分に疑えるもので、つまり、その意味において本願寺と大差ないんじゃないの?とも言えます。
石山本願寺は延暦寺のような歴史を持った霊山ではない。また「百姓の治めたる国」と言われた加賀の一向一揆(真に百姓の統治だったかは解釈がありそうですが)などを観ても、別の“新しい勢力”を観てとる事ができると思います。
また『桶狭間戦記』のラジオなんかでも繰り返し述べましたが、戦国時代は、何より武装村落である“惣村”が充分に強い力と主張を持っていた時代であったという史観があり、その惣村の者たちに絶大な支持と信仰を受けたのが石山本願寺であった事には大きな意味があると思います。
戦国時代にキラ星のごとく現れてその名を馳せた戦国大名たちと、その版図の変遷で歴史が語られて~これを仮に版図主義と言いますが~その版図においては“点”に過ぎない石山本願寺のその意味は、まだ充分には掘り下げられていないような………って、僕の話ですけどね。僕がまだ納得できていないと。
『織田信奈の野望』の本猫寺も、ちらっと近い事を言っていましたが、石山本願寺は、版図主義の戦国大名とは全く違った形での“天下統一”を目指していたのではないか?そんな事を考えたりもします。
う~ん、まあ、正直に言うと、そのネタで何か一本小説がかけないかな?とか考えているんですけどね。今は、ぼちぼちゆるゆるとその下調べ中みたいなものです(汗)










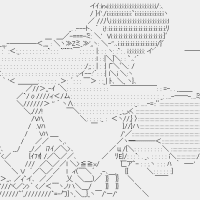
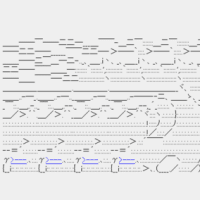
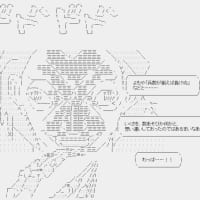
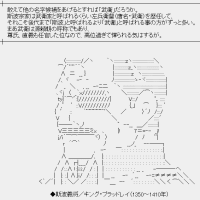
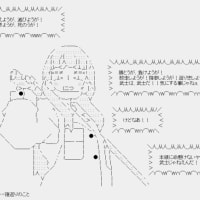
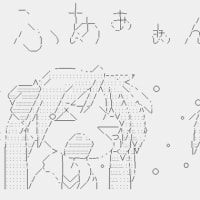

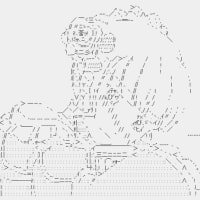

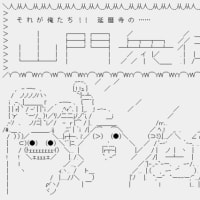
僕は、本願寺は、室町時代から続く宗教の腐敗を視るに、西洋における宗教改革、新たな宗教による民衆の価値観パラダイムシフト支配、簡単に言えば、日本的法王体制を考えていた節があるように思うんですよ。
僕の中では信長は、ナポレオンやカエサルを超える程の『旧体制破壊者=改革者』なので、それの台頭を許すとは思えないんですよね。
せっかく旧体制が軒並み衰退し出した頃だった訳ですし。
楽市楽座で、民衆の自由経済流通の拡大による利益拡大を考えていたらしき信長としては、法王体制は、不味いでしょう。
多分……
親鸞の自体は仏教に対する、宗教改革というか、ルネッサンス的な志向を感じたりしますが、本願寺の実質的創始者・蓮如がどうだったかは今、勉強中です。
ただ、今言えるのは、日本の仏教は元々、極めて政治的事由によって招聘された、ある種の学問・科学であり、また鎮護国家のための“神”として信者のためというより、国家のために輸入された経緯があると思います。
浄土宗、時宗、あと日蓮宗もかな?といった鎌倉時代に起こり民間に広まった宗派は、ある意味、民衆がはじめて接する“新興宗教”だったという位置付けで考えています。
延暦寺は比叡山という霊山を笠に着て横暴をはたらけますが、本願寺にはそもそもそういうものがない…はず。
それが何を意味するか…というのは考えをまとめていませんが、彼らは新しい勢力であり、また、本願寺の勢力が最盛を極める戦国時代は、また惣村をはじめとした民衆の力もまた旧来の権威を覆す力を持ちうる所まで来ていたという、これを符合させて考えています。
何か考えているとしたら、日本的法王体制…という事になると思います。ただ、朝廷や、幕府、堺商人たちをどのような位置づけで考えたか。
たとえば「戦国時代は状態であり統一政権など生まれない」と考えるか、考えないかで、その在り方は大分変わってきますよね。そこらへんですね。
自分以上の権威となる事に関して織田信長と相入れる事はないと思います。
ただ、信長は必ずしも宗教に対して敵対的な思考は持っていなかったようです。…持ってないようにも観えます。
本願寺が「俺が天下を統一する」と大見得を切れば、必ず信長と衝突したでしょうが、実際には本願寺はそうは言わなかった。
史実は10年戦争ですが、信長と石山本願寺の衝突は、本当に歴史の要請で、不可避のものだったのか?…というのがこの話の焦点ではあると思います。
僕が、石山本願寺を日本的法王体制の設立を目指していたと断じたのは、訳があります。
石山本願寺の敷地が、隣接する古代から存在する『生国魂神社の最初の鎮座地』に存在したという事実を知ったからです。
その敷地は、その以前は『古墳』だったとも言われていたそうです。
そういう『重要地』に『寺』を作った以上、何らかの意図が必ず存在したはずです。
信長も、それを感じとったのではないでしょうか?
……まあ、根拠は、今挙げたものしか、まだありませんが(^^;
あそこに坊舎を建設する事を決めたのは蓮如なので、やはり蓮如が何を考える人だったのか?という推理が必要そうですね。
また、ここで語っている本願寺の目的が蓮如の目的として、つなげて考え得るものか?は~教団の存続と隆盛という大きな目的では繋がるでしょうけど~また、いろいろ調べて行く必要がありそうです。
もっとうがった見方で云えば、神社勢力と結託した現場主導の計算的な神仏習合だった可能性です。
もともと、親鸞から蓮如に至る考え方は、それまでの仏教の政治食い込みと比べて、神道に近い考え方だったと思います。
曰く、民の為の神様の考え方。自然信仰。
そこで、神社勢力と繋がる事ができたなら、政治から民草に至る、新たな宗教信仰組織を形成する事ができても不思議ではありません。
世は応任の乱から厭世観の広がっていた戦国中期。
鎌倉以上に振興の信仰が広まる絶好の機会でした。
あの時点なら、キリシタンが広まるのを待つまでもなく、日本的な宗教新体制を作れたかもしれません。
全て、妄想です(^^;
しかし、可能性としては、開拓しがいのある場所だと思っています。
蓮如に野心が無かったとしても(武術指南ではない僧兵が大量にいた時点で、野心はともかく、最終的には『聖戦』発動できるまでを視野にいれていたとしても不思議では無いと思いますが)、民草の『力』をあの時点では、多分信長が一番理解していた気がするので、その完成を恐れたとしても不思議ではないかなと……妄想してました。