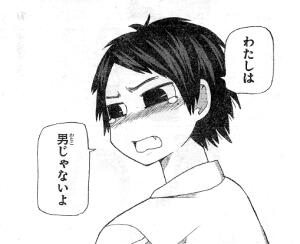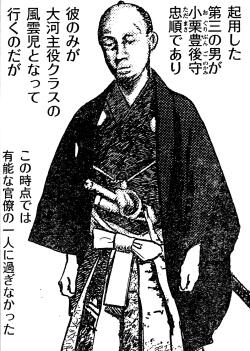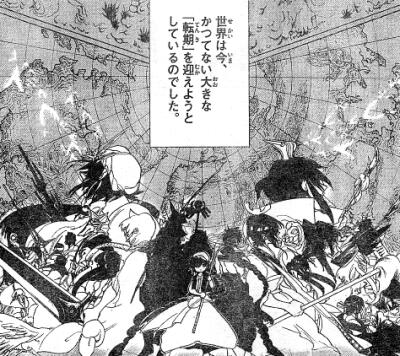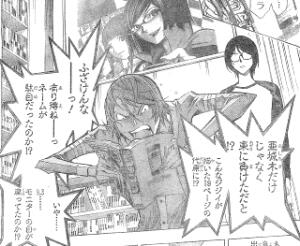【12月第2週:GANKON 第九願 神と人間】
http://www.tsphinx.net/manken/wek1/wek10539.html#719
【漫研】
http://www.tsphinx.net/manken/

サイコー「一気に駆け抜けるマンガがあったっていいだろ」
(『バクマン。』第158話より)
ローズ・トゥ・人気漫画家マンガ『バクマン。』(原作・大場つぐみ、作画・小畑健)ですが、サイコーのこのセリフにはちょっと反応してしまいました。やっぱり、僕は週刊少年誌で“そういうマンガ”が読みたいという気持ちはありますね。
『サザエさん』や『こち亀』、あるいは『ルパン三世』のような何時までも続けられる物語は別としても「終わるために生まれた物語は終わるべき時に終わって欲しい」と。週刊連載を読む“マンガ読み”なら、そう思う事は多々あるんじゃないかと思います。というか、海燕さんの以前の記事ですが、これと同じ気持ちになる事は僕にもあるって話ですね。(↓)
▼Something Orange:終わる物語と終わらない物語。
そりゃあ「人気のないマンガは、一気に駆け抜けざるを得ない」わけで、そのバランスの中で、まあ、キレイに終わる物語もあるのでしょうし、月刊連載などでは、然るべき時に幕を閉じるマンガの(どこが然るべき終り時か?ってのは意見が割れるとしても)比率も増えますから「まあ、それでいいじゃん?」と、そこで満足する事もできるんですけどね…。
あるいは「一気に駆けるけるマンガ」なんて概念、モロに解釈や心の持ち方の話にもできて、解釈次第、気持ち次第で「何言ってるの?「一気に駆ける抜けるマンガ」なんてそこら中にあるじゃん?」とか言い出したりもできるんですが…。その上で、自分の素直な心に耳を傾けると、僕はそこに関して“不満足”と言う事らしいです(汗)
『今週の一番』とか言って、ず~っと、週刊少年誌を観て来た人間として、あるいは発行部数の大きさから、ここが“最前線”という考え方があるとして、僕はもっともっと“ここで”、そういう『物語』を観たいなと思ってしまう。
それも「そんなマンガがあってもいい」なんて言う、稀な例なんかじゃなく「そうである物語は、そのように終り時を計って終わる」という考え方が基本にあって欲しいと思ってしまう。
少なくとも『面白い』物語は必ず長く続く力を持つ、という命題は真にはならないでしょう。売れる事と面白い事のギャップと言ってしまえばそれまでですが…。
………まあ、たとえば。100の“人気”を得れば、その作品は雑誌を支える力を持ち得る(当然、連載は続けられる)として、超人気マンガは1000ぐらいの人気は余裕で獲得するとします。…そうすると、1000の人気を得たその作品が、100を割り込むまでは、相当の時間を要するでしょう。当然、その時が来るまで連載は続けられると。
…で、この時、その作品は長らく100のノルマの達成を続け一時は1000まで行った超優良作品なわけですが、同時に900の人気に「見限られた」という考え方はできないでしょうか?900の多くは「飽きて」離れたのでしょうが、一部は「失望」というレベルに達しているかもしれない。
それは本当にそれでいいのか?「100残ってりゃいい」じゃなく「1000まで来たのなら、その1000の人気(顧客)に満足してもらう方法は何か?」という考え方はないのか?※「100残ればいいじゃない。それは、1000の人気に“いつまでも”楽しんでもらえるように全力を尽くした結果だ」という考え方をするとしたら、それは物語の持つ人気の力学…自然現象を無視したものではないか?
その「飽きたり」、「失望したり」してお気に入りの連載から離れた900の人気は、どのくらい再び別のマンガを手に取るのか?…僕みたいに「何であろうとマンガを読む事を決めている人」は外して……というか放っておきゃいいんですが(笑)
別の言い方をすると、最終的に「飽きさせる」、「失望させる」作品が、どのくらいのマンガ中毒を養成し得るでしょうか?まあ、全くいない事はないでしょうけど。しかし、むしろ最終的に「飽きさせる」マンガは、マンガの“卒業者”を多く輩出するのではないか?
芝居小屋などの興行で言えば、最初は楽しませても、客は最後にはアクビして飽きて、こっそり小屋から出てゆく…そういう興行をする小屋にリピーターはどのくらいつくのか?
………すみません。弁を弄しました。まあ、何かデータや裏情報があるワケではないので、100とか900とかね(汗)勝手な数字で単なる与太話です(汗)
でも、僕をマンガ好きにさせたマンガのほとんどは「一気に駆け抜けたマンガ」たちでした。そうじゃないものもあるでしょうけど、俄には思い浮かばないくらい(「僕の中ではここが最終回」とか勝手に決めて折り合いをつけてる気がする(汗))です。だから、そういう物語をもっと見たいな。語りたいな…と。本当、それだけですね。
http://www.tsphinx.net/manken/wek1/wek10539.html#719
【漫研】
http://www.tsphinx.net/manken/

サイコー「一気に駆け抜けるマンガがあったっていいだろ」
(『バクマン。』第158話より)
ローズ・トゥ・人気漫画家マンガ『バクマン。』(原作・大場つぐみ、作画・小畑健)ですが、サイコーのこのセリフにはちょっと反応してしまいました。やっぱり、僕は週刊少年誌で“そういうマンガ”が読みたいという気持ちはありますね。
『サザエさん』や『こち亀』、あるいは『ルパン三世』のような何時までも続けられる物語は別としても「終わるために生まれた物語は終わるべき時に終わって欲しい」と。週刊連載を読む“マンガ読み”なら、そう思う事は多々あるんじゃないかと思います。というか、海燕さんの以前の記事ですが、これと同じ気持ちになる事は僕にもあるって話ですね。(↓)
▼Something Orange:終わる物語と終わらない物語。
そしてそんな読者の望みに応えて、「終わらない物語」は生まれる。しかし、現代の商業主義は「終わる物語」でも「終わらない物語」でもない「終われない物語」を大量に生み出した。あきらかに物語的必然性を超えて続いていく物語に、多くのひとが失望した。
それは、そのときのことだけを考えるなら商業的に有益な選択であったかもしれない。しかし、長期的には業界全体に対する不信感を生み出し、不利益につながった一面もあるのではないか。
すべてを語り尽くしたはずなのに、終わることなく延々と続く物語は、なんとなく物悲しいものだ。そういった物語は、完全に読者に飽きられ、人気が衰えてはじめて終わっていった。
そりゃあ「人気のないマンガは、一気に駆け抜けざるを得ない」わけで、そのバランスの中で、まあ、キレイに終わる物語もあるのでしょうし、月刊連載などでは、然るべき時に幕を閉じるマンガの(どこが然るべき終り時か?ってのは意見が割れるとしても)比率も増えますから「まあ、それでいいじゃん?」と、そこで満足する事もできるんですけどね…。
あるいは「一気に駆けるけるマンガ」なんて概念、モロに解釈や心の持ち方の話にもできて、解釈次第、気持ち次第で「何言ってるの?「一気に駆ける抜けるマンガ」なんてそこら中にあるじゃん?」とか言い出したりもできるんですが…。その上で、自分の素直な心に耳を傾けると、僕はそこに関して“不満足”と言う事らしいです(汗)
『今週の一番』とか言って、ず~っと、週刊少年誌を観て来た人間として、あるいは発行部数の大きさから、ここが“最前線”という考え方があるとして、僕はもっともっと“ここで”、そういう『物語』を観たいなと思ってしまう。
それも「そんなマンガがあってもいい」なんて言う、稀な例なんかじゃなく「そうである物語は、そのように終り時を計って終わる」という考え方が基本にあって欲しいと思ってしまう。
少なくとも『面白い』物語は必ず長く続く力を持つ、という命題は真にはならないでしょう。売れる事と面白い事のギャップと言ってしまえばそれまでですが…。
それは、そのときのことだけを考えるなら商業的に有益な選択であったかもしれない。しかし、長期的には業界全体に対する不信感を生み出し、不利益につながった一面もあるのではないか。
………まあ、たとえば。100の“人気”を得れば、その作品は雑誌を支える力を持ち得る(当然、連載は続けられる)として、超人気マンガは1000ぐらいの人気は余裕で獲得するとします。…そうすると、1000の人気を得たその作品が、100を割り込むまでは、相当の時間を要するでしょう。当然、その時が来るまで連載は続けられると。
…で、この時、その作品は長らく100のノルマの達成を続け一時は1000まで行った超優良作品なわけですが、同時に900の人気に「見限られた」という考え方はできないでしょうか?900の多くは「飽きて」離れたのでしょうが、一部は「失望」というレベルに達しているかもしれない。
それは本当にそれでいいのか?「100残ってりゃいい」じゃなく「1000まで来たのなら、その1000の人気(顧客)に満足してもらう方法は何か?」という考え方はないのか?※「100残ればいいじゃない。それは、1000の人気に“いつまでも”楽しんでもらえるように全力を尽くした結果だ」という考え方をするとしたら、それは物語の持つ人気の力学…自然現象を無視したものではないか?
その「飽きたり」、「失望したり」してお気に入りの連載から離れた900の人気は、どのくらい再び別のマンガを手に取るのか?…僕みたいに「何であろうとマンガを読む事を決めている人」は外して……というか放っておきゃいいんですが(笑)
別の言い方をすると、最終的に「飽きさせる」、「失望させる」作品が、どのくらいのマンガ中毒を養成し得るでしょうか?まあ、全くいない事はないでしょうけど。しかし、むしろ最終的に「飽きさせる」マンガは、マンガの“卒業者”を多く輩出するのではないか?
芝居小屋などの興行で言えば、最初は楽しませても、客は最後にはアクビして飽きて、こっそり小屋から出てゆく…そういう興行をする小屋にリピーターはどのくらいつくのか?
………すみません。弁を弄しました。まあ、何かデータや裏情報があるワケではないので、100とか900とかね(汗)勝手な数字で単なる与太話です(汗)
でも、僕をマンガ好きにさせたマンガのほとんどは「一気に駆け抜けたマンガ」たちでした。そうじゃないものもあるでしょうけど、俄には思い浮かばないくらい(「僕の中ではここが最終回」とか勝手に決めて折り合いをつけてる気がする(汗))です。だから、そういう物語をもっと見たいな。語りたいな…と。本当、それだけですね。
 | バクマン。 15 (ジャンプコミックス) |
| 大場 つぐみ | |
| 集英社 |